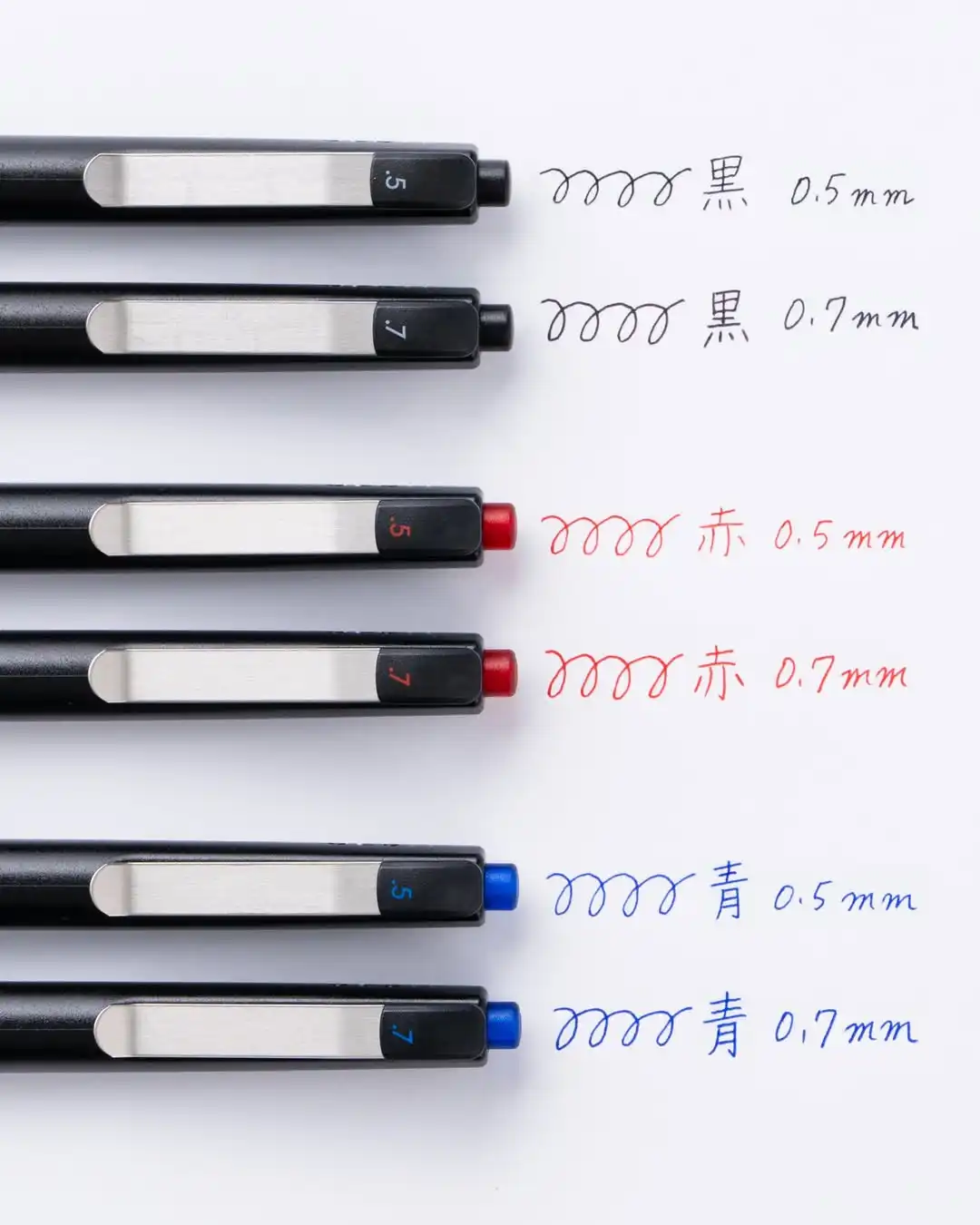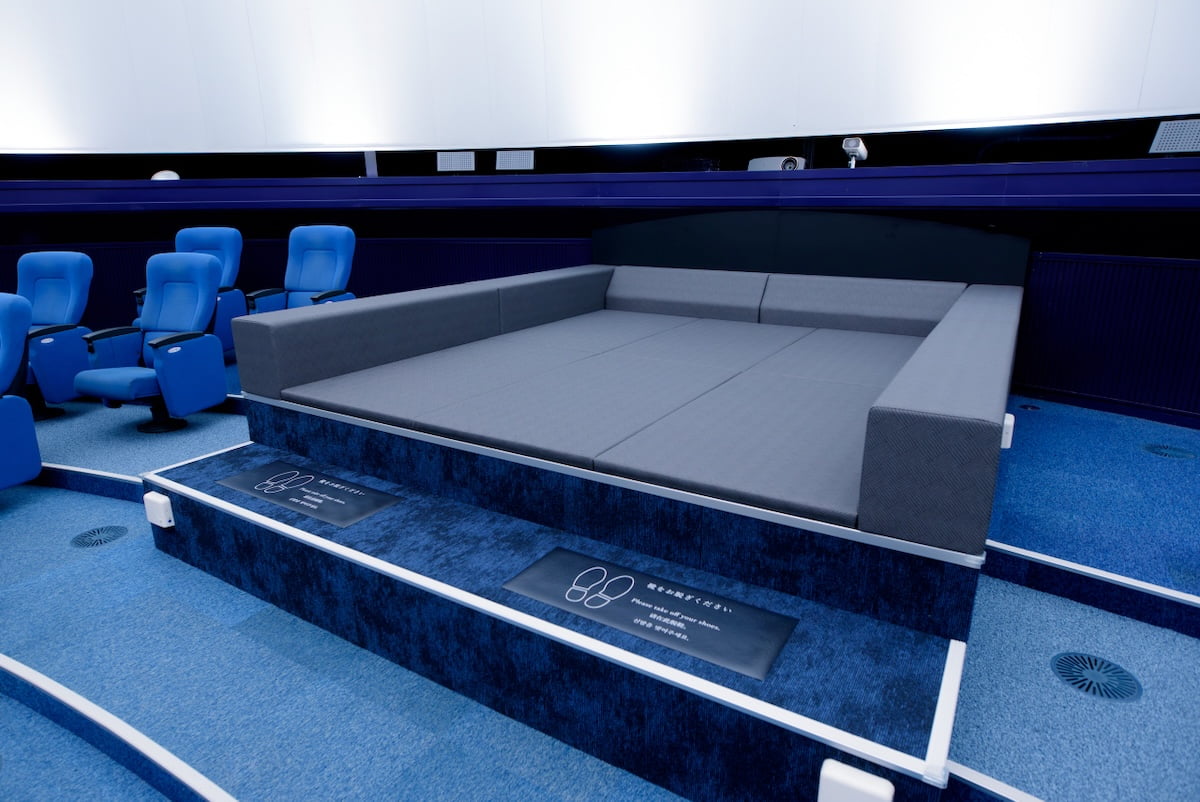◎水戸岡ワールドが島根県に登場! 「ばたでん」 「 一畑電車」 「天叢雲(あめのむらくも)」 鉄道事業再構築実施計画 一畑電車 県 松江市 出雲市 「みなし上下分離方式」 「単なる移動手段の車両ではなく、乗車することを目的とする魅力的な車両」
水戸岡鋭治(みとおかえいじ)先生(78歳) 「仕事をしながら旅をする。旅をしながら仕事をする。そういう時代の先駆け的な電車になるのではないか」(水戸岡) 。 車両愛称は「天叢雲(あめのむらくも)」 水戸岡 ワールド 島根県 「出雲の山並みに湧き出る雲を車窓から眺め、神話に思いをはせてほしい」 石飛貴之常務 「通勤通学も一つの短い旅」 水戸岡先生 国、県、松江、出雲両市 「誰もが乗って楽しい車両」 水戸岡先生 「コンパクトだけど楽しさと感動が詰まった車両。多くの方に親しまれる存在になってほしい」 現在の案では夕日をイメージした茜色を基調としていますが、雲を強調する配色に変更する予定とかで、 「『天叢雲』にするとできればもっと雲の色にしたい、できればシルバーメタリックで、それに金の雲が書いてあるような。最後の電車ができるまで渡した日デザイナーは正解を求めてやるべき」
車名に関しては、出雲神話において素戔嗚尊(スサノオノミコト) 八岐大蛇(ヤマタノオロチ) 「天叢雲剣」 「天叢雲(あめのむらくも)」
一畑電車 松江城 出雲大社 「天叢雲」
イメージを見る限り、既存の7000系・8000系をベースにしたような仕様で、そこに「水戸岡テイスト」 「天叢雲」 米子市 後藤総合車両所 ♥♥♥
▲車内デザイン
刑事物のドラマを見ていると、警察組織内部の隠蔽体質
「 Blue Wall of Silence」(ブルー・ウォール・オブ・サイレンス) Blue は多くの警察官が着用する制服の色(→警察組織)で、青は警察を象徴する色として広く認識されています。Wall は外部からの調査や批判を遮断する「壁」、Silence は沈黙・隠蔽の意味。直訳すると「沈黙の青い壁」 「警察内部の口止め文化/不正隠蔽体質」 blue wall of silence 「警察内部で不正を守るために築かれる沈黙の壁」 「仲間を売ることは裏切りである」
警察の暴力行為
汚職・不正捜査
内部告発者(whistleblower)が孤立する問題
警察改革・人権問題の議論
ニューヨーク州の弁護士・旦 英夫 『米語ウォッチ アメリカの「今」を読み解くキーワード131』(PHPエディターズグループ、2024年)
The Blue Wall of Silence Breaking the Blue Wall of Silence break the blue wall of silence の形でよく使われる]
Many officers knew what happened, but the Blue Wall of Silence
The police officers formed a blue wall of silence
日本語で近い表現としては、次の物が該当するでしょう。
「警察内部の 不祥事隠し体質」
「組織防衛の沈黙」
「内部告発を許さない文化」
ただし、Blue Wall of Silence 「警察」 Wiktionary YourDictionary
この語が一般社会や報道で大きく広まった契機として、警察の不正・暴力事件が表面化した事例が挙げられます。1970年代のニューヨーク市警 「 Frank Serpico事件」 ロドニー・キング “blue wall of silence” 「内部の沈黙コード」
「Blue Wall of Silence」 「Blue Wall of Silence」 「警察官は仲間を裏切らない(Cops don’t tell on cops)」 「Blue Code (of Silence)」「Blue Curtain(青いカーテン)」 2021年12月、ミネソタ州の裁判所で、黒人ジョージ・フロイド Blue Wall of Silence 「沈黙の青い壁」 Blue Wall of Silence 「ボディカメラ(body cams)」 スマートフォン
Investigators found it difficult to break through the blue wall of silence
The blue wall of silence この句は、本来は警察文化を指して使いますが、「特定の集団が仲間の不正を守るために沈黙する文化」「組織ぐるみの隠蔽体質」 ♥♥♥
There seems to be a blue wall of silence
◎アチャー、またやってしまった!! ▲消えたUSBメモリー
2022年以来3年ほどバージョンアップしていませんでしたが、今年の日本語ソフト「一太郎2026プラチナ」 「Windows10」 「Windows11」 「8Gの容量が必要です」 USBメモリーディスク(16G) 一太郎ファイル USBメモリー 「Windows11」 「おいおい、そんな~!!」 英語試験 リスニングの試験 エクセル
▲35年分の資料 これをもう一度打てというのか?!
専門業者に泣きつくことにしました。3年前にも同様の悲劇を経験した時にお世話になった東京の「デジタルデータリカバリー」 USB 、「急ぐ場合は成功報酬を含めて18万円(税別)、13万円は前払いでいただき、もし作業をやってみて復元できなくても返金はなし。うまくいった場合には残りの成功報酬を支払う。ゆっくりでよければ成功報酬を含めて9万円(税別)6万円は前払い」 USB アララ! 特に私が希望していた「一太郎」 バックアップ
今回もこの会社にお願いしましたが、結局、1本のファイルも復元できなかった、と連絡があり、USB 「バックアップを取っておく」 「喉元過ぎれば熱さを忘れる」 ♥♥♥
◎やったー、救世主現る!! この春休みに、今までの作成資料を一から打ち直すのかと思うととても憂鬱になっていました。この二年間に発行した通信「あむーる」 「あーあ!」 「一太郎」 「バックアップファイル」 USBメモリー バックアップファイル 「一太郎」 「バックアップ」 「バックアップの履歴から開く」 バックアップ バックアップファイル USBメモリー
ただしこれは「一太郎」 エクセルファイル テキストフィイル 「読取革命」 エクセルファイル 「読取革命」 エクセル変換 エクセルファイル ♥♥♥
昨年は2月17日が勝田ケ丘志学館 メールで 添削してもらえないか、との要望がありました。引き受けて入試前日まで英語作文の添削を徹底して行いました。「それでは行ってきます」 神戸 「須磨シーワールド」 「合格しました!」 志学館 「あむーる」
八幡先生へ 1年間、添削指導をしてくださりありがとうございました。丁寧な解説プリントや、返却の際の何が分かっていて何が分かっていないのかを、自分で気づかせてくださるアドバイスはとてもありがたく、毎回たくさん考えて問題に取り組むことができました。1年間でレベルアップできたと感じています。
その影響でしょうか、今年も2月17日に最後の授業が終わってから、メールで過去問の指導をして欲しい、という生徒が数多く現れました。メールで内容を返信してもよかったのですが、やはり実際に答案を解説してあげた方が、身につくだろうと思い、添削答案を持って米子 ハグ 「共通テスト」 勝田神社 ハグ 「自己ベストが出ました!」 ハグ 「これはセクハラじゃないよね?」
▲私が合格祈願を捧げた神田神社
これには私には想い出があるんです。あの当時は担任や教科担当が、本番当日試験会場で、最後の激励をして送り出していました(今は会場には入れません)。私も毎年試験会場に駆けつけていました。当日、島根大学 ハグ 「あれはセクハラじゃないんですか?」 ♥♥♥
ちょっと古い話になりますが、昭和27年、本田技研工業 本田宗一郎 藍綬褒章 宮内庁 本田
本田
サラリーマンの場合は職人と違って特別な道具を使っているわけではありませんが、それでも、筆記用具、カバン、書類、机の上などがいつもきちんと整理されているのといないのとでは、周囲に与える印象は大違いです。使い込まれてよく手入れの行き届いた道具は、見る人に爽快感を与えます。また、自分の仕事に関係する道具を大事にする人は、腕のいい職人さんに対するのと同様の信頼感を他の人に与えるものです。メジャーリーグでも伝説となったレジェンド・イチロー 「道具を大事にするということは、自分を大事にするということ」 「道具が助けてくれる(ミスを防いでくれる)」 「準備こそが成果を生む」 イチロー選手 「強い選手になるにはどうしたらいいですか?」
大事なバットを芝生の上に寝かせたりしないことです。ほんのわずかな芝生の湿り気が、バットのバランスを崩すこともある。バットを地面に叩きつけるなどはもってのほかです。地面にぶつかった衝撃で、重さや木目、密度のバランスが崩れるかもしれません。 バットを作る樹は自然が長い時間をかけて育てています。バットは、この自然の樹から手作りされているのです。一度バットを投げたとき、とても嫌な気持ちになりました。それ以来、自然を大切にし、バットを作ってくれた人の気持ちを考えて、僕はバットを投げることも、地面に叩きつけることもしません。もともと道具を大事に扱うのは、プロとして当然のことです。ボールを投げたり打ったりする前に、まずはそういうところに気持ちをもっていかなければダメです。 イチロー選手 年7月6日、近鉄戦で左腕・小池秀郎 一度だけありました。「 あれだけのバットを作ってもらって打てなかったら自分の責任ですよ」 イチロー選手 久保田五十一 「何人かの選手から、自分の手掛けたバットについてお礼を言われたことは過去にもありました。でも、バットへの行為そのものを謝罪されたのはあの一度だけですね」 久保田 イチロー イチロー選手 イチロー選手 道具を大切にする姿勢 だけは、みんな見習わなくてはいけないと感じています。「道具を大切にできない人は、いつかその道具に裏切られる」 青木 功(あおきいさお) ある町工場に、腕は確かだけれども仕事が少し雑な若い職人がいました。彼は作業が終わると、使った道具類を机の上に放置したまま帰ってしまいます。「また明日使うんだからいいだろう」 「なぜ自分の道具まで片づけたんですか?」 「道具はな、仕事の結果を一番近くで見ている相棒だ。雑に扱えば、雑な仕事しか返してくれない。大切にすれば、困ったときに必ず応えてくれる」 「道具を大切にすることは、仕事そのものを大切にすることだった」 と。
またこんな話もあります。ある木工職人の話です。 彼は若い弟子に、古びて錆びたノミを見せながらこう言いました。「これはな、俺が修行を始めた頃に買ったノミだ。30年使って、刃は何度も研ぎ直し、柄も二度取り替えた。でも、こいつはずっと俺の相棒だ。」 「そんなに古い道具を、なぜまだ使うんですか?」 「道具はな、使う人間の癖を覚えるんだ。 大切に扱えば扱うほど、手に馴染んで、仕事の質を上げてくれる。 道具を雑に扱う人間は、仕事も雑になる。」 「壊れたら買い替えればいい」 「お前の腕が上がったのは、道具を大切にし始めた頃からだ。」
ある有名なフランス料理のシェフは、新入りの料理人の技術を見る前に、まずその人の「包丁の研ぎ方」 「キッチンの布巾の畳み方」
道具が汚れている=仕事が雑である
道具の配置が乱れている=思考が混乱している
道具を大切にする人は、次に使う瞬間のことを常に考えています。つまり、「先読みの力」
1000年以上続く寺社仏閣を修復する宮大工さんの世界では、道具(鉋や鑿)を研ぐことが修行の基本です。あるベテランの棟梁は、「道具を粗末に扱う者は、材料(木材)の声を聴くことができない」 「成果物(仕事の対象)への敬意」
これら全てのエピソードが伝えていることは
道具を大切にする姿勢は、仕事そのものへの姿勢を映す鏡である。
手入れを続けることで、道具は自分の一部のように馴染む。
「大切に扱う」という行為が、集中力や丁寧さを育てる。
道具を大切にすることは、単なる物の管理ではなく、 自分の仕事への誠実さを育てる行為なんですよね。♥♥♥
一定の土地から得られる収穫は、投下された労働量、資本量に比例してある程度までは増加するのですが、ある一定の限度を超えると次第に減っていく、というのが「収穫逓減の法則」(しゅうかくていげんのほうそく) 「生産量を増大させようとすると、生産効率が落ちる 」 増収率は次第に減って いき、一定の量を超えると、今度は減収に転じてしまうという 現象を表しています。つまり、所定のインプット量から、一定のアウトプット量につながっていたのが、インプット量を増やし続けると、アウトプット量が追いつかなくなってしまう ということで、このことは、農業以外の分野にも当てはまる法則として知られています。
最近の分かりやすい例で言えば、ペッパーフードサービス 「いきなり!ステーキ」 出雲市・松江市 イオン 松江店 コチラ )。「世界の亀山モデル」 シャープ つの事業に頼って大きくし過ぎた結果、苦しくなってしまった好例 だと思います。
最近、グループ内での不適切会計疑惑が持ち上がり連鎖的に拡大し、内部管理体制などの改善計画の策定方針を表明したモーターの世界的大手・ニデック(旧日本電産) 永守重信(ながもりしげのぶ) 。「ニデックの経営は岸田社長にすべて委ねる。これでニデックは、しっかり再生できると信じている」 「短期的な収益を重視しすぎる企業風土の弊害は明らかだ。(現場に)プレッシャーがあったことも否めない」 と、 疑惑について同社の岸田光哉社長 ニデック M&A(企業の合併・買収) 永守 「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」 永守 「目標必達」 永守
同じことをずっと続けていると、効果が下がってくるのです。これは勉強でも同じことが言えます。朝から晩まで一日、今日は数学だけ、あるいは国語だけと集中学習をすることもできるにはできるのですけれども、どんな酔狂な学校でも、そんなことを考えたりは絶対にしません。飽きてしまって能率が上がらないのは目に見えているからです。実際にかつて、東京 「頭の切り換え」 「よく学び、よく遊べ」
私の体験談です。退屈な講演を聞いていると、30分くらいまではいいのですけれども、その後、だんだん疲れてきます。この「収穫逓減の法則」 「もうとても聞いてはいられない…」 ♥♥♥
事前知識もなしにいきなりtoolbox talks 「工具箱の話」 toolbox talks 松下佳世 『同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ』( イカロス出版、2020年 )
「じゃあtoolbox talkをしに行くから通訳よろしくね~」 「なぬ?toolbox talk? そうかそうか、作業前に工具についても話しておかないといけない、というわけね」 松下 「工具箱の話」 「ツールボックストーク」 これは全米安全評議会が1940年代半ばに発行した専門誌の中で、労働者に対して行う毎週の「安全ミーティング」 “Fairyland Weekly Toolbox Meeting” 「業務前の短い安全講話」 「安全講話」「安全朝礼」「作業前ミーティング」
Toolbox talks =(朝礼などで行われる)安全講話 toolbox talks 「安全ミーティング」 toolbox “toolbox meeting”“toolbox talk” 「Training(研修)」 「安全ミーティング」 「堅い」「長い」「上からの一方通行」 meeting ではなくtalk が使われるようになりました。作業開始前に行う短時間の安全ミーティングを指し、ほぼ毎日実施されることが多く(5分~10分)、現場責任者(職長・監督)が主導します。現在では建設現場・製造業・鉄道・インフラなどで、作業前の安全確認ミーティングを指す一般的な現場[業界]用語となっています。「道具箱を囲んで話す」という言葉の裏には、現場の安全は現場の人間が守るという、プロフェッショナルな自覚が反映されています。主な内容としては、当日の作業内容、危険箇所(高所作業、重機、足場の濡れ具合など)、天候や周囲環境の注意事項、保護具(ヘルメット・安全帯)の確認で、安全対策を共有することが目的です。(例)「今日は気温が35度を越える予報だ。こまめに水分を補給をして、気分が悪くなったらすぐに報告するように」「昨日からの雨で床が滑りやすくなっている。資材の置き場所を整理して、通路を確保しよう」「今日は高所作業がある。ヘルメットと安全帯の点検を各自もう一度行うこと」 ♥♥♥
We have a toolbox talk
Today’s toolbox talk
Let’s have a quick toolbox talk
Alright everyone, let’s have a quick toolbox talk
今年の箱根駅伝 青山学院大学 黒田朝日選手 青学大 「青学は往路で選手を使い切った」 青学大 「山のスペシャリスト」 原監督 「全国レベルの駅伝で、こんな山登り、山下りのコース設定は他にない。なぜそこに向き合わないのか。その認識を強く持っているのが青山学院だ 「これ、たまたまだと思いますか?」 原晋(はらすすむ)監督
2004年 予選落ち
2005年 予選落ち
2006年 予選落ち
2007年 予選落ち
2008年 22位
2009年 8位
2010年 9位
2011年 5位
2012年 8位
2013年 5位
2014年 優勝
2015年 優勝
2016年 優勝
2017年 優勝
2018年 2位
2019年 優勝
2020年 4位
2021年 優勝
2022年 3位
2023年 優勝
2024年 優勝
2025年 優勝
2月8日にも、「宮古島大学駅伝」 箱根駅伝 青山学院大学 「宮古島大学駅伝」 青山学院大学 黒田朝日 黒田 然 上野山拳士朗
箱根駅伝 青山学院大学 原晋監督 『決定版!人が替わっても必ず結果を出す 青学流「絶対王者の鉄則」』(祥伝社、2025年) 原監督 挨拶・掃除・感謝」 「三悪習」 ①言い訳をする ②他人のせいにする ③傍観者となる ウソをつくな ごまかすな 裏切るな
どれも当たり前のことですが、徹底するのはそう簡単ではありません。ウソもごまかしも裏切りも最終的には全部自分に返ってきます。人はどうしても易きに流されやすいからこそ、心を鍛えることが大事なのです。原監督 「3つの行動指針」
◎感動を人からもらうのではなく、感動を与えることの出来る人間になろう。 ◎今日のことは今日やろう。明日はまた明日やるべきことがある。 ◎人間の能力に大きな差はない。あるとすればそれは熱意の差だ。 学生が成長するためには、次の5つのステップを踏むことを指導するとのことでした。①知る→②理解する→③行動する→④定着させる→⑤そして伝える
そうか!青学の強み 「青トレ」 「原メソッド」 「練習のとき以上の力は、試合では絶対に出せない」 「人間教育」 ♥♥♥
パナソニック 「知的遊び心」 ①アマノジャクであること (常識の中に居座ったり、イエスマンであってはいけない。常に現状を否定し、他人の言ったことを一旦は疑ってみる ) 、 ② 非 まじめであること (「不まじめ」とは違う。遊びながら仕事をし、仕事をしながら遊ぶ ) 、 ③いろんな人と幅広くつきあうこと (異分野、異業種の人と付き合うことで常に新鮮な刺激を受ける ) 、 ④好奇心を持つこと (どんなことでもつまらないと思ってはいけない切り口をチョット変えてみるだけで思いもかけない発見がある ) これらは、私が生徒たちにいつも教室で語りかけていることです。 そんな「独創的なはみ出し人間」 本田技研工業 「5つのセオリー」 ①「自分のために働け、会社のためにはたらくのではない 」、②「能ある鷹は爪を出せ 」、③「失敗を恐れるな 」、④「物事の判断はすべて現場、現物、現実に依れ 」、⑤「人まねをするな。自分で考えろ、自分の手でやれ 」
積極的に働いた結果の失敗は大目にみるが、ノープレイ・ノーエラーは徹底的に排除する、というのがホンダ 「人のやらないことしろ!」 衆議院選挙 「チームみらい」 「人のやらないことをやる」 ♥♥♥
バカな奴は単純なことを複雑に考える。普通の奴は複雑なことを複雑に考える。賢い奴は複雑なことを単純に考える。(稲盛和夫)
吉川尚輝(よしかわなおき)内野手(31歳) 「両側関節鏡視下股関節唇形成術」 右股関節 左股関節 昨季は開幕から3番を担い、岡本和真内野手(29歳)
両股関節 都城 都城 「さぁ行こう!」 吉川選手 両股関節手術 「そこ(開幕)を目指してやっている感じです。ただ、まだどうなるか分からないし、場所が場所だから手術もあんまり(アスリートでは)前例がない。はたから見たら『動けてるじゃん!』って思うかもしれないけど、自分のペースでトレーナーの方と一緒にやっていきたい。焦りたいけど、焦らず頑張りたい」 「『少し(患部の)調子悪いです』とか意見を言ったり、メニューが変わることもある。それでもちょっとずつ動けてきている。少しずつ強度を上げながらできている」 「打撃練習は思いっきり下半身を使ってとか、まだトレーニングが足りていない部分がある。当てて打つ分にはいいという感じ。守備もいろんな動きがある。正面で捕るのは全然大丈夫だけど、今は人工芝ですけど、土(のグラウンド)とかいろいろ段階を踏んでいかないといけない」 「普段関わったり、しゃべることがない選手も多いから新鮮。(3軍では)目標が見えづらくなることも多いと思うんですけど、その中でやらないといけないと思ってやってると思うし、一人でも多く支配下、チームの戦力になってくれたらいい。みんな頑張ってるし、僕も頑張るし」 「頑張ります、本当に!」
私も3年前に右股関節 吉川選手 松江北高補習科 勝田ケ丘志学館 松江駅構内 日赤 「回復が早い人だと二週間で退院する人もいます」 理学療法士 作業療法士 松江 「共通テスト」 「共通テスト」 山口整形外科 吉川尚輝選手 吉川選手 ♥♥♥
私は毎年生徒たちに「親を大切にすること。感謝の気持ちを持つこと」 「親孝行したい時には親がもういないんだよ」 境野勝悟(さかいのかつのり) 『日本のこころの教育』(致知出版、平成13年) 岩手県・花巻東高校
『蟹工船』 小林多喜二(こばやしたきじ、1903~1933年) 多喜二 小樽高商(現小樽商科大学) 多喜二 多喜二 多喜二 小樽 多喜二 セキ 多喜二 「三日後の11時から五分間面会を許す。五分でよかったら東京の築地署まで出頭しなさい」 「五分はいらない」 「一秒でも二秒でもいいから、生きているうちに息子の多喜二に会いたい」 小樽駅 多喜二 「おばあちゃん、だめだ、そんなことしたら危ない」 「こんなところで一晩待っていたら多喜二に会う時間に間に合わない」 憲兵さんが見て、あまりにも寒そうなので、お母さんのところへ火鉢を持って行きました。すると、お母さんは、「ああ、ありがたいけど、多喜二は火にあたってないんだから、私もいいです」 「お母さん、何も食べていないんでしょう、食べなさいよ」 「いや、多喜二は食べていないからいいです」 多喜二 多喜二 「お母さん、ごめんなさい」 「ほら、お母さんだ、見ろ」 多喜二 「多喜二か、多喜二か?」 「はい、多喜二です。お母さん、ごめんなさい」 多喜二 「たきじーッ」 「お母さん、お母さん、しっかりしてください。あと二分ですよ。何か言ってやってください」
ハッと気がついたお母さんは、残りの二分間、多喜二 「多喜二ッ。おまえの書いたものは一つも間違っておらんぞーッ。お母ちゃんはね、おまえを信じとるよーッ」 小樽 多喜二 多喜二 「何か言いたいことがあったら言え」 多喜二 「待ってください、待ってください。私はもうあなたの鞭をもらわなくても死にます。この数か月間、あなた方はみんなで寄ってたかって、私を地獄へ落とそうとしましたが、遺憾ながら私は地獄へは落ちません。なぜならば、毋が、おまえの書いた小説は一つも間違っていないと、私を信じてくれた。むかしから母親に信じてもらった人間は必ず天国へ行くという言い伝えがあります。母は私の太陽です。その母が、この私を信じてくれました。だから、私は、必ず、天国へ行きます」 多喜二 「おまえの書いたものは間違っていない。お母さんはおまえを信じておる!」 セキ 多喜二 多喜二 セキ 「ほれっ! 多喜二! もう一度立って見せねか! みんなのために、もう一度立って見せねか!」 ♥♥♥
私は全国のいろいろな観光地を旅する中で、「似顔絵」 似顔絵 東京・新宿「高島屋」7階 「カリカチュアジャパン」 石原 瞳(いしはらひとみ) 「チーム八ちゃん」 石原 カリカチュア・ジャパン株式会社 千葉県我孫子市
画家を目指していたお父さんの影響を強く受け、2歳の時から絵を描いていた石原 手塚治虫 種村有菜 「自分の絵で人を感動させたい」 「カリカチュア世界大会」(ISCA)総合優勝
人物の個性や特徴を誇張して表現した肖像画「カリカチュア」 カリカチュア 「ISCAカリカチュア世界大会2021」 米国・ラスベガス 石原 瞳さん(いしはらひとみ、千葉県出身) 石原 総合優勝 スタジオ作品部門 アウトスタンディングカートゥーンスタイル部門 ベストカラー部門
▲世界一に輝いた石原 瞳さん、おめでとうございます!!
大胆な色使いと独創的なタッチが特徴的です。世界大会の主催者に石原 「個性や特徴のつかみ方がすごい」 石原 高島屋 ♥♥♥
▲石原さんに描いていただいた原画 気に入っています
下は2022年の「大学入学共通テスト リーディング 」
「大学入学共通テスト」 イギリス英語 イギリス英語 『ライトハウス英和辞典』 「大学入学共通テスト」 「圧倒的な「語彙力」を目指して」 「文化面の英米差」 建物の階数の呼び方の英米差 を取り上げました(下記パンフレット参照)。そのことが英文の中で出題されたのです(写真上)。階数の数え方はイギリスとアメリカでは違います。アメリカ英語 「first floor」 「ground floor」 イギリス英語 「〜(序数)basement」 問2 first floor third floor ③「2階上に上がる必要がある」
▲私の記事 見事的中!!
▲『ライトハウス英和辞典』(第7版)s.v. floor
思い起こしてみるに、やはりパンフレットの中で私が注意喚起をしたalmost 「ほとんど」 では誤解が起こりやすい)がリスニング試験に出題され(⇒コチラ です)、次年度は建物の階数の呼び方の英米差
イギリスの集合住宅に住む人のお宅を、住所を頼りに訪ねようとする時や、ホテルの部屋に入る際には、間違えないように気をつけなければならないポイントがあります。それは、階数表示。アメリカ英語を学んできた日本人にしてみれば、“first floor” “second floor” “first floor” は 日本でいう「2階」にあたり、“second floor”
その背景には、イギリスの家屋の古い様式があります。古い様式の家屋では、1階の3分の1ほどが半地下になっていて、“ground floor” “first floor” “second floor” ground floor first floor first floor ground floor first floor ground floor ♥♥♥
3年連続で1位となった名古屋市立大学 あいち銀行 名古屋市教育委員会 名古屋市立大学
2位の大阪公立大学 「公大授業」
3位の島根大学 「じげおこしプロジェクト」 「地域人材育成コース」 「しまね産学官人材育成コンソーシアム」
また、今回私立大学で唯一トップ10入りをした近畿大学 のどぐろの完全養殖に成功
◆大学の地域貢献度ランキング 1位「名古屋市立大学」公立 2位「大阪公立大学」公立 3位「島根大学」国立 3位「徳島大学」国立 5位「信州大学」国立 6位「佐賀大学」国立 7位「鹿児島大学」国立 8位「山口大学」国立 9位「周南公立大学」公立 10位「近畿大学」私立 私の地元の松江市 島根大学 「地域人材育成コース」 「じげおこしプロジェクト」 「地域貢献人材育成入試」 「SDGSユニット認定制度」 「SDGsユニット」
過去の調査結果を振り返ってみると、2015年には40位だった島根大学 島根大学 「地域に根ざし、地域社会から世界に発信する個性輝く大学」 島根大学 大谷学長 「本学は、『地域に根ざし、地域社会から世界に発信する個性輝く大学』を目指すとともに、学生・教職員の協同のもと、学生が育ち、学生とともに育つ大学づくりを推進することを島根大学憲章に掲げ、地域社会とともに歩み、地域の課題解決や人材育成に積極的に取り組んできました。今回の調査で順位が上がったのは、長年にわたり地域との連携を継続してきた成果が実を結んだものだと考えています。」 ♥♥♥
VIDEO
尊敬する故・松下幸之助 「なぜ成功したんですか?」 「成功の理由」 ①身体が弱かったこと ②学歴がなかったこと ③やはり、強運であったこと
この三つの理由をあげたのです。エーッ??!これは解説をしないとちょっと理解できないでしょうね。特に身体が弱いこと、学歴がないことなどは、普通の人にとっては成功の条件とは絶対に言わないはずです。これらのことはきっと運が悪い理由や原因に挙げられるものでしょう。松下
松下幸之助 「これは便利だ。きっと世間で受け入れられる」 二股ソケット 大阪電灯 「そんなもんダメや!」 幸之助 「あの店に行ってご主人に会ったら、こんなふうにご挨拶して品物を納めてきなさいよ」「この番頭さんには、こう言ってお金をいただいてきなさい」 幸之助 幸之助 「成功するには運が必要だ」 幸之助 幸之助 「周囲の人がみんな偉く見えた」 「苦情を言ってくる人には笑顔で接せなあかん」 幸之助 「自分の意見をちゃんと聞いてくれた」 幸之助の 「自分が成功したのはやっぱり運がよかったから」 「運」 幸之助 幸之助 和歌山県海草郡和佐村 和歌山市 幸之助 政楠 大阪 「幸之助も尋常小学校の四年生だ。もう少しで卒業だが、大阪の火鉢店で小僧が欲しいという話がある。ちょうどいい機会だから幸之助をよこして欲しい」 幸之助 大阪 幸之助 幸之助 幸之助 大阪 五代自転車店 幸之助 「船場学校」 幸之助 五代自転車店 幸之助 大阪電灯 関西電力 幸之助
幸之助 大阪築港 幸之助 幸之助 幸之助 「夏でよかった。冬だったら助からなかった」
また、松下電気器具製作所 松下電器 幸之助 「やられる!」 幸之助
幸之助 幸之助 幸之助 「自分は運が強い。滅多なことでは死なない」「これほどの運があれば、ある程度のことはきっとできる」 幸之助 幸之助 松下政経塾 幸之助 幸之助 「運のない人間はあきまへん。その次は、愛嬌ということでんな」 「運と愛嬌のある人間かどうか」 幸之助 「女は愛嬌とはよく言うが、男も愛嬌だ」 松下政経塾 高市早苗総理 「運の良さそうな顔をして」 と 「目いっぱいの笑顔をつくった」 ♥♥♥
私の住んでいる松江市
私は毎年「大学入学共通テスト」 コチラ をご覧ください)、共通テスト英語の平均点 予想 「指標」
「大学入試センターから発表される中間平均点速報の第一弾 よりも1、2点低いのが最終平均点となる。」 毎年これを私は追検証していますが、 大学入試センター 「歴史は繰り返す」 「経験」 ♥♥♥ 【リーディング】 中間① 64.80点(中間② 62.86点) → 最終平均点 62.81点 【リスニング】 中間① 56.42点(中間② 54.67点)→ 最終平均点 54.65点 ◎History repeats itself.(歴史は繰り返す)
惜しまないためには、惜しみない努力がいります。今日できることは今日にしかできません。明日できるという保証はどこにもないのです。そう思えば惜しんでいる暇はないのですが、それには覚悟が要ります。人はどうしても弱いもので、やすきに流れる存在だからです。常に「惜しむな」「惜しむな」
私の大好きなシンガーソング・ライターのさだまさし 「ミスタープロ野球」 長嶋茂雄(ながしましげお) さだ 「今日の試合を見に来てくれたお客さんの中には、一生のうちたった1回だけ見に来たという大が必ずいる。一生に一度だけ見に来てくれた人に、元気のない長嶋を見せたくない。調子の良い悪いはあるけれど、ダメならダメなりに『あの長嶋の空振り三振はきれいだった』と言ってもらえるようなフルスインクを心掛けた」 「最も記憶に残る男」 長嶋 さだ 「対談の中でこの言葉が最も心にしみた」 さだ 「フルスイング」
1974年暮れ、さだ 「グレープ」 「精霊流し」 「叙情派フォークの旗手」 京都府 舞鶴市民会館 さだ さだ グレープ さだ 「仕方がないよ」「あれで良かった」 グレープ 吉田政美(よしだまさみ) さだ さだ 「ああするしかなかった」 グレープ 「セイ!ヤング」 舞鶴市民会館 グレープ グレープ 「何人かの聴衆の失礼を心からおわびします。ですが、このことでどうか舞鶴を嫌いにならないでください」 さだ
さだ さんは常に「フルスイング」 「全力投球」 長崎市NBCビデオホール 「全力投球」 さだ 「そう考えたら惜しんでなんかいられないよね。精一杯その日の自分に出来ることをやるしかない。結果的に出し忘れたことはあっても、出し惜しみしたことは一度もない。それは断言できるね」 「いいコンディションの時ばかりじゃなかったし、声が出なかったコンサートの時は終わった後にひどく落ち込んだこともあった。ただ、体調の良し悪しや出来不出来はあっても、一度も手を抜いたり、流したりしたことはない。その日出来るすべてをステージで出してきたと断言できる。これは人生の誇りのひとつだね」 さだ 「拍手への恩返し」
私もこの49年間、一時間一時間の英語の授業に常に「フルスイング」 日赤 「お加減はいかがですか?今から30年以上も前に英語を教えていただきました。ありがとうございました。」
▲年月を重ねて味が出てきた「グレープ」
さだ 「第21回グッドエイジャー賞」 「活きいき・楽しく・かっこよく」 さだ 「こんな立派な賞をもらえるはずがないと思って、たらいがつってないかと考えながらステージに上がりましたね。最初はドッキリを疑いましたが、どうやら大丈夫みたい。」 「いい歳の取り方をしているって改めて言われても、そういう自覚もなしに漠然と歩いてまいりました。精一杯生きてきたことだけは確かですけど」 「一生懸命にやっていると時々褒めてくださる方がいる。とってもうれしい」 「50年歌ってきて、本当に育てていただいたと感じる。自分でゴリゴリやるより、ヒット曲を作っていただいて、その責任感でやってきた。もうすぐコンサートも4600回になりますが、お客さんが来るから背中を押されてやってきました。50年のうち、30年は借金を返してきたので、あまり実感がない」 「憧れに向かって歩いてそれにたどり着いた時、達成感というか幸せを感じるのかもしれませんね」 さだ 「拍手」 「拍手への恩返し」 ♥♥♥
僕はこれまで4,623回のコンサートを重ねてきて、手抜きをしたことは一度たりともありません。きょうできることはきょうしかできない。明日もできる保証はありません。ですから、僕は「惜しむな、惜しむな」って自分に言い聞かせながら、すべてのステージは一回しかないという思いで立っています。特に70歳を過ぎてからは体力の衰えも感じますし、身近な人が亡くなる経験もしていますので、このコンサートが俺の最後のコンサートかもしれない。恥ずかしくないように、出し惜しみせず一所懸命やろうと心懸けてきました。これからもその姿勢を貫いていきたいと考えています。 ―さだまさし
◎週末はグルメ情報!!今週はオムライス
▲巨大なオムライスの看板が目立つ!!今は値上がりしました
勝田ケ丘 志学館 米子市両三柳 「ローリエ」 「オムライス」 境港 米子 JR境線 三本松口駅 三本松口駅 オムライス 「オートバックス東米子店」 「ローソン米子三本松口店」 「ローリエ」 「オムライス」 オムライス 「ローリエ」 モーニングサービス 「オムライス」 「ハンバーグ」 「ハンバーグ」
オムライス のソースはなんと全部で11種類!どれもふわふわの卵と相性抜群なので、色々な味を楽しめます。お好みで選ぶことができます。
「ローリエ」 「エアドッグ」 限定のサービスランチや豚ロースカツランチ、豚の生姜焼きランチ、照り焼きチキンランチなど、庶民的なものからちょっとリッチなものまで、幅広いメニューが並んでいます。看板メニューのオムライス オムライス
▲オムライスと海老フライの最高の組み合わせ
人気者と人気者の組み合わせで、ボリュームたっぷりのおすすめセットメニュー「オムライスセット」(1,580円) オムライス&スープ・サラダ 海老フライ・ハンバーグ・明太子スパ・鶏の唐揚げ・クリームコロッケ 「海老フライ」 「デミグラスソース」 デミグラスソース デミグラスソース 「海老フライ」(2本) ホットコーヒー 「ハンバーグ」
グルメ番組でも紹介された人気洋食店です。米子 「オムライス」 松江市 「食べログ」 オムライス
二回目の訪問です。今日はセットでハンバーグ オムライス 「ミニ」 ハンバーグ 「キーコーヒー」 食べログ ♥♥♥
◆近畿大学の躍進◆
◎入学志願者数日本一の快挙(10万5890人)
◎世界初のクロマグロの完全養殖
◎行列・完売が続く専門料理店「近畿大学水産研究所」(大阪梅田・東京銀座)
◎関西一きれいな校舎―きれいな女子トイレ(化粧室)
◎つんくプロデュースのど派手な入学式
◎ネット出願「エコ出願」100%達成
◎オープンキャンパスでのおもてなし
◎民間企業からの受託研究実施件数全国3位
◎活発な高校訪問の営業活動
◎「英語村」 「近大マグロ」 近畿大学(157,563人) 千葉工業大学(162,005人) ノドグロ 近畿大学
From 2016 it is going to adopt the name of Kindai University. Kinki is one of the biggest universities in western Japan with more than 32,000 students, but only 329 of them are from overseas. Kinki University in Japan is going to change its joke-inducing name as it seeks to raise its international profile and appeal to English-speaking overseas students. The university is to change its name to avoid any misunderstanding. The Kinki name is drawn from its surrounding local region – but the university has had to counter other interpretations. The new name of Kindai University is a combination of “Kinki” and “Daigaku” for university. The shift in name is part of its plans for a more international identity. “The word ‘kinky’ also means perverted. We have no other choice than changing the English name because we are serious about pursuing a more international school culture,” the university’s dean, Hitoshi Shiozaki, told the AFP news agency. ” We aim to get more foreign students coming here, so we’ve decided to change our English name to ensure there is no misunderstanding,” the university told English language newspaper the Japan Times. It is not clear whether the change in name will affect the university’s English language newspaper, the Kinki Times.
近畿大学 「Kinki University」 「Kindai University」 近畿大学
英語圏において「Kinki」 「変態的な」 「kinky」 informal having or showing unusual ways of getting sexual excitement )。このため、大学側は国際的なイメージの向上と、より多くの海外学生の誘致を図るために、英語名称の変更を決断したのです。新しい学部開設(=国際学部 「KINKI UNIVERSITY」 「KINDAI UNIVERSITY」 「近大大学」 kinky 「性的に異常な」 「変態の」 「海外の学会で自己紹介をすると、失笑され、良い気持ちはしなかった。近畿は由緒ある言葉だが、国際化を本気で進めるためには、英語表記の変更は仕方がない」 近大 学長の塩崎仁志 「’kinky’という言葉は、わいせつという意味も持ちます。より国際的な学校文化を追求することに真剣に取り組んでいるため、英語名を変更する以外に選択肢はありませんでした。」 「より多くの外国人学生を迎え入れることを目指しており、誤解がないように英語名を変更することにしました」
英語名の変更は、大学が国際化戦略を積極的に推進していることを示す象徴的な出来事でした。単なる名称変更ではなく、グローバル化への強い意志と、海外学生への魅力を高めるための戦略的な取り組みと言えるでしょう。この事例は、企業や組織の国際展開において、ブランドイメージの重要性を改めて認識させるものです。
近畿大学
海外学生の増加: 「kinky」
国際的な知名度向上: 新しい英語名「Kindai University」
ブランドイメージの改善: 誤解を招く可能性のある名称を解消することで、大学のブランドイメージを向上させ、よりポジティブな印象を与えることを目指しました。
国際的な競争力強化: グローバル化が進む高等教育市場において、国際的な知名度とブランドイメージは、大学の競争力を左右する重要な要素です。英語名の変更は、この競争力強化の一環として位置付けられていました。
これらのメリットを踏まえて、近畿大学 英語名称変更
私たちが近畿大学
潜在的なリスクへの対応: ブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性のある要素を事前に特定し、適切な対策を講じることの重要性。
戦略的な意思決定: 国際化戦略を推進する上で、大胆な意思決定と迅速な行動が不可欠であること。
継続的なブランド管理: ブランドイメージは、一度構築すればそれで終わりではなく、継続的な管理と改善が必要であること。
企業や組織は、近畿大学 ♥♥♥
出版科学研究所
インターネットの普及や街の書店の減少、コンビニでの売り場縮小などから、紙の雑誌の売り上げ不振が続いています。昨年は、子育てや絵本に関する情報を発信する福音館書店 『母の友』 講談社 『週刊現代』 『週刊ダイヤモンド』
英語教師を続けてきた私自身を振り返って見ても、若い頃は『英語青年』『時事英語研究』『English Journal』『現代英語教育』『英語教育』『言語』『言語生活』 『英語教育』(大修館書店)
紙の書籍・雑誌は、過去最高の推定販売金額を記録した1996年から、減少傾向が続いています。コロナ禍 「巣ごもり需要」
本田健『読書で自分を高める』(だいわ文庫) この本は 自己啓発の視点で、読書の意味や価値が書かれた本です。 そもそも本を読む意味は何なのか?本を読むと何が変わるか?どうやって読書を始めたらいいか?どんな本を読めばいいか?など、読書の意味が身に沁みるヒントが満載の本でした。 本を読み、自分の人生に取り組むこと、それを「読書力」 本に書かれた著者の人生、知識、経験、洞察を自分の人生に取り組む「読書力」 読書をすることで、お金、人間関係、仕事、恋愛、様々な「事例」を無意識のうちに知ることができます。 意識するしないにかかわらず、本を読むことは、人の経験という事例を知識として自分に内在化させることです。 だから、「こうすればこうなりやすい」という他者の経験を知識として取り入れることにより、行動も上手くいきやすくなります。結果的に、成功しやすくなるのです。 本は、著者が仕事や人生で得た学びを格安価格で話をしてくれるようなものです。読書をすることは、自己投資の効率、コスパで言えば最高。 何事も、知っているのと知らないのでは、大きな差があります。 たとえそれが実践的なものでも、「本にはこう書いてあったな」という予備知識があるのとないのとでは、全然理解が違ってくるものです。そして、 読書にはタイミングというものがあります。 同じ本を読んでも、それが心に響く時とそうでない時がありますが、それは読書にはタイミングがあるからです。 自分が必要としているタイミングで出会った本は人生にとって大きな意味がある本となる。 出会うべきときに出会うべき本を読む。そんな本との「出会い」を見逃してはいけません。 読書の基本は気になった本を読むことです。たくさん本を読む中で時々、「これは!」という本と出会います。 最初から、「良い本」だけを見つけようとせずに、読書は基本的に自由に数重視で読んでいく。そうすれば、その中から、自分にとってのベストな本を見つけることができるものです。 体の健康のために食事が必要なように、心の健康のために読書が必要です。ただ日々を生き、食べて消費し、生殖するだけの人生はもったいない。 どんなジャンルの本を読もうと、それは必ず、自分の人間性に影響を与えていくものです。 何より、本を読めば、自分の最高の人生のモデルが見つかります。読書で、自分の理想の人生を模索し、参考にするのです。 その本を読んだことで確実に人生の進路が変わったと言える本がありますか?その本を読まなければ今の私の人生はなかったという本です。私の場合は、渡部昇一『知的生活の方法』(講談社現代新書) そういった経験をしているからか、本を読むことは一つのチャンスと考えて、時間とお金が許す限り、気になる本は買って読むことにしています。 実際、人生の進路で悩んでいて、偶然立ち寄った本屋さんでふと立ち読みした本の中で、その先のヒントが見つかった経験とか、今悩んでいる問題の答えが偶然読んだ本の中で、その解決策が見つかることも珍しくありませんでした。 こういう「読書の力」 その本を読むか読まないか、そんな小さい行動がその後の人生に影響を与えてくる。 それが読書の不思議なところですが、自分の人生を振り返ると、読書には本当にいろんな面で助けられました。 だからこそ、今日もこれからも、本を読まずにはいられません。「今よりもっと」 「この問題をどう解決すればいいのだろう?」 人生は限られている。実生活の中で何もかも体験することはできない。そこで読書が重要になる。本や新聞の中には無尽蔵の知識や情報が満ちている。人間の思考のさまざまな道筋が痕跡を残している。それをたどることは論理的思考の訓練となろう。 感動の追体験は情緒をはぐくみ、正義を愛し卑怯を憎むことを学んで徳性を養うこともできる。読書はそうした人間の基礎をつくる国語力を涵養する。そのおおいなる力をもう一度思い返したい。 ―『産経新聞』2006年10月29日 以前私が勤めた島根県立津和野高等学校 学校司書 司書 松江北高 東出雲町町長 鞁嶋弘明(かわしまひろあき) 先生 学校司書 松江北高 その生徒たちの共通点は、とてもよく本を読んできた図書館の常連の生徒たちだった 松江北高
私が大好きな建築家の安藤忠雄(あんどうただお) 「こども本の森 中之島」(名誉館長 山中伸弥) 瀬戸内海 「こども図書館船 ほんのもり号」 安藤 松山市 「坂の上雲ミュージアム」 「こども本の森 松山」 月刊『致知』6月号(2025年) 「読書立国 」安藤忠雄・山中伸弥「読書は国の未来を開く」
読書とは自分の世界を広げてくれる心の旅であり、人間の成長にとって、最高の栄養は本であると実感しています。いまこそ国を挙げて読書をしなければいけません。そのために命ある限り「こども本の森」プロジェクトを続けていく覚悟です。(安藤忠雄) 1日30分でも1時間でも、違う世界に連れて行ってくれる読書は、心を満たしてくれる大事な習慣です。私の尊敬する鎌田 實(かまたみのる)先生
読書は、人生の土台を築く習慣です。土台は建物の下に埋まっていて見えないけど、これがしっかりしているからこそ、沈まずに立ち続けることができます。だからこそ死ぬときに後悔が残らないように、読書という習慣で、人生の土台を盤石にしておくといいと思います。 また私の尊敬する故・渡部昇一先生 「読書の効用」 江藤裕之先生 ♥♥♥
読書は自分で経験しようと思ったら何十年もかかるような、その著者の一番大事なエッセンスをパッと掴むことができる非常に便利なもの。時空間を超えた著者との対話ができる。書かれた内容について自分で考え、共感や批判を通して物の見方を養う。そういう追体験を積み重ねていくことで自己を高めていくのが読書の大きな意義だ。
最近、英語圏の若者文化やネット上で、situationship 「曖昧な関係」「はっきり定義されていない恋愛関係」 situationship = situation(状況)+ relationship(恋愛関係) です。relationship (人間関係)ではなく、situation (その時々の状況)に任せる関係だというニュアンスです。結婚のことなどは考えず、その時々の交際を楽しむことは、若い世代の新しいやり方かもしれません。もっとも、自分は真剣な交際を求めているのに、相手との関係がsituationship 「situationshipから抜け出したいのなら、相手にはっきりと恋愛、仕事、家族、人生観などを尋ねて、交際を続けるかどうかを決断しなさい」 「タフな質問をして拒絶されることを恐れていては、何も解決しません!」 situationship relationship にしたいなら、一番大事なことは、勇気を出してお互いに心から誠実なコミュニケーションをとることなのでしょうニューヨーク州弁護士・旦 英夫 『米語ウォッチ アメリカの「今」を読み解くキーワード131』(PHPエディターズグループ、2024年)
▲米国最新のキーワードが取り上げられた好著
situationship
恋人とは言えない
でも友達以上の親密さがある
付き合っているとは言えないけれど、デートはする曖昧さがある
将来の約束や明確な定義がない
という関係性を指しています。
ニュアンス・使われ方としてはカジュアル・口語的な表現で、主に恋愛・デーティングの文脈で使われ、少しネガティブ/モヤっとした感情を含むことが多いようです。使い方(文法)は名詞として使います。よくある形は次のような使い方です。
be in a situationship
a situationship
使用例を挙げておきましょう。
① 状態を説明する We’re in a situationship
We hang out all the time, but we’re not dating. It’s a situationship
② 不満・悩みを表す I’m tired of being in a situationship
③ 関係性の説明 She’s in a situationship
I’m tired of being in a situationship
④ 付き合っていないことを強調 It’s not a relationship, it’s a situationship
We’re not officially dating, but we’re in a situationship.
Our situationship ( 私たちの曖昧な関係は何ヶ月も続いている)
⑤比喩的に situationship
While the season has already started, the superstar athlete and the owners of the team are in a situationship
また近年では、この言葉がシチュエーションシップにある相手そのもの を指す表現として使われることも増えています。例えば、 situationship
◆relationship / friendship との違い
用語
明確さ
特徴
relationship
明確
恋人・交際関係
friendship
明確
友達
situationship
曖昧
境界がはっきりしない
上の表が示す通り、situationship 「定義されていない曖昧な恋愛関係」「友達以上恋人未満で、関係性がはっきりしない状態」 ♥♥♥
柏野健次『英語教師のための語法ガイド』(大修館、2025年) do one’s best I’ll do my best.は「(自信はないが)やってみます」という意味を表わす。しばしば、疑いの気持ちを含み、結果が疑わしい時に使われる。外科医が手術前にI’ll do my best.と言えば、患者や家族は落胆するだろう。 また、『ジーニアス英和辞典』(第6版)
I’ll do my best.は多くの場合、「疑いの気持ち」「自信のなさ」という意味合いを伴い、「やれるだけやってみる」という意味を表す。ただし、スポーツ、コンテスト、入学試験のような競争相手がいる文脈では、通例話し手は自ら進んでその行為を行うために 、「最善[全力]を尽くす」という意味になる。 「do one’s best=全力を尽くす」 『LEAP Basic』(2025年) do one’s best「全力を尽くす▲自分の持っている全てを出す」 コチラ です)。どちらかというと、自分自身のことについて「(やれるかどうか分からないけれども)できるところまで最善を尽くしてやってみるよ。 」 “I’ll do my best.”
ブルージェイズ(Blue Jays) 岡本和真内野手 岡本選手 do my best Hello everyone. My name is Kazuma Okamoto. Thank you very much for this opportunity. I’m very happy to join the Blue Jays. I will work hard every day and do my best for the team. Thank you for your support. Nice to meet you.(皆さん、こんにちは。岡本和真です。この機会をいただき本当にありがとうございます。ブルージェイズに加わることができて、とてもうれしいです。私は毎日一生懸命努力します。そしてチームのために全力を尽くします。ご声援ありがとうございます。はじめまして) (下線は八幡)
その間、一度もうつむくことなく、テレビカメラ8台、日本と米国とカナダから集まった約50人の報道陣の前で、よどみなく語りました。用意した英語長文のあいさつを完璧にやりきった安堵感があったのか、最後は“Go Blue Jays!” 岡本選手 「日本一になれなかったけれど、次は世界一になりたかった」
さて元に戻って、岡本選手 “I’ll do my best” “do my best” 「毎日一生懸命取り組み、チームのために全力を尽くします」 “work hard” “I will work hard every day and do everything I can for the team.”
ただ気を付けたいことは、他人に応援メッセージのつもりで“Do your best.” 「上から目線」 「あなたには余り期待していない」「あなたはまだ全力を出し切ってはいない」「失敗してもいいから、とりあえずやってみなさい」「結果は期待していないけれど、まあ頑張ってみて」「応援しているけど、いい結果が出なくても私はがっかりしないから失敗しても大丈夫だよ」「今のあなたはまだベストを尽くしていないのでは」 「冷たく」「事務的」「気持ちがこもっていない」「“もう言うことないからこれ言っとく”感」 「上から目線」 努力の有無を話し手が評価している構造 になっているからです。「bestを尽くせ」と言うことで、今はベストじゃない可能性を前提にしているのです。励ましというより「努力を求める指示」 デビッド・バーカ『英語じょうずになる事典(上)』(アルク、2017年) “Do your best!” 「お前は今持てる全ての力を出し切っていないじゃないか。全力でいけよ! 」
前向きに応援したい時には、次のような表現の方が自然で温かく伝わります。Good luck!(幸運を祈っているよ)/ You’ve got this!(君ならできる)/ I’m rooting for you.(応援してるよ)/ Hang in there!(頑張れ)/ Come on!/ Don’t give up!/ You’re nearly there!/ Break your leg! ♥♥♥
▲松江・月照寺(あじさい寺)
▲月照寺の「大亀」
「ばけばけ」 トキ 山陰のあじさい寺・月照寺 「大亀伝説」 ヘブン先生に 月照寺 大亀 「出雲国松江藩6代藩主の松平宗衍(むねのぶ)公の頃、 夜になると池に住む大亀が城下へ出てきて、 人を襲うようになった――という噂があった。」 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) ●松江藩主が亀を愛で、死後に巨大な石像を造立した。⇒松江藩松平家では、六代目藩主・宗衍
● 夜な夜な石亀が城下で暴れ、人を襲うようになる。⇒祀られたはずの亀は夜になると妖力で動き出し、 城下町で悪さを働くようになった――という伝承があります。
● 住職が説法し、大亀 大亀 大亀 「自分でも暴れるのを止められない。 どうか貴方にお任せしたい。」 宗衍 大亀
● 他にも残る“池の大亀”の口承⇒江戸中期、池にいた亀が関係している別の言い伝えも残されています。 夜ごと巨大化しては寺から抜け出し、 子どもをさらったという恐ろしい民話です。 石像を造り墓所へ安置した途端、 その怪異が止んだと伝わります。
● 現在は「触ると長寿になる大亀」として親しまれる⇒巨大な亀は今でも月照寺のシンボルで、頭をなでると長寿祈願になるといわれ、多くの参拝客が訪れます。ただし、夜の境内では人魂を見たという話も残っており、 松江らしい怪談スポットとして人気があります。
◆ トキ ヘブン
ヘブン先生 トキ 小泉八雲 トキ 八雲 私もこのお寺に来ると必ず立ち寄るのが、六代廟門 大亀の石像 小泉八雲 『知られざる日本の面影』 「月照寺の大亀」伝説 大亀 大亀 大亀 大亀 「私にもこの奇行を止めることはできません。あなたにお任せいたします」 大亀 大亀 7代目治郷(はるさと) 大亀 大亀 宍道湖 堀川 大亀 今日も多くの観光客の方々が、この大亀
NHK連続テレビ小説「ばけばけ」 松江市 月照寺 JR松江駅 「ばけばけ」 ♥♥♥
将棋棋士としての姿とお茶の間に親しまれるギャップの大きさは、余人をもって代えがたい器の大きさを感じた。 (1月27日通夜にて 羽生善治九段)
将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、 「重戦車」「一分将棋の神様」 「ひふみん」 加藤一二三(かとう・ひふみ) 加藤 矢倉将棋 矢倉・棒銀 「一二三」 南口繁一 「福岡のダイヤモンド」 加藤 藤井聡太 加藤 「長年にわたって私とともに魂を燃やし、ともに歩んでくれた妻に深い感謝の気持ちを表したい」
「神武以来(じんむこのかた)の天才」 「負けは財産です」 「精一杯将棋を指して、立派に名局の数々を生み出すことができました。これが私の人生における最上の誇りです」 「ひふみん」 紫綬褒章 旭日小綬章 文化功労者 仙台白百合女子大客員教授 加藤 羽生善治王座・王将 中川大輔七段 加藤 羽生 「指す手がなくなった」 羽生 加藤 「あれ?あれ? あれ? あれ? 待てよ、あれ? おかしいですね?」 「もしかして頓死?えっと、こういって、あれれ、おかしいですよ」 「歩が3歩あるから、頓死なのかな?えー」 「大逆転ですね、たぶん」「NHK杯史上に残る大逆転」 「歩が3歩あるから」 「ヒャー! 驚きました」 加藤 羽生 加藤 「一応王手をかけていったら、何か(相手が)危ない、というのが分かって。加藤先生が『あれ?』と言ってましたけど、まさに私の心情を言っていただいたような感じでした」 「羽生さんも心の中で『ヒャー!』と言った?」 と聞かれると、羽生 「ヒャーとまでは言ってないですけど、あれ?とは思っていました」 加藤先生
時は1982年の名人戦。相手は9連覇中の中原誠名人 加藤先生 「あ、そうか!ウヒョー!」 中原名人
あの天才・藤井聡太六冠 藤井聡太 加藤一二三 「趣味は藤井聡太」 藤井 「日刊スポーツ」 「ひふみんEYE」 藤井
14歳で棋士になり、20歳で名人に挑戦。「将来の名人は確実」 「指し手に自信が持てず、このままではトップに立てない」 「努力をするなかで限界を突破し、飛躍させるために」 「敵と戦う時は勇気を持って戦え。弱気を見せてはいけない。慌てないで落ち着いて戦え」 「旧約聖書」 「それまでは対局中に迷いがあったが、自分が考えた手を指せばいいと思えるようになった」 ヨハネ・パウロ2世 聖シルベストロ教皇騎士団勲章
加藤先生 「ひふみんアイ」 加藤九段 「うな重」 「モスグリーンは平和の色、青は闘志をかきたてる色」 「ひふみんとニャンぶらり」 米長邦雄日本将棋連盟会長 ひふみん 「加藤さんと同じものを。量は加藤さんのより多くしてね」 『家の光』 「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」 ギネス世界記録 「あの字がよく解読できますね」 「よく眠ること」 東京・聖イグナチオ教会 ♥♥♥
2007年5月27日、ZARD 坂井泉水(さかいいずみ) コチラ です)。私は坂井泉水 追悼展
▲東京での追悼展にも行ってきた。「Zard Gallery」
▲町田市で開催された「ZARD/坂井泉水 心に響くことば展」
ZARD/坂井泉水『君に逢いたくなったら…』(ミュージックフリークマガジン、2025年、2,420円) 『ZARD/坂井泉水 ~forever you~』 ZARD/坂井泉水 大黒摩季 ZARD 春畑道哉 川島だりあ 小澤正澄 坂井泉水 DEEN・池森秀一 FIELD OF VIEW・浅岡雄也 坂井泉水 ZARD 長戸大幸 大阪、東京 「ZARD MUSEUM」 坂井 坂井泉水 坂井泉水 坂井泉水 「30周年ライブ」 B ZONE ZARD 「デビュー35周年(2026年)」 ZARD 「ZARD35周年YEAR」 Zard ZARD 「Forever you」 コチラ )。♥♥♥ ◆ZARDベスト35曲◆ 第1位 「心を開いて」 「あの微笑みを忘れないで」 「マイ フレンド」 「揺れる想い」 「Don’t you see!」 「負けないで」 「息もできない」 「君に逢いたくなったら…」 「Oh my love」 「遠い日のNostalgia」
第11位 「かけがえのないもの」 「永遠」 「Good-bye My Loneliness」 「DAN DAN 心魅かれてく」 「きっと忘れない」 「夏を待つセイル(帆)のように」 「Today is another day」 「眠れない夜を抱いて」 「Forever you」 「来年の夏も」 「運命のルーレット廻して」 「好きなように踊りたいの」
第23位 「IN MY ARMS TONIGHT」 「My Baby Grand ~ぬくもりが欲しくて~」 「あなたを感じていたい」 「少女の頃に戻ったみたいに」 「雨に濡れて」 「突然」 「止まっていた時計が今動き出した」 「Season」 「この愛に泳ぎ疲れても」 「もう少し あと少し…」 「サヨナラは今もこの胸に居ます」 「愛が見えない」 「遠い星を数えて」
VIDEO
「パンティストッキング」 『読売新聞』 5月29日付けの記事、五十嵐 文「とらべる英会話」 「日本で主流の、腰までつながったタイプはpanty stockings ではなく、pantyhoseと呼ばれることが多い。 」
参考書や辞典類の中には「panty stockingは和製英語」 『ウィズダム英和辞典』(第3版、2013年) 「×panty stockingsとしない」 『ライトハウス英和』(第3版、1996年) 「panty stocking とは普通はいわない 」 「日英比較 英語では「パンティーストッキング」とはあまり言わない 」 結論的に言うと、panty stocking 「和製英語」 OED New Supplement メリアム・ウェブスター社 12,000 Words (1986)『和製英語事典』(丸善出版、2014年) △「通じる場合もある」として「一体型のパンストのことだと分かる人もいるでしょう」 OED 「英語として存在したことがある≠今自然に使われる」 stockings →pantyhose へ移行する途中で説明的に使われた複合語で、特に広告文・技術的説明・ファッション史・辞書的文脈で見られました。
私の調査の概要をお伝えしましょう。私たちの編集顧問の故・ボリンジャー博士 Neiman-Marcus Emporium Capwell 「誰も聞いたことのない表現」 「広告では使われる可能性がある」 メリアム・ウェブスター社(Merriam Webster) 「panty stockingsと常に複数形で広告などに使われることがある」 ボリンジャー博士 イルソン博士 「聞いたこともなければ使ったこともない」 ChatGPT 、「古い」「説明っぽい」「カタカナ英語」「不自然」「違和感が高い」 pantyhose/ tights イギリスの大言語学者であったR.Quirk panty stocking(s) .”、文法学者M.Swan J.Whitcut is used in Britain. We say tights , but I believe Americans prefer pantyhose or panty hose .”(以上『現代英語教育』1984年3月号の土屋裕樹
「オフィスで生足はOKか」「ストッキングをはくのがマナー」 「パンスト」 “panty stocking” 「“panty stocking”をください」 “stocking” は,ストッキングや長靴下を表しますが、これは“panty” とは合体しない言葉なのです。panty とstockings は別々の概念なので、英語ではこの2語を組み合わせて使う慣習はないのです。「パンテイストッキング」 “pantyhose” “hose” もまた、長靴下やストッキングという意味があります。なんだかまぎらわしくて、混乱するのも無理はありませんね。一方のイギリス英語 “tights” です。日本では冬にはく厚手のものをタイツ、薄手はストッキングと言いますが、そんな区別をせずに「タイツ」でOKです。以上は、『読み出したら止まらない!英語 おもしろ雑学』(知的生きかた文庫、2019年) まとめておきましょう。
pantyhose 日本語の「パンスト」に一番近い腰まで一体型の薄手のストッキング:
She's wearing pantyhose stockings 太ももまでで止まるタイプで、ガーターで留めることが多い:She
bought a pair of stockings tights パンストより厚手で秋冬用・ファッション用:Black tights 以上のことから、「和製英語ではないけれど、普通に使われる英語ではない」 『ライトハウス英和』(研究社) ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はカレー 2024年に、「第1回 日本ロケ弁大賞」 「大賞」 「オーベルジーヌ」 「オーベルジーヌらしさ」 「オーベルジーヌのロケ弁が現場にあると、その番組は高視聴率!」 「オーベルジーヌ」 四谷 新宿御苑 「オーベルジーヌ」 レトルトカレー
▲米子「天満屋」の「カレースクランブル」会場にて
大量の国産牛肉と香味野菜で出汁を取ったビーフブイヨン。国産玉ねぎを72時間ぐつぐつ煮込み甘味を最大限に引き出し作る玉ねぎブイヨン、玉ねぎペースト。上質のバターと乳脂肪分が高い濃厚な生クリーム。そして24種類のスパイスを絶妙なバランスで混ぜ合わせ、継ぎ足しを繰り返し深みあるカレーに仕上げています。レトルトカレーは全て中辛口のみとなります。じっくり煮込んだたまねぎの甘み。バターと生クリームの濃厚なカレーソース。ゴロゴロの国産牛肉をじっくり煮込んだ、王道欧風カレーを堪能することができます。
レトルトカレー 米子 天満屋 「カレースクランブル」 「甘い……」 「ふーーん、意外にもこの甘さがウケているのか?」 「オーベルジーヌ」 レトルトカレー 食べてみてまず驚いたのは、その甘味です。このような甘いカレーは初めて食べました。これがじっくりと煮込んだ玉ネギの甘味なんでしょうね。大量の牛肉と香味野菜で出汁を取ったビーフブイヨン。国産玉ねぎを72時間煮込み甘味を最大限に引き出し作る玉ねぎブイヨン、玉ねぎペースト。上質のバターと乳脂肪分が高い濃厚な生クリーム。そして24種類のスパイスを絶妙なバランスで混ぜ合わせ、継ぎ足しを繰り返す深みあるカレーに仕上げます。でもその甘さが結構クセになりそうな甘さなんです。そして中にゴロゴロと入っている牛肉の塊の量に驚かされます。じっくりと3日間煮込んだ玉ねぎの甘味、やさしく包み込むような上質なバターと生クリームのハーモニーを感じます。そしてじわじわとこみ上げてくるスパイスと素材の旨味。こだわり抜いた素材と手間ひまかけた仕込みが自慢のカレーを再現しています。♥♥♥
▲牛肉のかたまりがゴロゴロ入っていて美味しい
「ヨストの法則」 「顧客を獲得するために同じ人に対して何回もアタックする場合、一番好印象を与えるパターンは毎日のように自分たちのことの情報をお知らせする」 ◎1日に20回、お客様のところへ訪問する ◎2日間で10回、お客様のところへ訪問する ◎10日間で2回、お客様のところへ訪問する ◎20日間で毎日1回、お客様のところへ訪問する この中で一番好印象を与えることができるのは、「20日間で毎日1回、お客様のところへ訪問する」 「うぜー」
「売るから売れなくなる」 「売っている」 「売られる」 「買いたくない」 「会いに行く」 「こんにちは~」 「君何しに来たの?」 「昼食をデリバリーやってるんですよ~」 「じゃぁ今度買うわ~」 「こういう店あるんだ」
私は出版社・教育産業の営業の人によく話すんですが、まずは顔見知りになって、先生の喜ぶ情報を届けて人間関係を作りなさい、と。かつて数研出版 荒田 広島市 「つばめ」 「すずめ」 「○○印刷でございます。よろしくお願いします」
会う時間より、会う回数を多くする。得意先まわりの営業は、とにかくこまめに顔を出してなじむのがコツと言われています。ちょっと近くに来たついでに、と繰り返し顔を出すことが、相手客の心をつかむのだ。というのも、こうした親しみや慣れというのは、心理的には「学習」と同じと考えられますが、学習は一般に集中学習よりも分散学習のほうが効果を上げるからです。これは「ヨストの法則」 。 「ヨストの法則(Yost’s Law)」 アドルフ・ヨスト(Adolph Yost)
人間関係で、相手に親しみを持ってもらうことは、自分の印象をよくする基本です。その場合にも、分散して印象づけることによって、トータルでは相手に強い印象
試験のための勉強をする時、あるいは何かの知識を身に付けようとする時、ずっと続けて勉強するよりも、こまめに休憩を挟んだほうが記憶が定着しやすくなります 。心理学ではこれを、「ヨストの法則」
「よし、今から3時間勉強するぞ」 「今日は絶対に10時間勉強するぞ」 このように意気込んでから勉強を始める人も少なくないと思います。しかし、休憩はただサボっているのではなく、記憶の定着には不可欠です 。このことを理解し、ぜひ上手に休憩を入れるといいと思います。
新しい情報を連続して覚えていこうとするときには、「20分集中、10分休憩」 。実は、これも心理学者のヨスト 「30分のうち10分も休憩するの?」「時間がもったいない!」 いきなりですが、次の単語を10秒間で覚え、10秒間が経ったらメモ用紙に書き出してみて下さい。捕鯨、読書、自動車、習慣、社会、冷水、時計、階段、校内、冷蔵庫、渋谷駅。いかがでしたでしょうか。『捕鯨』や『読書』、あるいは『冷蔵庫』、『渋谷駅』はきちんと覚えていても、『社会』や『冷水』『時計』は記憶が曖昧だったではないでしょうか。このように並んだ単語を一気に覚えようとすると、たいていの人は、『捕鯨』と『渋谷駅』をよく覚えますが、『冷水』『時計』などの真ん中に出てきた単語は忘れてしまいます。なぜなら、最初と最後の情報が記憶に残りやすいから です。このことは感覚的にも理解できることと思います。
初恋の人は忘れられない
ドラマの1話目や最終回は覚えているけど、間の回はほとんど覚えていない
最初に自己紹介した人は覚えているけど、3,4番目に自己紹介した人のことは覚えていない
これらの例も、最初と最後の情報が記憶に残りやすいことと関係があります。これは、時間でも同じなのです。3時間も続けて勉強すると、最初の30分や最後の30分の勉強は鮮明に覚えているかもしれませんが、間の1時間の勉強はすっぽり抜け落ちてしまうかもしれません。「20分勉強→10分休憩」 ♥♥♥
何度も帰還が危ぶまれた「はやぶさ」 宇宙航空研究開発機構シニアフェロー 川口淳一郎先生 ノーベル賞 京都大学iPS細胞研究所所長 山中伸弥先生 『夢を実現する方法』(致知出版、2013年)
山中先生 この頃、特に忘れられない思い出で、教育大学の学生さんが教育実習に来た時のことです。彼は柔道三役という腕前でした。その人と練習で組み合うと、いとも簡単に投げられる。受け身を取って一本にされるのは悔しいので、先生はちゃんと受け身を取らずに最後まで粘り、変な手の付き方をしてしまいました。そのために、腕がボキッと折れてしまったのです。実習の先生としてみれば、大変なことです。部活動をしている最中に、生徒の腕を自分のせいで折ってしまったのですから。その日の夜、慌てたように先生から電話がありました。電話を取ったのはお母さんですが、そばで聞いていると、先生は受話器の向こう側で平謝りをしている様子でした。しかしお母さんはその時、こう答えたのです。「いやいや先生、気にしないでください。うちの息子の転び方が悪かったんだと思います。怪我したのはうちの息子のせいです。明日からも気にせず、いろんな子を投げ飛ばしてください」 「身から出たサビ」 「おかげさま」 「何か悪いことが起こった時は「身から出たサビ」。つまり自分のせいだと考える。逆に、いいことが起こった時は「おかげさま」と思う。」
成功する人 失敗する人 幸田露伴 『努力論 』 『五重塔』 「 失敗を人のせいにしない」 露伴 「 大きな成功を遂げた人は、失敗を人のせいにするのではなく自分のせいにするという傾向が強い」 「あの時はああではなく、こうすればもっとよくなっていたのでは?」 失敗や不幸を自分に引き寄せて反省し考えることを一生やり続けた人間 と、常に他人のせいに責任転嫁し続け何もしない人間 とでは、かなりの確率で、運の良さがだんだん違ってくることは間違いないでしょう。こうした態度の違いは、長い間に大きな差となって、運のある人とない人の差に、つまりは成功する人と失敗する人の差となって現れることになるのです。幸田露伴 二本の紐 に喩えて紹介しています。一本の紐はザラザラゴツゴツとした針金のような紐で、それを引くと掌は切れ、指は傷つき、血がにじんできます。耐えがたい苦痛に耐えて、それでも我慢して引き続けると、大きな幸運を引き寄せることができます。しかし、手触りが絹のように心地よい感触の紐を引っ張っていると、引き寄せられてくるのは不運だというのです。私が卒業生たちに求められて、色紙や卒業アルバムにサインをする際に、「 力を尽くして狭き門より入れ」(聖書ルカ伝)
尊敬する故・松下幸之助 cf. 中島孝志『ほんとうは失敗続きだった「経営の神様」経営伝―松下幸之助』(メトロポリタンプレス、2011年 「 失敗を素直に認める」 野村克也 「失敗 と書いて成長 と読む」
大切なことは、何らかの失敗があって困難な事態に陥ったときに、それを素直に自分の失敗と認めていくということです。失敗の原因を素直に認識し、「これは非常にいい体験だった。尊い教訓になった」というところまで心を開く人は、後日進歩し成長する人だと思います。 ―『松下幸之助一日一話』(PHP研究所) 「僕はな、物事が上手くいった時にはいつも皆のおかげと考えた。上手くいかなかった時はすべて自分に原因があると思っとった。」 ―松下幸之助
尊敬する経営コンサルタントの小宮一慶(こみやかずよし) 「成功したときは窓の外を、失敗したときは鏡を見る」 松下幸之助 「電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、全部自分のせいだと思え」 一倉 定(いちくらさだむ)
故・高原慶一朗 (株)ユニチャーム 「原因自分論」 「世の中の景気が悪い」「部下がちゃんと働かない」「需要が落ち込んでいる」「上司が認めてくれない」
「あなたのせいだ」と相手を責めたくなったときこそ、その指先を自分に向けよう。「原因自分」の考え方が失敗を生かし、人を成長させる。(高原慶一朗)
企業・政治家・学校現場の不祥事が続いて、その度に責任のある幹部が出てきては謝罪をするのが通例のようになっています。中には「極めて遺憾である」 「残念だ」 「キツネはワナをとがめるが、自分自身をとがめない」 ウィリアム・ブレイク(1757-1827) 「原因自分」 ♥♥♥
巨人の丸佳浩(まるよしひろ)外野手(36歳)
その丸選手 丸選手 「見て感じたことを伝えさせていただきました。球団としても育成選手にも実戦の場を設けてくれている。当然、お金も人手もかかっています。そこに3軍の選手がどういう意識を持ってやってるのかお話をしました」 ソフトバンクホークス 甲斐 周東 牧原大 「なかなかそういう選手がジャイアンツに出てきていない」 「(3軍選手は)一番練習しないといけない立場。何をやらないといけないかの意識改革じゃないけど、そういう意識をどう持っていけばいいか。今の時代に合う指導法をしつつ、どう向上心を持ってやっていけるか」 「新体制になってから、また今までと違った取り組みをしていくという話だった。僕も見ていきたい」 丸選手 丸選手
福岡ソフトバンクホークス 丸選手 桑田真澄2軍監督 駒田徳広3軍監督
丸選手 千賀滉大投手 甲斐拓也捕手 周東佑京選手 牧原大成選手 石川柊太投手 工藤公康 『工藤メモ』(日本実業出版社、2025年) ホークスの育成選手がなぜ大成できるのか?よく言われるのは、「一軍、二軍、三軍がうまく機能しているから」ということです。確かに、ホークスには王会長をトップとしたシステムがしっかり構築されています。二軍のみならず三軍にまで目が行き届き、王会長以下、各監督、スタッフ間で情報の共有がちゃんとなさえている点は12球団随一といってもいいかもしれません。 あともうひとつ、私がホークスの育成力として優れていると思うのは「一芸を伸ばす力」です。「この選手のここが誰よりも秀でている」と見抜いたら、その一芸=長所を徹底して伸ばしてあげる。この見抜く力と育成力があったからこそ、先述した育成出身の選手たちは大きくせいちょうできたのです。甲斐選手は、方の強さとフットワークのよさが大きな魅力でした。だから入団当初はピッチャーをリードする力やバッティングには目をつむり、彼の長所を伸ばすことに注力しました。まずは彼の最大のウリとなるポイントを認めてあげて、経験を積ませたわけです。 (pp.48-49) 育成入団の選手は多いので、活躍できずに消えてしまうケースも多いのですが、中でもどんな選手が育成から這い上がるのかに関しては、活躍する選手の共通点は、投手なら球速・変化球・制球力 強肩・長打力・俊足 負けん気の強さ 甲斐 牧原 周東選手 ソフトバンク 「春季キャンプで今宮健太、松田宣浩など主力選手たちがユニフォームを泥だらけにしてノックを受けていました。豊富な練習量は小久保裕紀監督、松中信彦さんの現役時代から継承されていると聞いて、強さの秘訣が分かりました。ファームにいる選手たちも千賀、甲斐、牧原という育成入団からサクセスストーリーをつかんだスターを見ているので、追いつきたいと練習や試合に取り組むモチベーションが高い。各ポジションで競争のレベルが高いので常に緊張感が漂っていました」 育成契約に限らず、支配下で入団した選手も一本立ちせずに伸び悩むケースも多く見られます。場当たり的なFA補強も一因でしょう。丸佳浩 高橋由伸監督 岡本和真選手 さらには、 巨人の2、3軍で指摘されるのが練習量の少なさです。入団しただけで満足し、周りからは他球団以上にチヤホヤ祭り上げられて、ろくに練習も積まず消えていく選手をたくさん見てきました。ハングリー精神で何としてでも這い上がってやるという気概が足りないのでしょう。巨人を取材するライターは違った見方を示します。「桑田さん、駒田さんが練習をやらせないということはない。質だけでなく量も重視した上で、桑田さんは『自分で何が足りないか考えて取り組まないとダメだよ』と若手の選手たちに伝えていました。ネットスローやウエートトレーニングなど遅くまで自主練に取り組んでいる選手たちはいますし、能力を伸ばしてきて楽しみな選手が多い。育成から支配下昇格した菊地大稀、三塚琉生、ファームで今年結果を残した育成の宇都宮葵星、園田純規はチームの核になれる逸材です。彼らが1軍で活躍すれば、刺激を受けて台頭する選手がどんどん出てくる可能性があります」 丸選手 ♥♥♥
日本の季節・春夏秋冬の移り変わりは、文化風土的にも審美的にも非常にありがたいものです。しかし、その環境にいかに適応するかという点では、人間に一定の苦労をかけるものであることも、考慮に入れておかねばなりません。特に老人は、環境に対する適応能力が著しく落ちるものです。だからこそ、冬は暖かいところにいて、夏は涼しいところにいる方がいいのです。昔の人々が、わりと早くに亡くなっていったのは、冷暖房が発達していなかったので、気温変動にうまく身体を適応できなかった面も大きいのだと感じます。
尊敬する故・渡部昇一先生 ドイツ イギリス 「これでは日本人は、ヨーロッパ人に勉強でかなうはずがない。彼らの一年は、日本人の一年よりも夏の三ヵ月分だけ長いのだから」 クーラー 『知的生活の方法』(講談社現代新書)
ある年、思い切ってクーラーを付けたのである。それはまったく魔法の如きも のであった。夏休み中、まるまる東京にいて勉強できたのである。健康状況は良 くなったとしても悪くはならなかった。疲労しないから体力が落ちないのだろう と推測している。
▲私の一生に大きな影響を与えた一冊です
これはまさに、心の底からの実感であり、先見性に優れた指摘でした。しかし、これをクーラー
しかし、老人は環境適応力が大幅に落ちるるのだから、若い頃と同じ感覚ではいけません。老人の場合には、冷暖房は必須です。加えて言うならば、どのように使うかも十分に気をつけなければなりません。夏の夜、寝る前に寝室を冷房しておくのは構いません。しかし、寝ている間も冷やし続けると寒くなり過ぎます。朝まで冷房をかけて、冷気に当たり続けるのは身体によくありません。寝る前に冷房を切る方法もありますが、それだと、寝ている間に部屋の温度はどんどん高くなってしまいます。朝まで適度な涼しさを維持するには工夫が必要になってくるのです。最近は冷房機能もどんどん進化しているので(タイマーなど)、それを使うのもいいでしょうが、先生は、寝室を直接冷房をせずに別の部屋で冷房をかけて、寝室の戸を開けて寝ることにしておられました。廊下を冷房して寝室の戸を開けておくのが一番いいのですが、廊下には冷房をつけていない家が多いでしょう。たとえば隣の部屋を冷房して、その部屋と寝室の扉を開けておけば、ある程度機密性の高い家ならば同じような効果が出るでしょう。二階建ての家で寝室を一階にしている場合ならば、二階を冷房しておけば冷気が下に降りてきます。暑くも寒くもなく、朝まで快適な室温で寝られるのは、体力も奪われずに済み、誠に幸せと言わねばなりません。
問題は冬です。夏の暑苦しさは、エアコン 暖房 東京 上智大学
その後、先生はドイツ ドイツ セントラルヒーティング セントラルヒーティング 暖房
しばらくしてオイルストーブが日本に入ってきました。イギリス ドイツ イギリス エアコン 暖房 エアコン をどれほどかけても暖気は上にいってしまうのです。部屋全体が温まるほどにかけると、どうしても頭がボーっとしてしまうが、それでも足先は冷たいままです。仕方なく、なお電気スリッパを履いたりしてみたがダメで、小さい書斎に移って、足は小さい電気ストーブで温めたりもしました。
そこで、新しく建てた家の書斎では「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「頭寒足熱」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 エアコン 「床暖房」
暖房 「床暖房」 渡部先生 「床暖房」 「床暖房」 「床暖房」 ♥♥♥
東京・銀座 「カフェーパウリスタ」 明治44年12月 のことでした。このお店は、その後の喫茶店の原型となったとも言われている有名な老舗です。当時、お店の正面にはブラジルの国旗が翻り、夜ともなれば燦々と輝くイリュミネーションの店構えに、人々は胸をときめかせたものでした。店の中に入ると北欧風のマントルピースのある広間、大理石のテーブル、ロココ調の椅子。海軍の下士官風の白い制服を着た美少年の給仕が銀の盆に載せたコーヒーをうやうやしく運んできます。価格は一杯5銭。当時としては超破格値だったために、「 カフェーパウリスタ」
▲落ち着いた「カフェーパウリスタ」の店内
当時、銀座 水上瀧太郎、吉井勇、菊池寛、佐藤春夫、芥川龍之介、森 鴎外、谷崎潤一郎、与謝野晶子、正宗白鳥、徳田秋声、井上ひさし ジョン・ 「 銀 座カフェーパウリスタ」ブラ ジルコーヒーを飲みに行く」ということから、「銀ブラ」 、「あなたは本日、銀ブラを楽しんだ事を証明します」 「銀ブラ証明書」(スタンプカード) 「銀ブラ」 「銀座をブラブラする」 「銀ブラ 本当の意味」 「ブラジル」 「そりゃあ、ないだろう」 「銀ブラ」 「銀座をぶらぶら」 「銀ブラ」 飯間浩明『三省堂国語辞典のひみつ』(三省堂、2014年)
▲『三国』の裏話
『三国』の利用者から次のようなはがきをいただいたことがあります。 「第6版の『銀ぶら』の項目に〈東京の銀座通りをぶらぶら散歩すること〉と説明してありますが、家族に『それは間違いだ』と言われました」 そのご家族の方によれば、「銀ぶら」とは「銀座のカフェでブラジルコーヒーを飲むことだった」と言うのです。「銀座」で「ブラジルコーヒー」だから「銀ブラ」――たしかに、この説は新聞やテレビなどで接することがあります。「銀ぶら」の発祥とされるカフェのこともよく取り上げられます。でも、はたして本当の話でしょうか。 結論から言うと、これはいわゆる民間語源説です。つまり誤りで、残念ながら『三国』としては採用することができません。 「銀ぶら」ということばが使われだしたのは大正時代のことです。『新らしい言葉の字引』(1918年)に〈銀ブラ 銀座の街をぶらつく事〉とあるのが、古い説明のひとつであるようです(『日本国語大辞典』第2版)。大正時代の文章では「銀ぶら」とひらがなでも書かれます。以下は1925年の例です。 〔上略〕「銀ぶら」などゝいふ言葉が流行して、一部の(イカラな連中の間に銀座が憧憬の巷になって居るのなど、余り結構な好みではないと思って居た。 (中村武羅夫『文壇随筆』新潮社161ページ) 「ブラジル」ならばひらがなでは書かないので、この点でも「ブラジルコーヒー」説は疑問符がつきます。最も肝心なのは、古い文章では「銀ぶら」はみな「銀座をぶらぶらする」の意味で使われているということです。「銀座でブラジルコーヒーを飲む」の意味の文章は見当たりません。ことばの使用実態からは、「銀ぶら」は「銀 座をぶらつくこと」と解すべきです。 「銀ぶら」の発生源は慶応大学の学生だとも言われます(水島爾保布『新東京繁昌記』などの説)。一方、日本文学者の池田弥三郎は<われわれ慶応の学生仲間たちも、銀座へでも行こうかとは誘い合ったが、銀ブラでもしようか、とは言わなかった〉(『銀座十二章』朝日文庫)と述べていて、結局、言い出しっぺは分かりません。 『三国』第7版では、利用者の誤解を解消するため、次のように説明を加えています。
ぎんぶら[銀ぶら](名・自サ)〔俗〕東京の銀座通りをぶらぶら散歩すること。〔大正時代からのことば。「もと、銀座でブラジルコーヒーを飲むことだった」という説はあやまり 〕 (下線は八幡) 話としては「銀座をぶらぶら」よりは「銀座でブラジルコーヒー」のほうがおもしろいのは確かです。でも、「おもしろいこと、イコール真実」ではないということにも注意する必要があります。 (pp.60-61) 人の命にかかわるような話でもありませんし、どうでもよいといえばどうでもよいことかもしれません。でも、『三省堂国語辞典』 飯間浩明(いいまひろあき) 「銀ブラ」 ♥♥♥
「旅人検視官 道場修作 長野県 車山高原殺人事件」 内藤剛志(ないとうたかし、70歳) 道場修作(みちばnしゅうさく) 道場修作 諏訪大社 車山高原 奈良半宿 イングリッシュガーデン 蓼 科野菜 信州 そば 天狗水 内藤 西村京太郎先生 十津川警部 今回の舞台は、亡き妻が愛した俳人・小林一茶 車山高原 道場 車山高原 森尾由美 渡辺いっけい 松原智恵子 松澤和輝 道場 道場
内藤 「過去のシリーズでは、亡き妻・由美子が雑記帳に書き記した“あなたと行ってみたい場所”を旅してきたんです。ただ今回は、由美子が以前旅した場所を訪れました。実は由美子が先に訪れた場所に来るのは初めてなんです。それが何よりも今回新しいんじゃないでしょうかね」 「今までの道場シリーズでは必ず近くに海があったんですが、今回の車山にはないんです。車山高原は空に近い場所で、亡き妻・由美子のいる場所を連想させるなと。空を見上げる…僕なりの理由ですが、いつもと少し違う方向を向いているのではないかなと思います」 「このシリーズでは初めて亡き妻がかつて訪れた場所へ引き寄せられてきます。この引力は、今回のドラマが終わっても先に続くと思いますので、皆さんこれからの道場を楽しみにしていてください。言いたいですけど言えません(笑)。大きなことがきっと起きますので、ぜひご覧ください」 ♥♥♥
―今回の台本を読んで 毎回、新しい発見と喜びがあります。過去のシリーズでは、亡き妻・由美子が雑記帳に書き記した“あなたと行ってみたい場所”を旅してきたんです。ただ今回は、由美子が以前旅した場所を訪れました。実は由美子が先に訪れた場所に来るのは初めてなんです。なので、それが何よりも今回新しいんじゃないでしょうかね。由美子がこの地で修作に見せたかったことは何か、というのが今回のテーマのような気がします。 ―舞台となる長野県の魅力 長野県は撮影で何度もお世話になっている場所です。美味しくてきれいな水っていうイメージで、空や山々であったり全てそこから始まっている気がしますね。地元の野菜や蕎麦・米・肉もすべて美味しいです。 今までの道場シリーズでは必ず近くに海があったんですが、今回の車山にはないんです。何が違うかなって考えると、車山高原は空に近い場所で、亡き妻・由美子のいる場所を連想させるなと。空を見上げる…僕なりの理由ですが、いつもと少し違う方向を向いているのではないかなと思います。 そんな空や、この風景の中で皆さんに何か感じていただければ嬉しいです。 ―視聴者の皆様へのメッセージ 素晴らしい風景の中で、誰が犯人か?なぜその事件が起きたのか?を皆さん推理してください。そして、このシリーズでは初めて亡き妻がかつて訪れた場所へ引き寄せられてきます。この引力は、今回のドラマが終わっても先に続くと思いますので、皆さんこれからの道場を楽しみにしていてください。言いたいですけど言えません〔笑〕。大きなことがきっと起きますので、ぜひご覧ください。 VIDEO
かつては民放各局が競って制作しながら、いつしか消えていった2時間ドラマに関して、旅情ミステリーの王道的作品で、主演は“刑事役”といえばこの人、第一人者の内藤
「テレビ局それぞれの事情があって今地上波ではもうほとんどないですね。僕ら作る側として言えば、(これまでは)番組がたくさんありすぎて、何か当たり前にやり過ぎてしまった側面がないか、という反省点はあります」 内藤 日常の死角を切り取ったサスペンスから旅情ミステリーまで、2時間ドラマ枠の歴史は、テレビ朝日 「土曜ワイド劇場」 市原悦子 「家政婦は見た!」 日本テレビ系 「火曜サスペンス劇場」 TBS系 「ザ・サスペンス」 「月曜ドラマスペシャル」 「月曜名作劇場」 TBS系
ところが、2000年代に入ってから陰りが見えるようになります。2005年に「火曜サスペンス劇場」 「土曜ワイド劇場」 「月曜名作劇場」 内藤
「シリーズものは、やっぱり半年たてば新しいもの(続編)があるとか、“次”が保証されているみたいなところがあったんですね」。 内藤 「そうすると『これぐらいの作りでいいだろう』と、べつに手を抜いたわけじゃないけど、どうしても似たものになってしまったんじゃないでしょうか。やっぱり新しいものになっていかなきゃいけない。そこをやり忘れていたかもしれませんね」 放送枠が消えた後も、テレビ朝日系「西村京太郎トラベルミステリー」 「赤い霊柩車」、 「おかしな刑事」
若者を中心としたテレビ離れが急速に進む中、高騰する制作費の割に視聴率が稼げなくなった昔ながらの2時間ドラマは、もはや地上波では新作の制作は厳しいものがあります。BSでも再放送がせいぜいで、新作のレギュラー枠は難しいと思われます。そんな風前のともしび状態の中で始まったのが道場検視官シリーズ 内藤 「刑事ドラマや時代劇もそうですが、悪い人がいて正義の味方がいて、悪い人は捕まるか、罰を受ける。それを親子で見て、人の心が形成されていたと思うんですよね。悪いことはしちゃいけないと知らせる役割が2時間ドラマにはあった。そこはもっときちっとやった方がいい」 内藤 「ご遺体に向き合ってきた仕事柄、人の死に対し非常に心を使う人であり、一方でそこから離れたいとも思っている」 「人生を生き直そうとしている男です。人生はいつでもやり直せる、まだまだ楽しいことがいっぱいあると伝えられたら」 「BSだと出演者とスタッフの距離が近く自由度も高い。地上波よりも小回りが利いて、現場の意見も反映されやすいですね」 「修作は新しい世界を歩みます。視聴者のみなさんも、新しい生活であったりとか楽しさを見つけてみませんか」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はチョコレート オランジェ 松江市内 J. Kowari Pays Natal 米子東高校 米子のHOK 「ひとりじめスイーツ 贅沢(ぜいたく)オランジェ」(410円税込) 栄光堂ファクトリー イオン 米子
▲HOKでは410円。イオンでは368円。ずいぶん値段が違います!
小さく割れたビターなチョコレートにグランマルニエに漬けたオレンジピールを合わせています。ほろ苦さがアクセントになっている大人向けのオランジェ ♥♥♥
この会社は、2019年3月5日に開催された「FOODEX美食女子Award2019」 「ひとりじめスイーツ アップルチョコレート」 米子HOK
【コンセプト】 【オリジナリティ】 【ビジュアル】 【その他】 「ひとりじめスイーツ」 評価ポイントとしては、甘すぎないのでお酒にも合う、リンゴの食べ応えと歯ごたえがしっかりあって少量で満足できる、個包装は仕事の合間などにも食べやすく食べ過ぎも防げそう、パッケージも可愛くて目にとまりやすい、などが挙げられています。♥♥♥
「緊張」 「緩和」 さだまさし さだ 「緊張」 「緩和」 「緊張」 「緩和」 さだ 「アイスクリームとウェハース」 アイス ウェハース アイス ウェハース さだ 文藝春秋 さだ 『噺歌集』 「ぜひ音源で聞きたい」 (株) ユーキャン 「さだまさしステージトーク大全『噺歌集CD』1982~2003」 「さだまさしステージトーク大全2『続 噺歌集CD』2004~2011」 「妖怪かっ飛びジジイ」 「お父さんとポチ」 「エレクトーン『ハイ』事件」 「23時間57分の一人旅」 さだ 「大全3」 さだ 「ウェハース」 「腹立つよね。『歌は帰ってからCDで聞きますから、もっとしゃべってください』というお客さんがいるからね。もちろん、もっと歌ってほしいというお客さんもいるけど、どうも世間では『さだまさしコンサート=トーク』とみられている。これは何とかしたいと思う」 〔笑〕。
2011年秋、翌年に予定していた歌手生活40周年記念ツアーの企画会議で、さだ 「歌を取るのか、トークを取るのか。お客さんにまともに突きつけてみるのはどうだろうか?」 「さだまさし」 さだ 「一度やってみたかったし、やるならまだ体力がある今しかないと思ったね。70歳では多分無理だろうからね」 「さだまつり」 長崎 「さだまつり」 「前夜祭」 「しゃべるDAY」 長崎ブリックホール さだ 長崎 長崎 「紫陽花の詩」「精霊流し」「島原の子守歌」「邪馬臺」「神の恵み」「かすていら」 「Birthday」 「ウェハース」 「お客さんに一切れのかすてぃらをお出しして、差し向かいでじっくりゆっくりしゃべり尽くす。いわば『かすていらナイト』だね」。 「後夜祭」 「うたうDAY」 「きだまきしとテキトー・ジャパン」 「豪華メンバーと一緒に新鮮でたくさんの具材がてんこ盛りのチャンポンを囲んで、みんなでパーティーのように賑やかに騷ぐ。こちらは『チャンポンナイト』だね」 。 二日間で完結する「さだまつり」 「後夜祭」 「前夜祭」 「前夜祭」 「後夜祭」 「前夜祭」 「前夜祭」 「後夜祭」
コンサートツアーも終盤に差し掛かった2012年11月23日、福岡サンパレス 「さだまつりツアーを振り返って」 さだ 「もう二度とやらない企画だね。しゃべるだけがこんなにつらく、歌うだけがこんなにつらいとは思わなかった」 さだ 「緊張」 「緩和」 アイス ウェハース さだ 「ただ、お客さんも明確な答えを見つけたと思う。普段の何でもないコンサートがいかに優れていたかってね」 さだ 「さだまさし的なもの」 「さだまつり」 さだ 「さだまさし的なもの」 さだ さだ 「さだまさしコンサートは、歌とトークの絶妙なバランスで成り立っている」
私も2012年9月28日~29日、そんな「 さだまさし40周年記念コンサート」(旧・広島厚生年金会館) 「前夜祭」 「線香花火」「親父の一番長い日」「長崎小夜曲」「かすてぃら」「驛舎」「BIRTHDAY」 「虹 」 雪村いずみ 「十津川村のヘビ女」「妖怪かっとびジジイ」「23時間57分の二人旅」 高校入試 再び第二夜は「後夜祭」 一部 は「もう来る頃」「春爛漫」「サクラサク」「転校生」「まんまる」「決心~ヴェガへ」「かすてぃら」「TOKYO HARBOR LIGHTS」「東京」「夢ばかり見ていた」 二部 は「きだまきしとテキトージャパン」 第三部 へなだれ込みます。さだ さだ 三部 で大サービスのヒット曲オンパレードでした。定番の「精霊流し」「無縁坂」「雨やどり」「秋桜」「案山子」「道化師のソネット」「北の国から」「関白宣言」の最後のラララ 「風に立つライオン」「糸遊」「女優」「あなたへ」 ( 岩崎宏美 「スマイル・アゲイン」「主人公」 さだ いかにバランスのとれたもの (!)〔笑〕であったかを痛感した二日間でした。私はここでバーバリー ♥♥♥
「大学入学共通テスト」 難関大学
大学入試センター 「試験問題評価委員会報告書」 次年度の試験を予想する上で、これは本当に貴重な資料です 。実は、今までこの報告書を読むと、次年度の問題傾向や、初めて出題された新傾向問題が次年度にどうなるのかを占うのに、ずいぶん役立つということを実感してきました。「こんな問題すぐ消えてなくなるよ」 「いやこれは来年も絶対出題される!」 「 追試験」 新傾向の問題が登場する際には、その前年の追試験で予告リハーサルが行われてきた ことは、私たち英語教師なら誰でも知っていることです。 「大学入学共通テスト問題評価・分析委員会報告書」 では3種類の報告書が公開されています。 (1)「高等学校教科担当教員の意見・評価」 (2)「教育研究団体の意見・評価」 (3)「問題作成部会の見解」 「共通テスト」 本試験 追試験 「共通テスト」 ♥♥♥ 【リーディング】 ・大問構成は昨年通り(第1問~第8問) と予想しています。第4問と第8問が昨年の新形式です。 ・複数箇所対応問題 《難》 「共通テスト」 センター試験 ・ 複数解答問題 《難》 ・時系列並べ替え問題 ・「意見」と「事実」問題 …「なくなる、なくなる」と噂されている問題ですが、私は必ず出題されるものと予想しています。小・中学校で小さい頃からネット情報の真偽について教育がなされていることからも、現代におけるこの重要性を認識した背景があります。 ・第6問は「心温まるいい話」 本試験・追試験 ・NOT問題 not/ error/ remove といったキーワード ・推測問題 「共通テストR」 の特徴で、本文に直接書いていないことを、書かれた内容から推測して答える問題です。設問では、most likely/ imply/ infer といったキーワード ・要約・タイトル付け問題 第1段落 ・最終段落 が大きなヒントになることを確認してきました。・図表・グラフ・イラスト問題 【リスニング】 《難化予想》 リスニング平均点 ・大問構成は従来通り
「大学入学共通テスト」 「 不正行為」 大学入試センター 「大学入学共通テスト」 不正行為 「共通テスト」
大学入試センター 不正行為 「解答はじめ」 「解答やめ」 「解答やめ」
現在の学習指導要領を反映して初めて実施された昨年の「共通テスト」
2日間を通じた再試験の対象者は128人で、体調不良者などを対象とした追試験と併せて1月25日と26日に実施されました。本番に向けて最高の体調で臨みたいものです。
私は毎年本番終了後の翌日に、「共通テスト」 「共通テスト」 ♥♥♥
お正月の風物詩『箱根駅伝』 青山学院大学 青学大 青学大 原監督 青山学院大学 小田和正 「Far East Cafe」 箱根駅伝
▲緑豊かな本学キャンパス
2004年の就任後、さまざまな逆境をはねのけ、箱根路の頂点を極めてきました。監督就任と同時に原監督 「タイムじゃない。表情や私生活を見ると分かる。合宿所で一緒に暮らしずっと見てきた強みですね」
2004年 予選落ち
2005年 予選落ち
2006年 予選落ち
2007年 予選落ち
2008年 22位
2009年 8位
2010年 9位
2011年 5位
2012年 8位
2013年 5位
2014年 優勝
2015年 優勝
2016年 優勝
2017年 優勝
2018年 2位
2019年 優勝
2020年 4位
2021年 優勝
2022年 3位
2023年 優勝
2024年 優勝
2025年 優勝
2003年中国電力のの社員だった原 原監督 「選手の前で謝ってください」 10年間の苦労 でした。「前の優勝は監督が主導したが、次はおまえらが勝ち取ってヒーローになれ」
青学大の原監督 原監督 「自分で考えなさい」 「指導者から言われた練習をしているだけでは絶対に強くなれませんよ」 「学生が練習メニューなどについて、『僕はこう考えます』と言ってきたら、私と正反対の意見でも、まずは思うようにやらせます。それを踏まえて最善の策を考えればいい。その方が学生も納得します。」 異端を恐れない。大学駅伝界の異端児を自認する原監督 「青学は浮かれている」 「陸上で活躍すれば野球やサッカー選手のようにテレビに出演できる」 「出るくいは打たれるが、出過ぎたくいは打たれない」 原監督 原監督 「ぼくはファーストペンギン。最初にやる人はたたかれますから。」 原監督 「ただの儀式」 「丸刈り」 原監督 「体育会特有」 「ミスをしたら丸刈りの罰は意味がないのでは。丸刈りにすればいい、という考え方になってしまう」 原監督 「指導しない指導」 学生寮の掃除当番は1年生だけではなく、4年生を含めた全員が担当します。「4年生には“いばるな”と言っている。掃除など嫌なことは進んでやる。それがお兄ちゃんの役目」 原監督 全日本大学駅伝 「もっと引き締めた方が良い」 全体ミーティングでも「1年生だろうが、正しいと思ったことは言いなさい」 *************
今年は歴史的な逆転劇でした。青学大の1区は16位でした。直前にランナーの変更がありました。 1区を走る予定だった選手が2日前に胃腸炎になり、4区を走る予定だった小河原選手 平松選手 黒田朝日選手 青学大 原晋監督 「5区には黒田朝日がいる。3分30秒先頭と離れていてもなんとかするだろう」 「ギリギリだった」
私はもちろん、テレビの前で箱根駅伝に釘付けになっていました。第102回大会となった今年の箱根駅伝、往路からとんでもないドラマが待っていましたよね。特に5区の山登り。あんな展開、誰が予想できたでしょうか?小田原中継所の時点で、トップの中央大学と青山学院大学 「さすがの青学でも、このタイム差は厳しいかも…」 黒田選手 原監督 「箱根史上最強ランナー」「シン・山の神だ!!」
なぜ、青学大 黒田朝日選手 「山の神」 黒田選手
彼の走りの秘密は、ここにあります。
エンジンの大きさが違う標高差800m以上を駆け上がるには、酸素をたくさん取り込む能力(心肺機能)が必要です。マラソンで鍛え上げた彼の心臓は、他の選手よりも圧倒的に「エンジン」が大きいんです。だから、苦しい坂道でも出力が落ちないんですね。
下り坂でも加速するスタミナ5区は登り切った後、最後に芦ノ湖へ向かう下り坂があります。多くの選手は登りで足を使い果たしてしまい、ここでペースが落ちがちです。ところが黒田選手
結果として、トップを走っていた中央大学に対し、この区間だけで4分以上の差をつけることになりました。3分24秒の借金を返すどころか、お釣りがくるほどの快走。これが「新・山の神」
黒田選手 原晋監督 「なぜエースを平地の2区で使わなかったの?」 「花の2区」 原監督 「リスクとリターン」
2区の場合(ハイレベルな混戦)エースを投入しても、他校のエースも強いため、稼げるタイム差は数十秒程度に限られます。
5区の場合(差がつきやすい)山登りは特殊なコースなので、適性のない選手や調子の悪い選手が走ると、平気で2分、3分と遅れてしまう「大ブレーキ」のリスクがあります。
原監督 「最もタイム差がつきやすく、失敗のリスクが高い5区」 「チームで一番信頼できる黒田選手」 「不確実な要素(山)」 「確実な資産(黒田選手)」 黒田選手 「黒田くんは2区に来るのか?5区なのか?」 もう一つ、青学の強さを支えているのがメンタル面です。原監督 「輝け大作戦」
「結束」から「個」へこれまでは「チームの絆」を強調してきましたが、今年は一歩進んで「一人ひとりが輝くこと」、つまり「個人の能力を最大限発揮すること」を求めました。
プレッシャーを「楽しむ」力「失敗してはいけない」と縮こまるのではなく、「自分が主役だ、輝く場所だ」と捉え直す(リフレーミングする)ことで、選手たちは過度な緊張から解放されます。
実際、黒田選手 「記録は狙っていなかった」 「楽しむメンタリティ」
史上初となる2度目の総合3連覇を達成した絶対王者は、一昨年9月にリニューアルした寮をフル活用して、食事面、メンタル面で大きなプラスとなっていました。以前の寮は調理する設備が整っておらず、業者が配達した食事を摂っていました。しかし、現在はOBで栄養士の鶴貝彪雅 原監督 美穂 「温かいご飯を食べれたり、ちょっと体調が悪い子に対してだったり、一人ひとりに合わせて提供ができている」 「今までだったらクリスマスやお正月でも関係なしで普通の料理しか来なかったけど、今はイベント食みたいなのを考えている。年末にはおせち料理的なものをつくったので、学生も喜んでいるんじゃないかな」
さらに食堂兼ミーティングルームが憩いの場になっています。選手たちにとって原監督 美穂 鶴貝 美穂 「食堂に行ったら話を聞いてくれる人がいるのって結構いいじゃないですか。緊張した時に抜いたりとか、ちょっと話したい時に話したりとか、そういった部分では(ストレスなどの)はけ口にはなっていると思う」 青学
前回大会の主力メンバーが6選手も卒業して抜けました。今季は新チーム結成時に原監督 「箱根駅伝、勝つ確率は0%だよ」 「青学大は往路で選手を使い切った。復路での逆転はある」 美穂 「毎年学生のすごさを身に染みて感じる。本当に急に成長しちゃうのでうれしい」 佐藤有一選手(4年) 黒田選手 「こういうところが競技力につながると思って全員に呼びかけた」
昨年2月に血液のガンで亡くなったチームメートの皆渡星七(みなわたりせな、21歳)選手
東海地区の中京大学出身の原監督 「私自身が箱根駅伝を走ったことがないからこそ、試行錯誤の経験の中で『箱根駅伝を勝たせるためにどうするか』という戦略を作り上げた」 青山学院大学 原監督 「技体心」 「正しいノウハウを持って一年間鍛えていけば選手はものすごく成長し、身体も出来上がって、最後には『勝つ』心意気になる」 原監督 「今回の常識は、明日の非常識です。我々もリミッターを切らなければならない」 ♥♥♥
▲島根県庁前の看板
この秋より朝のNHK連続ドラマ、松江を舞台にした「ばけばけ」 小泉八雲 セツ 松江城 八雲 セツ 「あげ、そげ、ばけ」
▲市内のバス停
松江市内 バス停 バス停 「あげ、そげ、ばけ」 松江市交通局 「市内中心部のバス停を、このイラストとキャッチコピーに、リニューアルしたいので、協力してほしい」 「プロジェクトゆうあい」 バス停 バス停 バス停 「プロジェクトゆうあい」 バス停 松江 松江市総合体育館 バス停 「 スサノオマジック」 デザイン のバス停 朝ドラの「ばけばけ」 「ゆうあいレポート」最新第53号 コチラ で読むことができます)。
リニューアルしたのはバス停 JR松江駅 「ばけばけ」 ♥♥♥
1月4日東京ドーム、2021年東京オリンピック(五輪)柔道男子100キロ級金メダリストのウルフアロン(29歳) NEVER無差別級王座戦 EVIL ウルフ 「これから先、もう柔道着を着て戦うことはないというアピール。頭は今朝、丸めた。入門した段階で決めていた」 EVIL 「朝日新聞」 アントニオ猪木
▲1月5日「朝日新聞」
1月3日の前日公式記者会見でいきなり殴りかかったEVIL 「お前が負けたら丸刈り並びに柔道禁止だ」 「やります」 「そのためにも負けられない」 EVIL ウルフ 「拷問の館」(HOT) EVIL 「1月4日デビュー戦。EVILとやらせて下さい」 「(EVILは)力を持った選手と思っていますが、ひきょうな凶器攻撃や反則をしてくる。稀に見るタチの悪い選手。スポーツマンシップの真反対にいる。正々堂々と倒すだけ」 ウルフ 嘉納治五郎
入場で柔道男子日本代表の鈴木桂治監督 小川直也 石井慧 「これだけ大勢が見てくれる中で試合をしたのは初めて。体に力が入らなくなったときに意識とは別のところで体が動こうとする感覚があった」
ゴングが鳴るとエルボー合戦を展開。柔道技で投げ捨てコーナーポストにEvil Evil Evil ウルフ Evil 「行くぞー!」 棚橋弘至 ウルフ ドン・ファレ Evil Evil 「これだけ大勢の人が見てくれるなかで試合をしたのは、僕の人生で初めてでとても大きな経験になりましたし、今日だけではなくこれからもずっとこれだけの人数に見られながら試合がしたいと思いました」 「おごってしまうと足をすくわれる。しっかり地に足をつけて成長する」 「正直、今日の勝利はビギナーズラック、どれだけ対策をされても、その上を行けるプロレスラーを目指していく」
くしくもデビュー戦の舞台がプロレス史に一時代を築いた棚橋弘至 オカダカズチカ 「運命的なものを感じる。棚橋さんが培ってきたものを、新しい形にもっともっと追求していきたい。プロレスは大きなバトン。いろんな形につなげていきたい」 ウルフ ♥♥♥
and so on =「など」 「など」 and so on and so on and so on and so on and so forth と同義です(ややフォーマル)。「などなど」というふうにさらに強調するために、…and so on and on, …and so on and so forth, …and so forth and so on とすることもあります。 商業文や学術書、専門書などではetc. を使います(書き言葉)。etc. はラテン語のet cetera の略でthe rest (残り)という意味です。 一方、日常会話ではand so on, and so forth でさえ少し堅い印象があるので、and all that, and things like that, and stuff like that などを使います。
and so on 「など 「など」 and so on 【1】and so onは人に対しては使いません。 【2】and so onは同類のものをリスト化するときに使います。 【3】and so onには相手が「同類のもの」を予想できる文脈が必要です。 【1】and so onは人に対しては使わない 1つ目の違いは、and so on and so on, and so forth, etc.の どれも人に対しては使いません。モノや物事に対する「など」として使うことが定例となっています。使っても文法的には正しいのですが、失礼な感じになるので、避けた方がよいでしょう。 代わりにand some others を使います。
【2】and so onは同類のものをリスト化する 2つ目の違いは、and so on など を買った」の「など」にand so on
【3】and so onには相手が「同類のもの」を予想できる文脈が必要 3つ目の違いは、同類のものをリスト化するにしても、and so on
and so on この文章は、リンゴ、オレンジ、バナナ…などでフルーツが続くことが予想できますよね。 なので正しいand so on 「ここから先は言わなくても推測できるでしょ」
We need to buy some vegetables like carrots, potatoes, onions, and so on.(にんじん、じゃがいも、玉ねぎなどの野菜を買う必要がある。)ここでは、and so on
She is smart, creative, hardworking, and so on and so on
×We went to London, Oxford, and so on.
and so on and so on and so on and so on and some other~ と言わねばなりません(デビッド・バーカー『英語じょうずになる事典(下)』(アルク、2017年)
『大学入試英語熟語最前線1515』(研究社、2024年) 「▲このsoは「そのように、同じ調子で」の意味。onは<継続>の用法。同様な例が続くことを示す表現」
etc. etc. フォーマルな表現 「など」 etc. 「~など」 「など」 「etc.」 etc. 「, etc.」 etc +ピリオド」 です。前の部分には例が続くためカンマとスペース1つが必要になります。具体的な例を列挙した後にカンマ(,)で区切ってその後にetc. etc. etc. 「etc.」 etc.. 」と2つピリオドを打つ必要はありません。etc. etc. etc. etc. etc. and the like :意味は「など」ですが挙げられた例は類似している必要があります。such as :意味は「など」ですが挙げられた例は前の言葉に含まれる必要があります。We saw lots of lions, tigers, elephants, etc.
と書かれていて、例えば「A, Bなど」のように2つ以上のものをリストアップした後にくっつけて、同じカテゴリーの似たようなものが他にもあるけど全てを書かない(書く必要がない)時に、この “etc.”
逆に言うと、“etc.” “etc.” “etc.” “etc.”
We saw lots of cars, trees, people, etc.
とは言えません。同じカテゴリーのものではなく、“etc.” etc. etc. such as ジェームズ・M・バーダマン『英語のワナにはまるな!これが正しい選択だ!!』(IBCパブリッシング、2013年) ♥♥♥
◎無事ですのでご安心ください! 1月6日(火)10時18分、松江市 震度5強 の強い地震が襲いました。私は近くのガソリンスタンドでファンヒーターの灯油を給油している真っ最中でした。今までに経験したことがないような地面がバウンドするような激しい揺れでした。ガソリンスタンドもパニック状態です。すぐに家に帰ると、さらに3回ほど強い揺れが襲ってきました。本当に久しぶりの地震で恐ろしかったです。前日の5日夕方、震度2の地震がありましたから、これが予兆だったのでしょう。私は早めに休んでベッドの中で揺れを感じておりました。震源は安来市広瀬町布部 広瀬町
******************
今日の話題です。social suicide 「社会的自殺」 松下佳世(まつしたかよ) social suicide suicide といえば「自らの意思で命を絶つ」 松下
そのまま「ソーシャル・スーサイド」 「仲間外れ」
social suicide 「社会的信用・評判・人間関係を大きく失う行為や状態」「自ら社会的つながりや役割を断ち孤立すること」「強い社会規範に反する行動によって社会的に終わること」 commit を伴って、自ら社会的つながりを絶つことを意味します。例えば、宗教や性的指向を告白して親族から勘当されたり、虐待を受け親と絶縁したり、前述の若者のように、仲間外れや集団無視によって孤立したりするケースなどが当てはまります。文脈によって、「仲間外れにされる」「村八分にされる」「社会的に自滅する/社会的に終わる」「信用を失う」「評判を台無しにする」「社会的に孤立する」 このように、suicide という名詞は、「自殺」や「自殺者」を表すだけでなく、比喩的に「自殺するようなものだ」 「自ら自分の生命を絶つこと、自害」(広辞苑) suicide は上記の意味に加えて、“You say that people commit suicide when they deliberately do something which ruins their career or position in society.” (自分のキャリアや社会的地位を故意に破滅させる行為のことをsuicideと言う)となっており(『コウビルド英英辞典』 「自殺」 「自滅」
social suicide 「社会的自殺」 「社会的な立場・評価・信頼・人間関係を自ら壊してしまう行為や状態」 social suicide social suicide
空気を読まない発言をして、周囲(学校・職場・オンラインコミュニティ)から一気に距離を置かれる。
炎上するような投稿をSNSにして、信用を失う。
ルールやマナーを無視して、学校や職場で孤立する。
グループ内で致命的な裏切りをする。
Posting that comment would be social suicide
He committed social suicide
Quitting without notice is career――and social suicide
She chose social suicide
使われ方のニュアンスとしては次のことが言えるでしょう。♥♥♥
比喩表現(かなり強い言い方)
「それをやったら終わる」「社会的に致命的」という警告や皮肉として使われることが多い
カジュアルな会話やネットスラングでも使われる
教えている高校生・浪人生の書く英作文をじっくり観察していて、unknown 「自分の知らない」 unknown words (自分の知らない単語)とやってしまうのです。でもこれでは「世間一般に知られていない言葉」 words I don’t know と書けばいいのです。例えば、an unknown writer と言えば、有名でない、あるいは世間一般にその存在を認められていない作家のことを指します。少なくとも一般的に(=圧倒的多数の人々に)知られていない、ということを示唆する単語なのです。基本単語なんですが、結構英語のできる日本人高校生もやりがちな誤りです。2023年に発刊された『ライトハウス英和辞典』(第7版、研究社) 「誤用注意報」
♥♥♥ Unknown to 『ライトハウス英和辞典』第7版
メリアムウェブスター社(Merriam-Webster) “2025 Word of the Year” slop slop 「ぬかるみ/泥」 「残飯のような水っぽい食べ物(飼料)」 “ぐちゃっとした価値の低いもの” 「AIでたいてい大量生産される低品質なデジタルコンテンツ」
メリアムウェブスター社 「不条理な動画、常軌を逸した広告画像、安っぽいプロパガンダ、かなりリアルに見えるフェイクニュース、ジャンキーなAIが書いた本」 Merriam-Webster社 「AIドロドロ」 グレッグ・バーロー社長 「私たちの画面には、ありとあらゆるものが投棄されています。「ワード・オブ・ザ・イヤー」はそれをたった4文字で表現した。英語はまたもや、その真価を発揮したのです」 バーロー社長 「この言葉は、とても分かりやすい言葉です。「AIという革新的なテクノロジーの一部であり、人々が魅力的で、腹立たしく、そして少しばかげていると感じるものです」。「Slop 」は1700年代に柔らかい泥を意味する言葉として使われ始めたが、より一般的に価値のないものを意味するようになった。その後、定義は拡大し、「人工知能によって通常大量に生産される低品質のデジタルコンテンツ 」を意味するようになった。」 「不条理な動画、奇妙な広告画像、安っぽいプロパガンダ、本物そっくりのフェイクニュース、ジャンキーなAIが書いたデジタル書籍などだ」
Merriam-Webster社 2024: polarization 2023: authentic 2022: gaslighting 2021: vaccine 2020: pandemic 2019: they 2018: justice 2017:feminism 2016: surreal 2015: ism メリアム・ウェブスター 「gerrymander」、「touch grass」、「performative」、「tariff」、「six seven」、「conclave」 「Lake Chargoggagogmanchauggagoggchaubunagungamaugg 」 Roblox merriam-webster.com で最も検索された単語のリストに登場するようになりました。
メリアム・ウェブスター 「パンデミック 」 「ワクチン 」
日本の「流行語大賞」は、高市総理 「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」
◎Macquarie: AI slop オーストラリア英語の標準辞書として知られるMacquarie “Word of the Year 2025” AI slop を選出しました。さらにPeople’s Choice(一般投票)
definition low-quality content created by generative AI, often containing errors, and not requested by the user(生成AIで作られた低品質なコンテンツ。誤りを含むことが多く、ユーザーが求めていないのに出てくるもの)
◎Oxford: rage bait イギリスの “Oxford Word of the Year 2025” rage bait 。rage は「激しい怒り」、bait は「(釣り針の)えさ」=人をおびき寄せる“えさ”という意味で、オックスフォード大学出版局
definition online content deliberately designed to elicit anger or outrage, typically posted in order to boost traffic or engagement(怒りや憤りを引き出すよう意図的に作られたオンラインコンテンツ。通常はトラフィックやエンゲージメントを増やす目的で作られる)
◎Collins: vibe coding イギリスの Collins “Word of the Year 2025” vibe coding でした。vibe は「雰囲気/感じ」を意味し、細かな仕様を厳密に詰めるというより“こんな感じで”とAIに自然言語で指示してコード生成する開発スタイルを指します。Collins プログラミングが「構文を正しく書く」から「やりたいことを言語化して依頼する」へと重心移動していることを、象徴的に表しています。
definition an emerging software development that turns natural language into computer code using AI(AIを使って、自然言語の指示をコンピューターコードに変換する新しいソフトウェア開発手法)
その他の辞書による今年の“Word of the Year 2025”
◎Cambridge Dictionary: parasocial イギリスの Cambridge Dictionary parasocial を“Word of the Year 2025” 「一方通行の関係(片方向のつながり)」
definition involving or relating to a connection that someone feels between themselves and a famous person they do not know, a fictional character, or an artificial intelligence(面識のない有名人や架空の人物、またはAIに対して、人が“つながり”を感じる関係に関すること)
◎Dictionary.com: 67(six-seven) Dictionary.com “2025 Word of the Year” 67(“six-seven”) を選定しています。67 はアルファ世代(Gen Alpha:一般に2010〜2024年ごろ生まれ)の間で広がった数字スラングです。楽曲のフレーズなどをきっかけにミーム化し、両手を天秤のように動かすジェスチャーとセットで、「まあまあ」「どっちとも言えない(たぶん)」「微妙」などの曖昧な返事として使われることがあります。ニュース見出しやSNSトレンド、検索結果など複数データを分析して選んだことも説明されています。
definition a viral, ambiguous slang term used among Gen Alpha; some use it to mean “so-so” or “maybe”(アルファ世代(Gen Alpha)の間で使われる、拡散した曖昧なスラングを指すこと。文脈によって「まあまあ」や「たぶん(どっちとも言えない)」の意味で使われることがある)
2025年は、各国の主要辞書がそれぞれの視点から「AI時代の言葉」 “Word of the Year”
辞書
2025
ざっくりと意味
Merriam-Webster
slop AIで大量生産される
Macquarie
AI slop 生成AIによる低品質コンテンツ
Oxford
rage bait 怒り・憤りを意図的に引き出して
Collins
vibe coding 自然言語の指示でAIにコードを
主要辞書の選定語を並べてみると、①AI生成物の氾濫(slop / AI slop) ②感情(怒り)を燃料にした経済(rage bait) ③制作手段そのものの変化(vibe coding) ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週は漬け物
▲「かつくら漬け」 いくらでもご飯が進む!
京都 「名代とんかつかつくら」 トンカツ 海老フライ 「かつくら漬け」
「かつくら漬け」 広島菜(ひろしまな) 胡瓜 ゴマ 広島菜 広島菜 「かつくら漬」 「かつくらオンライン」 「かつくら」 漬物壺 竹トング ♥♥♥
受験界では、as soon as possible = as soon as one can「できるだけ早く」 柏野健次『英語教師のための語法ガイド』(大修館、2025年)
多くのネイティブ・スピーカーは、as soon as you canは時間的余裕があることを表し、「できるだけ早く」という意味であるのに対してas soon as possibleは「緊急性」(urgency)を表し、「至急」という意味だと指摘します。(同書p.18) 私の調べたところでは、 as soon as possible
一般的で広く使われる表現
「可能な限り最速で」という意味
相手に対する依頼・要望でよく使われる as soon as possible
👉 「可能な範囲で最速」 as soon as one can
硬くてフォーマルな響き
“one” は一般の人を指す形式的な代名詞
「(その人が)できる時に」という意味合いが少し強い
as soon as possible as soon as you can
👉 相手の事情をある程度尊重しているニュアンスですね。両者のニュアンスの違いをまとめると次のようになるでしょう。
表現
直訳
ニュアンス
as soon as possible 可能な限り早く、至急
一般的・急いでほしい度が高い
as soon as one can / as soon as you can (その人が)できる時に早く
もっと穏やか・相手の都合を踏まえた感じ
結論的には、意味はほぼ同じ「できるだけ早く」 ♥♥♥
as soon as possible = 急いで!(少し圧がある)⇒指示感 cf. ASAP「大至急」
as soon as one/you can = 無理しない範囲で急いでね(柔らかい)⇒丁寧な依頼
ニュース番組(CNN)を見ていて「firefighter’s approach」 「えっ?消防士のアプローチ?…?」 松下佳世『同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ』(イカロス出版、2020年)
経営企画部の部長が、自社の課題や実施中の対策について説明をしたのに対し、コンサルタントが、This is just a firefighter’s approach.とコメントしました。表情はやや険しく、プレゼンを褒めているようには聞こえません。しかもコンサルタントはあえてjustまで入れて、「~にすぎない」「単なる~である」と強調したわけです。 使われている単語だけ見れば、中学生でも簡単に和訳できそうな単純な一文に見えます。Approachはいまやカタカナの「アプローチ」として、名詞でも動詞でも頻繁に見聞きする単語であり、ここでは名詞として使われていることは明らかです。複数の意味を持つ単語だとはいえ、状況から考えて「やり方、手法」などが無難であることはすぐに判断がつきました。 さて、問題はこのfirefighterをどう訳すかです。「消防士の手法」でいいのだろうか、と一瞬迷いました。直訳したとしても、話し手の意図したメッセージを伝えられなければ、通訳者としての仕事をまっとうしたことにはなりません。とはいえ、翻訳のように時間をかけて辞書やインターネットで調べることもできないのが通訳の辛いところです。 コンサルタントが発言をしてから、ここまでの思考に至るのにものの一秒ほどしかかかっていなかったと思いますが、この時は時計の針が止まったかのように感じました。納得がいく訳が思い浮かばないまま、「いまご説明くださった対策では、消防士的なやり方にすぎません」と訳すしかありませんでした。 両社の担当者同士の会話はそのあとも続きました。先ほどのことに気を取られていては、その後の通訳に影響が出てしまうので、頭の片隅に消防士さん一人を残しながら業務を続けました。すると、何ということでしょう。その後のやり取りでヒントが出てきたのです。 初めはわからなかった話し手の真意が、発言を聞いているうちにふとわかるということがあります。これは通訳だけでなく、家族や友人、近所の人との会話でも経験することではないでしょうか。まさに、待ちわびていたその瞬間がやって来ました。 消防士は通常、火災が発生してから初めて現場に向かい、消火活動に従事します。コンサルタントはそのことを指してfirefighter’s approachと発言していたのです。つまり、部長が説明した自社の課題と対策が事後的、場当たり的な「予防策を諧じていない手法である」とコンサルタントは伝えたかったようです(もちろん、消防士が予防措置を一切取っていないわけではありません。市民が安心して暮らせるように火災を防ぐための啓蒙活動を行っていることは、世界中で活躍する消防士の皆さんの 名誉のために付け加えておきます)。 ようやくコンサルタントの発言の意図に気づき、その後の会議の中でさりげなく「消防士的なやり方」を「事後対策」に言い直したのは言うまでもありません。今後どこかの会議で「firefighter’s approachはよくないから、予防策を講じよう」という発言が英語で出たときには、迷わず「事後の百策より事前の一策」とかっこよく日本語に通訳してみたいものです。 覚えておこう! Firefighter approach =予防策を講じていない手法 (pp.14-15) 辞典にはどこにも載っていない表現なので、ChatGPT “f irefighter’s approach” 「問題が発生したときにその場しのぎで素早く対処し、とりあえず“火消し″することに重点を置くやり方」 ・ 根本原因の解決よりも、緊急対応を優先する ・ 火事を消すことに注力するために、予防や長期的な対策よりも、発生した現在の問題を消火するように即時対応する ・ 長期的改善より短期的・応急的な解決策に偏る傾向
この表現はビジネスやIT運用、マネジメント、プロジェクト管理、医療、教育など幅広い分野でよく使われ、「いつもトラブルに追われている状態」 「恒常的に火消し対応をする仕事の仕方」 firefighter’s approach で、根本的な改善ができていない」firefighter’s approach だけでは問題が繰り返されるだけだ」
“ f irefighter’s approach” ♥♥♥
Our team has been relying 0n a firefighter’s approach
The firefighter’s approach We need a long-term strategy, not just a firefighter’s approach
Management keeps using a firefighter’s approach
The IT department is stuck in a firefighter’s approach
To move forward, we must shift from a firefighter’s approach
A firefighter’s approach Our team is stuck in a firefighter’s approach
A good manager should move beyond the firefighter’s approach
In crisis management, a firefighter’s approach
When the server crashed, the team’s firefighter’s approach
新年明けましておめでとうございます。
いつもこのブログをご覧いただきありがとうございます。無事に新年を迎えることができたことに感謝しているところです。たくさんの方々にご覧いただいているこのブログですが、毎朝喫茶店や電車の中で原稿を手直しながら掲載しています(写真下)。
米子東高校 勝田ケ丘志学館 昨年は以下のような活動をしました。
◎1月18日(土) 「共通テストリーディング・リスニング」のベネッセの電話取材
◎3月18日(火) 講演「英語は絶対に裏切らない!」岡山県立笠岡高等学校2年生
◎5月 『直前 問題演習 2026共通テスト 英語リーディング 』 (ベネッセ)
◎6月11日(水) 講演「英語は絶対に裏切らない!」鳥取県立米子東高等学校3年生
◎11月 『重要問題演習 2027共通テスト 英語リーデイング』(ベネッセ) 旅行は神戸 「須磨シーワールド」「南京町」 京都 「鉄道博物館」・「京都水族館」・「京都市京セラ美術館」 長谷川晶一『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』(文藝春秋、2025年12月)、 川相昌弘『川相塾「指導者は何を教えればいいのか」 』(日本写真企画)、工藤公康『工藤メモ「変化に気づく、人を動かす最高の習慣」』(日本実業出版)、小宮一慶『経営の教科書 成功するリーダーになるための考え方と行動[増補改訂版]』(ダイヤモンド社)
今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんのご健勝を祈っております。♥♥♥
株式会社・JTBパブリッシング 『JTB時刻表』 水戸岡鋭治(みとおかえいじ)先生
表紙には、先生が以前からずっと温めていた“夢の列車”を描きました(写真下)。実現するには技術的に難しいものも、敢えて気にせずに盛り込んでいます。老若男女が集う賑やかな列車です。『JTB時刻表』 「JTB時刻表だけは変わらないでいてほしい」 “どう変えていくのか” 『JTB時刻表』 “変え過ぎず、進化すること” 「Re(再び)デザイン」
創刊100周年と通巻1,200号の重なったこの記念号『JTB時刻表 2026年1月号』(1,500円税込) JR九州 「ななつ星in九州」 水戸岡鋭治先生 水戸岡先生 「JTB時刻表ファン倶楽部」 水戸岡先生 “チーム水戸岡” 備前家具製作所 ドーンデザイン研究所 「デザイン系統樹」 JR北海道 「赤い星」「青い星」 「備前丸」 「TODEN」
梶原美礼編集長 「未来に向かって走行する列車」 「今後、この『JTB時刻表号』が日本全国を走行する未来に向かって、JTB時刻表も101年目を出発したいと思います」 ♥♥♥
実に有り難い時代です。AIを調べればどんなことでも分かる(あるいはヒントがもらえる)便利な時代になってきました(ただし誤情報には注意が必要)。最近もニュース番組(CNN)に出ていた“firefighter’s approach”(消防士のアプローチ?) ChatGPT
教員になって故・エド・マクベイン(Ed McBain) 「 ラビット・テスト」(rabbit test) 妊娠 ウサギ
He said I’d have to see a doctor, take the rabbit test , make sure I was really pregnant, and then we’d see what we had to do. ―Ed McBain , Blood Relatives(1975)(彼は、医者に診てもらい、「ラビット検査」を受けて、本当に妊娠していることを確認して、それからどうするか考えようと言った。)
長年疑問に思っていたところ、 ふとしたことで、「フリードマン法」(Friedman test) フリードマン ラプハム(Friedman & Lapham) 妊娠 ウサギ ウサギ ウサギ ウサギ
このように、その場では分からなくても、疑問をあたためておくと、ふとしたことから解決した、という経験を今までにたくさんしてきました。大切なことは、分からないことを分からないままに放置しない 、ということですね。生徒たちにも口を酸っぱくして言い続けているところです。
今ならAI(例えばChatGPT “ rabbit test”(ラビットテスト) 妊娠判定 rabbit test
妊娠している女性の尿を雌ウサギに注射し →
数日後にウサギの卵巣を切開して変化(排卵、卵胞出血、黄体形成)を確認することで、妊娠しているかどうかを判定する方法でした。
ただし、動物を犠牲にする必要があり、手技が煩雑という問題がありました。女性が妊娠 hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン) ウサギ hCG rabbit test pregnancy test
The rabbit test Back then, before modern kits, they relied on the rabbit test
ここから生まれた有名な英語表現があります。“The rabbit died.”(妊娠している) 「ウサギが死んだ(The rabbit died)⇒妊娠している(She is pregnant)」 「ウサギが死んだ」 ♥♥♥
She took the test, and well…the rabbit died
In old movies, “the rabbit died
I took the test this morning. The rabbit died
She took a pregnancy test and when she saw the positive result, she exclaimed, “The rabbit died!
He anxiously waited for the doctor to tell him the test results, hoping to hear that the rabbit died
「No Rain, No Rainbow!」 rain =雨、rainbow =虹(ちなみにrainbow はrain (雨)+bow (弓)の複合語で「雨の弓」)ということで、直訳すると、「雨が降らなければ、虹は出ない 「つらいことの後にはきっと良いことがある」「苦労や困難がなければ、喜びや成功は得られない」「つらい経験があってこそ、良い結果や成長がある」 「苦は楽の種」「苦あれば楽あり」 「Rainbow State(レインボーステート)」 「虹の州」
このNo Rain, No Rainbow! 「No pain, no gain.」 「Every cloud has a silver lining.」
I had to work so hard to achieve this.――Well, as they say, no rain no rainbow
I know it’s hard right now, but no rain, no rainbow
That experience was painful, but no rain, no rainbow
Practice is tough, but no rain, no rainbow
これは日常会話で頻繁に使われる一般的なフレーズというより、以下のような場面でよく見かける表現です:
観光業(ホテル、ツアー会社、ギフトショップ)
雨の多いハワイの気候を説明する文章や広告
ハワイのモチベーショングッズ(Tシャツ、ポスター、アクセサリー)
SNS(特に虹の写真のキャプション)
地元の人が人生の教訓として使う場合もあるが、そこまで日常的ではない
岡村孝子(おかむらたかこ) 「 デビュー30周年」 『 No Rain No Rainbow』(2013年) 「雨なくして、虹はなし」(雨が降らなければ、虹も出ない) 急性骨髄性白血病 「自分も含め、今がんばっている方たちに「間違ってないよ」と伝えられたらと、この曲を書きました」 『No Rain, No Rainbow』 私は「悪いことのあとには、必ずいいことが起こるよ」という意味で捉えています。私の曲を聴いてくださる方は、自分と同年代がとても多いんです。私自身、この数年で父や仕事仲間を亡くしましたが、この世代は大切な人を失ったり、自身が病気と闘っていたり、さまざまな人生のつらさも経験しています。それだけに「どこで選択を間違えたのだろう」と、ときに思い悩むこともあるはず、でも「何も間違っていない。よくがんばっているよね」と、自分にもみなさんにも伝えられたらと思って、この曲を書きました。 (『女性自身』5月7日号 2013年) 「薬の副作用で髪の毛が抜けてムーンフェイスになって、音楽なんて聴きたくないという状態にもなりました。そんなとき、娘が『退院したらコンサートをするのだからセットリストを考えたら』と言って、ポータブルのオーディオプレーヤーを差し入れてくれたんです。それとほぼ同じ時期に、BS-TBSで私が出演したときの『LIVE ON! うた好き☆ショータイム』という番組が再放送されました。そのOAをたまたま病室で見ていたら、本放送にはなかった『岡村孝子さん、闘病頑張ってください』というテロップが入っていて、涙があふれてしまって……。闘病は孤独でしたし、誰にも思い出されずに消えていくのだなと思っていたときだったんです。でも、その番組を見て、千羽鶴やお守りの写真が何枚も私のスマートフォンに届いていることも思い出して、見守ってくださる方、頑張ってと応援してくださる方もいるんだと感じました。『ひとりじゃない』と、その時に気づいて、暗闇の向こうに白い明かりが見えて、そこに向かって歩いていくイメージで闘病生活を乗り越えられたんです。」(岡村談) 今、あなたの人生に大きな台風が直撃して、とても辛く、苦しい状態だったとしても、絶対に大丈夫です。その大嵐は、いつかきっと、必ず、美しい虹へと、変わることでしょう。「No Rain, No Rainbow!」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はケーキ、でも閉店 「丸亀製麺松江上乃木店」 松江工業高校 「ディメル」 古志原 温熱療法(テルミ) シュークリーム
「ディメルのシュークリーム」(180円)
私の大好きな、昔ながらの柔らかいシュー皮で、中には、これもスタンダードなとろ~りとろけるカスタードクリームがたっぷり入っています。
他にも美味しそうなケーキがいっぱい目につきます。今日は「モンブラン」 「ブルーベリータルト」 「Ciistand」
♥♥♥
「鉄道友の会」 「ブルーリボン賞・ローレル賞」 JR西日本 273系 「特急やくも」新型車両 「ブルーリボン賞」 特急「やくも」 381系 川西康之(かわにしやすゆき) 近畿車輛株式会社 JR西日本
▲雲のデザインがいいですね
「ブルーリボン賞」 「鉄道友の会」 「鉄道友の会」 「ブルーリボン賞」 新型特急「やくも」 「安全性と信頼性が確保された先進の機器構成を基本に、地域の特性を踏まえた独自デザインが高く評価されており、会員からも候補車両の他形式を大きく上回る支持を得たことから最優秀賞であるブルーリボン賞に選定」 たたら製鉄 宍道湖の夕日 「やくもブロンズ」 「ブルーリボン賞」 JR西日本 「SLやまぐち号」
◎「『担(27)う山(3)陰』に期待」 鳥取県の平井伸治知事 「受賞を実現していただき、ご慧眼に敬意を表したい。273系は『担(2・7)う山(3)陰』。受賞で『乗ってみたい』という客が必ず出てくる。蟹取県(かにとりけん)にもお越しいただければ」
特急「やくも」 「沿線の自然・景観・文化・歴史を尊び、お客様と交感する色」 「やくもブロンズ」 「モダンに八雲立つ、伝統を継承」 「山陰の我が家のようにくつろげる、温もりのある車内」 積石亀甲模様 麻の葉模様 鉄道総研 川崎車両 振子制御装置 「特急はくも」 伯備線 車両異常挙動検知システム
それにしても、この車輌、「日本鉄道大賞」「ブルネル賞」「ブルーリボン賞」 「特急やくも」 ♥♥♥
今から10年前の、2015年5月7日(木)、BSフジ「LIVE プライムニュース」 『松下幸之助(経営者)の“成長とイノベーション”』 反町 理(そりまちおさむ) 「中居君問題」 松下政経塾 野田佳彦(前内閣総理大臣・立憲民主党代表・衆議院議員) 渡部昇一(評論家・上智大学名誉教授) 松下幸之助 “経営の神様” P HP 松下政経塾 。 「松下電器は、何をつくるところか?」 「松下電器は人をつくるところでございます。あわせて電気製品もつくっております。」 「経営の基礎は人である」 松下 では、次の段階への一歩を踏み出せずにいる平成の当時、松下幸之助 松下幸之助 松下幸之助 番組の最後に、お二方から提言「今、松下幸之助に学ぶべきこと」 野田 「素志貫徹」 松下 「素直な心」 「素直な心で衆知を集めろと。素直な心がどんな世界でも一番役に立つ根源です。政治家もそう。その天才が松下さんだと思う。見るもの全部に学ぶ。悟るという姿勢です。」 渡部先生 「学校の成績万能でない知力がある」 「知力が今の学校で図れるような勉強の世界は重要で、そういう知識レベルが高いことが文明国だが、それとは違う知力があることを学校の先生も頭の片隅に置いておくべき」 松下 Intelligence Intellect 松下 渡部先生 Intellect 渡部先生 ハマトン 『知的生活』 「インテリジェンス」(Intelligence) 「インテレクト」(Intellect) インテリジェンス インテレクト インテリジェンス インテレクト 松下 インテレクト 松下 【1959年 大卒定期採用者への訓示(当時64歳)】 皆さんのもつ職能以外にですね 松下電器の社員として社会に対してどういう責任感をもつかということが相当大きなもんであるということをですね、この際自覚をしていただきたい。全てはそこから始まっていくだろうと、こう思うんですね。我々がいかにいい仕事をしようと、いかに悪い仕事をしようと、社会と離れては存在する価値がない。全部社会に関連してですね、我々の力というもの、我々の活動というものが有意義になるわけでありますから、そのことがですね、いちばん私はもう大事なもんだと思うんですね。松下電器は やはり社会の一つの大きな機関ですね、「公の機関」である。だから「私の機関」じゃないわけ。この会社はですね、やはり社会の公器である、公の製造機関であると。この会社に働く一切の人はですね、その社会の公の機関を預かっているという責任感に徹しなくちゃならんかと思うんですね。工場一つ建てるのもですね、この会社が一定の利益をあげるのもですね、一切がそういう観点に立って判断され、また許されるものであると、私はこう思うんです。会社が単にですね、会社のために利益をあげるということは公の機関としての立場からいくとですね、それは許されないことであると。会社の利益をあげるということも大事なことでありますが、その大事なことは、公の機関であるということを前提として会社が利益をあげることを許される。会社自身を私的に考えて会社自身のために、これだけ儲けないかんということになると、だんだん卑屈になってくるんですね、卑屈になってくる。今日そういう考えは許されないと 私は思うんですね。そうでありますから、松下電器は公明正大に経営していこうと、堂々と経営していこうと。非常に社会に対して強いものをもって経営していこうということが同時に考えられるわけですね。それはこの会社が公の機関であるという認識のもとに社会にものを言うていこうというわけですね、早く言えば。皆さん、そんなことはもう十分に承知しておられると思うけれどもですね、そういう考えをもってやっているということを皆さんに申しあげておきたいと思います。 実に興味深い番組でした。この番組のエッセンスを詳しく活字で見たい方は、コチラ で今でも追うことができます。♥♥♥
10年振りにWOWOW 「風に立つライオン」(2015年) さだまさし 大沢たかお イオン・松江東宝
アフリカで献身的な医療活動を行なった日本人医師・故・柴田紘一郎(しばたこういちろう)先生 さだまさし 大沢たかお さだ 「解夏」「眉山」 「テラフォーマーズ」 三池崇史 石原さとみ 真木よう子
ケニアの国境地帯で医療活動に尽力した日本人医師の献身的姿を描きます。1987年、大学病院に勤める医師の航一郎 シュバイツァー博士 貴子
映画の冒頭は、一人の黒人ケニア人が大震災と津波で瓦礫と化した宮城県・石巻市 「命のバトン」
1987年、日本人医師・島田航一郎 (大沢たかお は、長崎大学熱帯医学研究所 シュバイツァー博士 航一郎 貴子 (真木よう子 を遠く日本に残さなければならなかったのです。理想を胸に研究と臨床の充実した日々を送っていた航一郎 航一郎 和歌子 (石原さとみ は、確かなスキルと手際の良さで、航一郎 「オッケー、ダイジョブ」 航一郎 「Mr.大丈夫」 ンドゥング 航一郎 紘一郎 「俺は9人を殺した!」 「生涯かけて10人の命を救え!」 紘一郎 紘一郎 和歌子 ミケランジェロ・コイチロ・ンドゥング 「命のバトン」
泣きたくなるシーンが満載の映画でしたが、紘一郎 「ガンバレッー!ガンバレーッ!」 「ガンバレっていうのは人に言う言葉じゃない。これは自分に言っているんだ」 紘一郎 貴子 長崎 さだ 「八ヶ岳の野ウサギ」 鎌田 實(かまたみのる)
そして、エンドロールで流れるさだ 「風に立つライオン」 「アメージンググレース」 さだ フルバージョンの「風に立つライオン」 渡辺俊幸(わたなべとしゆき)
柴田先生 「大学病院にしか入らない」 柴田先生 「大学病院のベッドが空くまで待つ」 柴田先生 「お前が家内を殺した!」 「力足らずで申し訳ありませんでした」 英語を教えていた松江北高二年生(当時)の安樂万智子(あんらくまちこ) 宮崎市民ホール 「第33回高校生英語弁論大会」(全国国際教育研究協議会主催) 「運命的な出会い」 柴田紘一郎(しばたこういちろう)先生 安樂 「松江日赤」 長崎大学 柴田先生 柴田先生 宮崎 「先生のホームページも拝見させていただきましたが、英語科の教師としてすばらしい英語教育に、またあまたの一般事象への高いご見識を常に発信されている姿勢に感銘いたしました。」(柴田紘一郎) そんな先生が今年2月に旅立たれました(⇒私の追悼記事はコチラ )。♥♥♥
▲2013年宮崎での講演会にて 故・柴田紘一郎先生
先日『LEAP Basic改訂版』(数研出版)
基本熟語のgive ~upも「~をあきらめる ▲(今までやってきたこと )を途中であきらめる。「〔注意〕「(将来)~することをあきらめる」はgive up (on) the idea of doingと表現する」という記述で、高校生がよく間違える×My mother was ill, so I gave up going to the movies.(母の具合が悪かったので私は映画に行くのをあきらめた)がなぜまずいのかがよく分かります。これは意外な盲点です。 これについてもう少し補足しておきましょう。高校生は「give up=あきらめる」 give up 「(今までやってきたことを)あきらめる」
give up doingは「すでにしていることをやめる」の意。これから先のことについてはgive up the idea[all hope] of doingあるいはgive up trying to doという。[ジーニアス英和] 「彼は留学をあきらめた」を英作文にする際に高校生がよく書くのは、“He gave up studying abroad.” 「既にアメリカかどこかに留学していて、何かしらの事情でその留学を中止した」 「まだ日本にいて、留学の計画を練っていたけれどあきらめた」 “give up” “He gave up the idea of studying abroad.” “give up” 「あきらめる」 竹岡広信先生 『竹岡広信の英語の頭に変わる勉強法』(中経出版、2009年) 松江北高
▲この本みなさんにオススメです
高校生がよく英作文問題に書く次の英文も誤りです。
毋の具合が悪かったので、私は映画に行くのをやめた。gave up
give up give up give up 「やめる」 「あきらめる」 まず最初に、以下の2つの文を見てください。gave up gave up
もう一つ、非常に一般的な例を挙げて考えてみましょう。“I have given up 「ある特定の場面で1本のタバコを吸わないことにした」 「タバコは二度と吸わない(=禁煙する)つもりだ」 given up
要するに、give up give up give up give up give up give up given up given up give up 「give up=あきらめる」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週は和菓子 「菓子はな」 (米子市目久美町) の「どらやき」 「新宝楽」 こしあん 「わらび餅」 京都 本わらび粉 「わらび餅」 「一度食べたら病みつきになる!」 花田 鳥取県日野郡伯耆町 の 出身です。大学卒業後、和菓子好きが高じて岡山県にある和菓子の製造工場(老舗の「 源吉兆庵」 花田 米子市目久美町38-8 「菓子はな」 花田 「添加物を使わないから日持ちはしないし、限られた数しか作れないけど、手作りの味にこだわりたい。」 花田 「菓子はな」 花田 自慢の和菓子が並ぶ中、「どれがイチオシ?」 「(数秒悩んだ後に)う~ん、どら焼きですかね~」 。 花田 「どら焼き」 「どら焼き」 「どら焼き」 「どら焼き」 「どら焼き」 「菓子はな」 「どら焼き」 「どら焼き」
▲このどらやきがフカフカで美味しい!
特に「素材の味を生かすことを意識」 「私どものような個人店では大量に安定的な原材料の供給は必要ありませんので、地元産の品質の良いものを使ってその日にお出しできる商品を作っていきたいと考えています。その他にもできるだけ添加物は使わないようにしており、日持ちがしない難点はありますが、素材本来の味を安心安全に召し上がっていただきたいです。」
▲「菓子はな」のご主人
就職したメーカーでは、独立して個人店を経営している職人の方を招いて技術講習を行なっており、その講習での技術に衝撃を受けました。その時配属されていた部署では普段機械を使っていたので、手で作り出されるお菓子の様子は、まるでマジックを見ているようでした。和菓子は間口が広く、自然の美しさを表現する「芸術的なもの」 「日々の身近なもの」 「人生の節目を飾るもの」 「大切な誰かに贈るもの」 “人それぞれの人生が見える”
▲上品で美味しそうな和菓子が
「 どんなお店にしたいですか?」 「地元の人々に気兼ねなく立ち寄っていただける、地域に根差したお店にしたいと思っています。和菓子屋と聞くと、少し男性は入りづらいイメージかもしれません。現在も大半は女性のお客様ですが、男性でも仕事帰りにふらっと立ち寄り、どら焼き1つ買って小腹を満たしていただきたいです。これまでの経験を活かして、当店でしか食べられない商品をお客様に提供し続けたいと思っています。」 私は今この和菓子店にはまっています。 ♥♥♥
2000年代にテレビで大活躍していたあのマジシャン・セロ(51歳) 「鶴瓶孝太郎2時間SP スターの今を大調査」 セロ 「セロはなぜ消えた?」 コチラ です)。
● テレビ業界のプレッシャー セロ ● コロナ禍での活動停滞 セロ ●再起への決意 「希望のない時代に、マジックで感動を届けたい」 セロ 「日本のみなさん久しぶり!セロです!」 「ぶっちゃけ話すると、疲れました」 「半年おきに2時間のテレビ特番をやっていて、1個の特番で30個の新しいマジックを生み出さないといけなくて。前回よりももっと大きな驚きのマジックを期待される中で、生みの苦しみがたくさんあって、一回休憩したかった」 「ライブが僕の一番輝ける場所」 笑福亭鶴瓶 小泉孝太郎 ウェンツ瑛士 スーパーマジシャンのセロ セロ 「日本のみなさん、これから僕のマジックをたくさん見れることを期待してください!」 ♥♥♥
コーヒー 「UCCコーヒー本社」 と「銀座カフェパウリスタ」 から毎月届けてもらっています。コーヒーの美味しい喫茶店があると聞くと、すぐに飛んで行くくらいです。そのコーヒー豆に、今静かに危機が迫ってきています。すでに新聞各紙でも報道されている通り、コーヒー生豆の国際相場は、2024年2月には、アラビカ種 ロブスタ種 アラビカ種 ロブスタ種
2024年、ブラジルでは降雨量が少なく、雨期入りの遅れや、高温と乾燥した気候が続いたことによるコーヒーの木へのダメージが大きかったことから、2025年の生産量が大幅に減産になると予想されています。コーヒーを巡る状況は、世界的な需要増や生産国での異常気象による供給量の減少により、直近のコーヒー生豆国際相場(アラビカ種
「最近、コーヒー豆ってちょっと高くなった?!」 コーヒーの栽培には、昼夜の寒暖差や適度な雨量、肥沃な土壌など、非常に繊細な条件が求められます。特定の気候条件が揃った地域でしか育たず、主に赤道を中心に北緯25度~南緯25度の間に広がる「コーヒーベルト」で生産されています。ところが、近年このバランスが少しずつ崩れつつあります。特に大きな影響を受けているのが、世界最大の生産国であるブラジルです。2021年には歴史的な霜害(そうがい)と干ばつが重なり、アラビカ種 アラビカ種
さらに深刻なのが、コーヒー栽培を脅かす病害虫の拡大です。中でも代表的なのが、コーヒーベリーボーラー(Coffee Berry Borer) さび病(リーフラスト) 「高くなっている」 「この価格で維持できなくなっている」
さらに、コーヒー豆の多くは、ニューヨークやロンドンの先物市場で取引される「コモディティ(商品作物)」 パナマ運河 紅海 「豆はあるけれど港まで届かない」「届いても想定以上にコストがかかる」
こうした中で、価格や供給の安定性から注目されているのがロブスタ種 アラビカ種 ロブスタ種 「苦い」「重たい」「雑味がある」 ロブスタ ロブスタ ロブスタ ロブスタ 「仕方なく使う豆」 「風味の選択肢」
▲最高級のブルーマウンテンコーヒー
私たちはこれまで、当たり前のようにコーヒーを安い値段で楽しんできました。しかし、その価格の背後には、今日ご紹介した多くの「見えないコスト」 「これからのコーヒーの選び方」 八幡 ♥♥♥
▲JR227系「Urara」
先日、講演で倉敷 笠岡 JR西日本 227系「Urara(うらら)」 「マリンライナー」 笠岡駅 岡山駅 「Urara」 広島 和歌山 岡山・備後 227系
車両の愛称の「Urara(うらら)」 JR岡山支社
2両編成で、両車ともモーター搭載車です。編成番号は、2両編成が「R編成」 「L編成」 キハ40,47
JR西日本 「人、まち、社会のつながりを進化させ、心を動かす。未来を動かす。」 JR西日本 「人にやさしい車両」 岡山・備後エリア
岡山・備後エリア 227系「Urara」 「豊穏(ほうおん)の彩(いろどり)」 岡山 福山 尾道 広島 岡山 岡山 岡山支 社が加わったワークショップを開催して検討が進められました。その中では、 岡山 117系「サンライナー」
「Urara」 岡山 岡山・備後 エリア のシンボルマークは、車体各所に描かれていました。車内にもずいぶん配慮が加えられています。広島 転換クロスシート 広島 車いすスペース
拡大された出入口スペース 情報表示装置 車内防犯カメラ 多機能トイレ 吊手・手すり 吊手
運転台は広島 227系 「都市型ワンマン運転」
今後、山陽本線 岡山・備後 エリア 各線で、新たな岡山 「Urara」 米子駅 後藤総合車両工場 米子駅 松江駅 出雲駅 「試運転」 米子 荒島駅 「試運転」 山陰本線 ♥♥♥
◎なんと山陰線に「Urara」が運行!! 〔追記〕 米子駅 ダイヤ改正 ♦♦♦ 〔追追記〕 今日(12月16日)のテレビニュースで発表になりました。来年のダイヤ改正(3月14日~) 115系 「Urara」 車両は、衝撃を吸収する構造になっているほか、急病など運転士の異常を検知すると自動でブレーキがかかる緊急列車停止装置を搭載するなど安全性が向上、バリアフリーにも対応しています。「Urara」 新たに運行開始となる区間は、以下の区間です。 ・伯備線:新郷〜伯耆大山 ・山陰本線:伯耆大山〜西出雲 VIDEO
あの坪内逍遙(つぼうちしょうよう) 早稲田中学 「やめます」 「先生たちだって、やめることができないじゃないか!」 逍遥 「ぼくもやめるから、きみもやめろ」 「健康を害してまで、無理をなさる必要はないでしょう」 「生徒にだけ厳格で、自分に寛大では、生きた教育はできない」 「自分に厳しく」
教育者であり、宗教家(キリスト教)でもあった新島 襄(にいじまじょう) 京都 同志社英学校 同志社大学 新島 「幾百人の生徒に禁酒を説きながら、自らこれを破ることは、私にはできません」――「そうカタイこと言わないで。ここは船の中、誰も知るものはいません」――「人は知らなくとも、私の良心が知っています」 と、 ついに一滴も口にしなかったといいます。これも「自分に厳しく」
服部金太郎(はっとりきんたろう) 「 服部時計店」 「SEIKO」 服部時計店 「惜しいなあ!」 金太郎 金太郎 「君どうだ?酒はどうしてもやめられないかネ」――「は、どうも」 と、 恐縮はするのですが、禁酒の意志がありそうには見えません。「どうだろう?今日限り、私はタバコをやめるから、君は酒をやめてくれないか?」――「は……?」 服部金太郎
「自分に厳しく」 松江北高 「1時間を大切に!」 「勝田ケ丘志学館」
模擬試験 「やりっ放し」 「やっておけよ!」「見ておけよ!」 「忙しい」 と称してそういう先生が多いのも事実です。ひどい場合には自分で解くこともありません)では生徒は絶対にやらないのです。そこで、自分でも模擬試験(記述・マーク) 「見直しプリント」(2枚~4枚) 「見直し」 「見直しプリント」
▲11月全統プレテスト「見直しプリント」
大田高校 進路指導部通信「あむ-る」 毎週 発行しました。担任時代から毎週 続けていたことなんですが、これにより進学成績が飛躍的に伸びました。津和野高校 松江北高校 大阪大学・人間科学部 「自分に厳しく!」♥♥♥
▲「あむーる」12月最新号
翻訳家必携の英和辞典『リーダーズ・プラス』(研究社、1994年) “ archer” 「《英俗語》2000ポンド《Jeffrey Archerが売春婦Monica Coughlanを国外に出すために支払った金額から》」 “an archer” 「2000ポンド」 ジェフリー・ハワード・アーチャー(Jeffrey Howard Archer、1940~)
ジェフリー・ アーチャー Not a Penny More, Not a Penny Less (『百万ドルをとり返せ!』(永井淳訳・新潮文庫)page-turner でしたね。その後も作家活動を続けながら、1985年に上院議員となり政界に復帰し、43歳で保守党の副幹事長という要職につきます。しかし翌年、今度はコールガール(Monica Coughlan ロンドン市長 Archer A Prison Diary さて、ここでなぜ“ archer” 「2000ポンド」 Archer Jeffrey Archer “ a blessing in disguise” ♥♥♥
このスラングは、標準英語ではなく俗語/スラング に過ぎない。日常どこでも通じる言葉ではなく、むしろ非公式・インフォーマル な使われ方をする。
また、全ての英語話者が “archer = £2,000”
スラングの性質上、いつの時代・どの地域で使われていたかで認知度が変わる。
難関大学の入試問題を演習していると、「その他の点では」「別の方法で」 う意味のotherwise 「もしそうでなければ」 otherwise ①「もしそうでなければ」( =if …not) ②「その他の点では」(= in other ways)、③「別の方法で」(= in a different way) ここで生徒に尋ねます。「何でこんな意味が出てくると思う?」 これらを丸暗記してもすぐに忘れてしまうことでしょう。 授業ではこういうことをいつも生徒と一緒に考えています。 私が理想の単語集として評価する『LEAP』改訂版(p.304) 「①さもなければ ②ほかの点では ③ほかの方法で」 と記述し、other-「ほかの」+-wise [=way 方法、点]」 wise←way+sと otherwise other + ways ← other + way + s -s -s で、英語にはかなり見られます。always s s s s s s s -s は、古英語の属格の転用であろうと考えられていますが、中英語の段階で副詞形成語尾になりました。またonce, hence, whence, since などの -ce は -s の変形です。この話をすると生徒たちは「エーーッ、そうだったのか!」 未知 既知 「副詞のs」 そこで、way がいろいろな意味を持つ(「状態」「点」「方法」 他の状態 では ① 「 もしそうでなければ」 他の点 では ②「その他の点では」 他の方法 で ③「別の方法で」 「別の 点 なければ」 clockwise (時計回りに) crosswise (斜めに)が出た時にも応用できますね。 私が尊敬する故・渡部昇一先生 『人生の出発点は低いほどいい』(PHP研究所、2007年、2014年に復刊) ♥♥♥
これは大学の先生に限らないのですが、教師が常に忘れてはならないのは、教育 熱心であることと熱心に教えることは違うのだ、ということです。 教育の主目的は、学生が自主的に学ぼうと意欲を誘いだすことです。と同時に、 教師は学問を深く修めるという大切な責務を忘れてはなりません。自分の学問を二 の次にして、「教育とは、教育とは」と論じてばかりいるのでは良い教師とはいえ ません。あまりうるさく教えても、そうそう生徒のアタマの中に入るものではあり ません。むしろ「淡々」に近いぐらいでいいのです。もちろん、質問されたら、ピ シッと答えることができなくてはなりませんが。 私が学部で英文法を教えていた頃、学生たちによくこう話したものです。 「このような英文法は、君たち自身が教えることはまずないだろう。しかし、君 たちが家庭教師になったり、教壇に立ったり、あるいは塾で教える時には、生徒の 中にできる奴が必ず何人かいる。そして、そいつは変な質問をするに違いない。そ の時、スパッと答えられるか答えられないかで、その質問した生徒の運命が決ま ることがある。だから、その時、答えられるためにこの英文法をやっているのだ。 『十年兵を養うは、一日これを使うがためなり』と。 英文法というのは、そういうものなのです。たとえば、「nowadaysの末尾になぜ sがつくのですか」「このsは複数なのですか」 というような妙な質問をする学生がいないとは限りません。その時、教師がスパッと答えられるか答えられないかが、 その学生の学問的な目がパッと開くか開かないかの分かれ目になることもあります。 教師というのは、そういう瀬戸際に立ち会うこともある職業なのです。私はつねづね このことを、弟子たちに話しています。(pp.88-89)
竹岡広信先生 京都 数研出版関西本社 「チャート式」 「京都らしさ」 数研出版関西本社 京都御所・京都御苑 烏丸丸太町 丸太町駅
京都 数研出版 関西本社ビル 「京都らしさ」 京都 「新しい京都らしさ」 京都御所 京都市環境配慮建築物顕彰制度 優秀賞 SDA賞 日本サインデザイン奨励賞 竹中工務店
▲建物には数研の出版物が!
会社のすぐ目の前に京都御苑 京都御所 ♥♥♥
我が国の今年の「流行語大賞」 高市総理 「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」 オックスフォード大学出版局 「今年の言葉」(Oxford Word of the Year) 「レイジベイト(rage bait)」 aura farming , biohack )。意図的に怒りを引き起こすようなオンライン上の文章や画像を意味し(「(n.) 特定のウェブページやソーシャルメディアアカウントへのトラフィックやエンゲージメントを増やすために、意図的に怒りや憤りを引き起こすために意図的に設計されたオンラインコンテンツ。」 「怒りのエサ」 「炎上狙い」
2025年のニュースサイクルは、社会不安、オンラインコンテンツの規制に関する議論、デジタル・ウェルビーイングに関する懸念で占められており、今年のrage bait オックスフォード・ランゲージズ キャスパー・グラスウォール社長 「オンラインとオフラインの両方で『本当の自分とは何者か』をめぐる問いに特徴付けられる年だった」と述べた。その上で「ネットはかつて好奇心を刺激してクリックを得ることに注力していたが、いまは私たちの感情や反応を乗っ取ったり、影響を与えたりする方向に劇的にシフトしている」 「ブレーンロット(brain rot、脳ぐされ)」 グラスウォール 「怒りがエンゲージメントを呼び、アルゴリズムがそれを増幅し、絶え間ない『さらし』が我々を精神的に疲弊させる。二つの言葉はそんな強力な循環を形成する」
「「怒りの餌」は二つの単語じゃないか?」 Oxford University Press 「オックスフォード・ワード・オブ・ザ・イヤー rage bait clickbait )とは類似しているが、rage bait rage bait
また、Cambridge Dictionary 「parasocial(パラソーシャル)」 ChatGTP Cambridge Dictionary コリン・マッキントッシュ パラソーシャル
「Parasocialは2025年にいくつかの理由で際立っていました。今年、この用語への関心は大幅に高まりました。データからもわかるように、ケンブリッジ辞典やGoogleでの検索数が何度か急増しました。言語的な観点からは興味深いのは、学術用語から一般の人々がソーシャルメディアの投稿で使う用語へと移行したからです。また、2025年の時代精神を捉えており、セレブリティやそのライフスタイルへの一般の関心が新たな高みへと高まっているのです。」 Word of the Year 「偽名化」 「ミーム化」 「 グレージング 」「バイアス」 「バイビー 」「ブレスワーク」 「ドゥーム・スペンディング」 Cambridge Dictionary
もう一つ、イギリスのハーパーコリンズ社 Collins Dictionary 「今年の言葉」(Word of the Year) 「 Vibe coding」
今回ご紹介したイギリスの各社英語辞典が選ぶ「今年の言葉」 インターネット AI 「今年の言葉」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はラーメン 京都 倉敷駅 天満屋 「麺酒 一照庵(めんさけ いっしょうあん)」 岡山市内 倉敷市内 天満屋 倉敷店 岡山
岡山 岡山 ミシュラン 「一隅を照らす」 「自分が今いる場所で精一杯努力し、光り輝くこと」 「一照庵」 岡山本店 「一照庵」 「鶏中華そば」 「ミシュランガイド京都・大阪+岡山 2021年」 「ミシュランプレート」 「おかやまラーメン博グランプリ」 「麺酒 一照庵 天満屋倉敷店」
鶏中華そば クラム
鶏中華そば 生醤油
鶏中華そば 塩
鶏中華そば 生醤油 旨辛仕立て
いずれもこだわりの素材を使ったラーメンで、盛りつけにもこだわっており美しいビジュアルも特徴的です。
「鶏中華そば クラム」(1,180円) 「一照庵」 ミツバ・ネギ・極太メンマ・半熟塩玉子・低温調理された豚と鶏のチャーシュー ネギ 白髪ネギ 「クラム(二枚貝)」 ハマグリ・アサリ・シジミ 自家製ホタテ油 鶏 ハマグリ・アサリ・シジミ ホタテ油 クラム 海苔 タマネギ ガーリックペースト 鶏チャーシュー ホタテの干し貝柱 三つ葉、ネギ、味玉、玉ネギ、メンマ チャーシュー 半熟卵 【左】貝のむき身のガーリックペースト、【右】ホタテの干し貝柱の粉末
これらをスープに少しずつ溶かしていくと、スープの味わいがさらに微妙に変化していくのです。最後までラーメンを楽しむことのできる工夫をしていることが感じられます。「鶏中華そば クラム」
「麺屋のポテサラ」(550円) いぶりがっこ ゆで卵 秋田名産いぶりがっこ ベネッセ 中村友樹 ポテトサラダ ♥♥♥
▲渡部先生の最新刊
故・渡部昇一先生 二億円 を超える借金をして、現在の家を建てられました。巨大な2階建ての書庫を作って、世界に誇る自分の全蔵書(15万冊)を書棚に飾り、全蔵書と対面してから死を迎えたいと願われたからです。前の家にも書庫はあるにはあったのですが、本がだんだん増え続け、ついには応接室にまで本が溢れ出して、そのせいでホームパーティの開催も不便になってしまいました。本に深い理解のあった奥様の迪子(みちこ) 「この家には本権はあるけれども人権がありません」 「わが家に多いもの四つあり。読んでいない本、見ていないDVD、弾いていないピアノ、返していない借金」 「明日のことは明日のこと、明日のことを今日心配する必要なし」
こうして巨大な電動化された書庫(2階建て) 「全蔵書と対面してから死にたい」 15万冊 の蔵書(個人の蔵書としては世界一)が全て収容できるものでした。蓄えを吐き出し、さらには借金までする。「たかだか書斎にそんな投資をして」 「書斎の新築」 渡部先生 「楽園」 『95歳へ!―幸福な晩年を築く33の技術』(飛鳥新社) 渡部先生 渡部家
「 本の引っ越しにね、五百万円もかかるらしいのよ」 「渡部家の崩壊は本の崩落から始まる」 「地震がきて、崩れ落ちた本で圧死するなら本望!」 「うちにはねえ、本の権利、本権はあるけれど人権がないのよ!」 ♥♥♥
▲渡部昇一先生の書斎
しばらくの間離れて聴いていませんでしたが(彼女も三児の母です)、先日久しぶりに一青 窈(ひととよう) 「アレキサンドライト」 「ハナミズキ」 マシコタツロウ 「もらい泣き」「ハナミズキ」 武部聡志(たけべさとし) 一青 窈 「アレキサンドライト」
VIDEO
1830年に、ロシアのウラル山脈で発見されたアレキサンドライト アレキサンドライト ニコライ1世 アレクサンドル2世 「アレキサンドライト」 アレクサンドル2世 アレキサンドライト アレキサンドライト アレキサンドライト 「アレキサンドライト効果」 アレキサンドライト 。 「昼はエメラルド、夜はルビー」
かつて一青 窈 松江(島根県民会館) 松江 「太平楽」 松江北高 「きがる」 松江 ♥♥♥
▲お昼時、出雲蕎麦「きがる」の行列
“ Blood will tell.” は、「 血は争えない」 という意味を持った諺で、どの英和辞典にも載っている表現です。これは、親子や兄弟の間の血縁関係が、個人の性格や行動に影響を与えることを示していて、具体的には、子供は親に似ていることが自然であり、血は争えないというニュアンスが含まれている 慣用句です。blood=血筋 の意味です。血筋は語る、が直訳ですが、生まれの良し悪し(血筋)は黙っていてもおのずと現われる = 血筋は争えない、という意味になったものです。しかし、私の調べたところでは、この諺は現代でも意味は通じますが、《古風》 Asahi Weekly 「デビッドセインのこれを英語でどう言うの?」 「古風である」 Like father, like son. Like parent, like child. “Blood will tell.”
口語としてはほとんど使われることはなく
使われるとすれば 皮肉っぽく 、または 意図的に古風な雰囲気を出す時で
書き言葉や文学的文体では見かけることがあるという位置づけです。
ネイティブの感覚としては、「意味は分かるが、日常で言えばやや時代がかった/修辞的に響く」
You can’t escape your nature. (人は生まれ持った性質から逃れられない)
It runs in the family. (家系的なものだ) ※センター試験に出題されたことがあります。2009年本試験第2問A問10です:You never seem to gain weight. How do you stay so slim?――Just lucky, I guess. It ( ) in the family . ①comes ②goes ③runs ④works
Like father, like son./Like mother, like daughter. (この親にしてこの子あり)
これらのほうが日常ではよく使われます。「古風だ」 ♥♥♥
毎日の授業の中で、英語の長文を読みながら、内容一致問題 必ず本文の該当箇所に下線を引いて根拠を明確にして○×判定をす る 「思考の痕跡」 「ただ何となく」 設問の「キーワード」(名詞・動詞)をヒント 「言い換え」 「原文典拠の法則」 「同一内容異表現の法則」 単語力不足 本文または選択肢の正確な意味を取ることができていないのです。そして時間内に読み切ることができません。教訓は、語彙力を大いに鍛えるべし! ここで一つ大切なことがあります。普段から練習では、「正解」 が分かったらそれでよし、とするのではなく、「不正解」 の選択肢(ダミー)もどこが間違っているのかをしっかり確認しておく。誤りの選択肢は、どこかが巧妙に「すり替え」 「記述なし」 正解 が分かれば次に行けばいいのですが、素早く、確実に それをやるためにも、練習では負荷をかけておくとよいのです。どんなに大変でもこれを忠実に実行しておくと、本番で成果が出てきます。「 原文典拠の法則」 自治医科大学 正解 正解 「答えさえ合えばそれでいい」 「原文典拠の法則」 「見直し」 「共通テスト」 「推測」 most likely~ で聞かれる)も出題されます。私が授業で強調していることは、先ほど説明した「原文典拠の法則」 「推測」 「原文典拠の法則」 推論問題 「心温まるいい話」 「センター試験」の第6問 「原文典拠の法則」 ♥♥♥
「使う」「利用する」 use utilize use=utilize utilize LDOCE ] 、“formal to use sth, especially for a practical purpose”[OALD ]とあります。LDOCE には“In everyday English, people usually say use rather than utilize : The money will be used to build a new sports hall. ”という注記も見られます。竹岡広信先生 『LEAP』 「日常ではuseの方が使われる」
ディビッド・セイン先生 『英語ライティングルールブック(改訂新版)』(学研、2024年) utilize 「最大限に利用する」 A. This office isn’t being used utilized
Aは単に「このオフィスは使われていない」という意味なのに対して、Bは「このオフィスはまだ100%活用されていない」という意味になります。このような大きな意味の違いを生むことがあるので、use utilize セイン先生 use utilize use utilize 「有効に活用する、最大限に活用する」 use utilize use 「使う」 utilize 「(最大限に)活用する」 utilize セイン
「この道具はどうやって使うんですか」
△How is this tool utilized?
◎How is this tool used?
「この新しい道具の使い方が分からない」
△I don't know how to utilize the new equipment.
◎I don't know how to use the new equipment.
The company utilized
We need to utilize
utilize 「目的に応じて戦略的に使う」「限られた資源を有効活用する」 utilize use ♥♥♥
松 下幸之助(まつしたこうのすけ) 松下電器 幸之助 「コーヒーをつくってくれるか。うちでコーヒーをつくる器具があったな。あれでつくってみてくれや」 幸之助 「ところできみ、うちのコーヒーメーカーの占有率はいくらや」 早速 秘書が調べると、外資系の二社が63%を占めており、松下電器 「わが社の占有率はかなり低くて、7パーセントです」 幸之助 「えらい少ないやないか。これは松下電器のいわばお家芸の商品や。それが7パーセントやそこらじゃあかんな。やはり一番にならないといかん。各メーカーの商品をいっぺん全部持ってこさせてくれ」
こうして市場に出回っているコーヒーメーカーを全部本社特別会議室に並べさせたのです。幸之助 「外資系の商品が63パーセン トも占めているということは、単に松下電器一社の問題ではない。日本の問題ではな いか」 キューリグエフィー アイリスオーヤマ UCC 幸之助 「きょう天下を取っていても、あすはパッと変わるような時代である。だから喫茶店でコーヒーを飲んでいるあいだにも、あす打つ手をどうするか考えるようでなければ経営者とはいえない。多くの人の声を聞いて。「ああ、そうか」では時すでに遅い。シェアが下がっていることまで指摘するのは、相談役の仕事とは違う」 ♥♥♥
かりにも経営者として人の上に立つ者が、人よりも先に憂い、あとから楽しむということでなくては、経営者として失格といわなくてはならない。体は休ませたり、遊んでいることがあってもいい。しかしそのときでも、心まで休養や遊びの中にひたりきってしまうのでなく、心は常に先憂でなくてはいけない。遊んでいるときにまったく遊びに心を許してしまうような人は、真の経営者とはいえない。 (『経済談義』より)
一つの単語が文脈によって真逆の意味を持つことができるものを、英語では「contronym」 「Janus word」(ヤヌス語) 言葉の逆説的な性質を示し、言語の多様性と複雑さを体現しています。この「 ヤヌス語」(Janus words) 「ヤヌス(Janus)」 ヤヌス ヤヌス神 「ヤヌス語」 「ヤヌス神」 January(1月) 「ヤヌス神」
文脈によっては正反対の意味を持つことができる ため、英語学習者にとっては特に注意が必要です。contronym 言葉の真逆の意味を持つことができる ため、会話や文章において混乱を招く可能性があるので厄介なんです。例えば、「left」 「去った」 「残った」 文脈によって意味が180度変わる ことがあります。例えば、The judge will sanction 「行動を認可する」 「行動に罰を与える」 sanction 「宣誓」 「承認」 「経済的不承認、制裁」 peruse 「精査する、精読する」 「ザッと読む、目を通す」 両義性を持つ単語 は、言葉遊びや文学的な表現において豊かなニュアンスを提供してくれますが、我々非ネイティブにとっては混乱の元となる こともあります。これらの単語は、会話や文章の中で、文脈を注意深く選ぶ必要 があります。例えば、「The window is open.」 と言った場合、それは窓が「開いている」 という意味にも、「壊れている」 という意味にも取れます。このように、contronym
動詞のclip 「クリップなどで留める」 「はさみなどで切り取る」 『英語教育』 「クエスチョンボックス」 scan 「~を注意深く調べる」 「~をざっと見る〔読む〕」 defeat 「打ち負かすこと」 「敗北」 dust 「ほこりなどを払う」 「まぶす」 「ヤヌス語」
日本語にも同様の現象が見られます。例えば、「おもむろに」 「ゆっくり」 「突然に」 文化庁 「おめでたい」 「縁起が良い」 「お前はなんておめでたい ヤツなんだ」 「考え方が甘い、楽観的だ、愚かだ」 「憎い」 メリアム・ウェブスター社(Merriam Webster) 「ヤヌス語」 コチラ です♥♥♥
好業績を継続している企業では「ビジョン」 「理念」 ビジョン 「存在意義」 「ミッション」 理念 「行動規範」 ビジョン 理念 「目的」 「目標」
粉飾や偽装など不正を働く企業や政治家が後を絶ちませんが(例えば最近ではビッグモータ 小林製薬 トヨタ自動車 JR九州、ミニストップ、ニデック 「目的」 「目標」 「目的」 「目標」 「目的」 「目的」 「目標」 「目的」 「目標」
「 目的」 「 目標」
目的: 最終的に行きつくところ、あるいは存在意義 目標: 目的に至るまでのその通過点 、具体的な評価、目的達成のための手段 そもそも「目的」 「存在意義」 「目標」 「目的」 「 目標」 「 目的」 「目的」 目的 目的 存在意義 ピーター・ドラッカー 「独自の商品やサービスを提供すること」 「働く人を活かす」 目的 目的 「50億円の売上高をあげよう」 「2億円の利益を出そう」 「目標」 「東証一部に上場しよう」 目標 「50億円売ろう」 目標 目的 「50億円分売れるくらい良い仕事をしよう」 目標 「50億円売ろう」「2億円の利益を出そう」 「目標」 「目的」 「数字を出してこい!」 東芝 「良い仕事」 「お客さま第一」 目的 目的 藤本幸邦老師 曹洞宗円福寺 「お金を追うな、仕事を追えだよ」 「仕事」 「良い仕事 目的 「良い仕事」 「お客さま第一」 目的 「お客さま第一」 「良い仕事」 「目的」 「目標」 「良い仕事(1.お客さまが喜ぶこと、2.働く周りの仲間が喜ぶこと、3.工夫)」 「良い仕事」 「お客さま第一」 「良い仕事」 「もうこんなものでいいか」 「良い仕事をしよう」 「お客さま第一」 目的 「お客さま第一」 「良い仕事」 「良い仕事」
私(=八幡 「目的」 存在意義 「英語を通じて社会貢献をする」
目的 目的 ♥♥♥
今日11月26日は、【1126=イイフロ(いい風呂)】 「いい風呂の日」 「いい風呂の日」 日本浴用剤工業会 「いい風呂の日」 「いい風呂の日」
▲八幡家のお風呂(パナソニック製)
12月を目前に控え一段と寒さが厳しくなり、「お風呂」 「 書庫」 (尊敬する渡部昇一先生 と「お風呂」 「お風呂」 ミサワホーム 「お風呂」 ミサワ 米子 パナソニック 「これだっ!!」 人造大理石 浴槽 ジェットバス 美泡湯 ミストサウナ 冷暖房 乾燥 ヒーリングライト、音楽、 シャワー パナソニック 松江南高校 ミサワホーム 「こんなにお風呂にお金を使う人は初めてです」 「部品の生産をもうしていないので、修理することができませんから大切に使って下さい」
11月21日(金)にBSフジ 「華丸大吉が行く 大人もハマる神授業」 バスクリンつくば研究所 「ぽかぽか入浴学」
科学で解明された入浴の驚きの健康効果があり、 お風呂につかると得られる健康を保つ3つの作用を学びました。①温熱 ②制水圧 ③浮力 ①湯温は40℃前後、②時間は10~15分、③就寝90分~120分前、④全身浴 家で温泉気分を楽しめる名湯を再現する入浴剤 浴槽がいくつも並んだ入浴評価室で6つの温泉入浴剤を当てるクイズに挑戦し、華大の地元・福岡にある原鶴温泉 入浴剤 バスクリン社 私は毎日の入浴剤にほとんどバスクリン社 「きき湯」「アーユルタイム」「夢ごこち」「日本の名湯」 「バスクリン」 株式会社バスクリン アース製薬 「バスクリン」 「きき湯」「日本の名湯」 アース製薬
▲この中の「山代」がお気に入り
▲パソコン疲れで凝り固まった首・肩に効く最近の私のお気に入りの「デジケア」
バスクリン 「津村順天堂」 津村重舎 東京・日本橋 津村 「くすり湯 薬剤中将湯」 津村順天堂 ツムラ ツムラサイエンス ツムラサイエンス社 株式会社バスクリン アース製薬株式会社 「合併による成長戦略」 「バスクリン」「きき湯」「日本の名湯」「アーユルタイム」「夢ごこち」 アース製薬 アース製薬 ♥♥♥
来年の「共通テスト」 【第6問】(物語文) 「心温まるいい話」 八幡 ① 「令和7年度大学入試共通テスト問題評価・分析委員会報告書」 ② 「追試験」第6問 「追試験」 「心温まるいい話」 ① ②
▲2025年共通テスト追試験第6問
ある男の子が一人で祖父母のところに旅行することになり、その道中で起きたことに関する物語を読み、ワークシートを完成させるという設定です。資料を読んで適切なイラストを選択したり、登場人物の感情の移り変わりをたどったりするなど、よくできた設問だと感じました。約720語で4つの設問。英文の量・難易度共に標準的で、設問数とのバランスも適切であると思いました。先生方にオススメしておきます。
しかしながら、 「令和7年度大学入試共通テスト問題評価・分析委員会報告書」 では、この問題に対して幾つかの疑義と改善点が述べられています。まずは、 英文で書かれているのに、日本国内と思われる場面設定は不自然に感じる、という点です。日本国内が舞台となっていると思われる物語を、英語で読ませることの不自然さが指摘されているのです。果たして不自然でしょうか?しかし私はそれは大きな問題にはならないと思います。日本の高校生に身近な設定で話が展開しているのです。 問1 に関わるワークシートの「Draw a picture that best shows Hiroki and the “chocolate woman after she had gotten on the train.という指示のbestはワークシートの指示としては不自然だと感じる」という点も指摘されていますが、私には全く問題ありません。英語の試験・教科書・説明文でもよく使われる自然な表現です。この問いは物語文のある場面をイラストで答えさせる問題です。第4段落の“I moved my backpack from the aisle seat .”(aisle がキーワード)と“I retreated away from the left armrest and shifted my body toward the window .”の部分でほぼ正答は一義的に決まるので設問に問題はありませんが、“As she sat down, she spread her arms and legs into the space I had occupied before.”という部分が、心温まる物語の善良な登場人物が取る行動と余り結び付かないものではと疑義が表明されています。正解の根拠となる老婦人の行動(腕と足を広げて席に座る)について、「心温まる物語の善良な登場人物が取る行動と余り結び付かないものであった」 「解答には影響が及ばないとはいえ、受験者に読ませる文章の質をより高いものにするため、この指摘を今後の問題作成に生かしていきたい。」
問2 は、生徒が苦手とする事象の時系列の理解を問う問題です。この時系列整理問題は選択肢を先読みして、日本語で簡単にメモしておくだけで、効率的に解くことができます。選択肢④の英語を理解するのに高い力が求められたと考えられます。③が偽肢であることは明白ではありますが、④の“She shows interest in something else to make things less awkward.”という英文が、やや分かりにくかった受験者は少なくなかったと思われます。そしてそれが第7段落の“… then she took out her phone and started tapping on it”の部分との対応を見抜く問題です。上手い「抽象化」の言い換えです。④の内容と必ずしも結び付かなかった受験者もかなりいたと思われます。「もう少し明瞭な選択肢でも良かったと思われる」 問3 では、登場人物ヒロキとチョコレートの女性の性格を本文から読み取る力が求められました。 英文の内容から登場人物の特性を問ういい問題でした。 問4 は、ジュンコがヒロキに対して感動した理由を問う問題で、“You’ve handled this situation in a way that’s beyond your age.”(年齢以上にしっかりとふるまった)の抽象化であり、本文の正確な読解ができれば正答を得ることのできる問題でした。選択肢にも紛らわしいものはありませんでした。総じて私はよくできた、それでいて「心温まるいい話」 過去の「センター試験」 「心温まるいい話」 ♥♥♥
今日取り上げるのは、「ランチェスターの法則」 「ランチェスターの法則」 第一次世界大戦 「戦力二乗の法則」
「第一法則」 「一騎打ちの法則」 「第二法則」 「集中効果の法則」 「戦闘力= 武器効率(質)×兵力数の2乗」 兵力と火力の積の小さいほど、戦闘をするたびに加速度的に損害が大きくなり、結局は敗けるというものです。例えば、戦闘機100機と50機が戦うと、二乗の法則が働き、50機の方は全滅し、100機の方はわずか14機の損害ですむというのです。戦力を分散させずに、ここぞというポイントに集中させた方が勝つというのは、誰にでも分かる戦術ですね。この法則をビジネス界にあてはめてみると、ライバル会社に勝つには特定の分野に資本も労力も集中させた方が良いということです。しかもこの法則に従えば、たとえ小企業とはいえ、特定の分野や地域に全戦力を集中させれば、限定つきとはいえ、大企業にも勝ち得るということになります。現実に、経営者の中にはこの一点集中法で成功をおさめた人が多いのです。これが「ランチェスターの法則」
アシックス 鬼塚喜八郎(おにつかきはちろう)社長 鬼塚社長 「錐もみ商法」(きりもみしょうほう) 「錐もみ商法」 鬼塚会長 「経営資源が分散しないように一点集中で事を進めていく」 「経営資源とは面積で表すことができ、同じ力(面積)であっても横に広げるよりも縦に伸ばすほうが対象に刺さりやすい」 「オニツカタイガー」 鬼塚会長 オニツカ 「この商品どう思う?」 鬼塚会長 「最終顧客に密着」 最終顧客 鬼塚会長 「オニツカタイガー」 「オニツカ」 鬼塚(株)
バスケットボールの一流選手が「オニツカタイガー」 鬼塚会長 「錐もみ商法」 ランチェスター「弱者の戦略」
その後、鬼塚(株) 鬼塚会長 「錐もみ商法」 鬼塚会長 ランチェスター戦略 「自分のやってきたことがランチェスター戦略なんだ」
後に、(株)オニツカ、(株)ジィティオ、ジェレンク(株) (株)アシックス ランチェスター戦略 アシックス 野口みずき アシックス
「我々は、技術ありき、生産ありき、販売ありきのビジネスをしてきた。しかし、彼らは、工場に投資する代わりにマーケットに投資している。今後、我々が飛躍するためには、見習うべきところは見習わないといけない」 ランチェスター戦略 「起業は弱者の戦略で」 ランチェスター戦略 オニツカ オニツカ 鬼塚喜八郎 「オニツカ錐もみ商法」
こうしてオニツカ アディダス 鬼塚 オニツカ アシックス アシックス ミズノ 「強者の戦略」 「起業は弱者の戦略でナンバーワンを目指す。1位になったら強者の戦略へ切り替えよ」 「ランチェスターの法則」 ♥♥♥
10月に巨人を戦力外となっていた重信慎之介外野手(しげのぶしんのすけ、32歳) 「すべての可能性をフラットに」 「自分でも辞めるときはスパッと辞めるのかなと思っていたけど、時間がかかりました。今は次に進むしかないという前向きな気持ちです」 「10年前、夢と覚悟を胸にこの世界に飛び込み、毎日が挑戦であり、学びであり、戦いでした。うまくいかない事がほとんどでしたが、うれしいことも悔しいことも沢山経験させていただきました。そのすべてが自分の財産であり、かけがえのない時間です」 「入団してから今日まで、たくさんの方々に支えられ、ここまで野球人生を歩んでくることができました。指導してくださった監督・コーチの方々、チームメート、裏方の皆さん、そしてどんな時も応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました」 「どんな時も応援してくださったファンの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんの熱い声援、拍手、笑顔が、自分にとってどれだけ力になったことか。思うような結果が出せず苦しんだ日々も、皆さんの存在が前を向いて走る力になっていました」
▲重信選手のトレードマークのヘッドスライディング
早稲田大学 「だからこそ野球には絶対に手を抜きたくなかった」 坂本 小林 「何か予定や目標がないといけない。じっといていられないタイプなんですよね」 重信選手 ♥♥♥
私は全国に100以上ある「 水族館 を制覇する」 「須磨シーワールド」 「京都水族館」 水族館 サメ 水族館 サメ 「JAWS」 サメ サメ ジンベイザメ 水族館
サメ 水族館 サメ 水族館 サメ サメ 水族館 サメ サメ サメ サメ なんかの菌『水族館飼育員のただならぬ裏側案内』(集英社インターナショナル、2025年) サメ サメ ▲この本実に面白い!!
要するに、サメ 水族館 ①餌が与えられていること 、②共存しやすい環境が作られていること 、そして、③個体ごとの行動パターンなどが影響している からです。
さて、厳密に十分なエサを与えられてお腹がすいてはいないはずなのに、実はまれに、サメ スチーブン・ スピルバーグ 「ジョーズ」 サメ サメ サメ サメ サメ 水族館 サメ
そうなると大切な魚の数がどんどん減っていってしまいますが、それでもサメ 「外敵がいる状態(自然に近い環境)を作ることで、他の魚たちが自然に近い行動を起こすようになるから」 イワシ イワシ コチラ に書きました)。これは外敵がいる緊張状態だからこそ見られる光景なので、サメ イワシ 水族館 ♥♥♥
『現代用語の基礎知識』(自由国民社) 『現代用語の基礎知識 選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」』 「ノミネート語30」 トランプ大統領 「前半は新語・流行語が少なかったと言えるが、トランプ大統領の再登場で関税関連、その後、米、物価高、異常気象、首相首班指名等で数多くの言葉が生まれた」 「それらの言葉は来年にもつながるものだろう(例えば、クマ被害、気象、高市首相関連等)。また、ピンポイントで盛り上がった言葉(ミャクミャク、国宝、古古古米等)に勢いがあった」 「本年度はスポーツ関連の言葉が少ない珍しい年でもある。分断が叫ばれる昨今、政治のエンタメ化も進み、ネットとオールドメディアの岐路とも言える年ではないだろうか」
■発表された「ノミネート語30」
「エッホエッホ」 「オールドメディア」 「おてつたび」 「オンカジ」 「企業風土」 「教皇選挙」 「緊急銃猟(クマ被害)」 「国宝(観た)」 「古古古米」 「7月5日」 「戦後80年(昭和100年)」 「卒業証書19.2秒」 「チャッピー」 「チョコミントよりもあ・な・た」 「トランプ関税」 「長袖をください」 「二季」 「ぬい活」 「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」 「ビジュイイじゃん」 「ひょうろく」 「物価高」 「フリーランス保護法」 「平成女児」 「ほいたらね」 「麻辣湯」 「ミャクミャク」 「薬膳」 「ラブブ」 「リカバリーウェア」 では、英米にはこのような流行語大賞 ウェブスター辞典 メリアム・ウェブスター社 「ワード・オブ・ザ・イヤー」(Word of the Year) 「ワード・オブ・ザ・イヤー」 「流行語大賞」
メリアム・ウェブスター社 「ワード・オブ・ザ・イヤー」 「Polarization(分極化)」 ウェブスター 「Polarization」 「2つの顕著に異なる対立グループに分裂すること。特に、グループや社会における意見、信念、または利害が連続体ではなく、対立する両極端に集中する状態」 ウェブスター ピーター・ソコロフスキ 「この言葉には少し皮肉なところもありますが、実際には誰もが同意するものです」
一方イギリスでは、ウェブスター 「Polarization」 『 オックスフォード英語辞典』 オックスフォード大学出版局 「ワード・オブ・ザ・イヤー」 オックスフォード 「ワード・オブ・ザ・イヤー」 「Brainrot(脳ぐされ)」 「Brainrot」 「Brainrot」 brainrot rotted my brain オックスフォード大学出版局 「Brainrot」 「特に、取るに足らない、または挑戦的でないとみなされる素材(現在は特にオンラインコンテンツ)の過剰消費の結果として生じると思われる、人の精神状態または知的能力の低下。また、そのような低下につながる可能性があるとされるもの」 「弊社の専門家は、特にソーシャルメディアにおける低品質なオンラインコンテンツの過剰消費の影響に対する懸念を表現する言葉として、「brain rot」が今年新たに注目を集めたことに気づきました。この用語の使用頻度は、2023年から2024年の間に230%増加しました」
言葉の意味について考えてみます。brain rot Brain Rot 「脳ぐされ」 Brain Rot Brain Rot 「Slop」 Brain Rot 「脳が腐ってドロドロになりそうな、そんなインターネット環境に生きる私たち」 Brain Rot
日本における2024年の流行語大賞 「ふてほど」 「Polarization」 「Brainrot」 「ワード・オブ・ザ・イヤー」 「Polarization」 「Brainrot」 「Brainrot ♥♥♥
大好きなさだまさし 「グレープ」 「精霊流し」(1974年) 「根暗」 「無縁坂」(1975年) 「マザコン」 「雨やどり」(1977年) 「軟弱」 「親父の一番長い日」(1979年) 「長すぎる」 さだ 山本直純(やまもとなおずみ)先生 「歌に時間制限があるのはおかしい」 「初めから批判覚悟で作った」 「二百三高地」 「防人の詩」(1980年) 「戦争礼讃」「右翼」 広島 長崎 「夏 長崎から」 「売名行為」「偽善者」
彼の代表曲でもあり、自身最大の炎上ソング「関白宣言」(1979年) 「女性蔑視」 「これで関白ならあんたの人生たいしたことない」 さだ 「こういう時代にあって「関白宣言」は歌いづらくなっているのですが、今日は原曲のままお届けします 」
さだ 「誤解っていうか、ちゃんと(最後まで)聴いてくれないんだよね。僕の歌長いから…」 「ちゃんと志を持って何かを伝えようとするのであれば、批判されることを恐れてはいけないと僕は思っています。僕らが発言していかなきゃいけない、本当は音楽にはそれだけの力があったんですが。だんだんにね、そういうことも難しくなってきつつある環境のなかで。でも僕はやり方を変えないでやっていこうと思う」 「決して炎上させたくて歌を作っているわけじゃない」
関白宣言 作詩・作曲 さだまさし
お前を嫁にもらう前に 言っておきたい事がある かなりきびしい話もするが 俺の本音を聴いておけ 俺より先に寝てはいけない 俺より後に起きてもいけない めしは上手く作れ いつもきれいでいろ 出来る範囲で構わないから 忘れてくれるな仕事も出来ない男に 家庭を守れるはずなどないってこと お前にはお前にしか できないこともあるから それ以外は口出しせず 黙って俺についてこい お前の親と俺の親と どちらも同じだ大切にしろ 姑小姑かしこくこなせ たやすいはずだ愛すればいい 人の陰口言うな聞くな それからつまらぬシットはするな 俺は浮気はしない たぶんしないと思う しないんじゃないかな ま、ちょっと覚悟はしておけ 幸福(しあわせ)は二人で 育てるもので どちらかが苦労して つくろうものではないはず お前は俺の処へ 家を捨てて来るのだから 帰る場所は無いと思え これから俺がお前の家 子供が育って 年をとったら 俺より先に死んではいけない 例えばわずか一日でもいい 俺より早く逝ってはいけない 何もいらない俺の手を握り 涙のしずくふたつ以上こぼせ お前のお陰でいい人生だったと 俺が言うから必ず言うから 忘れてくれるな 俺の愛する女は 愛する女は 生涯お前ひとり 忘れてくれるな 俺の愛する女は 愛する女は 生涯お前ただ一人 VIDEO 「関白宣言 「王手」 「関白宣言」 「女性差別」、「女性蔑視」、「男尊女卑」 「ウーマンリブ運動」 「こんなにわがままを言う男がいるから世の中がダメになる」 「不器用な男のラブソング」 「愛する女は 生涯 お前ただ一人」 「俺より先に寝てはいけない 俺より後に起きてもいけない」 さだ 「歌を歌って悪口を言われ、日本に居場所がない」 中国 「長江」 中国 「高い塔はその影の長さで高さを測る。偉大な人は批判者の数で偉大さを測ることができる」 「一気に(バッシングが)気にならなくなった」
加藤タキ さだ 「『関白宣言』でまさし君が叩かれたとき、メディアを通じて母が吠えてた」 加藤シヅエ 「関白宣言」 「みんな行間をどれだけ読んでるのか?」 安倍寧(あべやすし) 「加藤シヅエがさだまさしを応援」 シヅエ先生 「関白宣言」 「行間を読みなさい!」 「何をみんな読んでいるのですか。何を聞いているんですか」 シヅエ先生 「私のファイティング・スピリッツがまたムクムクと」 「ありがとう」 「関白宣言」 さだまさし・加藤タキ 『さだまさしが聞きたかった、「人生の達人」タキ姐のすべて』(講談社、2023年) その当時、行間を読んで(英語ではread between the lines と言います)くれる人などいませんでした。さだ 「関白宣言」 遠藤周作先生 森繁久彌 山本健吉先生 「お前が言いたいのはここじゃないのはわかってる」 加藤シヅエ先生 「行間を読みなさい」
結婚をする前に、一緒になる女性に対して男性側の希望を言うこの曲の歌詞は、ちょっとくすっと笑えて、それでいて泣ける映画のようなストーリーが大きな魅力です。この曲を作ったそもそものきっかけは、“スナックのママの一言”でした。実は当時、山本直純先生 さだ 京都 スナック「鳩」 「最近の男は駄目になった。だから若い娘も駄目になった。男はん、しっかりしとくれやっしゃ。お師匠はん、そういう歌を作っとくれやっしゃ」 「まだ甘い」
現代において、「俺より先に、寝てはいけない! 俺より後に起きてもいけない!」 「関白宣言」
歌詞が物議を醸しメディアにも大きく取り上げられた「関白宣言」 林修(はやしおさむ)先生 「初耳学」
【後日談】 「関白失脚」 「関白宣言」 さだ ♥♥♥ VIDEO
◎週末はグルメ情報!!今週はピーナツホイップ レーズン食パン バルミューダ 「パン屋さんの粒入りピーナッツホイップ」 松江市・ 田和山 「森のくまさん」 「パン屋さんの粒入りピーナッツホイップ」 「PEANUT & WHIPPED PEANUT CREAM」 ピーナッツクリーム
「パン屋さんの粒入りピーナッツホイップ」 丸和油脂株式会社 ピーナッツホイップ 「森のくまさん」 ♥♥♥
▲ふんわり軽いホイップ食感
▲これが最高っ!
「新聞報道は本当に当てにならない!」ことを実感しました。先日、米記者協会所属記者の「複数の関係者は、読売ジャイアンツが今季終了後に岡本和真をポスティングしないと見ている」
岡本和真内野手(おかもとかずま、29歳) 岡本選手 山口 俊投手 菅野智之投手 岡本選手 山口オーナー 「ずっと憧れでもありましたけど、常に目標にしていた。そういう舞台に行ける選手になりたい、行って戦える選手になりたいと思って今も取り組んでいますし。そういう気持ちは変わらずにずっと持っていました」 松井秀喜選手 「メジャーに挑戦しなければ、やめた時に後悔すると思う」 岡本選手 今オフのポスティングシステムでの挑戦については、ケガもあり「本当に日本一にできなかったので申し訳ない気持ちもあるが、僕としてもMLBで勝負したいという気持ちが強くて。どちらが強いというのはないが、ただ勝負したいという気持ちがあった」 「もちろん厳しい世界だということは分かっている。日本に残った方がいい、とか厳しい声もあるだろうし。ただ、それは自分が行ってみないと分からないこと。やってみないと分からないので、そういうことも承知の上で勝負したい」 「本当にない。欲しいと言ってくれる球団があれば本当に僕はどこでもうれしいです」 奈良・智弁学園高 「ケガが思ったよりひどかったので、自分のスイングができるかとか、ちゃんと治るのかとか不安はありましたけど、そこでメジャー挑戦を断念する気持ちはなかったです」
万能ぶりも兼ね備えた伝統球団の主砲に海を渡る機会が訪れたとあって、今後は激しい争奪戦が繰り広げることが予想されます。今季中にはカブスやフィリーズなど複数の球団関係者が視察に訪れ、岡本選手 松井秀喜 「ヤンキースのキャッシュマンGMは大谷(現ドジャース)の獲得にも失敗したため、日本人の大砲探しに躍起になっている。一部では村上(ヤクルト)の移籍先はメッツが最有力という話も出ている。岡本を是が非でも獲りたいはずだ」 岡本 「岡本は守備も良く、打撃の調子のムラが少ないことも魅力の一つと捉えられている。巨人とは業務提携を結んでいるだけに、情報共有もされているだろう。岡本獲得へは一歩リードしている部分は確かにある」
巨人・吉村編成本部長 「彼の描いている夢を球団がバックアップしながら、背中を押して挑戦させてあげたいなという気持ちになった」 「主軸、4番を長年務めてもらった岡本くんの抜ける穴を埋めるのは大変ですけど、彼がアメリカで活躍しながら日本のジャイアンツを見守って喜んでもらえるようにチームづくりをしていきたい」 坂本勇人選手 「寂しいですけど、彼がメジャーの舞台で活躍してる姿を早く見たい。活躍すると信じているので楽しみにしています」
ただ来季の巨人軍がとても心配です。今季に左肘じん帯損傷で離脱していた時期の巨人打線のひどさを思い出します。それでもケガを乗り越えて69試合で打率3割2分7厘、15本塁打、49打点と、存在感を発揮しました。通算1974試合出場、打率2割7分7厘、248本塁打、717打点と巨人打線を牽引してきた4番がもういません。一体どうするのでしょうか?リチャード 浅野 岡本 「代わりにはなれないですけど絶対、オレが打つっていう気持ちで動き出しています」 リチャード ♥♥♥
メリアム・ウェブスター 12回目 となる、アメリカ辞典界の老舗メリアム・ウェブスター社 『メリアム・ウェブスターカレッジエイト辞典』(Merriam-Webster Collegiate Dictionary ) 『第12版』 第12版 cold brew 、farm-to-table 、rizz 、dad bod 、doomscroll 、ghost kitchen 、cancel culture 、petrichor 、teraflop 、dumbphone 、hard pass 、adulting 、beast mode 、dashcam 、WFH 、side-eye 現代の言語と文化を反映したものとなっています。 新版では新たに、厳選語彙リスト(例:「1990年代の語彙」「名前が付けられないことが多いもののための10の単語」 calculate はラテン語で「小石」を意味し、古代ローマ人が足し算や引き算に小石を用いたことに由来)などが導入されました。親しみやすいアルマジロからトゲだらけのゾエア(「甲殻類の多くに見られる遊泳性プランクトン幼生」)まで、古典的な線画も健在です。何世代にもわたり、Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 第12版 印刷辞書の販売は前年同比で9% 減少した(~9月6日)ものの、デジタル化の成長に支えられ 総収入は安定している、と同社は報告しています。同社のウェブサイトは毎年10億回近く訪問されています。 オンラインアクセスへの移行にもかかわらず、物理辞書はバーンズ&エンターテインメント 『カレッジエイト』 メリアム・ウェブスター社 メリアム=ウェブスター 「過去10年間で、 オンライン辞書、シソーラス、モバイルアプリ、単語ゲームなどの強みを活かして、 当社の収益はほぼ500%増加しました。その大半はデジタル製品によるものです」とバーロウは語る。「しかし私たちは今も本を愛しています。だからこそ第12版を誇りに思うのです。この美しい赤い辞書は、事業規模では最大ではないかもしれませんが、多くの点で事業の心臓部なのです」 『カレッジエイト』第11版 メリアム・ウェブスター社 グレッグ・バーロウ社長 「人々はもはやカラマズーの位置やニコライ・リムスキー=コルサコフが誰かといったことを辞書で調べない。そのためにはインターネットを利用する」 enwheel 」など、難解で古風な語句も削除しました。「『カレッジ版』をより実用的で、デザイン性が高く、興味深いものにしたいと考えました」 バーロウ社長 「閲覧する喜びや楽しさを高め、研究に実用的なだけでなく、美しい本として完成させたかったのです」 分厚いリネン装丁の「カレッジエイト」新版 メリアム・ウェブスター社 バーロウ社長 「カレッジエイト」 。「印刷辞書は、この素晴らしい言語企業の成長や収益性にとって全く重要ではないが、それでも私たちの心の拠り所だ」 バーロウ社長 「本が大好きな人々が世の中にはいる。私たちも本を愛している」
「棚から辞書を取り出して単語を調べるという行為に、人々が感じるノスタルジーは確かに存在します」 「こうした参考書を自宅に置きたいという欲求があるのです。人々が感じる『何か』なのかもしれません」 メリアム・ウェブスター社 「カレッジエイト」 バーンズ・アンド・ノーブル オックスフォード大学出版局 「A Way with Words」 グラント・バレット 「現在、私たちは奇妙な状況に陥っています。人々は辞書を求めているものの、インターネットでは無料で情報を得られることに慣れているため、辞書にお金を払いたくないのです」 メリアム・ウェブスター社 バーロウ社長 『カレッジエイト』 lettered thumb notches )をそのまま残し、閲覧しやすくしています。バーロウ社長 メリアム・ウェブスター社 インド
紙の印刷版は、文化の保存、贈り物、家庭用品、学校での携帯電話の使用が禁止されている学生など、さまざまな理由で依然として重要です。「これまで記録されたことのない言語を話すコミュニティは数多くあり、それらの言語は積極的に抑圧されてきたために記録が残っていないのかもしれません。北米全域の先住民コミュニティが思い浮かびます」 北米辞書協会 リンジー・ローズ・ラッセル 「印刷された辞書があることは、その言語の正当性を示すものとなっています」 イリノイ大学 ラッセル 「辞書を瞑想の道具のように使う人もいて、辞書を開いて目についた単語をちょっと眺めながら、ちょっとだけ思考をさまようような感じですね」 Asahi Weekly 10月26日号では、この大改訂が取り上げられました。♥♥♥
【今回新語として取り上げられた語の例】 petrichor :乾燥した大地に雨が降ったあとに草花から放たれる心地よい香り
teraflop :1秒間に1兆回の活動小数点演算を実行可能《コンピューターの処理速度
を表す単位》
dumbphone :スマホ以外の低機能な携帯電話
farm-to-table :地元産の新鮮で安全な食材を使用する食の考え方
rizz :自然に沸き起こる魅力
dadbod :やや肥満気味のお父さん体形
hard pass :断固とした拒絶
adulting :大人としての自覚を持った振る舞い
cancel culture :社会的に好ましくない言動や行動を糾弾し、その当事者や集団を
排除する動き
Doomscroll :スマホなどで暗いニュースをひたすらスクロールして読むこと
WFH :在宅勤務(work from homeの略)
side-eye :軽蔑のまなざしを向けること
11月11日 は「チンアナゴの日」 チンアナゴ 東京スカイツリー 「すみだ水族館」 チンアナゴ チンアナゴ 「チンアナゴの日」 日本記念日協会 チンアナゴ チンアナゴ 日本記念日協会 チンアナゴ
▲京都水族館のチンアナゴ
「チンアナゴ」 顔が日本のワンちゃん「狆(ちん)」 なんです。英語では「スポテッドガーデンイール」(Spotted Garden Eel) チンアナゴ チンアナゴ チンアナゴ チンアナゴ 「チンアナゴの日」
プランクトンの取り合いで小競り合いをすることも
巣穴が近すぎると縄張り争いになることも
他の種類(ニシキアナゴやゼブラアナゴ)とは混ざらず、同種同士でコロニーを形成
チンアナゴ チンアナゴ チンアナゴ
調べてみて判ったのですが、11月11日は、記念日だらけな特別な日のようです。11月11日は、「チンアナゴの日」 ♥♥♥
記念日名
由来・理由
ポッキー&プリッツの日 細長くて「1」に見えるポッキーやプリッツ
麺の日 うどんやそば、麺のカタチが「1」みたい
サッカーの日 11人対11人でやるから
鮭の日 「鮭」の漢字が“魚へん”+「十一十一」
たくあんの日 大根を並べて干す様子が「1111」になるから
チンアナゴの日 チンアナゴが「1」に似てる、みんなで並んでいる姿が「1111」みたい
▲実に勉強になる面白い特集だった!
外国人教授が、新入生最初のレポート提出を求めたところ、下記のようなカバー・レターと共に、送られてきました。このカバー・レターにはさまざまな問題点が存在しますが、みなさんはどれくらい気がつきますか?ご興味のある方は、『CNN English EXPRESS』1月号(2017年、朝日出版) 「知らないと大ケガ!誰も教えてくれなかった英語の“リアル”丁寧表現」 ティモシィ・ミントン教授(Timothy D.Minton, 慶應義塾大学医学部教授) Dear Mr. Minton,
Hello.
I am sending you my assignment.
Please check it. 命令文にplease 中学校の英語の授業を思い出してみると、確かに「お願いごとをするときは命令形に “Please” をつける」 そのように学校で習ったものですから、当然と言えば当然のことかもしれませんね。ミントン先生 「命令そのものが不適切な状況や相手に使われている場合には、pleaseを付けても丁寧表現にはならないのです 」 “Please check it.” で考えてみましょう。命令する人(学生)とこれを受け取る人(教授)の関係を考えれば、そもそもこうした命令自体が不適切なものですから、いくらplease 日本で最もよく使われている『ジーニアス英和辞典』(大修館) 『ジーニアス総合英語』(大修館、2017年)
pleaseはどんな命令文にもつけられるわけではありません。相手がその行動をすることで話し手が利益を受ける場合に使うのがpleaseの基本です 。 Please bring me a cup of coffee. コーヒーを持ってきてください。 しかし、話し手でなく聞き手の利益になる場合でも、話し手が心を込めて相手に行動を促す時には、pleaseを文頭で使うことができます。 Please make yourself at home. どうぞお楽にしてください。 話し手の利益にならず、話し手が心を込めて行動を促すのでもない、指示や忠告を表す命令文にはpleaseをつけません。たとえば道案内のようなケースです。 Go straight and turn left at that corner. ×Please go straight and turn left at that corner. まっすぐ行ってあの角を左に曲がってください。 日本語の「~してください」は丁寧な言い方としてさまざまな場面で使えますが、pleaseには使える条件があります。やみくもにpleaseを使わないように注意しましょう。(p.41) 次の文は英文メールでよく見かける表現ですね。実際のところ、相手にどのような印象を与えると思いますか?
Please send the file by Friday.
命令文にPlease please
まずplease 「なあーんだ、やっぱりていねいになるじゃん」 please “Please give me all your money.” と言われても、「有り金を全部よこせ」という要求の理不尽さ自体に変わりはありません。“Please lend me 10,000 yen.” も理不尽な命令にあたります。「金を貸せ」などと命令する権利は誰にもないのです。冒頭の学生が教授にレポートをチェックしてもらいたいと、“Please check it.” (どうぞチェックして下さい)という言い方にネガティブに反応するのも同じ理由です。命令する人(学生)とこれを受ける人(教授)の関係を考えれば、そもそもこうした命令自体が不適切であり、これにplease please 相手にその行為を強く求めることが適切かどうか 」を考えることです。答えがイエスなら、please
Please sit down. これは「お座りください」のようなニュアンスになるでしょうか。答えはノーです。Sit down. は直接的な動作を伝える上から目線の命令です。Please “Please have/ take a seat.” のような表現をお勧めします。同じplease please “Please take a seat.” と言う場合は、命令しているようなものです。招待客の場合も、“Please take a seat.” と言われると窮屈に感じる可能性があります。ちょっと部屋を歩き回って、飾ってある写真やカーテンなどを眺めていたい、と思っているかもしれないからです。お客様にくつろいでもらいたい、というおもてなしの気持ちが、これでは逆効果になってしまいます(詳しくはT. ミントン『日本人の英語表現』(研究社、2012年) Close the door. (ドアを閉めろ)は命令的な文章です。一方、Please close the door. は一見丁寧そうですが、場面によってはイライラしているように聞こえます。怒っているけどギリギリ礼儀を保っているような印象を与えることもあります。「懇願」 「いらだち」
Please transfer at this station. ? この駅で乗り換えてください。→「お願いだから、この駅で乗り換えてください」というニュアンスに聞こえているかも
以下はplease
Please sit down. Please wait a moment. Open the door, please. Please send the file by Friday. 以下は相手に行動を強要するものではないため、命令にはならず、失礼になりません。このようなものは決まり文句となっていますね。
Please find (take a look at) the attached file. Please (kindly) be informed that my e-mail address has been changed to XXXX. Please do not hesitate to let us know in case of any questions. 丁寧な文にするコツは相手に選択肢を与えること です。では丁寧な、あるいは礼儀正しい表現はどのようにすればよいのでしょうか。先ほど見たサンプル文を丁寧なものにしてみましょう。下に行くほど丁寧になります。求められる丁寧さの度合いに応じて使い分けるのです。
Please send the file by Friday. Could you send the file by Friday? I was wondering if you could send the file by Friday? Is it possible for you to send the file by Friday? ポイントは相手に選択肢を与える ことです。Please Could you …? とすると、回答はイエスとノーの2通りできることになります。通常、イエスの答えを期待しているときの依頼のしかたですが、一般的に良く使われ、十分丁寧ではあります。I was wondering if you could … とIs it possible for you to …? もイエスとノーの回答ができる上、相手の都合も考慮しており、かなり丁寧な表現になります。
ソフトウェアの英文を日本人が書くと、次のようになることがよくあります。
Please click XXXX button. これをネイティブに校正してもらうと、必ず“Click XXXX button.” と修正されます。ユーザーに操作してもらうとき、“Click XXXX button.” で「XXXXボタンを押してください」のニュアンスが含まれます。Please
英語の命令形と日本語の命令形を同一に考えてはいけません。日本語と英語は、文法構造も異なり、言葉の発展してきた背景や経緯も異なる2つの言語です。考え方や使い方が異なるのは当然です。それでも、コミュニケーションには相手を思いやる気持ちが大切なことはどちらの言葉でも変わりません。please ♥♥♥
トンネルを抜けると駅に着きます。駅を発車するとまたトンネルに入ります。新幹線の新神戸駅 JR新神戸駅 「なんでこんな山の中に新幹線の駅を作ったんだろうか?!」 新神戸駅 神戸市 新神戸駅 神戸市営地下鉄 JR 阪急 阪神 「三ノ宮駅」 神戸市営地下鉄 バス 神戸市営地下鉄 「三宮駅」
いったいなぜ、「新神戸駅」 「三ノ宮駅」 弾丸列車 弾丸列車 東京 下関 東京 大阪 東京 下関 弾丸列車 弾丸列車 「新神戸駅」 神戸 「新神戸駅」 神戸市電 布引 「新神戸駅」 弾丸列車 東京 大阪 弾丸列車 山陽新幹線
案 場所 メリット デメリット
1.背山案 六甲山北側 用地買収が容易・トンネルが短い ルートが大回り・駅が市街地から離れる
2.中央案 六甲山中央 距離が短い 新幹線駅の設置ができない・トンネルが長い(23キロ)
3.◎表六甲案 六甲山南側 駅が市街地から近い 半地下方式
4.海岸案 海岸平野部 駅が市街地から近い 密集地・港湾を高架橋で通過するため実現が困難
表六甲案 弾丸列車 布引 「新神戸駅」 竹内正浩『妙な線路大研究 東海道・山陽・九州新幹線篇』(2022年) 山陽新幹線 「新大阪駅」 「岡山駅」 「新神戸駅」 神戸トンネル 六甲トンネル 神戸市電 神戸市営地下鉄 北神急行 「三ノ宮駅」 神戸市内 「三ノ宮駅」・「元町駅」・「神戸駅」・「新長田駅」 神戸市営地下鉄 「新神戸駅」 新幹線「のぞみ」 「新神戸駅」 東京・名古屋 神戸 「新大阪駅」 「三ノ宮駅」 「のぞみ」 「新神戸駅」
駅の構内にはレストランやお土産物屋さんがあり、時間つぶしにはもってこいです。改札内に入ると作業のできる「モバイルコーナー」
神戸 「新神戸駅」 「新神戸駅」 「三ノ宮駅」 ♥♥♥
ワールドシリーズはドジャース 山本由伸(やまもとよしのぶ)投手 「野球少年に戻ったような」 山本投手 山本投手 「僕が投げます。ワールドシリーズで野手に登板さえるようなことはしない」 ロバーツ監督 山本投手 キケ・ヘルナンデス選手 “You know what? Losing isn’t an option . Thank you my teammates, my coaches, our amazing staff and all the fans. We did it together! I love the Dodgers, I love Los Angeles! ありがとう!”(負けるという選択肢はない→何としてでも負けるわけにはいかない)ロバーツ監督 「翔平と同じで、何か人間を超えたものがある。練習の時も常に完璧を目指してるんだ。ヤマモトは素晴らしい人物で、チームのためにやってくれた」 スネル捕手 「ブルペンでもそうだよ。フォームも表情も全く崩れない。“壊れないマシン”ってみんなで呼んでる」
ドジャース(Dodgers) “dodge” 「よける、かわす」 「ドッジボール」 “Dodgeball” er ”を付けて“Dodgers”(よける人たち) s ”が最後にきています。これが基本的な意味になりますが、では一体何を「よける人たち」なのでしょうか?
何をよける人たちなのかは、チームの歴史を少し紐解く必要があります。ロサンゼルス・ドジャース ニューヨーク ブルックリン 「馬車鉄道(horsecar)」 「路面電車」(trolley) ブルックリン
これがきっかけで「ブルックリンの人たち=路面電車をよける人たち(trolley dodgers)」 “trolley dodgers” ブルックリン(Brooklyn) trolley 「Brooklyn Dodgers」 Dodgers ロサンゼルス・ドジャース(Los Angles Dodgers)
さてもう一つ、発音ですが、日本語では「ドジャース」 dodgers 「ダジャーズ」 Yankees「ヤンキーズ」 s 」は基本的に「ズ」と発音されます。それなのに、なぜ日本では「ドジャース」「ヤンキース」と「ス」で表記するのでしょうか。実はこれ、日本の慣習による表記なのです。日本のメディア、特に読売新聞やNHK、共同通信などでは、1950年代から1960年代にかけて「ス」表記が定着しました。当時は英語の発音よりも、日本語として読みやすく、書きやすい表記が優先されたのです。そのため「ドジャース」「ヤンキース」 「マリナーズ」 「ブリュワーズ」 ♥♥♥
「 お金を稼ぐことを目的に仕事をやっている人」 「 良い仕事をすることを目的に仕事をしている人」 「お金持ちになりたい」「地位や名誉を得たい」「格好良くみられたい」「家族を幸せにしたい」「もてたい」「マイホームを持ちたい」
良い仕事をすることを目的に仕事をしている人は、常に、今以上に良い商品やサービスを提供しようとして頑張ります。良い商品やサービスを提供し続ければ、お客さまは喜んでくれます。お客さまが喜んでくれたら、その分、結果として売り上げや利益が出ることになります。売り上げや利益が出るということは、会社であれば、儲かった分を社員や株主などに還元することもできます。さらには、納税により地域社会にも貢献することができますね。つまり、良い仕事をすることを目的にしている人は、「結果として」儲かるわけです。お客さまのため、社会のためという「利他心」 「利己」 「利他」
でも、実際は、なかなかこういった気持ちになれる人は少ないのです。お金や地位が目的化していることが、誤りだと気づいていない人も多いのかもしれません。そういう人は、仕事がだんだん荒れてくるか、疲れてきます。ルンルン気分で仕事をすることができなくなってきます(皆さんはルンルン気分で仕事をしていますか?)。お金や地位が目的の人は、一時的に地位やお金を得ても、本当の幸せにはなれず、地位やお金もあだ花のようにいずれは消えてしまいます。お金儲けをしようとする人ほどお金儲けができないのです。良い仕事をしようと全力を尽くせば、結果お金はついてくるのですが。重要なことは、お金を稼げるぐらいに良い仕事をすることなのです。「お金を追うな、仕事を追え」
お金儲けがしたいと思う人が儲からないのは、金儲けすることが仕事の目的になっているため、「お客さまのために」良い仕事をするという気持ちが二の次になってしまうからです。最初は「お客さまのため」と思っていた人も、お金儲けが目的になった途端に、お客さま志向はどんどん希薄になってしまいます。良い仕事をする気持ちが希薄になると、効率性ばかりを重視するなどして仕事はどうしても荒れてきます。「お客さまのために何ができるか」という肝心な視点も抜け落ちますから、当然、商品やサービスの質が低下します。人によっては法律違反まで犯してしまいます。これでは、到底、お客さまに喜んでもらうことはできず、結果として、会社全体の売り上げや利益は下がってしまいます。売り上げや利益が下がれば、社員や株主に還元することもできず、納税額も下がり地域社会への貢献度合いも低くなってしまいます。お金を追い求めると、坂道を転げ落ちるかのように経営が悪化し、何もかもがうまくいかなくなるというのはよく聞く話です。自分の利害ばかりを考える「利己心」で仕事をすると、仕事の質は低下しますから、結果的には儲けることはできないのです。これは別にビジネスの世界だけに限ったことではなく、役所でも政治家でも、教育の世界でも同じです。仕事を「手段」にしている人には限界があるのです。
一万円札の肖像になっている「日本資本主義の父」 渋沢栄一 「論語と算盤は一致すべし」 「論語」(=道徳) 「算盤」(=経済) 算盤 算盤 論語 算盤
私の経験で言えば、大学に入れることだけを目標に頑張っている先生と、英語の力を付けることを目標にひたすら努力している先生とでは、明らかに後者の先生の方が、大学に合格する生徒が多いし、卒業してからも感謝し続けてくれ、交流が続くようです。「お金を追うな、仕事を追え」 ♥♥♥
英語には、多くの学習者が混乱したり間違えやすいポイントがあります。その大きな理由が「日本語との違い」 「単数と複数」 単数 複数 “s” の付け忘れはよくあります。また、そんな “s” 以外にも、“Congratulations ” や “Thanks ”、“Cheers ” などにも必ず “s” がくっついてきます。これを高校生の中には間違える人がとても多いんです。英語では “Congratulation!” ではなく、必ず“s” をつけてCongratulations!
Congratulations on winning the award!(受賞おめでとう!)Congratulations on your graduation.(ご卒業おめでとう)Congratulations on passing the entrance exam.(入試合格おめでとう)みたいな感じですね。来日したトランプ大統領 高市早苗総理 “s” がつかない “congratulation” も単語としては存在しますが「おめでとう」の意味で使う場合は、いつも必ず “Congratulations ” になるので、s が無いととても不自然に聞こえます。この“s” には、元の言葉の意味を強める働きがあり、 「強意の複数」 s .やMany thanks .などにも“s” がつきますよね。 あふれんばかりの感謝の気持ちが複数形 s .” とは言っても、“Thank.” とは言いません。
このように、いつも複数形 s (もしくは es )が付くものは他にも、
Best wishes
Kind regards
My apologies
Cheers
Greetings
Condolences
などがあります。“s” をつけることで意味を強めているのですが、これらを見ていると、ある共通点に気付きませんか?お祝いの言葉だったり、幸せを祈る言葉だったり、謝罪の言葉だったり、挨拶の言葉だったり、哀悼の意だったり、これらを表したり伝えたりするのが上のフレーズや単語です。そこにはたくさんの言葉や気持ちが込められています。お祝いや謝罪の言葉、願いなどがたった一つではなくて、たくさん込められていますよ、という意味で複数形 「あふれんばかりのたくさんの祝福」 s !”、“My apologies ”、“My condolences ” の “s” を忘れることはもうないですよね!
まとめると、Congratulations! “s” は「強意の複数」 「あふれんばかりのたくさんの祝福」
それともう一つ。Congratulations! 「よく努力してあんないい旦那を射止めたね!努力が実ったね!」
〔参考〕 元来は新郎に対して言うものだが、最近では新婦にも言う人が多い。(『ライトハウス英和辞典』第7版) 〔語法〕 Congratulations!は努力して成功した人、めでたいことがあった人に贈る言葉。かつては、結婚式の場合、通例花婿に対して用い、花嫁にはI wish you great [every] happiness./ Best wishes!などと言うとされていた。しかし最近ではCongratulations (on your marriage)!も用いられるようになってきている。新年・クリスマスのあいさつには使われない。(『ジーニアス英和辞典』第6版) さらに、カジュアルな場面では、Congrats! ラ キャサリン・A・クラフト『簡単なのに日本人には出てこない英語フレーズ600』(青春出版社、2024年) ♥♥♥
You passed! Congrats!
『朝日新聞』11月3日付けの朝刊 「特派員通信 とらべる英会話」 「割り勘にしよう Let’s go Dutch.」 「相手がオランダ人やその関係者だったら、シャレにならないかもしれない。気持ちよく割り勘にするためにも、お互いをよく知る関係で使いたい表現だ」 「差別語」
その昔、覚えたてのこの英語を得意げに使ったことがあります。Go Dutch 「割り勘をする」 「割り勘」 split the bill を使いましょう。
オランダとか、オランダ人を意味するDutch Dutch
do the Dutch・・・自殺する Dutch courage ・・・酒の勢いなどの空元気 Dutch auction・・・セリ下げ競争(次第に下げていくセリ) double Dutch・・・さっぱりわからない言葉 Dutch uncle・・・ずけずけ批判する人 Dutch bargain・・・一杯やりながら取り結ぶ売買契約 Dutch comfort・・・さっぱりありがたくない慰め Dutch concert・・・バラバラな合唱 D utch gold・・・(銅と亜鉛の合金で模造金箔として用いる)オランダ金 Dutch defense・・・退却、降伏 I’m Dutch if it’s true.・・・それが本当なら首をやるぜ in Dutch・・・困難に陥った He is in Dutch with his boss.・・・あいつは社長の受けがよくない よくもまあここまで民族を卑しめることができるものだと感心させられますよね。変な意味、あまりよくない意味の言葉が多いのです。結局、これには歴史的な背景が関係しているんです。詳しくはR.Hendrickson, Encyclopedia of Word and Phrase Origins (1997)、Morris Dictionary of Word and Phrase Origins (1988)などを参照ください。イギリス・オランダ両国はシェークスピア時代のずっと後までは友好関係にあったのです。例えば、16世紀にスペインの属国であったオランダが独立を図ろうとした時、エリザベス1世は援兵を派遣しています。しかし、17世紀になると、オランダは海外に勢力を伸ばし英国を脅かし始めたのです。16~17世紀、オランダは海外に向かって大発展を遂げ、強国だったはずのイギリスをも圧倒していきました。イギリス艦隊を破ってジャワを獲得し、東インドからイギリス大勢力を追っ払ってしまいました。それまでのイギリスの優位が逆転してしまったため、オランダに対する恨みや劣等感から侮辱する言葉として盛んにDutch 「Dutch(オランダの)」
今話題にしているgo Dutch Dutch treat )」と言いながら、実際は「各自で払え」という意味。強烈な皮肉が込められていますね。外国人と食事に行って割り勘にしましょうと言いたいときには Let’s split the bill./Let’s have separate bills. を使うようにしましょう。
『大学入試瑛熟語最前線1515』(研究社、2024年) 「イギリスとオランダが軍事や貿易において覇権を競っていた17世紀に端を発するもので、イギリス人がオランダ人を蔑んだことによる。現在ではめったに用いられないが入試では出題される」 『ライトハウス英和辞典』(研究社) [ときに差別語] 『スーパーアンカー英和辞典』 ♥♥♥
本屋さんに行くと、『WiLL』 『Hanada』 『月刊WiLL』(ワック出版) ホテルニューオータニ 渡部昇一先生 「総合雑誌ですか、この時期にそれは剛毅ですね」 渡部先生 『WiLL』 ワック社 「ウィルアライアンス」(willalliance)
月刊誌 『WiLL』(ワック社) の元編集長、花田紀凱 飛鳥新社 『Hanada』 『 WiLL』 今井書店 『Hanada』 『 WiLL』 『WiLL』 「表紙から本文レイアウトまで模倣する行為は、不正競争防止法2条1項3号『商品形態の模倣』としかいいようがありません」 花田 『WiLL』 飛鳥新社 ワック社 花田 飛鳥新社 2016年4月、飛鳥新社 『WiLL』 花田編集長 『月刊Hanada』6月号 「一体何があったんだろう?」 今井書店 『WiLL』
『Hanada』 『月刊WiLL』 月刊『WiLL』 『Hanada』 月刊『WiLL』 『Hanada』
3月18日付で『WiLL』 「ワック」 鈴木隆一社長 『WiLL』 花田紀凱常務取締役 花田 『WiLL』 ワック 飛鳥新社 ワック 『WiLL』 花田
ご本人の説明はこうです。《2015年8月26日、突然、鈴木社長が「花田さんが私のストレスになっている。だから部員一同を連れてどこかの会社に移ってくれ。何なら広告担当のMさんも連れて行っていい」と言ってきたんです。僕は青天の霹靂というか、びっくりしました。実はその頃、鈴木さんは精神的にナーバスになっていて、言動もおかしなことがたくさんあったんです。そういうことがあったので、気が高ぶってそういうことを言っているのかもしれないから、僕はしばらく放っておいたんです。そうしたらまた何度もそういうことを言ってくる。「年内でどこか出版社を決めてくれ」と。移行には時間がかかりますからね。そうしたら「4月発売号をめどに替わってくれ」と。こういう話だったんです。そう何度も言われるんじゃしょうがないなと。それで僕は、出版社にも知り合いが多少いますから、いろんな方に話をして、飛鳥新社の土井尚道社長がぜひということで決まりました。決まったものですから、12月の初めに鈴木社長に報告したんです。飛鳥新社という名前はその時は出さずに、「ある出版社に決まりました」と。すると、いきなり鈴木さんは「花田さんもその出版社の社長もビジネス感覚がないね」と言うんです。まあ実際僕はビジネス感覚はないんですけどね(笑)。鈴木社長は「私はタダで持って行けとは言ってませんよ。そんな虫のいい話がありますか」と言う。「売る」と言うんですよ。「売ると言ったって鈴木さん、あなた出てってくれと、しかもしつこく言ってきたから私は探しただけだ」と。その間に売るなんていう話は一度も出ていませんでした。「そんなことは聞いてない」と言っても「それじゃビジネス感覚がない」と、この一点張りです。「じゃあ念のために伺いますが、いくらで売るんですか?」と訊いたら「5億円だ」と。今の出版大不況の中で、5億円も出して私と4人の編集部員とDTP担当1人を入れた5人を引き取って雑誌を継続しようなんていう出版社はないですよね。だから「そんなところないですよ。だったら鈴木さんが探して下さい」と言ったんです。》 《そのうちにいつの間にか、5億円という話は曖昧になってしまいました。一方で飛鳥新社には既に話はしているから、そちらはそちらで進んでいくしかない。それで、ワックで仕事をしながら飛鳥新社とも話を進めていました。一応5月号まではワックでやるということになっていたので、それまでは私は淡々と雑誌を作ろうと。よしんば別れることになっても、泥仕合ではなく淡々と別れましょうということはしきりに言っていて、その時は鈴木社長も「そうしよう」と言っていたんです。だけど、だんだん鈴木社長の言動もおかしくなるし、言っていることもエキセントリックになってきたんです。》
《昨年8月に鈴木社長から「花田さんは私のストレスだ」と、辞めることを申し渡されたのが騒動の発端なのだが、「私のストレス」とはどういうことなのか。あの会社で鈴木社長より年上なのは私だけでした。ワンマン会社だから、他の連中は異常なことがあっても何も言えないんです。これまでにも次々と社員を辞めさせてきました。でもそういうことについて、おかしいとか変だとか、誰も言えないんです。ところが私は多少言える。私は経営能力はないから、経営に関しては何も言わないようにしてきたんだけど、この10年間で、鈴木社長が営業ですね、広告。私が編集。そういう分業でやってきた。時には鈴木社長がいろいろ言ってくることもありましたが、私はそれがいいと思えばやったし、そうでなければ従わなかったんですよ。そういうことが、ワンマン社長の彼にとっては面白くなかったのかもしれません。 》 《そういう中で騒動の遠因となったのは、鈴木さんが病気を患って入院したことでした。もし鈴木さんに万が一のことがあったら、この会社はたちまち立ち行かなくなる。そうしたら30人近い社員とその家族が路頭に迷うことになる。だから、鈴木さんが信頼できる人、どこかの会社のOBでもいいし、経営がわかる人を連れてきておいて、顧問でも社長でもいいですが、置いておかないと、万が一の時に大変になる。そう何度も言ったのです。でも彼は全然聞かない。そういうことがきっとストレスと言えばストレスだったのかもしれない。さっき言った編集のこともあるし、病気になってからそういうことを言ったのも嫌だったのかもしれない。でもそういうことを言えるのは僕しかいないわけですよ。他は全員年下で、言うことを聞かざるをえないわけだから。》 結局、花田 ワック出版 鈴木社長 花田 《鈴木さんから「編集部員を連れて出て行け」と言われた後に、僕は若い編集部員と相談したんです。こういうふうになった、私は出て行かざるをえないが、あなたたちはどうする?と。そしたらみんな「一緒に辞めます」と。それで私が一応上司だから、3月いっぱいで辞めるというみんなの退職願を預かって、鈴木社長に渡したわけです。》 《編集部員には編集部員の考え方がある。鈴木さんと近しい人もいたし、僕とずっと長い人もいた。だからいろいろ考え方はありますよね。だからそれは彼らの判断なんです。「私は残ります」と言われたら僕はしょうがないわけです。だから部員に説明して訊いたら「私たちも辞めます」ということになった。鈴木社長は少なくとも一人くらいは残ってくれると思っていたんじゃないでしょうか。》 《結局、編集部員は全員辞めたわけです。それからずっと担当だったDTPも辞めた。『歴史通』の編集長を建前上の編集長にして、部員は誰もいないんだけど慌てて募集しています。でも集まったにしても、それをまとめていく役がいませんから難しいでしょうね。というか、私は筆者の方々にはお話して、連載は全部持って行くんですから。》 花田 『WiLL』 『WiLL』 ワック
《『WiLL』はロゴも私が考えたし、タイトルもiは小文字にするというのも私が考えた。それから私は『LIFE』という雑誌が好きなんだけど、あれを真似て赤地に白抜きにしたし、文字の太さも同じようにした。だからすごく愛着はありますよ。だからそれでやらせてくれと頼んだのです。》 《別れるにしても11年間苦労してやってきたし、僕も最後じゃなくなっちゃったけど、最後の場を与えてもらった。だから鈴木さんに恩義は今でも感じているんです。だから少なくとも泥仕合はやめましょうと。そう言っていたにもかかわらずこういうことになって、非常に残念なんです。》
ワック社
①まず、際限ない増ページについて。『WiLL』は特別号を除いて256ページが適正頁ですが(最初は240ページ)その後、増ページが常態化しピーク時には334ページに膨らみました。およそ100ページ増です。当然印刷費、用紙代はもとより、原稿料等も嵩み雑誌の収益を圧迫したのです。金額にすると年間約三千万円以上の損失になりました。編集の内容でみれば、本来の『WiLL』にそぐわないエンターテイメント系の連載が増えつづけました(AV監督の人生相談、爆笑問題の対談、等々)。 ②編集経費について。年間、千五、六百万円をほぼ花田氏が一人で費消していたので、削減を申し入れました。しかしながらこれもまた聞き入れられませんでした。媒体の性質にもよりますし、花田氏は役員でもあるのでプラスアルファ分をみてもその二分の一が小社の適正範囲と考えます。 ③他業と本業とのバランスを欠く。花田氏はWeb番組のレギュラー番組二本、紙媒体のレギュラー連載数本を持ち社外で活躍していますが、ここにきて社でその姿を見かける機会が減り簡単な打ち合わせにも不便を感じさせるほどでした。まったく報告のない週もありました。社長ならずとも本来の社業は大丈夫かと思わせるほどでした。 月刊『Hanada』 月刊『WiLL』 月刊『Hanada』 月刊『WiLL』
当時「ワックとは編集方針の違いがあった」 、「編集方針の違いなんてないんですが、あの時はそう言わざるをえなかった」 花田 「鈴木さんと路線の対立は全くないですよ。両方ともちょっと右寄りですから」 。 月刊『Hanada』 『月刊WiLL』 『月刊WiLL』 『Hanada』 『月刊WiLL』 『Hanada』
花田 『LIFE』 『WiLL』 『LIFE』 『TIME』
母標
作詩・作曲 さだまさし 彼女は息子のために石ころを積み上げて 祭壇を作り赤い花を植えた 昔花畑だったが今は何もなく 墓標がいくつも雨に霞んでいる 三年が過ぎても戦は町から去りもせず 今日もドローンが群れをなして東へ飛ぶ あのひとのキャビアがテーブルにこぼれた頃 町外れで彼女の息子は死んだ 名もない兵士なんてひとりも無いけれど 名もない一人の兵士として消えた アンダンテ・カンタービレが聞こえていたらしい 戦場は日暮れ間近だったそうだ ひざまずく石の下には何一つないけれど 彼は彼女の祈りの中に棲んでいる 誕生祝いの時計一つ残さなかったけど 彼は母の祈りの中で生きている 彼女は若い頃に子供を授かった 幸せな日が無かったわけじゃない 彼女の好きなカヴァレリア・ルスティカーナが聞こえる ただ彼女の耳にはもう音が無い しあわせがずっと続くなんて思わなかったけど 不幸ばかりがずっと続くはずもない ひざまずく石の下には何もないけれど 彼は母の祈りの中に棲んでいる ひざまずく石の下には何もないけれど 彼は確かにそこに居る さだまさし 『生命の樹』 「母標」(ぼひょう) 嶋村英二 木村“キムチ”誠 さだ 「夏長崎から2025」
戦死者の中には何一つ残せないひとも多い。だから墓標の下には遺品の一つも無い。それでも泣きながら弔う親にとってそれは立派な墓なのだと思う。かつて新井満さんはナバホ族の詩を訳した「千の風になって」という名曲で「そこに私はいません」と歌った。素晴らしい歌だが一つだけ僕の考えとは違う。僕は何もないそのお墓に「私は居る」と思っているのだ。悲しみ、弔うひとの心の中にきっとその魂は棲んでいると思っているからだ。 ―― アルバム『生命の樹』 「母標」ライナーノーツより
自分はこういうことを一度も考えたこともなかったので、ハッとしました。戦争や災害で、ひょっとしたら亡骸もなく遺品もないような悲惨な状態だとして、遺族の気持ちとしては何らかの形でその人が生きていた証を作ることが拠り所になります。そういう意味で「お墓」が弔う人には大切なものだというのは理解できますし、石ころの下には何もないけれど、間違いなく母の心の中にはそこに彼がいると語る、この歌は心を揺さぶります。この母がもし自分だったら、と思うと胸が痛みます。きっと、そうせざるを得ないことは想像することができます。被爆地・長崎 さだ 「母標」
さだ 「防人の詩」「遙かなるクリスマス」「広島の空」「キーウから遠く離れて」 「音楽はすべて反戦歌である。私は音楽家だから、音楽家の武器は音楽だけ。大切な人を守る方法はただ一つ、戦争をしないことだ」 「人間の心に浄化作用がある限り、必ず浄化される。我々が願う良い方向に、いつか向く日が来ると信じなくてはダメだと思う。」
20年間も続いた「夏長崎から」 「このコンサートが終わるまでの間に、ほんの僅かな時間でよいから、あなたの一番大切な人の笑顔を思い浮かべて欲しい。そうしてその笑顔を護るために自分に何ができるだろうか、ということを考えて欲しい。実はそれが平和へのあなた自身の第一歩なのです。」 「夏長崎から2025」 「そして、自分が何をなすべきかが分かったら、そこへ向かって歩きだそうじゃないですか」 さだ ♥♥♥
VIDEO
スカパーの「ミュージックエア」 「おんがく白書」 「ふきのとう」 細坪基佳(ほそつぼもとよし) 横浜赤レンガ倉庫 ふきのとう 「白い冬」「春雷」 「 ふきのとう」 「ふきのとう」 山木康世 細坪基佳 「白い冬」 CBSソニー 「白い冬」 「夕暮れの街」 さだまさし グレープ 「精霊流し」 「白い冬」 中島みゆき 瀬尾一三 石川鷹彦 「雨降り道玄坂」、「風来坊」、「春雷」 細坪
VIDEO 「 ふきのとう」 細坪基佳 ふきのとう 「 ふきのとう」
今から45年前の1974年、札幌のライブハウスでアマチュアで歌っていたところ、細坪 ふきのとう 「白い冬」「風来坊」「春雷」「やさしさとして想い出として」 日比谷野外大音楽堂 日本武道館 細坪 「 ふきのとう」
歌手としてデビューして、それが仕事になってくると、当然のどに負担がかかってくる。若いころはそれを無理やり力でねじふせて、声を出していた時期もありました。声出なくても、リハーサルやれば大丈夫だったし、またそれで酒飲んで、大声出して盛り上がって(笑)。朝になって『声出ないなー』って思っても、またリハやって声出して…って生活を繰り返していて。でも、そのうちだんだん治りが遅くなっていくし、どうも自分の描いた歌い方と違うし。グループを離れソロになってみるとそれが顕著になってきて、のどを痛めて声が出なくなる時期があったんです、その時に初めてその後(歌手として活動)できなくなる可能性があると思ったんです。それで自分ののどに対して意識を持ったんです。『お前(のど)のおかげで俺は(歌手として)生きているんだ』って。それが、酒だタバコだ、夜更かしだって、何をやっているんだという話ですよ(笑)。活動始めて20年くらいたってからかな……。遅すぎますよね。
歌手として長く歌っていきたいという思いは、のどのケアだけではなく、自身の表現方法にも大きな変化をもたらしています。
のどへの意識が変わると同時に、歌声の表現や発声にもより意識がいくようになったんです。まず、周りから私のハイトーンを褒められる機会が多いんだけど、もっと深みを出すために、低音を磨くことにしたんです。例えばAメロってサビに向かうメロディーだから、低く歌って、サビでスコーンと突き抜ける曲が多い。それまでは、『自分の売りはハイトーンだから、サビでスコーンと掴めばいい。この辺(Aメロ)はどうでもいいや』って思いがどっかであったかもしれない。でもそのAメロを低音できちんと聴かせられると、サビで今まで以上に『おっ』と思わせることができる。世界が広がったんですね。そのことに気付いてからは、表現がより面白くなったんだよね。今まで歌ってきた歌も、違うアプローチで表現してみたら面白かったり。それまでトレーニングとかケア、研究的なことをやってこなかったのが、急にやり始めて歌ってみると違う世界が見えて きて、表現の幅を広がりましたね。より音楽にのめり込みました。
僕を応援してくれるファンの皆さんは、僕と同年代が多い。歌い始めたころは、みんな少年少女だったけど、今はもう70歳近く(笑)。地方に行って僕が歌うのであればまだ来られると思うんですけど、野音に全員集合っていうと今の年齢がギリギリだと思ったんです。元気なうちに『今までここまでやってきたな俺たち』と振り返ると同時に、ここからもう一歩なにか踏み出すきっかけにもしてほしい。だから誤解を恐れずに言えば、僕のことを知らない若い人たちに訴えていこうという気はあまりないんです。老人たちの希望になってやるって思っています(笑)。音楽を通して、共通の思いを抱いて生きてきたファンの方々が全国にいらっしゃると思います。そういう方々と一緒にお祭りをやって、また明日に向かってそれぞれの道へ散っていく。そういうイベントにしたいと思います。自分でもワクワク、ドキドキしています。でも心配はしていない。なぜなら、失敗しても言わなきゃわからないってことを45年間で学んできたから(笑)。会場で会えるのを楽しみにしています。 (45年間の集大成とも言えるこのライブが終わった後)僕はどうなるのかわからない。終えてみて、『よし、次』というモードになるのか、『ここらで一息入れるか』となるのか。ただ、今は目の前の野音に全力で臨みたい。 私の大好きな曲「春雷」(しゅんらい) 山木康世 「メロディーは文句なし。でも詞はこれじゃない」 山木 「春雷」 「白い冬」 ♥♥♥
春雷 作詞・作曲 山木康世
突然の雷が 酔心地 春の宵に このままじゃ夜明けまで野ざらし ずぶ濡れ 春の雷に 白い花が散り 桜花吹雪 風に消えてゆく 過ぎた日を懐かしみ 肩組んで涙ぐんで 別れたあいつは 今 寒くないだろうか 春の雷に 帰るあてもなく 桜花吹雪 家路たどるふり 声なき花の姿 人は何を思うだろう まして散りゆく姿 この世の運命を 春の雷に散るな 今すぐに 桜花吹雪 命つづくまで 春の雷に散るな 今すぐに 桜花吹雪 命つづくまで VIDEO
「フィールズ賞」 広中平祐(ひろなかへいすけ) フィールズ賞 広中 広中 「ドイツのだれだれという若い 学者が、その問題を解いたみたいだよ」 広中 広中 「そうだったのか。それか!!」 広中 広中 広中 。「自分はバカだから、あの命題が解けなかったんだ。だからもっと勉強しよう フィールズ賞 「自分はバカだ」 「自分はバカだ」 広中 「もっと勉強しよう!」
もしこれが悔しさだけで終わっていたらどうでしょうか。「ドイツの若造が自分を出し抜き、あの命題を解いたなんて許せん!」 「何くそ」 広中 「ドイツ人のあの若い数学者を負かしてやろう」 「自分はバカだ」 「自分はバカだ」
広中 フィールズ賞 、「自分をバカだ」 「自分はバカだ」 広中 「数学バカ」 広中
漫画家の赤塚不二夫(あかつかふじお)
「自分をバカだと思え。」そう思えば、自分の知らないことでも、人に聞くことも教えてもらうこともできます。いわゆるエリートは、これができない。新人なのにヒットやホームランばかり狙う。犠牲バントもできないのに。
あのウォルト・ディズニー 「正直に自分の無知を認めることが大切だ。そうすれば、必ず熱心に教えてくれる人が現れる。」 ♥♥♥
受験生に英作文の指導をしていて、普通名詞 を裸で使うミスを犯す生徒が多いので、私は「名詞にはパンツをはかせてやってちょうだい」 「パンツ」 「a(n)」「the」「~s」 「ノーパンは絶対にダメ!」 a 母音 an 「a⇒an」 「an⇒a」 「ChatGPTに聞けば何でも解決する」 「もしそうなら来週から僕が来る必要はなくなるね」 ChatGPT 松江北高 「英語のなぜ?」 「学問探究講座」 one→an→a )を渡して解決しました。
私が若い頃と違って、インターネットが普及して何でも調べることができるようになりました。先日、プロ野球の「ドラフト会議」 サブロー新監督 ChatGPT 「上のくじを取るように」 『システム英作文』(桐原書店) 「台所は、アメリカの歴史のなかでは必ずしも自慢すべきところではなかった」(大分大学) 「実は自分もこれが一体どういうことか分からずに、原典にあたってみようと苦労して赤本を学部別に10年分以上調べたんだけれど、結局出て来ずに分からなかった。あきらめかけようとした時に偶然この文章を見つけて解決した。みんなはChatGPTなどのAIを使えば何でも分かると言うから、どんな解答が返ってくるか自分で調べてごらん。僕はこの件の苦労話を「チーム八ちゃん」のブログに数年前󠄂に書いたけれど、このブログの過去の記事を一つ一つ遡るような暇人はいないだろうから。」 ChatGPT 「どうやって?」 「台所」「チーム八ちゃん」 コチラ です)。恐ろしや、インターネット&AI時代
最近では、生徒はChatGPT 「志望理由書」 丸写しではなく自分自身の言葉で置き換えて、それをベースにして自分の言葉で再構築すれば立派な文章が出来上がります。恐ろしい時代ですね。
インターネット 「論文の書き方」 渡部昇一先生
いくらインターネット 渡部昇一先生 ウィキペディア 「共通テスト」 「事実」 「意見」 八幡 ♥♥♥
ちょっと話は遡りますが、巨人のDeNAベイスターズとのクライマックスシリーズ第2戦。「すげえ、試合だったな…。勝たせてあげたかった。本当に総力戦の素晴らしい試合だった。敗戦の責任は俺にある。選手は必死にやってくれた」 「野球って恐ろしいな」 阿部慎之介監督 戸郷 戸郷 戸郷 戸郷 大勢 マルティネス 田中瑛 宮原
延長11回裏。6-5と巨人が1点リードし、あと1人を抑えれば勝利という場面でした。阿部監督 田中瑛斗 田中 牧秀悟 山本祐大 度会隆輝 度会 田中 宮原 野村監督 長野 長野 「思い出起用」「その1枠が命取りに」
DeNAは主砲オースティン 宮﨑敏郎 ビシエド 筒香 林蒼汰 度会 蝦名
ただこの日も、大きなミスを巨人は幾つも犯していることを忘れてはなりません。先発の戸郷 リチャード 大勢 の速い 牽制球を後にスルーしてしまいました。記録は大勢 リチャード 若林 長野 田中瑛 野村監督 「負けに不思議の負けなし」 58失策 と鉄壁の守りでした。それが今年はリーグワーストの78失策 。これだけではなく記録に残らないミスも沢山見ました(特に外野手)。走者二塁から単打で本塁を狙った暴走気味の走者をアウトにできず、みすみす生還を許す場面がほとんどでした(完全に肩をなめられています)。反面、巨人の走者はヒットが出ても一つずつしか進むことができない走塁が目立ちました。盗塁数も無様。足が遅いのに加えて、リード面や打球判断のミスがほとんどでした。バントの成功率(7割2分5厘)はリーグワースト。投手陣は無駄な四球から崩れていきました。明らかに練習不足でしょう。ミスしたら必ず負けます。「負けに不思議の負けなし」 「自分自身も何が足りなくて勝てなかったのか、課題として自問自答したい。選手にも同じことを言った。大きな糧として来年にぶつけてほしい」 阿部監督
「受験」 志学館 八幡 「自分が陥っていた誤り」 八幡 基礎・基本 の大切さですね。「当たり前のことをバカになってちゃんとやる(ABC)」 『蛍雪時代』10月号(旺文社) 「1点が合否を分けるのリアル」
ヘルマン・ルムシュッテル 九州鉄道 九州鉄道 重要文化財 門司港駅 ルムシュッテル JR博多駅 博多シティ 「つばめの杜ひろば」
▲鉄道黎明期に大きな役割を果たしたヘルマン・ルムシュテル
ヘルマン・ルムシュッテル
九州鉄道 ヘルマン 二重橋 三大橋(天満橋、天神橋、難波橋) 九州鉄道 「九州鉄道会社のために採用されたことは、自身は勿論、ドイツの名誉なので、本国に尽くす精神を拡充して本国の名誉を毀損しないように、日本と九州鉄道会社のために尽くすつもりだ」
彼は新橋から有楽町を経て東京駅に至る市街高架線を作っています。日本鉄道が明治22(1889)年に、新橋から上野までを高架線で結び、三菱ヶ原に中央ステーション(東京駅)を設ける案を決定すると、彼の煉瓦のアーチに鉄道を架ける案が採用されました。彼は明治25(1892)年に九州鉄道
九州鉄道 豊州鉄道 九州鉄道
さらに彼が日本に大きな影響を与えた実績として、「メートル法」 ルムシュッテル 九州鉄道 「メートル法」
現在では世界でもトップクラスの高い技術を持つ日本の鉄道ですが、その黎明期には、あらゆる技術を欧米に依存していました。九州鉄道 九州鉄道 ヘルマン・ルムシュッテル 九州鉄道 蒸気機関車 ホーエンツォレルン社 クラウス社 門司港駅 ルムシュッテル 九州鉄道 ドイツ公使館 ルムシュッテル 九州鉄道 九州鉄道 263両 でした。製造国別に見ると、ドイツが50両 、イギリスが9両 、スイスが5両 、アメリカが199両 と圧倒的な多数派となりました。1894(明治27)年に帰国後は、国鉄に復職し、晩年は日本の鉄道発展のために鉄道資材購入顧問
九州鉄道 筑豊鉄道、豊州鉄道、唐津鉄道、伊万里鉄道
「鉄道友の会」 「日本国有鉄道門司鉄道管理局」 ルムシュッテル 中野五一 十河信二 博多駅 「JR博多シティ」 「つばめの杜ひろば」 「鉄道神社」 JR 博多駅 ♥♥♥
最近、尊敬する鉄道デザイナー・水戸岡鋭治(みとおかえいじ)先生 『PHP』11月号 「デザインの力で感動を届けたい」 『理念と経営』9月号 「経営も仕事も「感動」から始まる」 唐池恒二(からいけこうじ、九州旅客鉄道株式会社相談役) JR九州 「直感的にパッとひらめくアイデア」 「感動」 JR九州
水戸岡先生 岡山県 吉備津 吉備津神社 「もう少し勉強したい」 イタリア ミラノ ユーレイルパス 東京 「なんとかなる」 東京
当時、JR九州 石井幸孝 「水戸岡さんは日本の鉄道をどう思いますか?」 石井 JR九州 「速いだけで、ダサいですね」 JR九州 石井 「予算とスケジュールとルールさえ守れば、デザインに一切口をはさまない」 「だからいいんだ。鉄道を知っている人間では、ありきたりのものにしかならない。崖っぷちの経営状態にある会社は、いまだかつてないことをやらないとだめなんだ」 JR九州 唐池恒二 日立製作所 「コストが高い」「手間がかかる」「安全性に問題がある」
私が初めて長崎 「特急かもめ」 まばゆいくらいの白のボディに惹きつけられました。著書・水戸岡鋭治(みとおかえいじ)『電車をデザインする仕事 』(日本能率協会マネジメントセンター、2013年) 「かもめ」 「車両の白さを維持することが、JR九州のスタッフの誇りとなる。そしてそんな会社にお客様は夢や企業努力を感じてくれる。さらにメンテナンスのレベルアップにもつながる。私はそう伝え、現場に納得してもらってきました 。」 『THE 21』2014年6月号インタビュー(PHP) 国鉄時代からタブー色とされてきました。蒸気機関車が走っていた時代に、 石炭の「すす」で車体が黒く汚れてしまうために、車両デザインで明るい色合いが用いられることはなかったのです。その影響で、JRでも長い間「白」を使うことを極端に嫌っていました。水戸岡先生 「そして実際、お客様からは『白い車体がきれいだね』という言葉を多くいただいたそうです。そう言われたらもう、きれいにし続けるしかないですよね。このように、高いハ-ドルがあるからこそ、人は一層努力できるのです。」 水戸岡先生
先生の挑戦の集大成とも言えるのが、2001年にデビューしたクルーズトレイン「ななつ星・in九州」 「外から丸見えだ」 「ななつ星」 「まったく飽きない。毎回違う発見があるから」
相手を感動させるには、デザイナー自身が感動体験をきちんと積み重ねている必要があります。それまでの人生で楽しいとか気分がいいと感じたことは、「感動」 「イラストレーターやデザイナーになるには、どうしたらいいですか?」 「絵だけではなく、いろんなものに触れてたくさん経験し、そこから学ぶこと」 「すごいね」 「三つの好き」 「好きな仕事に就くこと」「好きな人と暮らすこと」「好きな土地で生きること」 「自分の好き」 「好き」 水戸岡先生 ♥♥♥
潜在意識 潜在意識 潜在意識 「クイーンエリザベス号」 「意識」 「潜在意識」 クイーンエリザベス号 神戸港 高知港 函館港
こういった性質のある潜在意識 「カキクケコの法則」 見山敏(みやまさとし) オムロン 株式会社ソフィアマインド 「ソフィア」 見山 見山 コチラ です)にも、貴重な情報がたくさん出ていますのでお勧めしておきます。
◎「カ」・・・紙に「書く」。 「書かれざることは実現しない。目標を文字にしてその実現を念ぜよ」
◎「キ」・・・希望をもち、望む結果がまちがいなくやってくることを「期待」しよう。 感謝の先取りを行ないましょう。これらの行為は、ちょうど大地に種を蒔いたその後に水を与え、太陽の恵みを注ぎ、肥料を施すことと同じくらいに願望を育てる上で大切な行為です。
◎「ク」・・・「口」に出して唱えよう。 「忙しい、忙しい」 「苦しい苦しい」 「大物になりたい」 ◎「ケ」・・・「決意」し「継続」する。 私達が決意しなければ物事は実現しません。断固として決意し続けることです。決意するということは代償を払うことをいとわないことです。肚をくくるということです。人から非難中傷されようが、信念を貫き通す覚悟をすることです。肚をくくれば必ず天地が味方してくれます。
◎「コ」・・・言うまでもなく「行動」するということだ。 いくら念じても行動しなければ何も叶いません。行動こそが全てです。潜在意識を味方にするとは、とりもなおさずこの行動の原動力を高めることなのです。
もう一つ。世界的ファッションデザイナーのコシノジュンコ 文化勲章 「か・き・く・け・こ」 『致知』2019年8月号 「『か』は『感謝』、『き』は『希望』、『く』は『くよくよするな』、『け』は『健康』。最後の『こ』は『行動』。この5つって、仕事でも人生でも重要じゃないかと思いますね」(コシノ談)
さらにもう一つ。仕事ができる、できないの基準は職場や仕事内容によるでしょうし、上下関係によってもその評価は異なったりするものです。でも、「この人は信用できる」 「かきくけこの法則」 「かきくけこ」 ①「か」……感謝の気持ち ②「き」……興味 ③「く」……苦労 ④「け」……謙虚 ⑤「こ」……更新 これも忘れずに心したいですね。今日は幾つかのバージョンの「カキクケコの法則」 ♥♥♥
尊敬する故・渡部昇一先生 「できない理由を探すな!」 「これは!」 「能力の壁」 「環境の壁」 「能力の壁」 「内なる壁」 「環境の壁」 「内なる壁」 「外なる壁」 「できない理由」 「内なる壁」 「外なる壁」
例えば、専門分野を本格的に勉強するために、外国の大学に留学したいと思ったとします。当然、さまざまな心配・不安・苦労を強いられることでしょう。慣れない異国での生活、金銭面の問題、言葉の問題、勉強の辛さ、対人関係等々。しかし、そこでさまざまな悪条件をあげつらって、やはり無理だと諦めてしまっては、結局何も得ずに終わってしまいます。そこで、もろもろの悪条件を乗り切ることは、ただ平凡に国内で勉強を続けるよりもはるかに自分のためになるし、その辛い経験は、結局は自分の血肉となるのだ、とこう考えるべきなのです。物事を簡単に諦めるという傾向は、最近の若い人によく見られることです。それは、一つのことに真剣に取り組んだことがないために、臆病になっているだけなのではないでしょうか。「できない理由」 「できない理由」 「やれることに着手せよ」「やれない理由など探してはならないのだ。どこかで決然と、断乎として始める」 渡部先生
私は学生時代に、渡部昇一 『知的生活の方法』(講談社現代新書) 渡部先生 「できない理由を探すな!」 「助けのロープ」
鉄砲撃ちの名人に、電線の上と地面にいる鳥とどちらが簡単に撃ち落とせるか?と聞いてみる。一見、地面にいる鳥のほうが撃つのはたやすそうである。しかし彼は、電線の上にいる鳥も地面にいる鳥も、撃つには同じくらいの労力と技量が要るというのである。難しさとしては大差なく、むしろ電線の上にいる鳥を撃つほうがかえって楽かもしれないということである。ならば、目標は高く掲げたほうが良い、ということになる。
私のような素人考えで見れば、地面にいる鳥を撃つほうがいかにも簡単そうですが、専門家から見れば、実際に要する集中力と技量は同じということです。これは素晴らしい教訓を含んでいる話だと思います。つまり、一見難しそうに見える目標でも、そこへ到達するのに必要な努力は、一見易しそうな目標とさして変わらないということです。逆に言うならば、一見たやすそうな目標も、難しそうな目標を達するくらいの努力が必要だ、ということです。目標が高かろうが、低かろうが、必要な努力は同じということなのです。ならば…。そんな訳で、「できない理由を探さずに、目標を高く掲げて、努力せよ!!」
“寝食を忘れる”という言葉がある。大きな事をなしとげるにはそのくらいの覚悟がなくてはならないということだ。終了時間ばかり気にしている人には大きな仕事はなしえない。これは確かに“若い人たちの一番覚えておくべき”ことに違いない。(渡部昇一) どんな逆境にあっても決して天を怨まず人を咎めず、自分を信じて心穏やかに道を楽しむ。これは天命だと受け入れることが大事なのである。すると、霧が晴れるように視界が開けてくるものである。(渡部昇一)
私にはここで思い出す話があります。「小枝にしばられたゾウ」
サーカスで使われるゾウがまだ小さな子供の頃、足には細いロープがつけられ、地面に刺さった小さな杭に結ばれていました。幼いゾウは何度も逃げ出そうとしましたが、その力ではロープを引きちぎることができませんでした。やがてゾウは「自分には無理だ」と諦め、挑戦をやめてしまいます。時が経ち、ゾウは大人になり、その力はかつての何倍にもなりました。しかし、大人になった今でも、ゾウは小さな杭と細いロープに縛られたまま動こうとしません。なぜなら、子供の頃に学んだ「自分にはできない」という思い込みが、今でも彼の行動を支配しているからです。
この話が伝えている教訓はとてもシンプルです。過去の失敗や経験が、現在の自分を縛りつけている可能性があるということです。かつての状況では「できなかった」ことが、今のあなたにはできるかもしれないのに、その思い込みによって行動を制限してしまっているのです。ビジネスや家庭の生活場面でも同じことが言えるでしょう。「自分には無理だ」 「本当にそうなのか?」 「どうせできない」 「小枝にしばられたゾウ」 「自分にできる」
① 過去の思い込みに気づく 自分が「無理だ」と感じていることを全部書き出してみます。次に、それがどのような過去の経験に基づいているのかを振り返り、今の状況と本当に同じかどうかを考えます。過去との違いに気がつくことで、「思い込み」を手放すことができるでしょう。
② 小さな挑戦を始める 過去の失敗に基づいた思い込みを打破するために、小さな挑戦から始めてみましょう。どんな小さな挑戦でも、まず第一歩を踏み出すことが大切です。小さな成功体験を積むことで自信を育てましょう。
③「できる」と信じる 自分が変わったこと、成長したことを意識し、「自分にはできる」と肯定的に捉える習慣を持つことが大切です。特に、過去の思い込みが顔を出したときは、意識的に「今の自分は違う」と思い直すことが重要です。
④できることから断固としてやる 自分にできる身近なことからやり始めることが大切です。
この本の著者がこんなことを言っています。♥♥♥
「 僕はかつて、平凡な人生に縛りつけられ、そこから抜け出せないかのように感じていました…。まるで自分を向上させる力などどこにもないかのように…。しかし、今では、その力が自分に備わっていること、すべてのひとにその力が備わっていることを知っています。誰でもしようと思えば何でもできるし、どこでも行けるし、なりたい自分になることができるのです。人間の可能性は無限にあり、人はそれぞれ、困難な状況を打開して未知の世界を創造する能力を与えられています。僕たちはその力を自覚し、それを活かす努力をすればよいのです」
受験用の熟語集の中には単にfor good=forever for good forever COD , CALD )、やむを得ないことかもしれません。しかし、両者の意味は全く異なります。“for good” 何かが永遠に終了し元に戻らない ことを示すフレーズです。これは通常、二度と戻ってこない決定的な変化や別れを表現するために使用されます。無期限に停止された行為や状態という点を強調したい時に使うのです。“it never changes back or comes back as it was before”(元あった状態に変わることがないあるいは戻らない)というCOBUILD の定義が参考になります。またOALD に挙がっている例文 This time she’s leaving for good .(=she will never return)の( )内に添えられた説明がそのことをはっきりと物語っていますね。
He left the company for good
She decided to quit her job for good
I’ve given up smoking for good
He left his hometown for good
He decided to quit smoking for good
I’m giving away my old clothes to charity for good
これに対して、“forever” 永遠に続くこと を意味し、時間的な制約なしにこれから何かがずっと続くことを示します。これは、永遠に続く愛や関係を表現するのにも使われます。感情的、詩的、ロマンチックな場面でもよく使われます。“OUR GIANTS WILL LIVE FOREVER
Their love for each other is so strong; they’ll be together forever
The memory of that special day will stay with me forever
Their love story will be remembered forever
The diamond is said to last forever
We promised to be friends forever
This road seems to go on forever
“for good” “forever” “for good” “forever” 石橋尊侍・里中哲彦・島田浩史『大学入試瑛熟語最前線1515』(研究社、2024年) for goodは習慣などを金輪際やらないという意味で使われることが多く、foreverは続けてきた状況をこれから変わらず続けるというニュアンスで用いられることが多い。
したがって、次の例では「辞める」という行為は永遠に続けられるものではありませんのでforever forever ♥♥♥
彼女は30年間勤めた仕事を辞めた。for good forever
あなたのことは永遠に愛し続けます。forever for good
鉄道の車両や駅舎のデザインをたたえる国際的な「ブルネル賞」 「ブルネル賞」 イザムバード・キングダム・ブルネル(1806~1859) 英国グレート・ウェスタン鉄道 「第12回ブルネル賞」
車両部門では、JR西日本 「ウェストエクスプレス銀河」 JR九州 「DENCHA(デンチャ)」 上野駅公園口駅舎 長崎駅
コンテストは4部門で実施され、欧米やアジアの鉄道会社などから、計120点以上のエントリーがありました。関西、山陰、山陽 「ウェストエクスプレス銀河」 瑠璃紺色(るりこんいろ) 優秀賞
▲JR松江駅で撮影
2020年10月、JR西日本の新しい長距離寝台特急列車「WEST EXPRESS 銀河」(ウェストエクスプレス) 松江駅 瑠璃紺色 ロゴ 「遠くへ行きたい」 「 WEST EXPRESS 銀河」 「多様性」「カジュアル」「くつろぎ」 「WEST EXPRESS 銀河」
関西圏の新快速などで活躍した車両「117系 」 えちごトキめき鉄道「雪月花」 「特急やくも」 川西康之 氏 がデザインを担当しています。「 WEST EXPRESS 銀河」 京都 出雲大社 東京~出雲市 「サンライズ出雲」 寝台急行「だいせん」 「 WEST EXPRESS銀河」 「銀河」 岩手県 「SL銀河」 東京~大阪 寝台急行「銀河」 「 WEST EXPRESS銀河」
「WEST EXPRESS銀河」 「遊星」 コチラ に詳しく出ています。10月7日(火)放送の「友近・礼二の妄想トレイン」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はコーヒー コーヒー好きの私は、美味しいコーヒーには目がありません。全国に美味しい喫茶店があると聞くと、飛んで行って味わっています。今までに飲んだコーヒーで一番美味しかった思い出は、教員に成り立ての頃に、神戸 「UCC本社」 ブルーマウンテンコーヒー 奈良 「奈良ホテル」 神戸 「にしむら珈琲」 京都 「イノダコーヒ」
▲落ち着いた銀座「カフェパウリスタ」の店内
私は東京 銀座「カフェーパウリスタ」 銀座駅 「森のコーヒー」 「『森のコーヒー』の最大の特徴は、自然の甘味と、その味わいを邪魔する雑味がきわめて少ないことです。ですからブラックコーヒーは苦手だけれど、『森のコーヒー』なら飲めますというお声をたくさんいただきます。これは豆の持つ甘味が、飲んだ後も口の中にやさしく残るからです」 長谷川社長 東京‥銀座 「森のコーヒー」
▲届けてもらっている「森のコーヒー」
喫茶店は高度経済成長期に増え、1981年には全国に15万4,630店もありました。その後は減少傾向で、2021年に、日本に喫茶店は5万8,669店となっています。その中でも、銀座の「カフェーパウリスタ」 三越 和光 「パウリスタ」 大隈重信 銀座 「鬼の如く黒く、恋の如く甘く、地獄の如く熱き」 「清新な朝食は一杯五銭のブラジルコーヒーとトーストパン フレンチトースト」 芥川龍之介 菊池寛 与謝野晶子 永井荷風 森鷗外 芥川 「饒舌」 「パウリスタ」 ジョン・レノン オノ・ヨーコ
「パウリスタ」 水野 龍 「ブラジル移民の父」 水野 水野 水野 「パウリスタ」 「サンパウロっ子のコーヒー」 「カフェーパウリスタ」
全国に20超の店舗を展開するまでになった「パウリスタ」 銀座8丁目 「コーヒー戦争」 ドトール スターバックス 「パウリスタ」 「パウリスタ」 長谷川勝彦(64歳) 「パウリスタ」 銀座 「 森のコーヒー」 、①カップテイスターの味覚格付けで常にトップクラス、②農薬不使用の生産者グループの手により栽培、③ブラジル有機認証団体やドイツ有機認証団体の認定書付きのコーヒー原料豆を100%使用、④カフェーパウリスタが農園から直接買い付けた産直品、⑤完熟した豆のみを一粒一粒手作業で収穫し、未熟な豆は選別除去、⑥乾燥工程の70%が天日乾燥、最後の仕上げの30%のみを機械乾燥、⑦伝統の技法で自社焙煎
▲「カフェーパウリスタ」のコーヒー 1杯900円
その「パウリスタ」 は、 平成半ばに、散々な騒動「銀ブラ論争」 「銀ブラ」 「銀座をぶらぶらする」 長谷川 「銀座でブラジルコーヒーを飲む」 「パウリスタ」 「根拠がない。誤説」 「銀座でブラジルコーヒー」 「パウリスタ」 「間違いだ」 長谷川 「ウソつき」 「銀ブラ発祥地」 「証明できる資料がそろっていない」 「パウリスタ」 「銀座でブラジルコーヒーでも飲もうか」 「パウリスタ」 キーコーヒー 柴田文次 ブラジル大使 「パウリスタ」 長谷川 「パウリスタ」 銀座 「銀座でブラジルコーヒー」 銀座
いつもコーヒーと一緒に届き、楽しみに読ませてもらっている「カフェパウリスタ森のコーヒーだより」 「パウリスタ」 ♥♥♥
かつてコンビニのセブンイレブン 「セブンカフェ」 コチラ をお読み下さい)。しかしながら、その「 セブンカフェ」
◎1975年~デキャンタストーブ式 ◎1994年~カートリッジ式 ◎2001年~エスプレッソ式 人間三度も失敗すれば諦めるのが普通なのですが、無類のコーヒー好きだったセブンイレブン 「ニーズはある」
セブンイレブン 「ブルーマウンテン」 「ブルーマウンテン」 「世界最高クラスの高級豆」「コーヒーの王様」 ブルーマウンテン ジャマイカ 「ブルーマウンテンエリア」 ブルーマウンテンエリア ブルーマウンテン ①決して広大ではなく生産量に限りがある、②全て手作業で収穫を行っている、③完熟したコーヒーの実のみを収穫している セブンイレブン ジャマイカ ブルーマウンテン
とはいえ、さすがセブンイレブン 「ブルーマウンテンブレンド」 「ブルーマウンテンブレンドをください。」 「ブルーマウンテンブレンド」R
▲カップも高級感が漂う!
このコーヒーに関して、公式サイトに書かれていることをまとめてみました。今年のものは、深化 と進化 を実現させた、3つのこだわりがあります。
❶産地豆を適正に配合したこだわりのブレンド ❷素材を最大限に引き出すこだわりの焙煎 ❸香りとコクを引き出すこだわりのドリップ 黒い重厚感のあるカップそのものにも、他のコーヒーとは異なる差別感・高級感が感じられますね。そして、飲む前から、かなり上品な香りがプンプンと漂ってきます。この凄まじいまでの香りは今までのコンビニ・コーヒーでは無かった芳香で、かなり期待感が高まります!実際に飲んでみると、酸味と苦味のバランスがバッチリです。しかもあっさりとした口当たりです。口に含んだ際の苦みがスーッとすぐに引き、雑味をほとんど感じません。ある意味「苦い」とも感じさせないほどの、ほどよい苦みと軽やかなコク。飲み込んだ後も、鼻先に抜ける芳醇な香りと軽く残る甘味が幸福感を与えてくれます。後味も非常にスッキリしていて確かに「バランスが良く」、そのレベルは今までのコンビニコーヒーとは段違いです。少し温度が下がった状態で飲むと、酸味がちらりと顔を出し、嫌みのない酸味の変化を楽しむことができます。一言でいうと「優雅」!飲みごたえと満足感が全然違います。まさに王様のバランス感覚を感じる味です。
お金に余裕がある日、気合を入れたい日、美味しいものと一緒に贅沢したい日、などにピッタリなのがこの「ブルーマウンテンブレンド」 250円 という価格は、コンビニ・コーヒーとしては少々お高いのですが、お金を出しても飲む価値はある!とだけは言っておきたいと思います。ちなみに、ローソン ファミマ 「モカブレンド」 ♥♥♥
長野久義外野手(ちょうのひさよし、40歳) 坂本選手 勝負強い打撃で入団から9年連続で100安打以上を記録したバットマンでした。広島から巨人に復帰後は、代打の切り札だけでなく、精神的支柱として若手が多いチームを支えました。誰からも愛された「チョーさん」 「プロ野球って簡単だなと思ってしまった自分がいたんですが」 「さすがにそう甘くはなかった世界でした」 長野選手 丸選手 「必要としていただけることは光栄なこと」 「素晴らしいチームメート、ファンの皆さんに会えて勉強になった」 「いつかユニホームを脱ぐことがあるとしたら、やはり巨人で脱ぐべきじゃないか」 萩尾選手 「長野さんはいつもめちゃくちゃ汗をかいている。それを見て僕も自分なりに汗をかくようにした」 「これから仕事に行くというスイッチみたいなもの。(代打は)気持ちの準備が一番大事だから」 桑田監督 「プレーしやすい環境や雰囲気づくりをしてくれた」 阿部監督 「俺が見てきた後輩の中で一番練習をしなかったけど、一番天才型だった」 「困った時のベテラン」 「チョーさん」
長野久義 「ジャイアンツ愛」 日本大学 北海道日本ハム 「巨人に入りたい!」 HONDA硬式野球部 長野 千葉ロッテ 巨人 「 ジャイアンツ愛」 内海哲也 オリックス 「ジャイアンツ愛」
そんな長野選手 「広島入りを拒否して引退するのでは?」 長野 選手 「『驚きましたが…』というような言葉は絶対に使いたくありませんでした。まずは選んでいただいたカープの方々への思いを一番初めに伝えるべきだろうと思いました。それからファンの方々やジャイアンツの皆さんへの感謝も。どう受け止められたかは分かりませんが、自分なりにしっかり考えたつもりです」
3連覇している強い広島カープに選んでいただけたことは選手冥利に尽きます。自分のことを必要としていただけることは光栄なことで、少しでもチームの勝利に貢献できるように精一杯頑張ります。巨人では最高のチームメートに恵まれ、球団スタッフ、フロントのみなさんの支えのおかげでここまで頑張ることができました。また9年間応援してくださったジャイアンツファンの皆様のおかげで苦しいことも乗り越えることができました。ジャイアンツと対戦することを楽しみにしています。 長野選手 「長野さんが、すでにお支払いになりましたよ」 「誰か別の人じゃないですか?」 「長野さんが…」 八幡 長野選手 「長野さんみたいになりたい」 大勢投手
気配りを忘れない人柄で、伸び悩む後輩たちへのアドバイスはもちろん、望まれれば自分が愛用する野球用具などを惜しみなくプレゼント、新入団の選手にはチームに馴染んでもらおうと真っ先に声をかけ、外国人選手は春期キャンプ中に食事に誘いました。試合でミスした選手に寄り添う姿もよく見たものです(泉口選手 「野球選手のかがみ」 「チョーさん伝説」 「失投」「甘い球」 。「自分も相手の投手も真剣。だから失投、甘い球というのは僕が決めることではないし、相手に失礼だと思う」 「好きな言葉は?」 「大学生の頃からスポーツメーカーのミズノさんにサポートしていただいたんですけど、プロ入りしてからも16年間ずっとサポートしていただいた。好きな言葉は『ミズノ』です。」 と。企業にまで愛される長野選手 ♥♥♥
昨日10月14日は、「鉄道の日」 「新橋駅(現在の汐留付近)」 「横浜駅(現在の桜木町駅)」 「鉄道の日」
鉄道の発展に貢献した先人たちを顕彰する 鉄道の安全・利便性を再認識する 次世代に鉄道の魅力を伝える 観光・地域振興・環境保護における鉄道の価値を広める
このように、「鉄道の日」 「グリーン車」
新幹線 特急列車 「グリーン車」 「グリーン料金」 「グリーン車」 ゆったりとした快適な旅を楽しみたいからです。飛行機のクラスと同様に、良い座席は料金がかかる分、設備もサービスも上質で、ゆったり乗車できることから、ラッシュアワーの混雑を避けたい時や、長距離旅行、ハイクラスの人々の移動などに長く愛されてきました。 「グリーン車」 「グリーン車」
その由来には諸説あるものの、有力なのは、かつての一等車の車体側面に引かれていた淡い緑色(若草色)の帯 にちなむというものです。国鉄 「グリーン車」 「グリーン車」
由来は他にも、急行列車の「特別二等車」において指定席と自由席を区別するために、1958(昭和33)年から指定席のヘッドレストに淡い青緑色のカバー が被せられたから、という説も存在します。また、「東海道新幹線50周年」 JR東海 一等車のきっぷが緑色 だったから、という説も紹介されていました。
かつて国鉄 「グリーン車」 「グリーン車」 「グリーン料金」
「グリーン車」 クローバーのマーク 「幸運の印」 黒岩保美(くろいわやすよし) クローバーマーク グリーンのライン クローバーマーク 現在では、JR九州 「DXグリーン」 東北・北海道・北陸新幹線 「グランクラス」 「グリーン車」 東海道本線 宇都宮線(東北本線) 「グリーン車」 コチラ )が連結されています。
▲九州新幹線「みずほ」グリーン車
▲新幹線「N700S」グリーン車
▲「特急ソニック」グリーン車
このようなグリーン車 福岡工業大学 ♥♥♥
In Japan, some trains have special cars called “Green Cars” that are fancier and have larger, more comfortable seats. Basically, they are the same as first-class cars in other countries. The fare in these cars is higher, so you need to buy a supplemental ticket if you want to ride in them. Japanese trains used to have three classes of cars, but the system was changed in 1960 to a two-class system. Then, in 1969, the name for first class was changed to Green Car. This name was chosen because first-class cars used to have a green stripe on the side under the windows, so passengers already associated the color green with first class. Today, the stripes are gone and cars are marked with a large, green four-leaf clover.
高市早苗 小泉進次郎 高市総裁 「全世代、総力結集で、全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ」 「だって今人数少ないですし、全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます 」 「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて、働いてまいります 」 「ワークライフバランスという言葉を捨てます」 高市総裁 「下々もそれを見習え、となってしまうんですよ」「それを『いい事』のようにトップが言うのがよくない」 「政治家本人が内心で『ワークライフバランスを捨てる』との思いをもって、仕事に精一杯打ち込むことは自由だが、それを口に出して、国民に対してメッセージとして発することについては賛同しがたい」 高市総裁 石破茂首相 「あそこまではっきりワークライフバランスをやめたと言われて、大丈夫かーいという気がせんではない」 「国家国民のために、次の時代のために(という)決意の表れだと思っております」 「ワークライフバランス(WLB)という言葉を捨てる。働いて、働いて、働いて、働いて、働いていく」「全員に働いていただく。馬車馬のように働いていただく」 「人は馬ではない」「時代に逆行している」 「政府が進めてきた健康的な職場づくりを否定する」 「公務員など働く人々に過重労働・長時間労働を強要することにつながり、政府が進めてきた健康的な職場づくりを否定する」 「男並み、男以上に働きます、をアピールしなきゃいけないのはしんどい」「ワークライフバランスは、よい仕事と両立するし、よい仕事に不可欠ではないか」
ワークライフバランス 「一部の経営幹部(や政治家)だけが、誰かにその責任を押しつけられる強者です。その人が『馬車馬のように24時間働くぞ』って宣言すると、97%の人は苦しくて肩身が狭くてやる気を失います」
総裁選後、高市 麻生 「皆様方はワークライフバランスを大事になさってください。私は今、一生懸命働いておりますけれど、今日、日曜日ですよ」 「総務省は、他府省に先駆けて『働き方改革』を進めている役所だと自信を持っており、『テレワーク』の利用率も霞が関ではナンバー・ワンです」 「無茶はしてはいけないけど、無理はしろ!」
まだ40代の頃、島根県立大田高等学校 「働いて働いて働いて働いて」 進路資料室 早朝講座 進路だより「あむーる」 進路検討会 「進路シラバス」 学校開放 面接練習 地区PTA 「どうやったらこんなに伸びるんですか?」
当時進路部長として、『合格わが道』(島根県立大田高等学校) 森山祐次校長 南場俊一教頭 ♥♥♥
『できるんだよ、君たちは』
進路指導部長 八 幡 成 人
今年度、大田高校は見事な進学好成績を記録した。担任の先生方は、その要因を「生徒がやる気になった」「クラス全員でお互いに励まし合いながら頑張ろうという雰囲気を最後まで持てた」「最後まで生徒に付き合う姿勢を担任だけでなく、各教科担当の先生方も示した」「チームワーク」「学年集団の団結力と先生方のきめ細かい指導の成果」 「個人 と集団 の相乗効果」 稲盛和夫 (人生の結果)=(考え方)×(情熱)×(能力) 考え方⇒情熱⇒能力
では学習を進める上で、大切だと思われる「考え方」を5つほどあげてみよう。① 授業は真剣勝負 ②自らの学習に満足感はあるか ③教科書が最良の参考書 ④答案を見直す ⑤恐れずに自己変革を
このような成功するための「考え方」の実例が、この小冊子 『合格・わが道』 「ウサギと亀」 (1)他人を気にせずに、(2)自分自身の力を信じ、(3)目標を1点に集中し、(4)最後まであきらめずに100%の力を出し切る 『できるんだよ、君たちは』(金八先生)
日本の音楽史に刻まれる記念すべき一夜となりました。小田和正(78歳) 横浜アリーナ 小田 オフコース 「アルバムTOP3入り最年長アーティスト」
『明治安田Presents KAZUMASA ODA TOUR 2025「みんなで自己ベスト!!」』 コチラ )、全国13都市28公演、延べ31万人を動員する人気を見せつけました。77歳7か月で実施する全国アリーナツアーは、小田 “史上最年長記録” 「78歳での全国アリーナツアーを完走した唯一無二のアーティスト」 小田 ライブスタートの直前、会場の照明が落ち、スクリーンに小田 小田薬局 『自己ベスト-3』 「自己ベスト島」 「ラブ・ストーリーは突然に」 横浜アリーナ 「wonderful life」 小田 横浜アリーナ 小田 「ありがとう『みんなで自己ベスト!!』は本日で終了してしまいます。明日からは皆さんが自己ベストを更新し続けていってください!」 「ありがとう!」
メンバーの挨拶が終わると花道沿いのステージへと移動して「夏の日」 小田 「woh woh」 「東京の空」 「たしかなこと」 小田 「たしかなこと」 「こころ」
ライブ中盤では、この30年間の小田 「全国ご当地紀行」 小田 「これぞ小田ライブ」
ご当地映像が終わると、2024年TBS系ドラマ『ブラックペアン シーズン2』の主題歌として書き下ろし、今回のツアーで初披露された新バラード「その先にあるもの」 「風と君を待つだけ」 「Yes-No」 「キラキラ」 小田 「言葉にできない」 小田
いよいよコンサートも終盤。ここで披露されたのは「すべて去りがたき日々」 「君住む街へ」 小田
鳴りやまない拍手と「小田さん!」 オフコース 「愛を止めないで」 小田 「Yes-Yes-Yes」 小田 「hello hello」「今日も どこかで」 「いつも いつも」
ステージ上に残った小田 小田 「クリスマスの約束」 熊木杏里、JUJU、スキマスイッチ、根本要(STARDUST REVUE)、松たか子、水野良樹(いきものがかり)、矢井田瞳、和田唱(TRICERATOPS) らが「僕らなりに御礼が言いたくて」 豪華すぎる顔ぶれの登場に会場はどよめき、客席からは割れんばかりの拍手と驚きの声が上がりました。全員で披露したのは「キラキラ」 小田 「ラブ・ストーリーは突然に」 小田
ダブルアンコールを終えても鳴り止まない拍手と「ありがとう!」 横浜アリーナ 聖光学園中・高 「my home town」 「my home town」 『明治安田Presents Kazumasa Oda Tour 2025「みんなで自己ベスト!!」』 小田和正 小田 「また会おうぜ!!」
関係者によれば、ツアー中の小田 小田
この日は「『みんなで自己ベスト!!』は本日で終了してしまいますが、明日からも皆、自己ベストを更新し続けていってください」 「Yes-No」 「キラキラ」 「YES-YES-YES」
小田 矢沢永吉(76歳) 小田 「更新のたびにどんどん年寄りにさせられている」 「将来の目標などを語ることなく、目の前の観客を大切にする姿勢を貫いている」
関係者によれば、ツアー後の予定は全く白紙で、何も決めていないといいますが、小田 「また会おうぜ!!」 「みんなで自己ベスト!!」 「明日からも皆さん、自己ベストの更新を続けてください」 「また会おうぜ!」 と♥♥♥
[バンドメンバー]木村万作 栗尾直樹 稲葉政裕 吉池千秋
[ストリングス]金原千恵子 吉田翔平 徳高真奈美 堀沢真己
【小田和正ツアー最終日公演セットリスト】 1.ラブ・ストーリーは突然に 2.Wonderful life 3.夏の日 4.woh woh 5.東京の空 6.たしかなこと 7.こころ 8.その先にあるもの 9.風と君を待つだけ 10.Yes-No 11.キラキラ 12.言葉にできない 13.すべて去りがたき日々 14.君住む街へ ENCORE 15.愛を止めないで 16.YES-YES-YES 17.hello hello 18.今日もどこかで 19.いつも いつも 20.キラキラ 21.ラブ・ストリーは突然に 22.my home town
二階堂ふみ(30歳) 「メイプル超合金」 カズレーザー(41歳) 「カズレーザー」 埼玉県立熊谷高校 筑波大学 同志社大学商学部 「X年後の関係者たち」 さだまさし 『さだまさしとゆかいな仲間たち うらさだ』(小学館文庫、2023年) “さだまさしマニア” カズレーザー さだ さだ さだ カズレーザー さだ さだ 「彼の曲の聴き方には感心する」 カズレーザー カズレーザー さだ カズレーザー さだまさし 「すっげえ好き。ライブ、超行きたいですけど、タイミングが合えば、もちろん行きたいですけど。(ライブの予定が)なきゃ困るとかでもない」 彼がさだまさし さだ 「北の国から」 「関白宣言」 「北の国から」 さだ さだ さだ さだ 「主人公」 「二軍選手」 「誰もが夢見るスターのポジションは もう僕らには与えられることはないけど」「彼は心から野球を愛してる 僕は心から歌を愛してる たとえ泥まみれで捨てられても笑ってみせる たぶん自分の事以上に愛してる そう 自分の事以上にね」
カズレイザー さだ 『夢の轍』(ゆめのわだち) 「償い」 さだまさし 「こんな歌を歌う人がいるんだ!」 〈人間って哀しいね だってみんなやさしい〉 さだ さだまさし さだまさし さだ 「やさしさ」 さだ 「やさしさ」 「前夜(桃花鳥)」 「遙かなるクリスマス」 「人間個人の幸せ」 さだ 「人間愛」
「個人の幸せ」がぶつかり合うこともあります。たとえば 「甲子園」 さだまさし 「ホームラン!」 「おっ、やったね」 さだ 〈また誰かの夢がこわれる音がする〉 さだ 「二軍選手」 さだ さだ 「やさしさ」「人間愛」 「「やさしさ」を定期的に取り込むためにさださんを聴いているところがある。聴いていなければ、もっとひどいヤツになっていたかもしれない」 カズレイザー ♥♥♥
アメリカのトランプ大統領 メラニア夫人 トランプ大統領 トランプ大統領 「ファーストレディが、よい体勢でなければ転げ落ちていたところだが、彼女は大丈夫だった。」「鋼鉄の階段の鋭い縁に顔から真っ逆さまに転落しなかったのは奇跡だ。手すりを握っていたから惨事を免れた」 「プロンプターなしで演説しても構わない。なぜならプロンプターは機能していないからだ(場内笑い) 誰がプロンプターを操作しているにせよ、大変な苦境に立たされるだろう(場内爆笑)。」 「国連による三重の妨害工作だ」 「国連が私にくれたものは2つだ。動かないエスカレーターと作動しないプロンプターだ」 「国連から得たのは壊れたプロンプターとエスカレーターだけだった。ありがとう」 プロンプター
この後、トランプ大統領 レビット報道官 「国連職員が故意に停止させたのであれば、その人は直ちに解雇され、捜査されるべきだ」 「トランプ大統領の前にいた人物が誤って安全装置を作動させた」 「国連の職員たちがトランプ氏らが使うエスカレーターの電源を切り、“資金が尽きたので階段を上っていただくしかありません”とトランプ氏に伝えることを冗談として話している」 レビット報道官 「国連で、誰かが大統領とファーストレディのエスカレーターを意図的に止めたのだとすれば、その人は直ちに解雇され、調査されるべきだ」
トランプ大統領 「役割を果たしていない」 「国連から得たのは、途中で止まってしまうエスカレーターだけだった。 ファーストレディがこんなに元気でなければ転ぶところだった。幸い、妻は元気だし、私たちふたりは絶好調だ」
「エスカレータの故障」 「out of order=故障中」 out of order 「故障した=out of order」 out of order out of order キャサリン・クラフト『日本人の9割が間違える英語表現100』(ちくま新書、2017年) 〇 The elevator has been out of order
○ The vending machine was out of order
? The vacuum is out of order
? If this watch should get out of order
? The door won’t open; the lock must be out of order
最後の文に関して、普通、家の錠前は機械と呼べるほど複雑なものではなく、公共性が強いとは言えないでしょうから、out of order ♥♥♥
トランプ大統領 国防総省(Department of Defense) 「戦争省」(Department of War) 「戦争省」 「戦争長官」 トランプ大統領 「我々は世界最強の軍隊を持っている。匹敵する国は他にない」 「強さ」 「戦士の精神」 トランプ 「戦争省だったころは信じられないほどの勝利の歴史があった」 ヘグセス国防長官 「我々は防衛だけでなく攻撃にも回る」 「力による平和」 「 国防総省」 「 戦争省」 「自分にノーベル平和賞を与えろ」 トランプ大統領 米国は1789年に陸軍などの運用を担う「 戦争省」 「 国防総省」 ヘグセス国防長官 国防総省 「戦争長官」「戦争省」「戦争副長官」 トランプ大統領 メキシコ湾 共和党 トランプ大統領 「 国防総省」 「 戦争省」 「 国防総省」 民主党 タミー・ダックワース議員 「なぜこの資金を軍人の家族支援や、紛争を未然に防ぐ外交官の雇用に充てないのか?」 「トランプ大統領は国家の安全保障を強化し、勇敢な軍人とその家族を支援することよりも、政治的な得点を稼ぐために軍を利用したいからだ」 ヘグセス国防長官 「『アメリカ第1主義』、そして『力による平和』を『戦争省』によってもたらし、この国の気風を形づくっていく」 「戦争省」 トランプ 「名称の変更のために多大な費用がかかるのに、権威主義的な国々への対応など軍が取り組むべき課題解決にはほとんど役立たない」 トランプ大統領 「それほど多くない」 国防総省
2021年、バイデン 9・11テロ 9・11テロ ジョー・バイデン前大統領 「アーリントン国立墓地のアフガニスタン戦没者墓地に並ぶ墓石をご覧いただきたい」 「戦争省」(Department of War) 「国防総省」(Department of Defense)
ところが、9・11テロから24年を迎え、米国全土が追悼ムードに包まれる中、米国のドナルド・トランプ大統領 「米国が攻撃されたならば、我々は最後までその全てを追及する」 「我々は一切の容赦なく彼らを叩き潰し、確実に勝利を収める」 「以前の国防省という名称を戦争省に変更した」 「戦争省」
トランプ大統領 「「戦争省」の省名の下で、我々は第一次世界大戦にも第二次世界大戦にも勝った。しかし、我々はその後『ウォーク』になってしまった」 ウォーク(woke) woke コチラ で)。今日では皮肉を込めて使うことが多くなっています。ヘグセス国防長官 「戦争省へようこそ。『国防総省』の時代は終わった」 「戦士(warrior)の気風」の回復を改めて訴え、「我々は『ウォーク省』になってしまっていたが、もうそうではない」 「太った軍を見るのは嫌気がさす。太った将軍や提督も絶対に受け入れられない」 「あまりにも長く我々米軍は、人種、ジェンダーに基づいて割り当てるクォーター制、いわゆる『史上初』…などの誤った理由で、あまりにも多くの制服組の軍人を昇進させてきた」 ♥♥♥
私がミステリーにどっぷりと浸かるようになったきっかけは、高校生の時に、エラリー・クイーン(Ellery Queen) 「国名シリーズ」 創元推理文庫 「読者への挑戦」 『ローマ帽子の秘密』『フランス白粉の秘密』『オランダ靴の秘密』『ギリシャ棺の秘密』『エジプト十字架の秘密』『アメリカ銃の秘密』『シャム双子の秘密』『チャイナ蜜柑の秘密』『スペイン岬の秘密』『日本カシドリの秘密』 『Xの悲劇』『Yの悲劇』『Zの悲劇』『レーン最後の事件』
作家エラリー・クイーン フレデリック・ダネイ(Frederic Dannay、1905~1982) マンフレッド・ベニントン・リー(Manfred Bennington Lee、1905~1971) 『ローマ帽子の秘密』 エラリー 「国名シリーズ」 バーナビー・ロス(Barnaby Ross) ドルリー・レーン(Drury Lane) 「レーン四部作」 『Xの悲劇』『Yの悲劇』『Zの悲劇』『レーン最後の事件』 ダネイ リー
ダネイ リー エラリー・クイーン バーナビー・ロス クイーン ロス 『ローマ帽子の秘密』 「バーナビー・ロス殺人事件 作品中で、 「以上の説明がわかりにくいとしたら、それは英語ということばが複数の人間のからんだ ややこしい話を説明するのに適していないからである」 など といった、人を食った書き方をするのも、いかにもクイーン エラリー・クイーン Ellery Queen’s Mystery Magazine (EQMM)フランス、カナダ、ポ ルトガル、オーストラリア、スウェーデン、日本 『EQMM』 もちろんこの誌名は、ミステリー作家であり初代編集長でもあるエラリー・クイーン クイーン 『EQMM』 「エラリー・クイーン」 フレデリック・ダネイ マンフレッド・リー フレデリック・ダネイ ダネイ 『EQMM』 MWA賞特別賞 『EQMM』 MWA賞巨匠賞
大学生・教員生活へと、私のミステリー中毒は続き、アガサ・クリスティ(Agatha Christie)、エド・マクベイン(Ed McBain)、アール・スタンリー・ガードナー(Earl Stanley Gardner)、ブレット・ハリディ(Brett Halliday)、ジェシカ・フレッチャー(Jesicca Fletcher)、パトリシア・コーンウェル(Patricia Cornwell)、ロビン・クック(Robin Cook) ♥♥♥
BS-TBSの歌番組「Sound Space S」 一青 窈(ひととよう) 「時を超えた、ここでしか聴くことのできない上質なサウンド」 「音づくり」
2002年に「もらい泣き」 日本レコード大賞「最優秀新人賞」 一青 窈 「もらい泣き」 「平成で一番歌われた曲第1位」 「ハナミズキ」 一青 窈 「Sound Inn S」 一青窈 マシコタツロウ 武部聡志 「ハナミズキ」 「アレキサンドライト」 一青 窈
1曲目は彼女を国民的シンガーへと押し上げた代表曲「ハナミズキ」 アメリカの同時多発テロ “カラオケで平成に一番歌われた曲” 船山基紀 船山 「歌詞が本当に素晴らしくて、アレンジを考える前に詞の世界にすごく入り込んで、うるうるしながらアレンジしました」 船山 一青 一青 「毎回やっぱり泣きたい気持ちになるんです。ピアノ1本で歌ったり、アカペラで友達と歌うときもあるし、こうやって船山先生にアレンジしていただいたり、どんなスタイルの時でも、私は自分がまるで小さな孤島にいて、その前に大きな海原が広がっていて、そこでみんなの幸せを祈り、叫んでいる…そんなすごく尊い気持ちになるんです」 裸足で 歌い上げる姿も懐かしかったです。
2曲目は「骨」(2023年) 笹路正徳 一青 武部聡志 堀優衣 一青 ゴスペラーズ の 北山陽一 「北山さんは大学の先輩で、当時私が書く詞を気に入っていただけて、『俺が曲をつける』と言ってくださったことがきっかけで、本格的に作詞を始めました」 笹路 「この曲に関しても自分なりに解釈すると、日常の中にちょっとギザギザ感があるといいなと思いました。そこはかとなく、ちょっと捻じれたような、そんな感じを目指しました」 一青 「そのギザギザ感が色気を知った感じになる」 「気持ち的にはちあきなおみさんの気持ちなんですよ。こういう物語がある時は芝居をしながら歌う感覚で、この曲は特にその要素が強いので、ライヴで歌う時もちょっと動きが派手になるんです。この番組は自由に動き回って歌っても許してくれるので(笑)、気持ちよく歌えました」
ラストは最新曲の「アレキサンドライト」 大嵜慶子 「大きな決断をしたママ友に向けて、彼女が強く生きていけるような詞をプレゼントしたいと思って書きました。これから先、何が待ち受けているかわからない、アレキサンドライトのように光によって色が変わるかもしれないけど、本来のあなたが持っている輝きを思い出して欲しいという思いを込めました」
実は、一青 大嵜 大嵜 一青 大嵜 一青 「当時、母を亡くした中で孤独な気持ちを抱え大学受験に臨んで、何のために大学生になるかもわからず、歌手になりたかったけどなれるかもわからず、不安の中をさまよっていて、そんな時音楽が支えになった。でも今はこんなにたくさんの人に囲まれて、幸せな音に包まれているんだなって。色々な記憶が蘇ってきて涙が出てきました」 大嵜 大嵜 「新曲なので、原曲の込められた思いやサウンドに込められた思いはそのまま踏襲しつつ、でも後半に向けてぐわーっと大きい波が作れるように、前半は極力引き算して弦とギターだけ、徐々にバンド一人ひとりが加わっていくっていうようなイメージでアレンジしました。エッセンスとしてティン・ホイッスルとフルートを入れさせていただきました」 一青 「とっても素敵なアレンジで、自分で歌いながら、こんな風に自分個人の人生を投影して何かを歌えるとは思わなかったので、そこも発見でした」 「こんなに長い時間を経ても、すぐにあの頃に戻れたり、また未来の希望のようなものをつかみに行けたり、本当に不思議。音楽って時間も泳げるというか、時を経て、何か不思議な縁を感じることができ感謝です」 一青 「夢のまた夢じゃなくて、夢に次ぐ夢が音楽には起こる。そんな番組で歌えることができて、私はほんとうにめちゃくちゃに幸せだっ♥」
この一青 窈 「Sound Inn S」 TVer(ティーバ) コチラ でもう一度見ることができます。ぜひご覧ください。私はつい最近『理念と経営』10月号(コスモ教育出版) 一青 ♥♥♥
▲一青さんのインタビュー記事が!!
田中将大投手(たなかまさひろ、37歳) 野茂英雄(201勝) 黒田博樹(203勝) ダルビッシュ有(208勝) 日米通算200勝目 (楽天119勝、巨人3勝、ヤンキース78勝)の金字塔を記録しました。1学年下の小林 細川 中川、田中瑛、大勢、マルティネス マー君 大勢 阿部監督 マルティネス 増田陸 増田大 田中将 田中投手 日米通算200勝に王手をかけながら3連敗と足踏みをしていた田中投手 「マー君、人の子、普通の子」 田中投手 野村(克也)監督 野村 「『マー君、困った時はアウトローだぞ』 と野村 マー君 『こっちでは(アウトローでも)放り込んでしまうくらいのパワーがあるバッターがいるんです。(だから対策として)ボールをベース上で動かしたりだとかが必要なんです』 といったようなコメントでした。現地で経験したことを言っていたのでしょうが、それで日本に戻ってきて通用するかというと、日本の野球は日本の野球です。メジャー時代にはボールに力があったし、球が動くのも大きかったと思うのですが、日本に帰ってきてそれをやっても、勝てませんでした。何かが違うんです。何かっていうのは、野村 小林捕手 田中投手 桑田2軍監督 「マー君のアウトローはどれ?」 「そんなに低いんですか?」 「それができたら勝てるから。アウトローが高くなる。変化球は甘くなる。それでは抑えられない。フォームは関係ない。僕が教えたのはそこだけ」 野村 桑田再生工場 田中投手
試合後の会見では、プロキャリアをスタートさせた2007年に楽天の監督だった野村克也さん 田中投手 野村 「やりましたよと。うーん、ただ、時間かかりすぎだ、バカ、と言われそうですけどね」 「マー君、神の子、不思議な子」 「プロ野球の世界に入って、最初にプロ野球のイロハをたたき込んでもらった方だと思います」 「ピッチャーはコントロール」 「原点の外角低めにいつでも投げられるようにしなさい、としつこく言われました」
巨人首脳陣の「覚悟」が、偉業を後押したと思われます。楽天を自由契約になっていた右腕の獲得は阿部監督 「まだまだできる」 内海投手コーチ 「初めの数カ月は気を使っていた部分もある」 「監督のマー君を勝たせたいという本気度が伝わってきたから」 杉内投手チーフコーチ 内海コーチ 「実績は到底かなうようなレベルじゃないけど、マー君の年齢の時に“もっとこうやっとけば良かった”ということは伝えられる。今が、その時やと。今までやってきたことを継続するんじゃなくて、思い切って何かに取り組む。俺はそれができひんかったから」 久保巡回投手コーチ 「もっと“こうじゃないですか”と気持ちをぶつけてきてほしい」
面白いことがありました。この日リリーフ登板した中川投手 「めっちゃいややったです正直(笑)。1点差やったし、一番接戦のケースじゃないですか、なので、本当にできれば投げたくなかった(笑)」 「でも逆をいえばこういう試合に、貢献できたというのはすごい一生に一度、あるかないかくらいのことだと思うのでそれは本当今となって勝ったので。一生残るのでそれは光栄に思います。200勝に最後、携われてよかったです」 小林捕手 中川投手 「写真撮ったらしいじゃないですか、僕だけ普通にトレーニングしていました。誰も呼びに来てくれなかった」 中川投手 田中投手 ♥♥♥
米国には、20世紀初期から「ブッククラブ」 「本を読みたいが近所に本屋がない」 “ブッククラブのパイオニア” 「ブック・オブ・ザ・マンス・クラブ(Book Of the Month Club)」 「アメリカ国民に、最上の新刊書を届けよう」 ハリー・シェアマン(Harry Scherman) 「ブッククラブ」
20世紀半ばまで、アメリカ合衆国における本の流通事情は非常に劣悪なものでした。人口と書店との比率を見ると、1914年時点で2万8,000人あたり書店1軒、1930年ではさらに悪化して人口3万人当たり書店1軒でした。1931年時点で、全米の85%の地域には大型書店は存在せず、70%の地域では小型の書店すらなく、66.6%の地域ではいかなる種類の書店もありませんでした。つまりアメリカの総人口の32%が書店とは無縁の生活を強いられていたのです。「本を買って読もうにも、家の近くに本屋がない」
1887年にモントリオールで生まれ、名門フィラデルフィア高校を卒業、その後1907年に小説家を目指してニューヨークに出てきたものの、ハリー・シェアマン 「J.Walter Thompson」 「本をメールオーダーで販売してみたらどうか?」 シェークスピア 「Book-of-the Month Club」 ブッククラブ ブッククラブ
ブッククラブ Doubleday Book Club Mystery Guild Ed McBain ♥♥♥
仁多郡 お米は昼間光合成でデンプンを作り、夜間に穂に蓄えられます。しかし夜の気温が高いとせっかく蓄えられたデンプンを消耗してしまいます。稲の登熟期(穂に実の入る時期)に昼の気温が高く夜の気温が低いことが、お米の旨味に大変重要な要素となります。仁多郡
お米500~600kgを作るために、田起しから収穫するまでには、150tもの水を必要とすると言われています。たくさんの水を必要とするお米だからこそ、水は命なのです。仁多郡 仁多米
圃場で刈り取った稲は籾のまま仁多郡
▲お米屋さんに新米入荷
「令和の米騒動」 「仁多米」 「仁多米」 5,380円 でした。ずいぶん高くなりましたね。でも毎日食べるもの、やっぱり美味しいお米がいいですね。「仁多米」 「あー、全然違う!!」 ♥♥♥
▲これが一番美味しい!!
◎炊き上がりは白く美しいツヤがある。 ◎強い旨味と粘りがある。 ◎豊かな甘みがある。 ◎しっかりとした粒感を感じる。 ◎もちもちの食感がある。
コーヒーが健康に良いことはよく知られていますね。多くの研究により「コーヒーの摂取は大腸がんリスクの低下と関連している」 ワーゲニンゲン大学 アビソラ・M・オイエレレ
「コーヒーの摂取量は1日3~5杯が最適と思われ、特に4杯飲むと死亡リスクが最も低くなっていました」 八幡 ブルーマウンテン、森のコーヒー コーヒーが大腸がんの再発を防止するメカニズムはまだ解明されていませんが、これまでの研究により主に3つの可能性が提唱されています。1つ目は、コーヒーの強力な抗酸化作用が酸化ストレスから細胞を守る機構を活性化させ、がんを予防しているという可能性です。2つ目は、コーヒーの摂取が腸内細菌の組成を調整し、これによりがんの予防や治療効果が促進されている可能性です。 そして3つ目は、コーヒーの摂取が大腸がん患者の肝機能を改善し、肝臓への転移の危険因子とされている非アルコール性脂肪性肝疾患を予防することで、大腸がんの転移を防いでいるという可能性です。研究チームは、今回の観察研究ではコーヒーとがんの因果関係まではわからないとした上で、「私たちが得た知見は将来の介入研究の役に立つと同時に、大腸がん患者の治療のためのガイドライン作りに役立つエビデンスにもなるでしょう。コーヒーが大腸がんの予後を改善するメカニズムを完全に理解するために、さらなる研究が求められます」
コーヒーには、胃がんや直腸がんなどのがんリスクを減らす効果もあると言われています。これはコーヒーに含まれるポリフェノールの一種である「クロロゲン酸」 「一部の論文で小児の白血病のリスクが上がるというデータもあるようだが、概ねコーヒーを1杯飲むごとにがんリスクが下がるという研究が多いようだ」
そのコーヒー豆 ブラジル ロブスタ種 アラビカ種 味の素AGF 「ブレンディ」 セブン-イレブン・ジャパン 「セブンカフェ」 UCC上島珈琲 カフェパウリスタ UCCコーヒー ベトナム 八幡 ♥♥♥
「ナースーログ(nurse log=看護師の木)」 「ナースログ」 「倒木更新」 「ナ-スログ」 だからあの風倒木のことを、森を看護しているんだ、看護師の役割をしているんだ。というので「ナースログ(nurse log)」 「ナースログ」 「ナースログ」
この事実に気づかず、森から倒木を排除してしまったら、森はどんどんやせていくに違いありません。実は、企業社会という森の世界にも「ナースーログ」 鹿児島県阿久根市 「A-Zスーパーセンター」(1997年~、24時間営業、売り場面積2万㎡) 「 AZ」 「ムダが富を生む」 「ムダとはいったい何か?」
もう少し卑近な例で考えてみましょう。たとえば、息抜きのための、ちょっとしたサボリの時間。これなども「ナースーログ」 。 忙しくて集中して働かなければならない時は仕事に没頭します。でも、ピークを過ぎたら少し休む。職場でぼーっとして過ごす時間がやはり必要です。それはなぜかといえば、ぼーっとすると意識が自由になります。いろいろなことがとめどなく頭に浮かんでくるからです。私が大好きで著書をむさぼり読んでいる新聞社に勤めていた頃の川北義則(かわきたよしのり) 「ナースログ」
私が教員になりたての頃は、放課後の時間に先生方で将棋をやったり、野球チームのユニフォームを作って定期試験中に他校との交流試合をやったり、校内で分掌ごとのソフトボールやバレーボールの対抗戦をやったものです。生徒達もそれを喜んで観戦していました。教員の囲碁・将棋大会も盛んに行っていました。英語科では長期休暇になると、みんなで遠方(北海道・東北・九州等)へ研修旅行に出かけたものです。忘年会なども遠方の温泉を貸し切って泊まりがけで行きドンチャン騒ぎをやっていましたね。飲み会も頻繁にありました。松江北高 体育祭 「3年生を送る会」 「ナースログ」
しかし、現在の成果主義一辺倒の社会では、「周りは全てライバル、失敗は許されない」 「ムダをもっとなくせ!」 ♥♥♥
マークー・トウェイン 『トムーソーヤの冒険』 「僕にもやらせてよ」 「そんなこと言わないでさ」 「仕事とは、いやでもやらなければならないこと」 「遊びとは、しなくてもいいのにあえてすること」
釣りは、漁師にとってはいやでもやらなければならない「仕事」ですが、それを趣味にしている人にとってはやらなくてもいいのにあえてする「遊び」です。同じように将棋は、プロ棋士にとっては仕事ですが、趣味で指す人間にとっては愉しいゲームです。テニス、絵画、ピアノ、陶芸、……何でもそうでしょう。やらなければならないことか、しなくてもいいのにあえてすることか、「仕事」と「遊び」の大きな違いはそこにあるのです。さて、そうなるとこんな疑問をもつ向きもあるでしょう。「仕事が大好きで、愉しくてしかたがない人、自腹で仕事の勉強をしたり、やらなくてもいい残業や休日出勤まで喜んでするような人はどうなのか?」 ゴーリキー 「仕事が義務なら人生は地獄だ。仕事が愉しみならば人生は極楽だ」
仕事を愉しめる人は、自分のやるべき仕事を、しなくてもいいのにあえてする「遊び」の領域にまで広げられる人なのだと思います。仕事をいやいややる人と、愉しみながらやる人と、どちらがいい仕事をするかは言うまでもないでしょう。愉しみながらいい仕事ができたら、これほど素晴らしいことはありません。その意味では、もちろん、「趣味は仕事」「仕事が生きがい」という人生があってもいいのです。ただし、サラリーマンの場合、自営業と違って、仕事は一生できるわけではありません。定年後、再就職したとしても、いつかは仕事を離れる時が来ます。いくら仕事が遊びのようなものだといっても、仕事を離れてしまえば、その愉しみはなくなってしまいます。実際、現役のときは仕事が面白くてしかたがないといきいきしていたのに、リタイアしたとたん、秋枯れの木立のようにしょぼくれてしまう人が少なくありません。仕事を愉しみにするのはいいのですが、仕事の他に愉しみを知らない人の老後は、やはり寂しいのではないでしょうか。仕事を辞めた後の人生は長く、平均寿命を考えれば、65歳まで働いても、あと20年はあります。この第二の人生を愉しく愉快に生きていくには「遊び」が不可欠です。だから、仕事が愉しい人も、愉しくない人も、若いうちから、もっと遊んだほうがいい。それには、面白そうだなと思ったら、とりあえずやってみることです。他人から見たらバカげたことでも、何かしら心に響くものがあれば、まずは手を出してみることです。
ちなみに、「仕事」 「趣味」 カール・ヒルティ 「仕事」 「趣味」
例えば、私は若い頃、将棋 学園祭 マジック 「趣味」
英語 竹林 滋先生(東京外国語大学名誉教授) ヒルティ 「仕事」 ある事に一所懸命になって自分を沈潜させてみたり、身も心もくたくたになるくらいに全力投球をすることで、面白さが出てくるもの、それが「仕事」 「仕事」 「仕事」 ヒルティ
「仕事」 「趣味」 「石の上にも三年」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はラーメン
▲米子高島屋の特設会場
米子高島屋 「第6回大京都展」(9月3日~9日) 「本家第一旭」(ほんけだいいちあさひ) 京都駅 「第一旭 本店」 「京都たかばし 本家 第一旭」 京都ラーメンの老舗で、創業昭和22年、60年以上の歴史を持ったお店です。すぐお隣が「新福菜館」(しんぷくさいかん) ラーメンの味は一種類だけで、味に絶対の自信がないとなかなかできないことですよね。この潔さはすごいものです。
「本家 第一旭」 「京都を代表するラーメン店」 京都 「第一旭」 「第一旭」 「第一旭」 「第一旭」 京都 「第一旭」 ◎スープ:豚骨×鶏ガラの深いコク 動物系の旨味がしっかりと感じられるにもかかわらず、飲み口は割とあっさりとしており、後味に重たさが残りません。スープの色は薄く、少し脂が浮いています。クセになるうまさです。 一説によると、このスープは豚骨でダシをとっているとのこと。白く濁る前の旨味だけが出ているほんの一瞬にだけ取れる清湯(チンタン)スープを使っているため、豚骨の臭みがないらしい。マジか?
◎麺:中細のストレートの絶妙な食感 歯切れが良く、ほどよいコシがありながら、スープをしっかりと絡めてくれる自家製麺です。
◎チャーシュー:ボリュームと旨味 薄くスライスされたチャーシューは、たくさん入っており、柔らかく煮込まれて、噛んだ瞬間に肉の旨味がじゅわーっと広がります。チャーシューは2回出産を経験した、体重120kg程度の雌豚(「中大貫」と呼ばれます)を使用しています。豚肉は普通、若い豚を使用しますが、それでは脂肪が多めで、スープに濁りが生じます。澄んだ醤油味のスープに良く合い、かといって「大貫豚」ほど大味にならない、そのために選んだのが「中大貫」です。国産豚ですが、近年では市場にほとんど出回らない「こだわりの品」です。
◎トッピングのこだわり 大好きな九条ネギ
▲高島屋の特設会場
朝からでも食べられる優しい味わいで、 脂や塩分のバランスが絶妙で、目覚めてすぐの胃にもすんなり収まる設計です。お昼時はお客さんでいっぱいだと聞き、午後の遅い時間帯にお邪魔したところ、空いていました。高島屋 「ラーメン」 「チャーハン」
▲9年ぶりに懐かしい味でした
大好きな九条ネギ ラーメン全体のお味は、私の大好きな広島 「すずめ」 「つばめ 」 松江 「太平楽」 しかし、一体なぜ今回、期間限定での米子オープンが実現したのでしょうか?鳥取県米子市 鳥取大学医学部 「第一旭」 「第一旭」 「本家第一旭本店」 大森高男さん(88歳)
大森 鳥取大学医学部 「第一旭」 「第一旭」 ♥♥♥
鉄道大好きの私は、毎週火曜日BS日テレで午後9時から放送されている「友近・礼二の妄想トレイン」 友近(ともちか) 「おしゃれクリップ」(日本テレビ系)
さまざまなキャラクター(演歌歌手・水谷千重子・ 西尾一男 友近 ハリセンボン 友近 西尾一男 友近 友近 「当時から自分が面白いと思うことをずっと人に発表し続ける子だった」 友近 「無罪」 友近 中川家・礼二 友近 “お笑いのために生きている”姿勢
友近 松山 道後温泉 「大和屋本店」(やまとやほんてん) 「能舞台」 「千寿殿」 道後温泉 「風姿花伝」 友近 ♥♥♥
CS放送のナショナルジオグラフィック 耐久技 ストリート・マジック デビッド・ブレイン 「奇術師デビッドが挑戦!世界の超過激パフォーマンス」 「日本編」 セロ 『マジック革命!セロ!!』
セロ・タカヤマ セロ 「感動的だった。本当の魔法使いがいると思った。それ以来『奇跡を起こす力』が欲しくなって、念力でコップを動かす練習を何度も繰り返した」 『プロマジシャンに教わる10回分のプライベートレッスン』 「学校でギャンブルをしている」 「マジックとの出会いで、空っぽだった自分が唯一、自分にしか持てないものを手にした」
父親の出身地である沖縄県今帰仁村 マジックキャッスルジュニアメンバー フューチャー・スター セロ セロ セロ 「パッションを感じていないものに時間を費やせない性格」 セロ 「ノーギャラでいいのでマジックをやらせてください」 「FISM横浜大会」 セロ 「僕の『一夜の成功』は15年かかった。僕は逆輸入のマジシャンのように言われることが多いけど、本当は10代の頃からずっと日本で努力をしてきたんだ」
▲マジシャンのセロ
セロ 、「この2時間に当時の持ちネタを全て詰め込んで、これ以上見せるマジックがないというほど出し切った。そうしたら放送翌日にプロデューサーから電話があって、『視聴率がとても良かった。もう1本、2時間スペシャルをやってくれないか』という相談だった。次に何をするかはわからなかったけど、もちろん、即答で引き受けた」 「忘れられない体験だった。自分のことをスターとは思ってないけど、セレブリティのライフスタイルを味わえた。サインを求められたら喜んでしたし、何よりも日本のほかのマジシャンたちに認められたことがうれしかった。この波にいつまでも乗り続けようと思っていた」 セロ
「ミュージシャンはヒット曲を作れば何度も歌えるけど、テレビで一度見せたマジックはもうやれない。『それはもう見た、はい次』と、マジックの扱いが消耗品のように思えた。その頃はやり始めたYoutubeなどでは、いろんなマジックの見せ方が出てきてたのに、テレビではそれまでと同じフォーマットでしかやらせてもらえなかった。」 番組の超目玉となる大掛かりなマジックばかりを求められました。前回を上回る規模とクオリティを保たなければならない、とのプレッシャーはそれは半端なものではありませんでした。やがてセロ 「マジックが汚れてしまったように思った。いったん全てから離れないといけないと感じた」 「マジック新世紀セロ生放送SP」 セロ コチラ です)、これを機に身を引きました。しばらくはバーンアウト状態が続きました。「マジシャンとしてのパッションを失くしてしまった。食事もおいしく感じられなかった。パーティーに行っても楽しく感じなかった」 セロ
テレビを離れてからも活動は続きました。日本でのショーの合間に海外を旅行したり、大会に参加したりして過ごしました。10年間はあっという間に過ぎていきました。コロナ禍で自分と向き合う時間が増え、2022年に迎えた49歳の誕生日。50歳を目前にして考えたのは、自分がこの世に存在する意義です。「自分のたどった軌跡は何も変えたくないけど、自分がなぜこの世に生まれたか、どう覚えられたいのかについて考えるようになった」
「マジックは僕のコミュニケーション能力を向上させて、たくさんの友達を与えてくれた素晴らしい芸術だ。いまは情報量の多さからどうしてもトリックだけを見せる短いクリップが流通しがちだけど、僕が知っているマジックはそうじゃない。言葉にできないけど不思議な力を見た時に感じる感動……かな。それがマジックだという認識を広めたい」 ったため、今の人たちがマジックをどう思っているのかを確かめる試みでもありました。 「 子供は正直だから、面白くなかったらそう言う。手応えを感じられるのは、自分がやっていることが間違ってないからだと思う」 セロ 。「マジックを見たときに感じる気持ちを覚えておいてほしい。今日、このマジックの『秘密』を教える代わりに、これを練習してお友達や親戚にその同じ気持ちを感じさせてほしい」 セロ セロ セロ 「えーッ!?」 セロ 「はい、終わり!帰ろうね」「いつでもマジックができる準備をすることはマジシャンとしての責任だと思う。パフォーマーだから、状況が許せばマジックを披露して、人から笑顔を引き出することはいまでも大好きだよ」 セロ
マジックには、見る人の「子ども心」を呼び起こす力があります。何歳であろうと、その人が内面に持っている「子ども心」がマジックに感動します。そのピュアな感動の気持ちを後世に伝えることが、今の自分の役目だというのが、セロ ♥♥♥
「この人生がいつ終わるかは、誰にもわからない。だからやること全てに意味を持たせたい。自分や他の人たちの人生を充実させるマジックをしていきたい」(セロ)
イタリア・トリノ 「FISM 2025(フィズム/国際奇術連盟主催)」 Ibuki(イブキ)(24歳) クロースアップ・マジック部門 グランプリ 「FISM」 “マジック界のオリンピック” マイクロマジック部門 FISM Ibuki 「洋服のボタン」 「世界一のマジシャン」 今回のIbuki Mr.マリック セロ Ibuki
この度、FISM2025にて、日本人として初めてグランプリを受賞することができました。この受賞は、決してひとりでは成し得なかったものです。アクトの演出を担った せとな、そしてマネジメントを支え続けてくれたHISA、共に歩んできたチームの存在に、心から感謝しています。この受賞をきっかけに、もう一度日本にマジックブームの風を巻き起こしたい。その先頭に立つ存在として、これからも挑戦を続けてまいります。 Ibuki
上手、不思議、面白いだけではグランプリーはとれません、派手なまやかし、巧妙な仕掛け。誰かの影を感じる演技 をFISMの審査員は見抜きます。その審査員全員の心を掴んだibukiさんに心から敬意を表します、おめでとうございました! Mr.マリック
Ibukiさんのグランプリ受賞に心から敬意を表します。「マジックで一番難しいのは、それを簡単に見せること」。まさにその本質を体現してくれました。本当におめでとうございます。 そして、これからのご活躍を心より応援しています。 Cyril ――「FISM」でグランプリを獲得したお気持ちを教えてください。 優勝するのを目指してはいたけど、こんなすぐかなうものなのかというのは。でもまあ、FISM 「FISM」 「クロースアップ・マジック」 「ステージ・マジック」 「ステージ・マジック」 「クロースアップ・マジック」 Ibuki 「クロースアップ・マジック」
――「FISM」では、どんなマジックを披露されたのですか? 服のボタンを使ったマジックなんですけど、このボタンがいろんなところに移動したりとか。マジシャンが登場して、まず服に4つボタンがついているダブルジャケットを着ていて、そのボタンに手をかざすとボタンが縫いついた状態で移動していって、そのボタンを切って並べたりしていろんなところに移動して、さらに縫いついて。いろんなものがとにかく“縫いついていく”というマジックです。
――マジックとの出会いはいつごろですか? マジックと出会ったのは小学生のころにクリスマス会にマジシャンが来て、そのマジシャンがトランプをプレゼントでくれたのが始まりです。マジックにそもそも魅了されて、トランプももらったんで自分でもやってみようみたいなかたちで始めました。独学でいろんな本だったりDVDを見たり、人に教わったりといろんな方から教わって独学で始めていきました。
――マジシャンは職業として活動しているんですか? 実はですね、サラリーマンをしながら趣味といったらあれなんですけど、兼業みたいなかたちでマジックをしておりまして。平日5日間働いて土日はマジックショーをやったりとかコンテストに出たりというふうな活動してますね。私自身も平日朝と夜練習して土日ショーやってってかたちですし、会社側にも色々土日休ませてくださいと融通を利かせていただいてるので。 マジシャン一本でもやっていけはするんですけど、ただ自分がやっぱりやりたいマジックっていうのが、本当に自分が好きなこだわり抜いたマジックなので、それを例えば営業先に持って行くとなるとその場のお客様にあわせてマジックをコーディネイトしなきゃいけないので、自分がこだわり抜いたマジックがそこにぴったり合うかっていうとちょっと変わってくるので、自分がやりたいマジックだけをしたいのならこのスタイルなのかなというふうな思いはあります。
――パフォーマンスする上で大切にしていることは? 一番は自分が楽しみながらやることですね。やっぱり自分が楽しいのがお客さんに伝わってお客さんも楽しんで見てくれるっていうかたちになると思うので、一番は自分が楽しんでやることですね。
マリック Ibuki ウサイン・ボルト
VIDEO
岩谷 テンホー(いわたに てんほー、71歳) 『みこすり半劇場』(ぶんか社) 岩谷 長崎県 五島列島 『週刊プレイボーイ』 『マグニチュード9.99』 『少年ジャンプ』 「育ててくれた雑誌」 「東京スポーツ」 「みこすり半劇場」 「『サザエさん』の世界にお色気を持ち込んだもの」
長年、いわゆる「かわい子ちゃん系下ネタ」、「頑固親父」、「時代物」、 「ブス女」 「野球ネタ」 「偉大なるマンネリ」 「エヘッ!!」
当然ながら作品発表の場はお色気ものの4コマ雑誌(艶笑4コマ誌)か、青年漫画誌に限られていますが、過去にはごく稀にファミリー向けの4コマ誌にゲスト作家として招かれたこともありましたっけ。その時の雑誌の予告には「あの岩谷テンホーがファミリー向け4コマ誌に!大丈夫か?」 『みこすり半劇場』(ぶんか社) 「みこすり半」 笑うために 読まれる雑誌であって、性描写により購読者の快楽を誘うことを目的とした雑誌ではないために、いわゆる「成人向け雑誌」
▲最新作2025年春号
近年は、「大阪スポーツ」 ぶんか社 『大盛!!みこすり半劇場』(690円) 松江駅 セブンイレブン 「大阪スポーツ」(180円) ♥♥♥
▲ハサミで毎日切り取って放り込んでいる!
今から48年も前、大学を卒業し、島根県教員採用試験 「辞令交付式」 山本和夫先生(島根県立短期大学教授) educate(教育する) ex(外へ)+duce(引き出す) 外へ引き出してやる お手伝いをさせてもらいたい、という決意を、期待に胸を膨らませながら述べたのでありました。あれから48年か。そういう教師を目指して、秋山 仁先生 「教師五者論」 +芸者+指揮者 秋山先生 コチラ をご覧ください)、ひたすら駆け抜けてきました。
19世紀のイギリスの哲学者であるウィリアム・アーサー・ウォード The mediocre teacher tells.The great teacher inspires .しかし偉大な教師は心に火をつける 。 「生徒の心に火をつける教師 」 いい先生は丁寧に説明してくれる。もうちょっといい先生は自ら範を垂れ、最高な先生は俄然やる気にさせてくれる 。(W.A.ワーズ) 私は大学に入れるために英語を教えているのではありません。英語の面白さ・難しさ・奥深さ を生徒に伝えて、大学へ行ってからも、そして社会人となってからも英語の勉強を続けてもらうために必要な基礎・基本 をしっかりと教え、本物の英語の力をつけるために毎日の授業をしています。決して「分かりやすい授業」 「面白い授業」 「生徒の心に火を付ける」 「分かりやすい授業」 「あ~、英語の勉強って面白いな」「ワクワク、ドキドキ」 「もっと勉強してみよう!」 「良い授業」 「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、そしてゆかいなことはあくまでゆかいに」 井上ひさし 「笑い」
生徒たちの心に火を付けるために、私は教え子たちに協力してもらって、学校案内やパンフレットでは知ることのできない大学生活の生のレポートを送ってもらい、それを「あむーる」 松江南高校 毎週発行 していた「学級通信」 大田高校 「進路だより」 津和野高校 「学校だより」 松江北高 「学級通信」「英語通信」 勝田ケ丘志学館 「あむーる」 リチャード・クレーダーマン
さて、冒頭の英単語のeducate(教育する) duce「導く」 「語根」 『 ライトハウス英和辞典』(第7版) 「単語のキズナ」 ❤❤❤ ◎educate e(=ex)「外へ」+duce「導く 」 「 教育する」 produce pro「前へ」+ duce「導く 」 「作り出す」 introduce intro「中へ」+ duce「導く」 ⇒「 中へ導き入れる」⇒「紹介する」
reduce re「後ろへ」+ duce「導く 」 「少なくする」 induce in「中に」+duce「導く 」 「誘惑する」
◎seduce se「離れて」+ duce「導く」 ⇒「わきへ導く」⇒ 「誘惑する」
◎duct 導くもの⇒ 「送水管」
◎週末はグルメ情報!!今週はラーメン 鳥取県境港市麦垣 「黄金」(こがね) お食事処「池田屋」
カウンター上のメニュー表をご覧ください(写真上)。ラーメンが今時450円 ってなかなか見かけない値段ですね。大盛は各種150円増しです。カウンター席とテーブル席の小さなお店ですが、お客さんが入れ替わり立ち替わり次々と入って来られます。活気があり、繁昌していますね。ご高齢の店主さんは熱い鉄板の前で大忙しです。
セットメニューも色々あります。私は「ラーメン+ギョーザ+ライス」セット(750円) 松江市 「太平楽」 「ギョーザ」(5個)
▲これで750円は安い!
▲このラーメンが絶品!
▲このギョーザもいける
▲半熟の目玉焼きが好相性
この日、私の周りのお客さんはみんな「焼きそば」 「焼きそば」 「ラーメン」 「焼きそば」 「焼きそば」 「肉玉焼きそば」(550円) 「肉玉」 ♥♥♥
言っていることとやっていることが違う人間には、尊敬の念を抱くことができません。石破総理 「当選したからといって公約をその通りに実行するとはならない」「これまでも自民党は公約を守ったことはない」 第27回参院選 石破茂首相(自民党総裁) 「国民の厳しい審判を頂いた。深くお詫び申し上げる」「ここから先はいばらの道だ」 「政治を停滞させない」 「一切の偽りのない心で、うそのない心で国家国民のために尽くす。その思いでこれから先、臨んでまいりたい」
7月28日に行われた「両院議員懇談会」 糸山英太郎(83歳) 「人間はたとえダメでも優しさや人間味があるものだが、石破にはそれがない。呼んで説教をしようとか電話をしてあげようかという気にもならない。負けたんだから辞めるべきだし、このままトランプが来た時も相手にしてもらえない。25%の関税が15%になったと喜んでいるが、しっかりと日本はお土産を取られますよ。ただ、このままの状況が続いて、野党が不信任案を出せば、自民党の中からも賛同者が出て、通ってしまう。8月15日ごろがヤマ場になる」
石破 安倍晋三首相 「選挙に負けたのに続投するのは理屈が通らない」 「惨敗後も“使命を果たす”というのでは国民に説明がつかないのではないか。やめるべきではないか」 「私だったら即座に辞めて、落選した人に謝って回る」 麻生太郎首相 ブーメラン 「自分の信念をしっかりと持ち、それを貫いている人」 「有言実行」 “Walk The Talk” WTT “No Action Talk Only” NATO 造語 WTT NATO
▲この本勉強になる!
「比較第1党としての責任、国家、国民への責任を果たしていかねばならない」 「比較第一党に胸を張るのではなく、過半数を達成できなかったことを重く受け止めるべきだ」 小泉農相 『読売新聞』 「石破降ろし」 安部派 内閣の支持率も過去最低(22%)。党内には石破首相 「石破辞めるな!」 「石破降ろし」 「じゃあ誰がやるの?誰が火中の栗を拾うの?」 石破内閣
広島平和記念式典 石破総理 「平和への誓い」
9月7日(日)石破首相 「石破おろし」 「石破おろし」 ♥♥♥
櫻木健古(さくらぎたけふる) 『強いリーダーの条件』(PHP文庫、1987年) 中日新聞社 櫻木 かなり追いつめられた心境にあった、そんな頃のある日、仕事机の上で一匹のハエが、ひっくり返ってジタバタしていました。飛び立とうとするのですが、もうその力が残ってないらしく、あお向けのまま、ただむなしく回転するだけでした。やがて、その努力をさえやめてしまいました。おそらく、死期が近いのに違いありません。すこし残酷とは思いましたが、ある可能性を期待して、ハエに蚊取線香の火をブーツと近づけていきました。
はたせるかな、アワヤというところで、ハエは勢いよく飛び立ち、怒り狂ったように部屋のなかを飛び回り始めました。“さいごの力”をふりしぼったのでしょう。「そうだ、これだ!」 櫻木 「死力をふりしぼれば、できないはずのことがで きる。おまえも、もういちど卜ライしてみろ。“さいごの力”を出しきって、やってみよ」 「もう一度だけ」 櫻木 「もし、これもまた失敗するなら、永久に著述のペンは持たぬ」 ♥♥♥
ChatGPT 「 生成 AI」 「AI Scraping War」(AIデータ収集戦争) war の部分を、battle 、fight などに置き換える場合もあります。インターネット上の情報を大量収集して利用する AI 企業に対し、その情報・コンテンツの所有者(ニュースを発行する会社や個人、芸術家、ソーシャルメディアなど)が権利・利益の侵害を訴えて争う「戦争」を意味します。英語でscrape は「かき集める」という意味ですが、ここではAI が多様なコンテンツから大量のデータを収集して、「ただ乗り」 scrape )悪用しているとして、使用禁止と損害賠償の支払いを求めているのです。メディア企業は、コンテンツの使用に対する補償を求めて提訴したり、ライセンス契約を交わしたり、あるいはその両方を行ってきました。多くの企業は、AIボットがウェブサイトなどから情報を大量抽出する行為(scraping )を止めるよう丁重に要請しています。『ニューヨーク・タイムズ』 ChatGTP Open AI社 マイクロソフト 「AI Scraping War」 「スクレイピング」(scraping) ChatGPT
AI学習によるインターネット上の記事の「ただ乗り」 「 読売新聞社」 「パープレキシティ社」 「 日本経済新聞社」 「 朝日新聞社」 「パープレキシティ」
スクレイピング 例えば、ChatGPT ChatGPT ChatGPT ChatGPT アマゾン・コム ニューヨークタイムズ AP通信 オープンAI
ちなみに、ChatGPT ♥♥♥
【補遺1】 チャットGPT 「ペアレンタルコントロール」 【補遺2】 AI(artificial intelligence) intelligence は不可算名詞 s を付けるのではなく、tools やmodels やsystems といった具体的な可算名詞 s やaritificial intelligences といった変則的な複数形を目にすることも増えてきました。今後の動向には注目です。♠♠♠
JR松江駅 松江テルサ マンホール 松江市 松江城 「松江城をめざそう!水の都おさんぽルート」 「おさんぽルート」 デザインマンホール 二次元バーコード(QRコード) 松江観光協会 マンホール ♥♥♥
渡部昇一・編『読めば人間力が高まる東洋古典の名言366を1冊にまとめてみた』(致知出版、定価2,200円、2025年8月) 致知出版 『四書五経一日一言』 『四書五経一日一言』 「四書五経」 渡部昇一先生 「四書五経」 「四書」 「五経」
四書 :『論語』、『大学』、『中庸』、『孟子』を指します。
五経 :『易経』、『書経』、『詩経』、『礼記』、『春秋』を指します。
これらの古典は、中国だけでなく日本や朝鮮でも広く学ばれてきました。この『四書五経一日一言』
◎日々の習慣に :366の言葉が収録されており、一日一言読むことで、古典の教えを日常生活に取り入れることができます。◎分かりやすい解説 :渡部昇一先生 ◎人生のあらゆる場面で役立つ :多岐にわたる名言が、人生の様々な局面で力を与えてくれるとされています。◎初心者にもおすすめ :「四書五経」 編者である渡部昇一 「日本人の教養の背骨を成していた時代が数百年あり、その普遍的価値は今でも失われていない」 孔子 「四書五経」
本書は膨大な東洋古典の名著「 四書五経」 渡部先生 「朋あり遠方より来たる、亦た楽しからずや」「至誠は神の如し」「富は屋を潤し、徳は身を潤す」「往く者は追わず、来たる者は拒まず」 「人を造る力がある」 「礼儀を重んじる」「志を立てる」「中庸を心がける」 ♥♥♥
『読売新聞』 「時代の証言者 秋山仁」 秋山 仁(あきやまじん) 「教師五者論」 学者、医者、易者、役者、忍者 ●学者・・・膨大な知識を自ら身に付ける必要性
●医者・・・相手の得手・不得手、性格やタイプを見抜く力
● 易者・・・相手の不安を取り除く力
● 役者・・・相手を惹きつけ、魅了する力
●忍者・・・タイミングのいい時期まで耐え忍ぶ力
もっともなご意見だと思います。長年の経験から私はこんなふうにまとめてみました。
① 教師自身が常に疑問を持ちながら、日々現在進行形で学び続けることが重要です。100を知って初めて1を教えることができるのですから、一生教わる人、日々学び続ける人であり続けることが肝要です。だからいつまでも『学者』
② 学力に欠陥・問題点のある子を早期発見し、適切なアドバイス・診療を施す『医者』
③ 級友達をまとめるのがうまい、縁の下の力持ち的な仕事を黙々とこなす、落ち込んでいる友達に優しく接することをできる、など本人が気づいていない子どもの持つ隠れた適性や可能性を見抜いて、将来的な予見をする『易者』
④ 授業を楽しく面白く演出して、子どもたちに感動を与える『役者』 『 役者』
⑤「教えるべきことは教えず、子どもたちに気づかせる」 『忍者』
私は今までの長い教師生活の中で、もう二つほど付け加えておきたいと思います。 ⑥学校の催し物、日常生活を盛り上げて、子どもと一緒にのぼせて遊ぶ『芸者』
私はさらに、⑦教師は集団の向かうべき方向を見据えて、教室内の生徒達を整理し、取り仕切る『指揮者』
今、私の周りには、医学部希望の生徒がかなりたくさんいます。医者 観察者 検査屋 修理屋 カウンセラー
いい先生は丁寧に説明してくれる。もうちょっといい先生は自ら範を垂れ、最高な先生は俄然やる気にさせてくれる。(W.A.ワーズ) 生徒達を俄然やる気にさせ、知的好奇心に裏打ちされた深い学びに向かうことができるように育てていきたいと思って、私は長年やってきました。♥♥♥
NHK連続テレビ小説 「ばけばけ」 松江市 「ばけばけ」 「あげそげばけ」 「ばけばけ」 「ばけばけ」 「ばけばけ」 「このドラマは『化ける』物語です。急速に近代化が進む明治の日本は、人々の暮らしや価値観がどんどん『化けて』いきます。その中で取り残された人々の思いは、時に怪談という物語に形を変え語り継がれてきました。それと同じように、うらめしかったトキの世界も、いつしか、かけがえのないすばらしいものに『化けて』いくのです」 小泉八雲・セツ 「あげそげばけ」 松江市の上定昭仁市長 「小泉八雲・セツのドラマ応援室」 NHK連続テレビ小説「ばけばけ」 観光振興課 松江 八雲 セツ 松江 ウェルドン 「ニューヨークを旅立つ八雲」
「あげ、そげ、ばけ。」 です。 松江 八雲 「あれも、それも、ばけるよ。」 「あげ、そげ、ばけ」 「松江をアゲて、不要なものをそいで、ばけていく」 八雲 「音の面白さを感じてくれれば」(松江市観光振興課)
▲JR松江駅バス乗り場
ロゴマークのコンセプトは、松江で出会い心の旅をともにするセツ 八雲 「あげ、そげ、ばけ。」 「あれも、それも、ばけるよ。」 「あげだ」「そげだ」 八幡 ♥♥♥
VIDEO
柏野健次(かしのけんじ)先生 『英語教師のための語法ガイド』(大修館書店) 『英語教育』(大修館) 「Ⅰ 英語の通説を疑う」「Ⅱ 英語の変化に気づく」「Ⅲ 英語をもっとよく知る」 「一歩進んで」
現場の教師(高校・大学・予備校・塾)にぜひ読んでいただきたい、正しい知識を得るための必読書だと思います。例えば、as soon as possible, be willing to do , I’ll do my best, make it a rule to do , may well, be on good terms with, quite a few, So much for today, speak ill of, take place, with a view to doing , be senior to, cannot but do , keep early hours, much more, of itself, after all, compromise, satisfactory, promise + O + to do などの項目は、現場で誤解している先生方も多いと思われる語法ですので、ぜひ目を通しておいていただきたい項目です。
例を見てみましょう。
What time is it (now)? 今何時ですか。
「今何時ですか?」と尋ねる場合、now をつけずにWhat time is it ? と言うのが普通、という乱暴な参考書をよく見かけます。確かにそれはそうなんですが、ではnow を付けると誤りかというと、決してそうではありません。私の直観では、さっき聞いたけど時間をもう一度確認したい時、知人に「え、今何時になったの?」と聞き返す場面ではnowを付けても違和感はありません。一体どんな時にnow が許されるのかを、本書は簡潔に、それでいて的確に押さえています。かつて南出康世先生 (1)時間の経過を知るために連続して時間を聞く時、(2)何かの予定までの時間を確認する時、(3)時差がある場合に現地の時間を聞く時
公開されている著者の語法コラムもとても勉強になりますので、併せてぜひお読み下さい。 「ジーニアス 英語語法メモランダム」 コチラ です) 「英語語法Handy Tips~ネイティブスピーカーは語る」 コチラ です) 私も若い頃、故・竹林 滋先生 『ライトハウス英和辞典』(研究社) ボリンジャー博士(D.Bolinger)、イルソン博士(R. Ilson)、アルジオ博士(John Algeo) 「ボリンジャー博士の語法診断(1)~(12)」 『現代英語教育』(1990年4月号~1991年3月号,研究社) 「ライトハウスQ&A」 「チーム八ちゃん」 ♥♥♥
その昔、松江北高 「学問探究講座」 松江北高 「探究的学習」 「源氏物語を読む」「ビートルズを歌う」「楽器を弾く」「陶芸」「数学の定理を深掘り」等) (1)受験に関係ない、(2)早朝の保護者・生徒の負担が大きい 「英語のなぜ?」
普段は英語は大嫌いだけど、すごく楽しくて、この時だけは英語を好きになった。/話を聞いて英語っておもしろいなと初めて思った。/すごくタメになりました。/英語の授業では学べないようなことを教えていただきました。とても興味深い内容で、わからないことをはじめて知るワクワクを感じました。/とてもためになり楽しい講座だったので来年の1年生にも受けて欲しい。/とてもいい時間が過ごせました。もっと早い時期にこの授業を受けたいです。/とても有意義な3時間でした。来年の1年生のみでなく、時間が許すのなら2年生も行ってほしいと思います。/とてもためになった3日間だけにすごく残念です。英語が好きになりそうです。/自分の知らなかった英語の不思議をたくさん知ることができ、とても楽しく興味深かった。3日間では短すぎると思った。/普段の授業や勉強で聞くことができなかった興味深い話を知ることができ、これからの学習にも意欲がでた。2年次も実施して欲しい。 英語には、「~する人」 -er/ -or/ -ar/ -ee/ -ess/ -ian/ -ant/ -eer などです。「学問探究講座」 『ライトハウス英和辞典』(研究社、第7版) 「「人」の意を表す名詞グループ」 -er -ist 「-er」 「-ist」 接尾辞(suffix)
▲『ライトハウス英和辞典』(第7版)
🔹「-er」 動詞
📌 例:
動詞・名詞
+ -er
意味
teach
teacher 教える人(教師)
write
writer 書く人(作家)
run
runner 走る人(ランナー)
bake
baker パンを焼く人(パン屋)
これに対して、ラテン系の動詞 「-or」 actor, creator
🔹「-ist」 名詞
📌 例:
基本語
+ -ist
意味
art
artist 芸術家
piano
pianist ピアニスト
biology
biologist 生物学者
Marx
Marxist マルクス主義者
「-ee」 employee は「雇われている人=従業員」を示します。employer は「雇う人」です。ちなみに、-ee -er interviewee (インタビューを受ける人)とinterviewer (インタビューをする人)、examinee (審査を受ける人)とexaminer (審査員)などです。♥♥♥
【訃報】 米子東高校 進路指導部・数学科 河本高志先生(48歳)
日本のコンビニ セブンイレブン・ジャパン ローソン ファミリーマート 5万5千店 を超え、昨年の市場規模は百貨店業界の2倍以上の11兆円。中でもセブンイレブン 吉岡秀子『セブン-イレブンは日本をどう変えたのか』(双葉社、2016年)
セブン&アイ・ホールディングス 鈴木敏文(すずきとしふみ) セブン-イレブン 「小売の神様」 鈴木 セブン-イレブン 鈴木 鈴木 「私はいつも『お客様のために考えるのではなく、お客様の立場で考えろ 』と言ってきた」 コンビニエンスストア 「すでにたくさんの小売店や商店が潰れていっているじゃないか」 「こんな状況で小さな店をつくって、それが拡大していくなんてことはあり得ない」 セブン-イレブン 鈴木 セブン-イレブン セブン-イレブン セブン-イレブン セブン-イレブン 鈴木 セブン-イレブン セブン-イレブン サウスランド社(現・セブン‐イレブン・インク) 鈴木 セブン-イレブン・インク セブン-イレブン セブン-イレブン スタートしてからも、周りからは反対だらけでした。例えば、おにぎりを初めて売り出した時も、みんな最初は賛成してくれませんでした。「鈴木さん、おにぎりは家庭で作るものだから、売れませんよ」 「家庭で作るから安心して食べられるんだ」「誰がにぎったか分からないものなんて、食べられない」 「いや、そんなことはない」 鈴木 「お客さんの立場で考える」 鈴木 「自動レジ」 「無人コンビニ」 セブン-イレブン 「無人コンビニ」 「人と接したい」 鈴木 「お客様のために」 「お客様の立場」 「お客様がどう感じるか」 セブン-イレブン
■コンビニ大手3社の概要 セブンイレブン ファミリーマート ローソン チェーン店全売り上げ (2024年2月期) 1店舗当たりの1日 の売り上げ 国内店舗数(9月末) セブン-イレブン 松江市 セブン-イレブン 松江市 セブン-イレブン セブン-イレブン
1.美味しい商品が多い
セブン-イレブン 「セブンイレブンはPB(プライベート・ブランドのこと)の食べ物が美味しい・高品質」 セブン-イレブン セブン-イレブン 「セブンプレミアム」「セブンゴールド」 セブン-イレブン 「金シリーズ」
2.手軽さの中に「上質さ」を含める、という独自路線
一般的なコンビニのイメージと言えば「安くて、手軽」 セブン-イレブン 「上質で、手軽」 セブン-イレブン 「手軽なのに、上質」「上質さの中に、値段や買いやすさという手軽さが込められている」
3.店員への教育が行き届いている
セブン-イレブン セブン-イレブン 「接客ルール」
1. 品揃え (お客様の欲しい商品をそろえる)鮮度管理 (常に新鮮な商品をそろえる)クリンリネス (清潔で気持ちのいいお店にする)フレンドリーサービス (感じの良い接客をする)
セブン-イレブン 「OFC(オペレーションフィールドカウンセラー)」 セブン-イレブン セブン-イレブン セブン-イレブン スーパーバイザー会議
セブン-イレブン 「セブンカフェ」 「セブンカフェ」 「おいしく飲みやすい本格派コーヒー」 「セブンカフェ」 コチラ をお読み下さい 最近では最高級のブルーマウンテンブレンド セブン-イレブン
▲私の家の近所のセブンイレブン 便利!
セブン-イレブン セブン&アイ・ホールディングス(HD) セブン-イレブン 生鮮コーナー ファミリーマート 電子看板 アプリ ローソン 無人店舗 ♥♥♥
故・渡部昇一先生 上智大学 渡部先生
定職に就くことなく50歳を過ぎていた先生のお父様が、偶然の縁で就職することになりました。そのおかげで先生は大学を受験することができたのです。そんな先生が、大学一年生の夏休みで帰省したら、お父様が仕事をクビになっておられました。授業料一年分はすでに納めてありますから、寮にいる限りお金の問題はありませんでしたが、来年の分の見通しは全く立ちません。育英会 上智大学 特待生 特待生 上智大学 特待生 「絶対に一番にならなければならない!」
ところが一番になろうとすると、どうしても「点取り虫」 「全ての教科で100点を取ることだけを目的にすればよいのではないか?」
「全学科100点」 佐藤順太先生 上智大学 渡部先生 特待生 日本育英会 荘内育英会 克念社育英会 特待生 上智大学 「点取り虫」
動機は授業料を節約するという金銭的なものでしたが、自然科学の授業にも真剣に没頭しました。専門課程ではないにせよ、大学教養レベルの自然科学の諸科目の試験を受け正確に理解しているという保証を得たため、その後の人生においても、自然科学関係の話題にも興味を持ち続けることができました。教養課程の諸科目を「百点取り虫」 ♥♥♥
「2024年Bun2大賞」 「ベスト文具1位」 「ウカンムリクリップ」 コチラ )。サンスター文具 累計220万個 を突破したブッククリップ「ウカンムリクリップ」
▲米子「ロフト」の売り場
■機能的な「ウカンムリ」の形が特徴! 「ウカンムリ」 ■「ウカンムリ」の形だからストレスフリー ■時間のうつろいをイメージした4色が仲間入り
「ウカンムリクリップ」 モーニングソーダ、デイムーン、サンセットチーク、ナイトアメジスト
▲ウカンムリクリップ サンリオバージョン ロフトにて
そんな大人気「ウカンムリクリップ」 サンリオバージョン 米子天満屋4階 の 「ロフト」 サンリオキャラクターズ 「ハローキティ」 「シナモロール」(880円) 八幡
♥♥♥ ・勉強中、ノートや参考書を開いておくのに最適 ・本を見ながらのパソコン作業に最適 ・レシピ本や楽譜などにも最適
▲重鎮ポール・ゴードン
私はカード・マジック 「パケット・トリック」 パケット・トリック 「趣味」 hobby ですね⇒ コチラ に詳しく解説しています)の一つでもあります(他にもいろいろな趣味を持っていますが……)。マジック・ショップにお邪魔して、まず最初にお尋ねするのが、「何か目新しいパケット作品はありませんか?」 パケット・トリック 八幡家 「蔵」
お洒落で、それでいて意外性・ストーリー性のあるパケット・トリック 「THE EVOLUTION」 ポール・ゴードン(Paul Gordon) カード・シャーク社 Christian Schenk 「Metamorphosis」 ゴードン カード・シャーク社 ゴードン パケット・トリック ジョン・バノン(John Bannon) “card god” ポール・ゴードン(Paul Gordon) ゴードン 「THE EVOLUTION」
▲実にきれいな作りのカードです
4枚のカラフルなイモムシが描かれた、きれいなカードを観客に示します。その中の1枚を裏向き(赤裏 赤裏 「子どものイモムシが親ムシに習って、1匹ずつ眠りについたのだ」 「ここでイモムシが目を覚ますと・・・表は何だったか覚えていますか?」 「イモムシ!」 イモムシ 蝶々の絵 青・赤・黄・紫 「イモムシが見事に成長して、美しい蝶になったのです!! 」 赤い裏 蝶4匹 ジョーダン・カウント+エルムズレイ・カウント
使われるカードは、とっても格調高く、アーティスティックで古めかしいデザインのもので、実にきれいな仕上がりとなっています。ちょっとお値段は高いのですが、この滅茶苦茶きれいな作りのクラシック・カードと、観客の衝撃度(今までに私が披露した人たちは、みんなクライマックスのあまりの鮮やかさに、ビックリ仰天でした)を思えば代金は安いものです。私はいっぺんで気に入りました。ゴードン エルムズレイ・カウント アンダー・エルムズレイ・カウント 米子 “Practice makes perfect.” ですね。♠♣♥♦
VIDEO
▲ポール・ゴードンの原案のカード
実は、上の作品には、その下地となった作品があります。1998年に、故・ニック・トロスト(Nick Trost) アルド・コロンビニ(Aldo Colombini) カード・マジック ポール・ゴードン(Paul Gordon) パケット・トリック 「Aurora Borealis」(オーロラ・ボロリアレス) 「眼力の確かさ」
「これは素晴らしい。ポールの作品のうちで最高のものの一つで、これからも使い続けるだろう」(ニック・トロスト) 「ポール、これはただただ、素晴らしい。非常に巧妙だ。使える。常にこれを使うつもりだ」(アルド・コロンビニ) その昔、2001年に、数量限定で販売されましたが、すぐに売り切れてしまいました。カードの特性からか、再販されることはありませんでした。それが20年の歳月を経て、カードの品質を上げて再販が可能となりました!ポール・ゴードン バイシクル タリホー ゴードン パケット・トリック 米子 ゴードン 「The Great Houdini Escape」「Smack In The Face Royal Flush」「JEEPERS CREEPERS」
スペードのエース 裏返って (黒色に)いきます。4枚とも黒色に裏返ってしまいました。続いて、今度は1枚を裏返して表向きにすると、2枚目以降のエースが全部表向き に変化してしまいます。ここで観客の観察力を確認するために(ゴードン “ observation test”(観察テスト) ラフ&スムーズ(r/s) 加工 ポール・ゴードン 「オーロラ・ボロリアレス」 アンダー・エルムズレイカウント、エルムズレイカウント、ダブルリフト ピンク裏 VIDEO 【後日談】 昨年、 勝田ケ丘志学館 「THE EVOLUTION」 「オーロラ・ボロリアレス」 パケット・ケース ポール・ゴードン 「これは困ったぞ!!」 。 もしかしたら電車の中で、他の書類を引っ張り出す際にこぼれ落ちたのかもしれないと思い、ダメ元で「JR西日本落とし物センター」 出雲駅 出雲警察署(会計課) パケット・トリック 【後後日談】 またやってしまいました! 年末にこのカードを買い物袋にいれて、古志原 「かつや」「松江市立図書館」「まるごう」 ♥♥♥
▲専用の辞書と併用すると効果的
「英語の勉強の8割までは単語の勉強」 「Scrabble Flash」
これは全米の小学校などで単語学習教材として使われていたもので、「ゲーム・オブ・ザ・イヤー」(Game of the Year) 約1分間の制限時間 に何個単語が作れるかを競うのです。制限時間終了後は、自分の正解数(スコア)と、そのアルファベットから作ることができた英単語の最大可能組み合わせ数が画面に表示されます(最初のうちはそのあまりの多さにショックを受けます〔笑〕)。私は現職教員時代には、ESS部 Scrabble
(株) タカラトミー 「ボグルフラッシュ」(Boggle Flash) PANTS とか ANT とか複数形のANTS とか NAP とかPAN とかTAN といった英単語を思いつく限り作っていくことになります。ここで「語彙力」 タカラトミー 「グローバル化が進行する社会背景を踏まえ た 製品」 「これはいい!使える!」 勝田ケ丘志学館 このデジタル玩具は、1人~複数人で遊べる3通りの使い方ができるようになっています。
①ゲーム1 ボグル 3~5文字の単語を作る最も一般的な遊び方です。制限時間内で3,4,5文字の単語をできるだけ多く見つけるというルールです。各ブロックのディスプレイに文字が表示されるので、ブロックをすばやく並べ替えて単語を作っていきます。正しい英単語を作るとピッと音がしてブロックが光ります。1度作った単語をもう1回作っても反応はありません。制限時間は説明書には記載されていませんが、実測で約1分15秒。なお、5文字で単語を作ると、ボーナスタイムとして制限時間に5秒が追加されます。 制限時間が近づくとピーッという警告音が鳴り始めて、時計マークが表示されるとゲーム終了です。再び最初のように横一列に5個並べると、自分が今作った単語の数と、提示されたアルファベットの組み合わせで最大いくつの単語を作成可能だったのかが表示されるのです。
②ゲーム2 ボグル5 5文字の単語を見つけるゲームです。上級編と言えるでしょう。表示されたブロックの文字を使って5文字の単語を作るとクリアとなり、次の新しい5文字のお題が表示されます。制限時間が来るまでにできるだけ多くの単語を完成するゲームです。
③ゲーム3 ボグルパス 複数人で遊べる対戦型のゲームで、制限時間にできなければ脱落していきます。瞬時の判断で勝ち残れるかどうかを試すゲームで盛り上がります。ブロックに表示された5文字を使って順番に単語を作っていき、制限時間内に単語を作れなかった人は脱落していきます。最後まで残った人が勝者です。1人のプレーヤーが単語を作るのに成功すると「NEXT」 の文字が表示されるので、次のプレイヤーにブロックを渡します。制限時間に作れなかった場合は「OUT」 と表示されて、その文字でできる正しい単語が表示されます。
「ボグル」 「ボグルパス」 このゲームの魅力は、英単語の語彙力が高ければ高いほど楽しめそうだということ。中途半端な語彙力だといまひとつスコアが伸びないので、好成績を残すにはもっと英単語学習に励む必要があります。そういう意味では英語学習のモチベーションを高めるのに有効な電子玩具だと思います。逆に言うと、知っている単語が少ない場合、例えば英語を習いたての幼児などに与えても、あまり楽しめないかもしれません。
当時は海外仕様のままで売られていたんですが、日本バージョンとして、高等学校で出てくる英単語に限定するとか、MAXの語数 を示すだけでなく、その解答 をも併せて表示するとか、単語の意味(日本語) まで確認するとか、プレーヤーのレベルに応じて制限時間をもうちょっと長く設定するように複数選択できるようにするとか、さらなる工夫の余地はあったと思いました。♥♥♥
VIDEO
言語研究者の中村明裕(なかむらあきひろ) 「頭が赤い魚を食べる猫 「頭が赤い魚を食べる猫」 多義的フレーズ 中村
ここから5パターンの「頭が赤い魚を食べる猫」
①頭が赤い、魚を食べる猫 ②頭が赤い魚を、食べる猫 ③頭が、赤い魚を食べる、猫 ④頭が、赤い魚を食べる猫 ⑤頭が、赤い、魚を食べる猫
私などは真っ先に① 番 「頭が赤い魚を食べた猫」の絵 であることは確かです。
多義文 文節同士の関係が複数パターン取れてしまう 。 「頭が赤い魚を食べる猫」 「頭が/赤い/魚を/食べる/猫」
頭は何の頭?
赤いのは何?
などなど、いろんな解釈ができてしまいます。でも今回の文章に関しては、多義になるべくして作られた文章ですので、その多義っぷりを精一杯楽しめばよいのです。「頭が/赤い/魚を/食べる/猫」
*******************
私は英語教師が仕事ですから、英語の有名なことわざ・Time flies like an arrow.(光陰矢のごとし) 「時の経つのは早いもので、イタリアに留学してから3年になります」(名古屋大学) Time flies. Time flies like an arrow. cf. Steven Pinker
【第1の解釈】 【第2の解釈】 ※likeをasの意味にとる。arrowの後にはtimes fliesが省略されている timeは動詞で「タイムを取る」 【第3の解釈】 ハエのタイムを取れ ※likeをas(~ように)の意味にとる。you time(あなたがタイムを取る)が省略されている 【第4の解釈】 【第5の解釈】 ※timeをfliesを修飾する名詞と解釈して「時・バエ」(そんなハエがいるかどうかは知らないが?) 【第6の解釈】 Time flies like an arrow. 『タイム』という雑誌は矢のように(=直線的に)飛んでいく ※著名な週刊誌『タイム』と解釈して固有名詞のように考える。 現実には【第1の解釈】 2~6の解釈 ♥♥♥
昨日の京都大学
But they were overtaken by a second, slower fall from the cloud ― a rain of suffocating ashes that piled up to a height of six to nine feet. Like a palpable fog or a quicksand, it trapped and enveloped people in their houses and even those fleeing in the streets. Their bodies were encased in ash as in a mold, and these casts of hardened ash are today the most moving evidences of the tragedy of Pompeii. By pouring liquid plaster into the now hollow molds, we can re-create the shape of the body, the form of the clothing, the footgear, even the last exhalation of men and women who lived and died in that ancient city.
訳文:ところがその雲からもう一つ別のもっとゆっくり落下したものが襲いかかった-窒息させる灰の雨であり,6~9フィートも積もった。手に触れることのできる霧とか流砂のようで,家の中の人や街路を逃げて行く人さえ,灰の雨は捕らえて包み込んだ。彼らの体は鋳型にはめたように灰の中に包まれ,灰が固まってできた鋳型は,今日ではポンペイの悲劇を表す最も哀れを感じさせる形跡である。今は空洞になったこの鋳型の中に液体状の石こうを流し込むと,体の形も衣服や履物の形も,この古代の町で生きて死んだ男女の最後の息づかいまでも再現することができる 。
この下線部分が分かるでしょうか?なんとなく分かる気はするのですが、衣服や最後の息遣いまでも復元できるという部分は、いまいち理解に悩みます。
ポンペイの悲劇は、ヴェスヴィオ山の噴火によって大量の火山灰と軽石が街全体を瞬時に覆い尽くしたことで起こりました。この英文にあるように遺体が火山灰に埋もれ、硬化した火山灰が型(mold)の役割を果たしました。このメカニズムは以下の通りです。
1.遺体と火山灰の固化 2. 遺体の分解 3.空洞の形成 4. 石膏による復元 ♥♥♥
やれコミュニケーション活動だ、ICT教育だ、探求的学習だ、という昨今の英語教育の流れで、いわゆる「訳読」 「化石だ」「前時代的だ」「日本語を介さずに英語を理解させないとダメだ」 「それを自分の言葉でどういうことか説明してごらん」 「何を言っているか分からない」 「訳せる」 「意味が説明できない」 「意味が分かっていない」 「キチンと読む」 山本史郎・森田修『英語力を鍛えたいなら、あえて訳す!』(アスク、2024年10月)
▲この本ぜひオススメです!
辞書 「学校英文法の基礎知識」+「英和辞典」 「英語の意味」 「訳すことはできる」 「意味を説明できない」 「意味が分かっていない」 Asahi Weekly 山本史郎先生(東京大学名誉教授) 「英文読解それってどんな意味?」
お盆明けの今日の授業は、京都大学1995年
Pliny the Younger (whose uncle, Pliny the Elder, was nearby and was among those killed) vividly described the eruption: it looked like *an Italian umbrella pine ― a tall “trunk” spreading out at the top to a dense cloud shot with flashes of lightning. 噴煙はイタリアカラカサマツのように見えた。-その背の高い『幹』がその頂上のところで稲妻のせん光を放つ厚い雲に向かって広がった 。)
一応これで生徒の訳文は成立です。でも何を言っているのかさっぱりわかりません。授業の中でダッシュ(――) 「イタリアカラカサマツのように見えた。」 「その背の高い『幹』がその頂上のところで稲妻のせん光を放つ厚い雲に向かって広がった。」 「イタリアカラカサマツ」 「イタリアカラカサマツ(Italian umbrella pine)」 それはまるでイタリアカラカサマツのように見えた ― 背の高い「幹」が上の方で広がっていて、濃い雲のような部分に稲妻の閃光が走っているようだった。
「イタリアカラカサマツ」
“a tall ‘trunk’ spreading out at the top to a dense cloud shot with flashes of lightning”
この描写は、たとえば次のような場面を想像させます:空に高く伸びた何か(噴煙)があり、それが頂上付近で横に広がり、まるでイタリアカラカサマツ イタリアカラカサマツ
幹(trunk)=柱状の何か=噴煙 ※比喩で“木の幹”と引用符でくくっている
広がった上部(dense cloud)=雲のように見える噴煙
稲妻(flashes of lightning)=光の走る様子=幹から派生した小枝
この文は、「空に高く伸びて上で広がる形状」を「イタリアカラカサマツ」 イタリアカラカサマツ 勝田ケ丘志学館 ♥♥♥
『報恩感謝』 「報恩感謝」 『知恩(ちおん)』・『感恩(かんおん)』・『報恩(ほうおん)』
まず、「知恩」 「感恩」 「報恩」 「知恩」 「感恩」 「感恩」 「報恩」
故・松下幸之助 「感謝の心のないところからは、決して幸福は生まれてこない。また、感謝の心が高まれば高まるほどに、それに比例して幸福感も高まっていく」
「感謝」
幸福感が高まる
ポジティブに考えられるようになる。
対人関係がよくなる。
体調が良くなる。
などが挙げられます。
私は神様の恩に報いて感謝することにしています。長く生きてきて、人智を超えたものがあると感じているからです。たくさんの不思議な出来事を経験してきました。自分が神様に守られていると実感します(昨年横断歩道を電動自転車で渡っている時に自動車にぶつけられましたが、かすり傷一つありませんでした)。もう50年以上も岡山最上稲荷奥之院 「今朝も目が覚めました。ありがとうございます」「今日も一日無事に過ごすことができましたありがとうございます」
右脚股関節 「共通テスト」 日赤 「共通テスト」 「共通テスト」 松江 北高補習科 勝田ケ丘志学館 山口整形外科 数年前󠄂、日赤 「この病院には高校時代先生にお世話になったという人達がいっぱいいます。これからも元気で教育に励んでください」 ♥♥♥
長い間JRに乗っていますが、今日松江駅 キハ47 ライト 米子駅 「サンライズ出雲」 ライト 境線 鬼太郎列車 ライト 「国の規約で昼も夜も前も後も点けることに決まっています」 博労町駅
ライト 「列車標識」 ライト ライト ライ ライト 「 列車標識」 「列車標識を表示すること」 ライト ライト 「列車標識の表示」 ライト ライト ライト 前部標識=白 後部標識=赤
なお、列車標識は前・後の両方に表示しなければいけません。列車の前 = 進行方向最前部には「前部標識」 「後部標識」
鉄道運転規則第6章鉄道信号第4節第233条で書かれていますが、昼間は省略できるとされており、実際省略もされていました。では、なぜ昼間も点灯するようになったかと言うと、「事故防止」
『乗ってるだけじゃわからない鉄道の大疑問』(青春文庫、2025年) 新幹線 ♥♥♥
入学者数が定員に届かない「定員割れ」の私立大 53.2% で、昨年度より6.0ポイント低くなりました。18歳人口が2.7万人増えたほか、制度改正で国の給付型奨学金などの対象も広がり、4年制大学を目指す人が増えた可能性があります。改善は5年ぶりですが、依然として多くの大学が定員を満たしていない状況は変わりません。学生募集をやめた大学もあり、入学定員は昨年度より1,114人少ない50万2,755人。一方、入学者数は1万6,107人多い51万839人でした。
定員に対する入学者数の割合を示す入学定員充足率も、私大全体では2年連続で100%を割っていましたが、今年度は101.61%でした。しかし、定員を満たしたのは大都市周辺の大規模大学が多く、地方の小規模大学を中心に状況はなお厳しいものがあります。三大都市圏(東京・大阪・愛知
私立大学の志願者数で今年は大きな動きがありました。今春、全国で最も志願者数が多かった大学は、千葉県習志野市 千葉工業大学 近畿大学 「受験生ファースト」 千葉工業大学 「興味のある学科は、全て判定してあげたかった」 「合格の可能性が高まる」 近畿大学 「近大マグロ」
私は週に3日利用しているJR松江駅 広島修道大学 「ここから 約170km先 冒険の入り口」 広島修道大学 松江南高校 広島大学 広島修道大学 八幡 広島修道大学 安田女子大学 「大学がコマーシャルをやるようになったら危険信号」 八幡 安田女子大学 広島修道大学 ♥♥♥
渡部昇一先生 『続 知的生活の方法』(講談社現代新書、昭和54年) 『知的生活の方法 「卒業論文の失敗談」 ラフカディオ・ハーン(小泉八雲) 八雲 ハーン ハーン ハーン 「締切り」 「はた!」 と気がついたのです。第一章を書いたとたんに、新しく調べたり、チェックしなければならないことが、突如として具体的に、緊急な形で続々と出てきたのです。それを果たすと必然的に次が決まってきます。メモをとっていた時は素晴らしいと思われたアイデアも、使いものにならないということがよくありました。これに反して書きながら思いついたアイデアは、チェックしてすぐ仕事に組みこんでゆくことができました。こんなことをしているうちに、論文は締切りに間に合わなかったばかりでなく、反復が多く、論旨も首尾一貫せず、きわめて不満足なものに終わってしまいました。現在の制度ならおそらく卒業できなかったはずですが、当時はまだのんきな時代で、論文提出も大学の事務局ではなく、指導教授に直接出せばよかったのです。先生の指導教授の刈田先生 この経験を通して先生が学ばれたことは、「まず書き始めることが大切!」 「卒業論文の失敗」
自らに恥じるところのあった先生は、卒論の反省を生かし、大学院の修士論文(修論)
つまり、何の目的意識もなく漫然と雑多なものを読むだけでは、結局はうたかたのように消えてしまって、自分の中に積み重なっていくものは何ひとつない、ということになりかねないのです。やがて、果たして自分が何を読んできたかさえ、定かではなくなってしまいかねないのです。
そんな経験から、先生は卒論や修論の指導にあたって、よく学生たちにこう言われました。「ある程度調べたら、ともかく書き始めたほうがよいですよ。調べるのはいくら調べても論文になるわけではない」 カールー・ヒルティ 「仕事をする術」 「本を書くならまず第一行を書け。準備ばかりしていると、いつになっても出来上がらないぞ」 「本当にそうだ!」 ♥♥♥
まず何よりも肝心なのは、思いきってやり始めることである。仕事の机にすわって、心を仕事に向けるという決心が、結局一番難しいことなのだ。一度ペンをとって最初の一線を引くか、あるいは鍬を握って一打ちするかすれば、それでもう事柄はずっと容易になっているのである。ところが、ある人たちは、始めるのにいつも何かが足りなくて、ただ準備ばかりして(そのうしろには彼等の怠惰が隠れているのだが)、なかなか仕事にかからない。そしていよいよ必要に迫られると、今度は時間の不足から焦燥感におちいり、精神だけでなく、ときには肉体的にさえ発熱して、それがまた仕事の妨げになるのである。 また他の人たちは、特別な感興のわくのを待つが、しかし感興は、仕事に伴って、またその最中に、最もわきやすいものなのだ。仕事は、それをやっているうちに、まえもって考えたのとは違ったものになってくるのが普通であり、また休息している時には、働いている最中のように充実した、ときにはまったく種類の違った着想を得るということはない。これは(少なくとも著者によっては)一つの経験的事実である。だから、大切なのは、事をのばさないこと、また、からだの調子や、気の向かないことなどをすぐに口実にしたりせずに、毎日一定の適当な時間を仕事にささげることである。……よく働くには、元気と感興とがなくなったら、それ以上しいて働き続けないことが大切である。もっとも、最初はあまり感興がわかなくても始めねばならぬ。 (ヒルティ『幸福論・第一部』)
英語の勉強の8割 までは「単語の勉強」 八幡 竹岡広信先生 『LEAP』新版(数研出版) 山本和夫先生 「アタマ+オナカ+シッポ」 establish(設立する)――establishment(設立)
e- は「外に」という接頭辞 st- は「立つ」という意味の語幹 abl はable (できる)の意味の接尾辞 -ish は動詞を作る時の接尾辞 -ment は動詞につけて名詞を作る接尾辞 establishment 「外に+立つ+できる+~する+こと→外に立つことができるようにすること」 「設立」 「ナルホド!」
◎e/ex- 「外に」《頻出》 emotion(感情)
◎st- 「立つ」 stand(立っている)
◎able 「できる」 ability(能力)
◎-ish 動詞語尾 astonish (驚かせる)ish (達成する)ish (終える)ish (出版する)ish (与える)ish (減じる)ish (栄養を与える)ish (磨く)ish (罰する)ish (消える)sh (押す)sh (急ぐ)
◎-ment 名詞語尾(動詞に付けて)《頻出》 government (政府)ment (達成)ment (行動)ment (議論)ment (楽しみ)ment (興奮)ment (合意)ment (約束)ment (娯楽)ment (発達)ment (雇用)
このような勉強に役立つものとして、八幡 ♥♥♥
●すずきひろし『語源×語感×イメージでごっそり覚える英単語事典』(ベレ出版、2025年) ●清水建二『英単語の語源図鑑』(かんき出版、2018年) ●竹岡広信『必携英語LEAP 改訂版』(数研出版、2024年) ●『ライトハウス英和辞典』(第7版、研究社、2023年)の「単語のキズナ」欄
▲先般の米子東高校での講演資料より
今年の巨人 巨人 「基本のキ」
失策数 犠打数 盗塁数
1位 阪神 45 113 84
2位 巨人 62 71 43
8月17日(日)の阪神戦 丸 巨人 岸田 才木 大城卓 巨人 増田大 田中将大 門脇 田中 キャベッジ 巨人軍 落合選手 巨人 長嶋茂雄監督 「地獄の伊東キャンプ」
「ミスしたら負け」 「共通テスト 」 「自己採点」 「自己採点」 82% もあります。模試会社の公表によれば85% とも言われています。ですから少々自己採点が間違っていても、「みんなで渡れば怖くない」実態があるので、合格していきます。でもよ~く合否結果分析を見てみると、自己採点が10点以上間違っている生徒は、まず難関大学には不合格になっています。ひどいのになると数十点も違います。笑ってしまったのは、数年前に浪人して北高補習科にやってきた生徒の成績開示を見ると、自己採点と117点(!) も違っていました。しかも地方の公立大学に合格してきていました〔笑〕。成績が悪いことよりも、自己採点がデタラメなことの方が問題ですが、もっと問題なのは、それをきちんと理解してミスをなくす努力をきちんとしている生徒が非常に少ない、という点です。なんとなく済ませてしまっています。担任も「きちんとしなさい!」 とは言うけれど、それ以上の手立てを講じようとはしません。その大切さに無関心なんです。私が松江北高 「ABC」(当 たり前のことをバ カになってち ゃんとやる) では、なぜ「自己採点ミス」
(1)問題を解く際に、自分の解答をきちんと問題用紙に転写していない。問題番号をずらしてしまう。不鮮明でどれにマークしたのかが読めない。消しゴムできちんと消していない。その結果、自己採点当日に自分の答案が再現できなくなる。 (2)問題用紙の解答を「自己採点用紙」に転記する際に写し間違える。もう1回点検することで防げるミス。 (3)正解と自分の解答を照合する際にうっかり○×を間違える。もう1回点検することで防げるミス。 (4)得点を小計、合計する際に暗算でやって間違える。丁寧に電卓を使って、2回計算することで正確に合計できる。自己採点当日、電卓を忘れ手計算でいい加減にやっている生徒も目につく。 (5)解答用紙にマークする際に、決められたようにマークしていないので(形、濃さ、消し忘れ)機械が読み取れない。練習の時から注意が必要。 これらはもう一度見直す(「 検算 」 「自己採点」 9,504人 です。長文問題1問6点違うと、28,621人 です。どうです?馬鹿にならないことが一目瞭然でしょう?たった1問でこれだけ順位が異なってくるのです。模試の判定でも、自己採点がデタラメ状態では、デタラメな志望校判定結果しか返って来ません。ましてやこれが本番となると…?この恐ろしさを生徒にきちんと伝えて、毎回追跡をかけて、限りなく自己採点ミスを0点に近づけていく努力を怠ってはなりません。現場では「忙しい」と称して、こうした努力を行っていない学校が数多くあります。私には本末転倒の「言い訳」としか思えません。生徒の「自己採点」 教員が「忙しい」 「ここできちんとやっておけば後で楽ができるのに。結局、後で苦労することになるのになあ…」 「負けに不思議の負けなし」 「自己採点」 「自己採点」
二次試験 「ミスしたら負け」 ♠♠♠
私はあの「ななつ星」 水戸岡鋭治(みとおかえいじ)先生 JR九州 JR九州名誉顧問 唐池恒二(からいけこうじ) 月刊『致知』 唐池 リーダー 三つの力 が必要だとおっしゃっておられました。一つは「夢見る力」 「気を満ち溢れさせる力」 「伝える力」 リーダー
唐池 ソフトバンクグループ 孫正義(そんまさよし) 孫 ソフトバンク 福岡 「五年後には百億円、十年後には五百億円、三十年後には一兆円にする」 孫 孫 「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、夢無き者に成功なし」(吉田松陰) 「気」が溢れているかどうか だと気づきました。7年間JRの外食事業に携わった唐池 月刊 『致知』 ①夢見る力、② スピードあるきびきびした動き、③明るく元気な声、④隙を見せない緊張感、⑤貪欲さ その三。その夢や自分の考えをいかに社員に伝えるか。これがとても重要です。よく口にされるのが、「伝えても伝わらなければ伝えたとは言わない」
唐池 一、夢見る力 二、気を満ち溢れさせる力 三、伝える力 「ななつ星」 『コンデナスト・トラベラー』
夢に向かって、気を満ち溢れさせるところから、閃(ひらめ)きも生まれます。閃きというのは何もないところからは絶対に生まれません。そのことについて毎日ずっと考え抜いているうちに、頭の中にアイデアの鉱脈のようなものができ、それが何かの拍子にポッと外に出てくるんです。唐池 D&S列車 「ななつ星」「ゆふいんの森」「あそボーイ」「いさぶろうしんぺい」「指宿の玉手箱」「或る列車」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週は麻婆豆腐 「みなみ」 「爸爸厨房」(パパちゅうぼう) 「麻婆豆腐」 米子 「麻婆豆腐」 「担々麺」 「麻婆豆腐ランチ」 麻婆豆腐 「虎楼」(ころう) 麻婆豆腐 爸爸厨房 麻婆豆腐 麻婆豆腐
このところ毎日真夏日が続いています。今年は猛暑です。松江 「真夏日」 dog days
We’re in the dog days
このように「dog days」 「夏の一番暑い時期」(7月下旬~8月中旬)
1.シリウス(Sirius)という星が関係している シリウス(Sirius) シリウス 「犬の星(Dog Star)」 2.シリウスの「太陽との同時出現」が暑さの象徴だった 古代ギリシャ人やローマ人は、夏の最も暑い時期に、the Dog Star シリウス 「犬の星の時期(Dies Caniculares)」 「dog days」 シリウス 「dog days」=「犬の星(シリウス)が太陽と共に昇る時期」=「1年で最も暑く、だるく、活動するのがしんどい夏の時期」 ということです。
dog days 「めざましテレビ」 林佑香 「あまゆかイングリッシュ」 dog days ♥♥♥
さだまさしさん(73歳) が、被爆80年の8月6日、19年ぶりの平和の大切さを訴える無料コンサート「夏 長崎から2025」 稲佐山公園野外ステージ 「自由に音楽ができる場所が無数にあることが平和の1つの象徴」 「広島原爆忌の晩、長崎から広島へ歌おう」 さだまさし 長崎市 市営松山ラグビー・サッカー場 「夏 長崎から さだまさし」 「広島原爆の日に、長崎から広島に向かって歌う。それだけで伝わる人には伝わる」 さだ 「夏 長崎から」 「このコンサートが終わるまでの間に、ほんの僅かな時間でよいから、あなたの一番大切な人の笑顔を思い浮かべて欲しい。そうしてその笑顔を護るために自分に何ができるだろうか、ということを考えて欲しい。実はそれが平和へのあなた自身の第一歩なのです。」 入場料無料 で始めたのです(当時彼は莫大な借金の返済に苦しんでいました)。それは、広島原爆忌 長崎 「平和を願う場所」 「無料でやる」 「売名行為」「ただとは何か別の意図があるのではないか?」「長崎県知事になるための事前運動だろう」「いや長崎市長を狙っているらしいぞ」 「中途半端」「趣旨が曖昧」 「長江」 さだ さだ さだ 「広島の夜」 長崎 「長崎の夏の風物詩」 稲佐山公園野外ステージ パナソニック さだ さだ 「夏 長崎から」 さだ
最も借金していた頃に始めた思いはあれから20年を経て変化していないか?風化していないか?
心の熱は下がっていないか?これが本当に必要なのか?
お客さんはどうなのか?これが本当に必要なのか?
20年間訴えてきた平和への思いは伝わっているのか?あるいは無駄だったのか?
子どもでも成人すれば(20年)親の手を離れてもいいのではないか?
自分が永遠に続けられるものでもないだろう?
これらを自分でもう一度客観的に見つめ直すために、一度現場を離れてみようという決意でした。長崎県 さだ 稲佐山 さだ 「夏の風物詩」 長崎
あれから19年が経ち、被爆80年の節目を迎える今年、「音楽は平和の象徴」 さだ 長崎 「被爆80年 長崎メディア共同プロジェクト」 「大量兵器でたくさんの人を殺すという戦争状況だけは僕は認めたくない。 (Q.被爆80年をどう捉えるか?) これは戦争の名残ですから、戦争が終わったということが一番大事な事。次に、原子爆弾は戦争を終えるために使ったとアメリカの人たちは昔言っていたけどそれは正しくないと僕は思っている。どうあっても一般人を大量に人の命を奪うというのはいくら戦争でも許してはいけない。だからこれ長崎が最後でありますように」 「夏 長崎から2025」 「希望を持ってあしたの長崎を、あしたの日本を、未来の長崎を、未来の日本を良くするためには、一人ひとりが自分の周りの人を大事にすることから始めないと」 「核が安上がり」などと、核武装を肯定するような意見を述べる国会議員の存在を「時代の怖さだ」 「戦争の果てに原爆が落ちたという事実がこの街にある。伝え続けていかないと」 「歌に大した力はない」 「でも人の心という碁盤に1個、石を打つことはできる。一人でも二人でも、届く人に届けていく」
広島 長崎 「今年で戦後80年、被爆80年という大きな節目ということに背中を押されて、あとで後悔してもいけないと思って、今年は強引にやる決意をしました」 さだ 今井美樹(62歳)、南こうせつ(76歳)、笑福亭鶴瓶(73歳)、立川談春(59歳) 長崎・稲佐山 さだ 「長崎小夜曲(ナガサキ・シティ・セレナーデ)」 長崎 広島 さだ 「いま、あなたの大切な人の笑顔を思い浮かべてみてください。そして、その笑顔を守るために何ができるかを考えてみてください」 「そして、自分が何をなすべきかが分かったら、そこへ向かって歩きだそうじゃないですか」
これまで、村下孝蔵、来生たかお、松山千春、谷村新司、都はるみ、小田和正、財津和夫、泉谷しげる、加山雄三、岩崎宏美、南こうせつ、小林幸子、平原綾香、スターダストレビュー 「フェスの元祖」 さだ 今井美樹 「PIECE OF MY WISH」 「いつも、遠くから祈る気持ちは持っていましたが、参加できたことで、ここにいられる意味を強く感じています」 さだ 「戦争が起きたら音楽が止められ、人が集まることが止められる。平和とは、どんな音楽でも自由に演奏できる、音楽会を開けること。最初の頃にコンサートに来た子供がお父さんお母さんになっている。その人たちが子供を連れてきょうここに来てくれた。バトンタッチの場になればいい」 とさだ 「僕は今年73歳。何処まで走ることが出来るか分かりませんが、精一杯走ろうと思っています」
▲翌8月7日「サンケイスポーツ」だけが大きく取り上げる!
平和を実らせる希望の種とその育て方を届けてきたさだ さだ 「今回が最後という気持ちで、恥ずかしくないステージにしよう。でもやはり最後という言葉は好きじゃないですね。だから被爆90年、10年後に元気で会いましょう!」 「またいつ会えるか分からないけど、最後というのが嫌なので約束をします。被爆90年の年にお互い元気で会いましょう!」 「夏 長崎から」 長崎県知事・ 大石賢吾氏 長崎市長・ 鈴木史郎氏 さだ 長崎 「これだけ気温が変化しているでしょ。今までの経験が通用しなくなった」 「ハピネスアリーナ」
なおこのコンサートの模様は、NHKBSで、8月23日(土)21:00~22:29で、BS4Kでは、9月13日(土)19:30~20:59に放送されます。♥♥♥
▲ラストは出場者全員で「祈り」を熱唱し大団円で閉幕
受験にも必須のイディオムtake ~ for granted 「~を当然のことと思う」 took it for granted that took for granted
Don’t take for granted
I took for granted
Don’t take for granted
「与えられて当然と思っている」という意味合いで、本人にその意識があるかどうか、自覚があるかどうかは別として、人だったら「そばにいて当たり前な人」「そばにずっといる人」、物ならば「あって当然」「あるのが普通なもの」という感覚です。
We take it for granted that
これらを全て含んだニュアンスです。このような文章をよく読んでみると、日本語の「当たり前のこと」だけでは意味を捉えきれていないのではないかと思えてきます。たいていは、“But that’s not true. So you should appreciate your family .” 「しかし、それはそうではない。だから家族に感謝するべきだ」などと上記のフレーズに続いたりします。take for granted それを当然だと思ってはいけない、そのことや物に感謝するべきだ 、という話の時によく使われるフレーズなのです。もしくは、自分は気付いているから感謝している、という時に使います。要するに「当たり前だと思っていて、感謝の気持が足りないぞ」 「当たり前」 「感謝」 MWALED ]
Don’t take for granted
She takes for granted.
We take it for granted that
もう一つの take for granted
She took it for granted that
They took it for granted that
He took it for granted that
日本語の「当然」「当たり前」
Don’t take for granted
アン・クレシーニ先生(北九州市立大学) 『なぜ日本人はupsetを必ず誤訳するのか』(アルク、2023年9月) クレシーニ先生
▲この本八幡のオススメ!
I realized during the COVID-19 pandemic that I had been taking for granted.
Don’t take for granted.
『ライトハウス英和辞典』(第7版) 「(慣れっこになって)(人・物事)の真価がわからなくなる,特に気にかける[ありがたい]ことでもないと思う:He takes his wife for granted . 彼は妻のことを気にもとめなくなっている」 ❤❤❤
横浜 長崎 「日本三大中華街」 神戸 「南京町」 中国 台湾 神戸 「南京町」 神戸 南京町 神戸
メインの道路の間を何本もの路地が通る南京町 「九龍街」
実はこちらは市民トイレの「臥龍殿」(がりょうでん) 諸葛孔明(しょかつこうめい) 「臥龍先生」 「臥龍殿」 陳舜臣 内装もまた中国風の装飾 が施されており、まるで異国に来たような気分 になります。多くの観光客が利用しているにも関わらず常に清潔 に保たれており、気持ちよく利用できます。左右に配された龍の彫刻は外国から取り寄せられたもの です。南京町
観光用の地図には簡単に「市民トイレ」と表示されているのですが、ここを作ったのは「南京町商店街振興組合」 南京町広場 「長安門」 「西安門」 南京町 南京町
地上三階建てのこの建物は「神戸景観・ポイント特別賞」 春節祭 台湾 「ここまでやるか!」
1階中央の展示室には「春節祭」 「平成5年度日本グッドトイレ10」 「臥龍殿」 神戸市 「景観ポイント賞」 「臥龍殿」 ♥♥♥
瀬戸内海に浮かぶ人口約3千人の島、直島 宮浦港 藤本壮介さん(ふじもとそうすけ、45歳) 「直島パヴィリオン」 直島町 「28番目の島」 「気軽に人が集まって、話をしたり、読書をしたり。そんな場所を作りたかった」 藤本 「見慣れた空や山、そして人が、作品を通して全く違って見える。そんな体験も楽しんでほしい」
直島町 番目の島 というコンセプトで2015年に作られたのが「直島パヴィリオン」 で「直島町制施行60周年」 『直島“パヴィリオン”』 「浮島現象」 「浮島現象」 多島美たとうび を誇る瀬戸内海でもしばしば見られる現象 です。直島
「直島パヴィリオン」 中に入ることもでき、 天気がいい日には上の写真のように作品越しの青空を撮れば映えますよ。作品自体はステンレス製のメッシュで作られていますが、かなり丈夫なので、少し高くなっている部分に乗っかっても不安定さは全くありません。中は結構広いので、グループで入っても問題なく楽しめると思います。高低差もあるので、写真を撮るにはむしろちょうどいいかもしれませんね。夜にはライトアップ されるのでまた雰囲気が一変しますよ。どこか宇宙船に乗っているかのような不思議な感覚も味わえます。 「直島パヴィリオン」 宮浦港 宮浦港 草間彌生 「赤かぼちゃ」 「I♡湯」 宮浦港 直島 無料 で見ることができるんです。 作者の藤本壮介 日本建築大賞 2025 年日本国際博覧会(大阪・関西万博)
「直島パヴィリオン」 ♥♥♥
髙橋真梨子(たかはしまりこ、76歳) 東京国際フォーラム 「EPILOGUE」 髙橋真梨子 「音楽の殿堂」 カーネギー大ホール 髙橋 「EPILOGUE」 「あなたの空を翔びたい」 最初のあいさつで「皆さん、こんばんは。とうとう最後のステージになってしまいました。16歳の時に歌の世界に入って60年。皆さんの後押しがなければここまで歌ってこれなかったと思います。温かい心に感謝です。今日は楽しく、そして皆さんに元気をもらって、私も元気をあげたい。本当に感謝です」 高橋 「感謝」 「真梨子さん~、今日も世界で一番かわいいです~」 「ありがとう。信じることにします」 「何歳になってもかわいいいと言われると嬉しいものです」
2023年1月、「各地を回る全国ツアーは体力的に厳しい」 「もう一回歌ってほしい」 「今回は歌い納めの覚悟」 「完全燃焼することができました。満足です」
「桃色吐息」「ごめんね…」「五番街のマリーへ」 ペドロ&カプリシャス 「ランナー」 「生きて 生きてゆきましょう あなたのそばで」 ヘンリー広瀬(81歳) 髙橋 「この気持ちがファンの皆さんに伝わってくれたらうれしい」 髙橋 約5,000人のファンが総立ちで見守る中、終演の幕が下りる時には「愛しています」 「(出身の)博多の人には『秘めた情熱』っていうのがすごくあるんです。言葉では『愛している』なんてあまり言えないから、手話で伝えるようにしました」 2,826回 を重ねました。これに単発のスペシャルライブが19本。321本のディナーショーを加えると実に計3,166回になります。トータルの観客動員数は730万人を超えます。紅白歌合戦にも6回出場し、紅組最年長記録も更新しています。髙橋 「ファンの皆さんとの大切な時間でした」 「引退とは言いません。だからいつかまたお会いしましょう」
なおこのラストコンサート「髙橋真梨子concert FINAL 2024~2025EPILOGUE」 WOWOW ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週は夜鳴きそば 国内外に96ホテルを展開するビジネスホテルチェーンの「ドーミーイン」 「夜鳴きそば」(無料)
「夜鳴きそば」 「ドーミーイン」 「夜鳴きそば」 「ご麺なさい」 「夜鳴きそば」 「夜鳴きそば」 そもそも「夜鳴きそば」 「夜泣きそば」 「夜鷹(よたか)そば」 「夜鷹そば」 「夜鷹そば」 「夜鳴きそば」 「夜泣きそば」 島根県立津和野高等学校 「夜鳴きそば」
ハーバード大学 松尾 芭蕉 井原 西鶴 板坂 元(いたさかげん)教授 「日本でする英語など畳の上の水泳とおなじだ」 板坂先生 『考える技術・書く技術』(講談社現代新書、1973年) ところが、そのころふと逆ピラミッド型のことを思い出した。われわれ日本人はピラミッド型の文に馴れている。つまり、どうでもよいことからはじまって大事な内容は文末の方に出てくる。そのため、日本語を聞くときは、生まれたときから文末に注意を集中するようになっている。それに対して、英語の方は逆ピラミッド型で、文のはじめに重要な主語・動詞があらわれて、文末に行くにしたがって些末な内容になる。だから、英語に馴れるためには、ヒヤリングの型をピラミッド型から逆ピラミッド型に切りかえねばならない。そう思って、まずラジオを聞きながら、文の切れ目だけを確認する練習をした。これにある程度馴れてきたら、つぎに文のいちばんはじめの語だけを聞きとる練習をする。それができるようになったら、今度は一番目と二番目の語をいっしょに聞きとる努力をする。こういうふうにして、だんだんと聞きとる語数を増加して行った。どれくらいかかったかは覚えていないが、二ヵ月くらいでいちおうは聞いてわかるくらいにはなることができた。 これが最上であるかどうかは別として、相当に成果があがるものである。わたくしの日本語は聞きやすいとアメリカ人からよく言われるが、右と反対に日本語を話すときに、文末をゆっくりと、しかもはっきり発音するように意識して話すので聞きとりやすいのだと思う。日本語では普通この逆ピラミッド型の文型で話すときに、文末をはやく不明瞭に話す。それが自然の話し方のスピードとなっている。ところが、日本学の権威といわれ、日本語がペラペラといわれている人をつかまえて、何人にも文末をはやくしゃべる、つまり自然なスピードで話して実験してみても、ほとんどの場合通じなくて聞き返される。ヒヤリングの型が身についていないためであろう。われわれ日本人にとっては、これと、まったく反対のことが英語についていえるのではあるまいか。 もし、日本で英語教室を開くとしたら、わたくしは逆ピラミッド型の練習を徹底的に行なうカリキュラムを組むだろう。はじめは、ことばなしに、タンータン・ターンといったリズムを練習させて、そのはじめのタンに当る語の聞きとりから聞きとる、というふうにすれば面白い英語教室になると思う。現在、日常の英語にこまることはないが、疲れたときや話に興味をおぼえなくなったときには、今でも気がつかないうちに文末ばかりを聞いているほどだから、この型練習はちがった言語体系のことばを練習するには基本的なトレーニングではないかと思う。とにかく劇や詩の朗読のレコードを、何回もくり返し聞いて、そのころは練習したものだった。 そのつぎに、わたくしが気がついたことは、知らない単語が出てくると一瞬ドギマギしてそのあとの文を聞きのがす癖が自分にあることだった。ハッと思ってその単語の意味を考えているうちに、相手の文はどんどん先へ進んでしまう。これを防ぐために、知らない単語があっても構わずに文を先へ先へと聞いて行く練習をはじめた。単語の一つや二つ知らなくても、これは印刷が悪くて字がかすれている文や活字の脱落した文を読むようなものだし、あるいは調子の悪いラジオを聞いているようなものだ、ということを何度も自分に言いきかせて、とにかく文の終りまで聞くことにした。その単語がたとえキー・ワードであっても、そのつぎの文、つぎのつぎの文と聞いていれば、全体をとらえることはできる。これはむつかしいようで、やってみると案外にはやく馴れるものである。 この方法は、英語の文を読むときも、わたくしは実行している。新しい単語が出てきてもそこで辞書を引かない。少くともパラグラフ全体は中断しないで読む。それでわからなければ、もういちど読みなおす、というふうに頑張って、できるだけ辞書を引かない。もちろん、一言一句をゆるがせにせず、辞書を何冊もしらべて読むこともなくはないし、けっしてわるいことではない。けれども、話を聞いたり本を読んだりするとき、思想の流れを中断するのは、ぜったいによくないと思う。とくに、日本人の場合、文法はアメリカ人よりずっと知っている人が多く、読む能力は相当に高いのだから、この方法は実行しやすいはずである。 英語の勉強を志す人には実に有用なアドバイスです。英語は大切なことを最初に言います。そしてその説明が次に続きます。日本の落語ではまず世間話などのマクラをふって、耳に馴染んだところで止めて本題へと噺は次第に熱を帯びていきます。つまり後の方になればなるほど大事なことが語られます。これこそが日本語の特性でもあります。つまり英語と日本語は正反対ということです。これが分かるだけで、ずいぶんと読みが違ってきます。私がこれに加えて生徒達に強調しているのは、英語は「抽象⇒具体」 ♥♥♥
私が毎日楽しみに読んでいる“The Grammarphobia” 英語文法・語法 コチラ で読むことができます
その2019年9月30日付の記事に、”I have the job of delivering the bad news.”という文が悩ましい、という読者の疑問を取り上げて、このjob はtask であってjob ではないのではないか?さらに、このof には「所有」の意味はどこにも含まれていない、という疑問を提示しておられました。専門の私などには全くナンセンスな質問だと思うのですが、その誤解を解き明かすために、job という名詞の語源や歴史を詳しく解き明かした上で、of の正体を丁寧に解説しておられました。今日私がここで取り上げたいのは、そのことではなくて、この記事のタイトルが、“A job is a job is a job” 「仕事は仕事であって仕事だ」
私がこの表現に初めて出会ったのは、教員に成り立ての頃だったと思います。あの当時は、海外の新聞から洋雑誌、小説に至るまで、手当たり次第英語を読んでいた時期です。アレッと思う表現はひたすらカードに採って、いろいろと調べて疑問を解決しようと努力していたのです。その当時は、辞典も今のように親切ではなく、ネットもありませんでしたから、理解するにも苦労の連続でした。この表現は、Gertrude Stein Sacred Emily n の中に出て来るものです。“Rose is a rose is a rose is a rose.”
Rose is a rose is a rose is a rose
よくアメリカ人が“A rose is a rose.” “A rose is a rose is a rose.” “A rose is a rose is a rose is a rose.” 安藤貞雄先生 の 『英語イディオム・句動詞大辞典』(三省堂、2011年) 「バラはあくまでもバラだ《それ以上でも以下でもない》(G.Stein, Sacred Emily )▲しばしばA story is a story is a story. のようにもじって使用される」 A rose is a rose is a rose is a rose. バラはどこまでいってもバラだ《◆米国の詩人・小説家G.スタインの言葉;物事の本質はどこまでいっても変わらないことをいう場合によく引用される》 『ジーニアス英和辞典』(第6版)
ところで皆さんは「バラ」 「薔薇」 松江北高補習科 勝田ケ丘志学館 薔薇 「佐渡(サ土)の人々口々に、サー微笑みに中一本」 薔薇
私は学生時代に、読書の際に出くわした、rabbit test, like sevens coming out, nervous Nellie, peaches and cream, Ten-five ♥♥♥
「まさか」 マルティネス 宮崎 「あー、またか」 と絶望していたところ(これで3本目です)、その裏に途中出場の若林楽人外野手(わかばやしがくと、27歳) 岸田行倫捕手(28歳) 現役時代の指揮官さながらの絶叫が、東京Dに響き渡りました。若林 「最高でーす!」 「サヨナラ慎ちゃん」 阿部監督 「全員が助けられました」 マルティネス 「今日はここで決めないとダメだと。本当に集中してアドレナリンを全部、出して行きました」
カウント2―2からバットを短く持ち、内角147キロ直球を前進守備の中越えへ運べいました。勝利目前で追いつかれる展開に「嫌な流れの中で試合を決められる一打を打てたことが本当に…。今までの中でも興奮しました」 「聞こえてるということは集中してないのかと思ったんですけど〔笑〕。でも本当にうれしい」 「和真さんもいたのでいい勉強ができると見ながら、聞きながら」 岡本選手 「試合に出てない時間こそ、実績を残してる人たちに聞いて引き出しを作ることを大事にしてました」 「すごい緊張感の中でプレーしたい。最後まで本当に戦力になりたいと思ってます」
今日私がご紹介したいのは試合後のお立ち台です。この日のヒーローインタビューは「キッズナイター」 「どうやったらプロ野球選手になれますか?」 若林選手 「運だと思います」 「さすがに運だけではプロ野球選手になれないと思いますが」 「しっかり練習してあとは運、を拾う。ゴミを拾うとか」 「ゴミを拾う」 若林 「それが当たり前と教わってきた」
「点さえ取ればそれでいい」 松江北高 北高 「小さい頃からお母さんから人の嫌がるトイレをきれいにするといいことがあると言われ、中学校時代からこうやってトイレ掃除をしている」 大阪大学 北高 「何で?」 「まっさらにきれいにしておけば、明日一時間目の授業をやる先生も気持ちがいいでしょ」 大阪大学大学院 読売新聞 股関節 北高補習科 米子 「先生、カバン持ちます」 九州大学 「困っている人を助けてあげるといいことがあるから、大学に行ってもそのことを続けてね」 「今回よく分かりました。そうします」 「運」 若林楽人選手 「運を拾う、ゴミを拾う」 今年の不調極まりない巨人軍 「運」 石川達也投手 田中瑛斗投手 大勢 中川 「運」 「運」 ♥♥♥
ロサンゼルス・ドジャース ドジャース メッツ FOX ケン・ローゼンタール デイブ・ ロバーツ監督
And manager Dave Roberts was brutally
“Yeah I don’t know. It was corners in right there, ball to the middle of the field. I think he just had a brain cramp
ドジャース 大谷翔平 ベッツ T・ヘルナンデス 大谷 大谷翔平 ドジャース ロバーツ監督 「翔平は本塁を狙うべき状況だった。一回を切り抜けたことで相手側に流れが傾いてしまった」 ヤンキース 大谷 「残酷なほど正直に 語った」「残酷なまでに 正直な感想を述べた」 brutally brutally 「(情け)容赦なく、手加減することなく」 brutally honest/ frank などでよく使われる用法です。「容赦なく正直に感想を述べた」 副詞 『ライトハウス英和辞典』(第7版) 「残酷に;容赦なく」 研究社 「副詞の徹底的な見直し」
そして続くロバーツ監督 「思考停止」 brain cramp ♥♥♥
I had such a brain-cramp
意志は強いのに、運 運 チャンス 運 チャンス チャンス
ノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士 「あっ、これで行こうか」 「アッ、これだ!」
ノーベル賞受賞者の話を聞いていると、確かに「偶然」 田中耕一 白川英樹 田中 小柴昌悛 「偶然」 「偶然」 「偶然」 「よくよく聞いてみれば、なんだ、偶然だったのか」 偶然 偶然 運 偶然 運 偶然 運 偶然 運
あの発明王のエジソン 「私は、たまたま価値のあることをやったということがない。私の発明には一つも偶然の産物はないのだ」 エジソン 「偶然の産物」
私のささやかな経験で言えば、英語の本を読んでいて、知らない、見たこともない表現に出会った時に、カードにメモしておいて心に留めてアンテナを張っておくと、不思議なことにその後、何度も何度もその表現に出くわすのです。そんな風にして、英語の勉強を続けてきました。
白川 小柴 田中 「偶然」 偶然 偶然 Chance of favors the prepared mind. ―Louis Pasteur「幸運は準備された心に味方する」 パスツール ニュートン 偶然 「偶然」 「意志はあるのに…、努力はしているのに…」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はドリンク 米子 松江駅 ローソン 「アンバサ」 ローソン 「懐かしのアンバサがファンタとコラボ!?よく分からんけど飲んでみよ スッキリハジけるっ!!!」 「アンバサ」 「ファンタ ホワイトグレープ&アンバサ」(172円) “懐かしいのに新しい” 「アンバサ」 ローソン 「懐かしいもの見つけました」「ついに来たか…」「今飲んでもやっぱり美味しいなぁ」「懐かしすぎて即買い」 「アンバサ」 ローソン 「懐かしいのに新しい」 「アンバサ」 販売終了になったという説が流れるほどついぞ見かけることのなかった「 ア ンバサ」 「アンバサ」 「アンバササワーホワイト」 「アンバサ」 「カルピスソーダ」 「スコール」 コカ・コーラ社 「スコール」 「アンバサ」 「カルピスソーダ」 「スコール」 「アンバサ」 「全体的に弱い味で何か物足りない」 「アンバサ」
かつてはコンビニやスーパーで当たり前のように見かけた「アンバサ」 コカ・コーラ社 「需要の減少」「商品整理」 「カルピスソーダ」 「スコール」 「アンバサ」 「マイルドな味と適度な炭酸」 「存在を知られていなかった世代」
2021年以降、「アンバサ」 「Qoo」 「アンバサ サワーホワイト FROM Qoo」 「若年層へのリブランディング」 Qoo 「アンバサ」 「知らない世代にも飲んでほしい」 「アンバサ無い!」 ♥♥♥
▲懐かしさでいっぱいになりました!
ワイドショーの司会、映画やテレビドラマでも活躍された落語家でタレント・桂小金治(かつらこきんじ、1926― 2014) 桂小文治 桂小金治 『アフタヌーンショー』 「怒りの小金治」 『それは秘密です』 「泣きの小金治」 月刊『致知』(致知出版) 小金治
桂小金治 「いい音ならこれで出せ」 「ふるさと」 「俺にできておまえにできないわけがない」 「おまえ悔しくないのか。俺は吹けるがおまえは吹けない。おまえは俺に負けたんだぞ」 「一念発起は誰でもする。実行、努力までならみんなする。そこでやめたらドングリの背比べで終わりなんだ。一歩抜きん出るには努力の上の辛抱という棒を立てるんだよ。この棒に花が咲くんだ 」 「偉そうな顔するなよ。何か一つのことができるようになった時、自分一人の手柄と思うな。世間の皆様のお力添えと感謝しなさい。錐(きり)だってそうじゃないか。片手で錐は揉めぬ」 「努力の上の辛抱を立てたんだろう。花が咲くのは当たりめえだよ」 「ハーモニカは3日も前に買ってあったんだよ。お父ちゃんが言っていた。あの子はきっと草笛が吹けるようになるからってね」 このお父さんの全ての言動に、たくさんの学びがぎっしりと詰まっているように思います。 「いい音ならこれで出せ」 「俺にできておまえにできないわけがない」 「一念発起は誰でもする。実行、努力までならみんなする。そこでやめたらドングリの背比べで終わりなんだ」
桂小金治 「商売」 「笑売」
小金治 小金治 「貰って食べよう」 「今これを盗んで食べたら、一生イモを食べる度に、この日盗んだことを思い出す。それでも食べるか?」 小金治 ♥♥♥
松下幸之助 江口克彦(えぐちかつひこ) 『いい人生の生き方』(PHP研究所新書、2006年) 「人生」 ある王様が家来に「人生とは何か、まとめて教えてほしい」と指示した。「かしこまりました」と家来はさっそく国中の優秀な学者を集めてその研究をさせた。学者たちは、ああでもない、こうでもない、侃々諤々の議論を重ねること数十年、ついに膨大な成果をまとめることに成功した。 王様のところに恐る恐る報告に参上すると、王様は、そのあまりに膨大な報告書に驚き、「もう少し簡単にまとめてくれないか」と要望した。そこで学者たちはまた数十年をかけて半分の量に圧縮し、王様に報告に出かけた。もう十分に歳をとってしまった王様には、それでもかなりの報告書であり、とても読みきることはできない。ふたたび「もっと簡略に」と要請した。また、学者たちは懸命に努力してようやく一冊の分量にまとめた。 さあ、これで大丈夫だと出かけていくと、王様は、余命いくばくもない状態になっていた。病床にある王様には一冊の分量でも多すぎた。それを読む気力はなくなっている。王様は声も絶え絶えに、「その報告書を読みきるに十分な時間は残されていない。そこで人生とは何か、ひと言で言えばどういうことか」と訊ねた。一人の学者が王様の耳元で「人生とは、生まれて、生きて、死ぬことです」と説明した。王様は大きく頷いて「そうか。わかった」と言って息を引き取った。
「生き方」 「普通の生き方」 「よく生きる」 「 自己実現」 竹内 均先生(たけうちひとし、東京大学名誉教授) 「自己実現」 ①自分の 好きなことをやり、②それで十分にメシが食えて、③のみならず、それが他人の役に立ち、また他の人から評価される 「理想の職業とは?」 ① 好きなことをやり、②食べるのに十分なお金が手に入り、③ときどき人から感謝される 竹内先生 「教職」 「自利」 「利他」
仕事が本当に好きになれば、それは「仕事」という名の趣味になります。楽しくてたまらなくなってきます。仕事に夢中になれないのは、仕事が本当に好きなところまで至っていないからです。寝食を忘れて取り組んでこそ、大きな成果を手に入れることができるのです。まだそこまで至らない人は、「楽しい趣味」と「退屈な仕事」という、子どもっぽい二分法をしてしまうのです。事を成功させようと思えば、いろいろな情報や知識が必要になってきますが、好きであれば、情報や知識は、自然と集まってくるものです。傍からも提供してもらえるようになります。しかし好きでなかったら、目の前に落ちている幸運でさえ、それを拾おうともしません。与えられた仕事が好きになるように努めていきたいものですね。「好きこそものの上手なれ」 「君にこの仕事を頼みたい」 『ライトハウス英和辞典』(研究社) 島根県 研究社
「仕事の楽しさ」と「遊びの楽しさ」は全く違います。そのことをしっかりと心に銘記しておきたいものです。楽しく仕事をするのはいいことですが、楽しさの意味が違います。遊びの中にある「責任のない楽しさ」 「責任のある楽しさ」 ♥♥♥
私がまだ松江南高校 島根県松江市 インターハイ ウィンドウズ 「ワード」 ツアイト社 「JG」 バレーボール会場 「JG」 「バレーボール速報ニュース」
「Z’s WORDJG」 ツァイト社 「DTPソフト」(Desk Top Publishing) DTP Mac Adobe Pagemaker PC-98シリーズ MS-DOS Mac 「Z’s STAFF KID」シリーズ ツァイト Windows95 「JG」 「ワード」 「一太郎」 「JG」 アスキーサムシンググッド この時作った作品は、我ながら美しいものが出来たと満足でした。終了後、ツァイト社 「JG」 「とても美しい文書だ」 「部品」ディスク 「あむーる」 「JG] マイクロソフト 「パブリッシャー」(Publisher) ジャストシステム 「一太郎」 フォント クリップアート部品 「JG」 ♥♥♥
故・小倉昌男(クロネコヤマト) 「クロネコヤマト」 宅急便 ヤマト運輸 「宅急便」 「急」 走っているデザイン になっていることは有名です(写真下)。いつも私が言っていることですが、見えないものは何万回見ても見えないのです。対象に興味を持って初めて見えるようになります。セブンイレブン キユーピー、キヤノン、シヤチハタ ジャパネット(Japanet) 乗車券 特急券
荷物の宅配・集荷といえば、“クロネコヤマトの宅急便♪” ヤマト運輸 “宅急便” 宅急便 「急」 “急” “急” “急”
▲「急」の文字に注目!走っていますネ!
いつごろから、どのような理由でこのデザインを採用したのか?ヤマト運輸
「記録が残っておらず、はっきりとした狙いや理由はわかっていません。このデザインは、宅急便サービス開始時の1976年1月20日から同様のものを使用しています」 たしかに、宅急便 黒い親猫が口に子猫をくわえた姿でおなじみの「クロネコマーク」 アライド・ヴァン・ラインズ社 小倉康臣社長 「宅急便」 「宅配便」 「宅急便」 ヤマトホールディングス 「大切な荷物を安全に届ける」
「宅急便」 「関心を持っていただき大変光栄です」 「2019年11月にヤマトグループは創業100周年を迎えます。次の100年に向けてさらに成長していくため、お客さまのご期待に沿えるよう、それぞれに合ったサービスをお届けし続けます」
1976年、ヤマト運輸 「電話ひとつで、翌日、確実にお届け致します」 宅急便 「クロネコヤマト」 ヤマト運輸 アライド・ヴァンラインズ社 ヤマト運輸 小倉康臣社長 「careful handing(丁寧な荷扱い)」 ヤマト運輸 小倉康臣 ヤマト運輸
親黒猫が子猫をくわえる歴史あるマークの誕生秘話や意味、急の字の隠しデザインなど、仕事に自信と誇りを持って取り組むヤマト運輸
▲リニューアルされたクロネコのロゴマーク
2021年3月1日に、ヤマト運輸 「クロネコマーク」 クロネコマーク クロネコマーク クロネコマーク ヤマト運輸
「ヤマト運輸は2019年に創業100周年を迎えました。今後も社会インフラの一員として、お客さまや社会のニーズに正面から向き合い、新たな物流のエコシステムを創出し、豊かな社会の創造に持続的な貢献を果たすべく2020年1月に『YAMATO NEXT100』という中長期の経営のグランドデザインを発表しました。この時に、これから先のヤマトのブランドやシンボルマークがどうあるべきかといった検討を開始しました。その際、4月1日から“ワンヤマト体制”として、ヤマト運輸を中核とした新たなヤマトグループに生まれ変わることが決まり、リニューアルしたロゴマークの使用がスタートすることになりました」 新たなヤマト運輸 クロネコマーク ♥♥♥
I scored a goal!
Well...technically, I scored a goal Yessssss! from the
the sideline, and Mattie, who had arrrived with Mum, celebrated so
loudly that you would have thought I had more talent than Bale and
Messi combined. The truth is, Mo kicked the ball at me a little too
hard (that's his trouble――his left foot is, if anything, too
powerful) and instead of receiving the ball and aiming for the goal
I turned away as if someone had kicked a hand grenade in my direction.
But the ball happened to hit my leg, and somehow bounced off me and
straight into the goal.
It was a fluke. But a goad is a goal.
僕はゴールを決めた!
えっと…形の上では、僕はゴールを決めたことになる。パパはサイドラインの外から
「よっしゃあああ!」と叫び、ママと一緒に来ていたマッティは、人が聞いたら僕が
ベイルとメッシを合わせたよりも才能があると思うんじゃないかいうくらいの大声で
ほめてくれた。本当のところは、モーが僕に向かってボールをほんの少し強すぎる感じ
で蹴って(これがモーの厄介なところなんだ、やつの左足は、どちらかと言うと、力が
強すぎるのさ)、そのボールをもらってゴールをねらう代わりに、僕は、まるで誰かが
僕の方に手榴弾を蹴ったみたいに背を向けちゃったんだ。でもボールはたまたま僕の脚
に当たって、どういうわけか跳ね返ってまっすぐゴールに入っちゃったんだ。
まぐれだった。でもゴールはゴールさ。
「3年生7月進研模試」 「問1 下線部(ア)で、サムが自身の得点について「形の上では」と言い直したのはなぜか。60字以内の日本語で説明せよ。ただし、句読点も字数に数える。」 technically 「形の上では」 technique(技術)――technical(技術的な)――technically(技術的に) technically
technically 副詞 「 技術的に」「専門的に」 technically 副詞
It is technically
This problem is technically
のような使い方のtechnically 「技術的には」 「形式的には」「表面上は」「建前としては」「厳密に言えば」「実務上は」 堅く言えば(形式的には)そうだけれども、裏では違うんだよ」というニュアンス(言外の意味)がある ことです。上記の英文でいえば、「それは厳密に言えば違法だ」(→だけど普通は違法と見なされない)「この問題は表面的には複雑だ」(→だけど実際には簡単に解決できる)のような含みがあるのです。ですから当然、次に続くセンテンスでは( )内のような説明が出てくることが予想されますね。翻訳家の中村保男(なかむらやすお) technically 「 理論的には」 「 理屈から言えばそうなる(しかし実際にはそうではないことがある)」「形の上ではそうなる」「表向きは一応そういうことになっている」 “but~” と事情 が述べられるのを予期するのはそういう理由なのです。上の進研模試 「サムはシュートを決めたのではなく、強烈なパスをよけようとして背を向けた際に、脚に当たったボールがたまたまゴールに入っただけだから」 副詞 technically 「形の上では」
デビッド・セイン(David Thayne) 『100語で簡単!ネイティブに伝わる英会話』(成美堂出版、2017年) technically Technically 「 厳密には~なのだが」「一応は~なのだが」 なんだか事情がありそうだ という含みを伝えている副詞
① technicallyで、「厳密には~なのだが」という意味に。 ② technicallyを使って、表現した内容とは違う意味を相手に伝える。 ③ Technically, yes.で「一応はイエス。でも事情がある」という感じに。 そのことは、OALD の用例 It is still technically technically 山岸勝栄 『スーパーアンカー英和辞典』(学研) 「専門的[法的]に言えば,厳密に規則を守るとすれば」▲規則と実際にずれがある、あるいは何らかの抜け道があるというニュアンスで用いる 」 Online gambling is technically illegal, but it is very popular. (ネット上のかけ事は厳密には違法であるが、広く行われてい る) 副詞
学習辞典における副詞 「追い込み」 -ly と示すのみ、といった粗末な扱いが多く見られます。副詞 Sidney Greenbaum 副詞 副詞研究 John Sinclair 英語副詞 「チーム八ちゃん」 advisedly, lamely, religiously, periodically, abundantly, reliably, basically, identically, increasingly, recently/lately, strenuously, habitually, comfortably, lazily 副詞 「・英語語法」 ❤❤❤
人生には3つの坂があると言われます。『上り坂、下り坂、そして 突然やってくるまさか』 小泉純一郎 松下幸之助翁 「人生の上り坂、下り坂、まさか」 親鸞聖人
第27回参議院選挙 鈴木宗男議員(77歳) 「もう選挙には出ませんから。ひとつのけじめ、終止符です」 「目に見えない力により生かされた。しっかり働きたい」「天が、神様が与えたくださった私への使命だと思っている。77歳ですが、生まれ変わったような気持ち。鈴木宗男は生涯政治家です」 「まさか」
「まさか」 ライデル・マルティネス ブライト 岡林 辻本 上林 細川 「まさか」 マルティネス 阿部監督 「まさか」 7月21日(月)にもこの逆の「まさか」 井上 小幡 伊藤将投手 泉口 大山 大山 リチャード リチャード 「なかなかね、ホームランが出ないこう打線なので…ま、冗談で宝くじが当たったらって言ったけど、うん。当たったらね、そういうホームランできる力を持ってるんで、今日は起用してみたんですけど。はい」 阿部監督 「あ、折れた!」 岡本 「やったな、やっちゃったなあって感じでした。打った瞬間、歓声がすごかったんで、その振動でボールも伸びたのかな思います」 吉川尚輝内野手(30歳) 吉川 伊原 佐々木 「本当ね、意地を見せてくれました」 「まさか」
巨人-阪神の伝統の一戦は前半戦ですでに18試合が終わり、5勝13敗と大きく負け越してはいますが、その中の10試合は1点差勝負の僅差の試合です。オールスター後の後半戦にも何が起こるか分かりません。「まさか」 ♥♥♥
近年、「みどりの窓口」 島根県 「みどりの窓口」 島根県 JR 松江駅 「みどりの窓口」 JR松江駅 「みどりの窓口」
▲JR松江駅の「みどりの窓口」
▲JR米子駅の「みどりの窓口」
「みどりの窓口」 「みどりの窓口」 特急列車 東海道新幹線 「マルスシステム」 「マルス」 「M ulti A ccess seat R eservation S ystem」 「M agnetic electronic A utomatic seat R eservation S ystem」 「みどりの窓口」
これまで台帳管理方式で発券していたきっぷは、赤や青が多く、マルスシステム マルスシステム マルスシステム端末 「みどりの窓口」 マルスシステム端末 「みどりの窓口」
▲JR松江駅
現在では、自身のスマホからオンラインでも指定券を購入することができるようになっていますよね。また「みどりの窓口」 「みどりの券売機」 「みどりの券売機プラス」 JR松江駅 「みどりの窓口」 JR東海 「みどりの窓口」 「みどりの窓口」 「JR全線きっぷうりば」 「みどりの窓口」 「みどりの券売機」
以上をまとめると、昭和30年代まで、国鉄の指定券や寝台券は、列車ごとの台帳で管理され、予約の時には、台帳を保有する駅や統括センターへ電話連絡をしていました。しかし、この方式では、予約完了までにかなりの時間がかかったばかりか、聞き間違えや書き間違え、さらにはダブルブッキングも少なくありませんでした。この問題を解決するため、昭和40年(1965)、当時の国鉄は指定席の購入をオンライン方式に切り替え、主要駅などにコンピューター回線を通じて指定席券を販売するための窓口が設置されました。それが、最初の「みどりの窓口」 「みどりの窓口」 ♥♥♥
2022年の12月1日(木)に、長崎 「ハウステンボス」 アムステルダムシティ ミッフィー 「ディック・ブルーナ・ショップナインチェ」 ミッフィー 「ナインチェ・カフェ」 「nijntje ナインチェ」 ミッフィー 「ミッフィー専門店&カフェ」 ミッフィー ミッフィー ミサワホーム 松江北高図書館 ミッフィー ハウステンボス コチラ です)。
さて今度は、ミッフィー 長崎・ハウステンボス アムステルダムシティ ミッフィー 「ミッフィー・ワンダースクエア」(Miffy Wonder Square) ハウステンボス 「ミッフィーとなかまたちのあこがれの休日」 ミッフィー ミッフィー ミッフィー ディック・ブルーナ(Dick Bruna、1927-2017) ハウステンボス “ミッフィーのカワイイ世界観”
ハウステンボス ミッフィー ミッフィー ディック・ブルーナ ハウステンボス 「長崎オランダ村 ハウステンボス オリジナルミッフィー ハウステンボス ハウステンボス 「憧れの異世界。」
絵本やグッズに使われている「ブルーナカラー」
エリアは飛行機とヨットに乗って作品の世界観を楽しめる2つのライド型アトラクションのほか、ミッフィー 高村耕太郎社長 「ハウステンボスのオランダの街並みの良さを生かしながら、新しい楽しさを追加していく。本来の良さと未来に向けた成長を担うプロジェクトになる」
高村社長 「ハウステンボスが華やかな場所になっているし、成長していく可能性があると九州の方に思ってもらいたい」 ミッフィーエリア 「泊まることがすてきな場所だと思ってもらうための施策が多くなってくる」
さらには、2023年4月に期間限定で初登場した、オフィシャル・ホテル「ホテルアムステルダム」 ミッフィールーム 「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」 ミッフィールーム 「ホテルヨーロッパ」
ミッフィー 「誕生70周年記念 ミッフィー展」 大丸神戸店 ミッフィー ミッフィー ブルーナ ♥♥♥
東京・山野楽器 DVD『さだまさしコンサートツアー“51”』(7,700円) 「五番街」 東京ガーデンシアター 「驛舎」「東京」「1989年 渋滞」「51~2024ver.~」「ひき潮」
「デビュー50周年 さだまさし 『さだまさし50th Anniversary コンサートツアー2023~なつかしい未来~』(4枚組DVD) さだ 『コンサートツアー“51”』 数字の51と言えば、イチロ- 大谷翔平 さだ デコイチ 「 機関車SD(さだ)51」 “心の列車” 「SD51 1973」 「SD512024」 「マS48」 「サシR6」 さだまさし 『銀河鉄道999』 「今回知っているヒット曲はありません。今日が初めての人は、全部さだの新曲だと思って聞いていただくか、新人のコンサートに来たつもりで…」 「驛」 「それぞれの旅」 「指定券」 「まほろば」 「空蝉」「ひき潮」 ♥♥♥
<収録内容>
1. 驛舎 ★★★ 2. それぞれの旅 3. 指定券 ★★★ 4. 決心~ヴェガへ~ 5. 東京 6. 1989年 渋滞 -故 大屋順平に捧ぐ- 7. さだ工務店のテーマ2020 8. 北の国から~遙かなる大地より~ 9. pineapple hill 10. ジャカランダの丘 11. 51~2024ver.~ 12. Believe 13 いのちの理由 14. まほろば ★★★ 15. 空蝉 ★★★ 16. ひき潮 VIDEO
◎週末はグルメ情報!!今週はちゃんぽん 鳥取県米子市 高島屋デパート 島根県・隠岐の島町 米子市富士見町 「隠岐チャンポンライトハウス」 隠岐の島 米子 看板メニューは「隠岐ちゃんぽん」 「隠岐チャンポン」
看板の「ちゃんぽん」は“島の味”。実はこの店、もともと、隠岐空港 隠岐の島町 西郷港 「味太郎」
隠岐時代、店を切り盛りしていたのは原 千代子 「味太郎」 千代子 直美 「味太郎」 「みなさんに愛されてきた味なので、途絶えてしまうのはどうかなと思った」 千代子 「娘がやりたいというので、今なら数年かけて指導することができるので、いいタイミングだからということで、決断した」 直美 直美 米子市 直美 「覚悟が必要でプレッシャーも結構ある。とにかく、お母さんのそばで、教えてもらってしっかりと覚えていこうと思っています」
復活した「ライトハウス」 「とんこつちゃんぽん」 千代子 「隠岐の頃よりおいしくなっているんじゃないですか」
千代子 「これからも娘にはしっかりと受け継いでもらいたい」 直美 「いろんな方面から来てもらって、ちゃんぽんの味を楽しんでもらいたいという気持ちでいっぱい」 一番人気はなんといっても「とんこつちゃんぽん」(1,100円)
麺は「麺半分」や「麺なし」も選ぶことができます。少食の方やスープを楽しみたい方には嬉しいサービスですね。自家製チャーシューのトッピングに、がっつりライスと一緒にいただくのもおすすめです。ただ私には、長崎 「江山楼」(こうざんろう)
♥♥♥
「上善は水のごとし」 老子(ろうし) 老子 理想の生き方 を見い出していました。水は、柔らかくしなやかでありながら、一方では硬いものを穿つ強さも持ち合わせていますよね。しかも、万物に恵みを与え、争うということなく低いところに留まろうとします。水は高い所から低い所に向かって流れます。そんなしなやかさと粘り強さこそ、“究極の理想”だと言うのです。
老子 「上善如水」 「上善如水」 老子 老子 「人よりも上に行こう」「人を蹴り落としてでも上を目指そう」 老子 「人と争わず、常に低いところに留まりなさい。まるで水のように」
ちなみに老子 「住まいはしっかりとした土地の上がよく、物の考え方は奥深いのがよく、人との交わりでは情の深いのがよく、言葉は誠実であるのがよい。政治はよく治まり、事の処理能力は高いのがよく、行動は時を誤らないのがよい」
「上善如水」 「無為自然」 老子 老子 「争わず、低きところに留まる」
①万物に理を与えている点。水がなければ生き物は存在することができません。しかし、それだけ大きな存在でありながら、水が他と功名を争うことはありません。それどころか、他の汚れを清め、他を動かす力を持っています。 ②人間が一歩でも高い位置を望むのに、水は反対に低いところ、低いところへとおのれを運んでいこうとします。力を誇示することなく、あくまで謙虚な存在です。 ③低いところへ行く毎に、谷川から大河、さらに大海へと大きな存在になっていきます。 ④岩をも打ち砕く巨大なエネルギーを持ちながらも、普段はその力を秘めています。常に自分の進路を求めてとどまるところがありません。 ⑤時に氷となり、霧となり、その形を自在に変える柔軟な変化対応力を有しています。 大きく多様な力を持ちながら、絶えず自分を低い所へ運び、自在に形を変えながら、一時も停滞しない水のような有様を一つでも身に付けることができれば、理想の生き方に近づけるはずです。♥♥♥
2024年8月19日(月)に放送されたカズレーザー 「X年後の関係者たち」 「QRコード」 (キューアールコード) 「QRコード」 「QRコード」
「 QRコード」 デンソー デンソーウェーブ 「QR」 Q uick R esponse(クイックレスポンス) 「QRコード」 デンソーウェーブ バーコード バーコード 「QRコード」 「直島」 QRコード ▲今や、英語の単語集にも「QRコード」が!
「QRコード」 デンソー バーコード 「バーコードより多くの情報を盛り込めるコードを作って欲しい」 日本電装 原昌宏(はらまさひろ)
原 「正確に速く読み取れること」 デンソー 「QRコード」
バーコード 「QRコード」
特許権者のデンソーウェーブ 「QRコード」 特許権を行使しない と宣言しています。近年「QRコード」 「QRコード」 「QRコード」 「QRコード」 デンソーウェーブ 「QRコード」 「QRコード」 「欧州発明家賞」 バーコード 「QRコード」 「QRコード」 「誤り訂正機能」 「QRコード」 「QRコード」 リーダー(読み取り機) バーコード 「QRコード」 ♥♥♥
「共通テスト」 センター試験 英文法問題(穴埋め・語句整序・誤文訂正) 八幡 英文法 センター試験 センター本試験 第2問A の問5 でした。
問5 Our PE teacher, a ( ) professional basketball player, is coaching the school team. ①previous ②late ③once ④former
意味「私たちの体育の先生は、元プロのバスケット選手だが、今は学校のチームのコーチをしている」 ④ のformer ① のprevious 「以前の」「前の」
previous Fumio Kishida was the previous previous Shohei Ohtani is a Los Angeles Dodgers player. His previous Longman Essential Activator previous person, thing, or time is the one that existed just before now or before the time you are talking about“という記述が役立ちます。それに対して、former Shinzo Abe and Kakuei Tanaka were former former Shohei Ohtani’ s former James Tschudy former previous
たとえば、She is a former previous former previous 「前の…」 former 「元〇〇」「過去〇〇であった」 previous 「順番的に一つ前である」
ご参考までに、上の問題に対する赤本(教学社) 黒本(河合塾) ♥♥♥
①previousは「前の~、以前の~」の意であるが、ある程度の基準を設けて「それより前の」の意味で使う。「市長」のように順序がはっきりしているものなら使えるが、プロのバスケットボール選手では、何より前かが分からないのでここでは不可。 formerはかつて特定の仕事、地位、あるいは役割を持っていたが、いまはもう持っていない人について述べるのに用いる。
▲最新コンサートプログラム
2025年3月26日(日)に、4年ぶりに島根県民会館大ホール さだまさし 4688回目 のコンサート(もちろん前人未踏の日本記録 です)へ行ってきました(前回はコロナ禍の真っ最中!)。デビュー51年目の軌跡と奇跡が凝縮された白熱のステージを堪能してきました。舞台の最後には、自分がいかに好きなことをやって過ごしているかをしみじみと語っておられましたね。例のドキュメンタリー映画『長江』 年間187回 」という地獄のような回数の年もありましたっけ。私は毎回コンサートに行く度に、歌う曲順、トークの内容を一言漏らさず、暗がりの会場の中でひたすら記録している「ま虫」
さだ 「さださんにとってライブとはどのようなものですか?」 どう言ったらいいんだろう、何かに例えようがないんだよね。なんでこんなにライブをやるんだろうね。歌が好きなわけでもないのに。でも歌作りは好きなんですよ。歌ができた瞬間が一番興奮するのね。その瞬間を共有したくてライブをやっているんだろうね。「俺、いい仕事したでしょ?」って言いたいの。だけど作ってから3ヵ月も経つと飽きちゃうから、「早く次の曲作んなくちゃ」と思って……その繰り返しでずっと続けてるんだろうね。あとは、コンサートでは毎回悩みながら歌ってるんですよ、「この歌ってもしかして、こういうふうに歌ったほうがいいんじゃないか?」っ て。そういう発見が常にあるから飽きないんだと思う。 そうした発見をしたいが故に、彼はライブをずっと続けているんですね。
かもしれないね。あと、僕は大声を出すというのが一番のストレス発散で。多少腹が立ったりストレスが溜まったりしているときでも、ステージでは全部吐き出して忘れられる。だから「これは思い出すたびに腹が立つな」と思うことはライブで吐き出して、反対に覚えていなきゃいけないことはトークにする。 僕のコンサートでは、トークが安心してくつろげる場所なのかなと思っていて。僕の歌は、色々感じたり考え込んだり、キュンとしたり怒ったりと、心に働きかける曲が多いから、トークのときくらいは肩の力を抜いてゆっくりしてもらえたら。アイスクリームに添えられているウェハースみたいなもんだよね。アイスクリームを食べて舌が冷たくなると甘味を感じなくなるから、そしたらウェハースで舌を温めてもらって、またアイスをおいしく味わってもらうっていうことなんだけど…。まぁ、うちはウェハースから売れるアイス屋(笑)。なんなら「ウェハースだけで買えませんか?」っていう人もいるくらい(笑)。だから来年はウェハースだけのライブもやろうと思っていますよ。
国難のコロナ禍でコンサートが一切できなくなった時にも、「ショーを止めてはいけない」
回数にはあまり意味がないと思うんですけど、ショービジネスに関わる人間の責任というのかな、それは感じますね。コンサートはお客さんがいなくなったら自然にできなくなりますが、足を運び続けてくださっているのだから、その方々の期待に応えていかなきゃいけない。だから、ありったけのものをステージに並べるんです。『お客さんがお腹いっぱいになって飽きちゃうよ』ってよく言われました。でも、お腹いっぱいにならなかったら、来てくれたかいがないじゃないですか。幸いにも胃拡張のお客さんが多くて、何を出しても食べてくれますしね〔笑〕。
さだ
結果論だけど、それが自分を支えてきたんじゃないかなと思いますね。もしもステージがなかったら、ここまで生きてくるのは大変だったろうなとは思う。コンサートがあるから行かなきゃって思うし、お客さんに来てもらった以上は楽しんで帰ってもらわなきゃって思うしね。で、コンサートっていうのは毎回同じことは絶対にできないでしよ。昨日良いライブができたからって、同じようになぞろうとすると絶対にうまくいかない。掴んだと思っても、翌日にはどこかにいっちゃう。毎回違うからこそ、常にうまくいくように求める。それが楽しいのかもしれないね。 さだ
もういっぺん『さだまさし』を生まれ変わってやるかって言われたら、真っ平御免ですけどね。こんなにしんどいことは、やりたくねえ。波瀾万丈すぎる。でも、苦しかったけど、今でも苦しいけど、それが自分に与えられたものだろうなと思ってます。次はもっと分かりやすく人の役に立つ人生がいいな。お医者さんとかさ。被災地に行くと、いつもうらやましいもん。でも、避難所行って歌うとさ、みんないい顔で笑ってくれたり。ああ、これはこれでいいんだなって思ったり……分かった、もういっぺんやる、『さだまさし』 そんなさだ 『生命の樹~Tree of Life』 「Believe」 「Tomorrow」 「母標」 「初恋駅」 當麻寺 「残月」 グレープ 吉田 「生命の樹 –序–」 <さだまさしの現在進行形の“うた”> さだ 《Tree of Life Premium》 さだまさし ♥♥♥
60代、70代になると、できないことが増えてくるのは当たり前じゃないですか。何もしないと下がっていく下りのエスカレータに乗っているような年齢ですよ。だけど、ぼくはそれを当たり前だと思わないで、下りエスカレータを上に向かって逆走しています 。音楽活動も財団のほうも逆走して二階に上がろうとしている。万が一上がれたら三階、いや屋上をめざしますもん。みんな自分の人生を二階建てとか三階建てで終わらせようとするからいけないんです。病気や事故のことも考えられなくはないけれど、でもぼくは上がれるところまで逆走しますね。そりゃしんどいですけど、黙って立っていたら後に下がるだけですから、一歩ずつでも歩かなきゃ。 (さだまさし) VIDEO
VIDEO
生徒から「「~になる」という意味で、becomeとgetはどう違いますか?」 Longman Essential Activator (1997) によれば、become get get become available, calm, clear, famous, happy, important, necessary, obvious, poor, powerful, proud, sad, silent, successful, useful などの形容詞 get get 形容詞 で も、clearer, happier, more famous, more important のように比較級 get はannoyed, bored, damaged, lost, broken などの過去分詞 better との相性はget become get / become better 名詞 become become get
これとよく似た単語にgrow grow old/ tired/ worse/ larger の例で考えると、上の辞典では、“slowly and gradually become old, tired, etc.”と意味を載せています。つまり「ゆっくりと徐々に~になる」 grow ♥♥♥
6月25日(水)に、フジテレビ系の「アンビリーバボー「仰天全国騒然…噂の真相!!プリンセス天功埋蔵金㊙真実を解明せよ!!」 プリンセス天功 大爆発脱出イリュージョン
プリンセス天功 朝風マリ 引田天功 PRINCESS TENKO(プリンセステンコー) 「マジシャン ・オブ・ザ・イヤー」 PRINCESS TENKO AWF(アフリカ野生動物保護財団) 「ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールでフランク・シナトラとボブ・ディランと共演した」「北朝鮮の金正日総書記から白頭山の天然記念物の犬を贈られた」「プーチン大統領からも犬をプレゼントされた」「アラブの王族から支払われたギャラが石油だった」「バービー人形で有名なマテル社と契約し、『テンコー人形』が全世界で800万体以上売れた」 プリンセス天功
女子プロレス団体・マリーゴールド マリーゴールド 露出 も減ったようですね。
アニメのキャラクターやバービー人形にもなった「プリンセス・テンコー」 生涯契約 があるでしょ!」と、アメリカのマネージャーに叱られます。バービー人形で有名なマテル社よりプリンセステンコー人形
年齢設定は永遠に24歳 太っても痩せてもいけない 髪の毛の色は黒色 前髪の長さは規定の長さに従う 話し声はミステリアスでなくてはならない 化粧は指定された物を使用する 電車に乗ってはいけない コンビニやスーパーへ行ってはいけない 買い物は全て通信販売で買わなければいけない 東西南北に一人ずつボディーガードをつけなければならない 日本人と結婚してはならない(アニメの中でアメリカ人と恋に落ちる設定のため) 同じステージに「引田天功」と「PRINCESS TENKO」が現れてはいけない 本人曰く、全身100ヶ所の取り決めがあるとの事。
そんなテンコー 「お金は正しく扱えば、貯まるよー。自分の汗がついたお金は、支払いに使っても手元に返ってくると言われているの。だから、大昔の人はお金に自分の汗を染み込ませて使ったという記述が残っています。それからね、支払いの最後に、自分の汗の染み込んだお金を渡すと、支払ったお金が戻ってくるとも言われているの。これは悪魔がお金を操作しようとしても、人の汗がついているものには手を出せず戻してしまうという言い伝えから。お金は汗を出して稼ぎなさい。そして使うときは汗して手に入れたことを忘れずに 、ということなのよね」
プリンセス天功 『ちょっとHappyになる小さな魔法』(主婦と生活社) 米国アニメ・バービードール 「プリンセス・テンコ― 」 バービー人形 万体 を売り上げたシーズンもあるのです。そして、個人契約の公演の報酬が超高額です。中東の石油王や国家元首の誕生パーティーなどに呼ばれ、時給5千万円 油田やダイヤモンド などを贈呈されることもあったそうです。プリンセス天功 年収 は、想像もつかないくらい高額 なことは確かでしょう(億単位 かな)。確かに、北朝鮮の金正日 プーチン首相 引田天功
発明王エジソン 「発明は大気の中にある」 エジソン プリンセス天功 ♥♥♥
BSフジ 「輝き続けるチューリップ」 「輝き続けるキヨシロー」 中島みゆき、BOØWY、尾崎豊、オフコース、加山雄三、髙橋真梨子、THE ALFEE、竹内まりや 「輝き続ける」シリーズ
チューリップ 福岡 「日本のビートルズ」 チューリップ チューリップ チューリップ 大野拓家 つのだ☆ひろ 吉田栄作 海老原優香 チューリップ 大野 「吉田さんとつのださんが本当にすてきなことをいっぱい話していらっしゃいますし、ライブ映像もいっぱいです! ぜひご覧ください!」 つのだ 「僕の場合はチューリップと僕の生活の記録を少しずつ話しているので、聞いているファンの皆さまからすると失礼なことを言ってとんでもないと思っている方もいらっしゃると思いますが、これはあくまで私の私見でございますので…(笑) 。『つのだ☆ひろの野郎、ひねくれてやがる』と思ってくだされば結構でございます。番組をどうぞお楽しみください!」 吉田 「約2時間の番組の中でチューリップの50年の歴史を語り尽くせたかは分かりませんが、なるべくたくさんの名曲と共にチューリップの魅力が語られていると思います。ぜひご覧ください!」 そんなチューリップ チューリップ チューリップ 財津和夫(ざいつかずお) チューリップ 財津 「チューリップとは?」 「コーラス」 オフコース
VIDEO
さてちょっと前になりますが、2017年3月18日に、 BS朝日の「ザ・インタビュー~トップランナーの肖像~」 が取り上げたのは、チューリップ 財津和夫(ざいつかずお) 1948年、5人兄弟の末っ子として福岡県に生まれ、米軍基地の近くで育ち、米軍関係者向けのラジオ放送を聞けたため、物心ついたころから洋楽に親しんでいたといいます。ミュージシャンとしての道を歩むきっかけとなったのは、高校生の時に見た映画「ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!」 ビートルズ 財津 チューリップ 「魔法の黄色い靴」 「心の旅」 チューリップ 財津
昔、故・多湖 輝(たごあきら)先生 「不得意は、うなだれていた頭を上にあげるだけで、ただの得意ではなく大得意になる」 「ああ、なるほどなあ~」 「 不得意」 「 大得意」 文字の一画の違い であり、漢字「不」の字の縦の棒 を、うなだれた頭と見たてて、これを「よいしょ」と上にあげれば、「大」の字になるということでした。オッ、この話は使えそうだなと思いメモしておいたのでした。
実は、この奇妙な比喩も、心理学的に見るとあながち見当外れとも言えないところがあります。人間の心には「過補償」 「過補償」 デモステネス デモステネス どもりました・・・・ 。絵に描いたような青びょうたんの姿であり、ここから後年の大雄弁家たる彼の姿を想像するのはおよそ不可能でしょう。転機が訪れたのは16歳の時でした。伝承によれば彼はこの年、ふとしたことからアテネの政治家カリストラトス デモステネス
「不得意こそ大得意に転じる」 ♥♥♥
巨人の小林誠司捕手(こばやしせいじ、36歳) 赤星、田中瑛、大勢、マルティネス
赤星投手 佐野 赤星 赤星 宮崎 赤星 「誠二さんのリードに、自信を持ってテンポを意識して投げました」「全体的にゾーン内に集められたし、勝負するってことを忘れずにいけたのでよかった」 試合を生中継していたBS日テレで解説を務めていた元メジャーリーガーの五十嵐亮太(46歳) 「外をこれだけ見せてそろそろ内くるんじゃないかなっていうところで外いき続けてるとかね。そろそろ内くるんじゃないかな、また外みたいな」 宮崎 「あぁ~…。味がある!味がある。味があります」 小林 「やっぱりバッター心理を知っている。もちろんね、特徴をつかんでるからっていうのもあるし。これだけ外見せてたらそろそろ内くる…コントロールいいピッチャーって両サイド投げ分けがしっかりできるじゃないですか。だからこそ内がそろそろくるって思うんだけど、外いって外いってずーっと外。宮崎に関しては全球外ですからね」
試合が早く終わったせいか、試合後にはその小林捕手 「勝利捕手インタビュー」 「いやもう赤星が本当に頑張ってくれました」 赤星優志投手(25歳) 「(赤星)優志には、とにかく(DeNAは)いいバッターそろってますけど、攻める気持ちだけは持って攻めていこうというふうには言ってました」 小林捕手 小林 。「いやもうほんと(マウンドに)上がってくるピッチャー、気持ちもこもってましたし。1―0でほんとにマウンドでとても緊張すると思うんですけど、本当に最高のパフォーマンスを出してくれたなと思いますし、自信を持って腕を振ってくれたと思いますので。僕も自然と気持ちが出ました」
2回に飛び出した中山礼都(なかやまらいと) 「1―0っていうのはチーム力っていうか…はい。ピッチャー陣の本当に凄さだと思うので。そこは本当に自信を持ってやっていきたいと思います」
最後に、小林 「いや、もう本当にピッチャーのおかげだと思ってますし。こうやって1―0で勝てたっていうことは、またバッテリーとして強くなれたと思いますし。やっぱり勝った瞬間っていうのはみんなとてもうれしいと思いますんで、次も頑張りたいなと思います」 小林捕手
巨人が6月18日の日本ハム戦(東京ドーム)に2―1で競り勝ち、連敗を「4」で止めたことがありました。同点の7回に飛び出した丸選手 小林誠司捕手 西舘 「代打・小林」 小林 阿部監督 「犠打」 小林 ウィーラー巡回コーチ
阿部監督 「代打で犠打だけど(球場も)盛り上がってくれてるんでありがたいですよね。やっぱりチームの士気が上がりますよ」 小林選手 「代打の切り札とかではないのに、小林が出てくるだけで球場の空気が一変する。今のチーム内で彼ほどのムードチェンジャーはいないし、流れを引き寄せる力を持っている」
13日のオリックス戦(京セラ)で5回の守備から途中出場した際も、敵地ながら割れんばかりの大歓声を受けました。4回までで6失点と大乱調だった先発・赤星投手 。「まだまだ若い選手に負けたくない」 赤星投手
小林捕手 小林 赤星 髙橋光 阿部監督 「(小林の活躍で)盛り上がったでしょ? たまにしか出られないのに、決めてくれるのは素晴らしい」
一時は正捕手まで務めた小林は、年々出場機会を失い、正捕手の座を追われて数年が経過しているが、FAで甲斐が加入した今年は、岸田、大城卓の後の第4捕手扱い。キャンプから二軍での調整を強いられ、一軍の実松バッテリーコーチは『甲斐が入ったのは球団の方針。捕手の層は厚くなったけど、誠司にも必ずチャンスがあるから腐らないでほしい。まだ衰えていないし、経験も豊富。必ず必要な時が来るから』と呼びかけていた。開幕一軍からも外れ、ようやく昇格したのが5月24日。それでも小林は腐ることなく、休日返上で練習をするなど、二軍では若手の手本になっていた。最高で1億円あった年俸も一時3,000万円まで下がった(今季は4,000万円)が、態度は全く変わらない。今の巨人の中で一番歓声が大きいのは、ファンもそういう姿勢を認めているからです。球団としても、あの人気面は捨てがたいですから。 「世界の小林」「小林タイムリー」「小林誠司!!!!!世界のKOBAYASHI!!!!」「世界の小林が久々に凱旋」「世界の小林緊急来日!!」 赤星投手 「小林さんと組みたかった」 赤星投手 小林捕手 小林捕手 オコエ 昨年は菅野投手 小林捕手 菅野 赤星投手 ♥♥♥
私は現役の頃、「北高の強みは集団の力」 「受験は団体戦」 北高 「共に闘う仲間」
よく「受験は団体戦だ」と言いますが、私は浪人するまであまりピンと来ていませんでした。しかし浪人生の時はクラスメイトと相互添削をしたり、良い参考書を教え合ったり、と互いに切磋琢磨しあい、その言葉の意味がよく分かりました。共に同じ目標を持ち、足を引っ張り合うのではなく、高め合うことのできる仲間は私の宝物です。 一人ひとりの力はそれほどではないけれども、みんなで一つの目標に向かって取り組むと、すごい力を発揮するものだとして、「 受験は団体戦だ」 北高 東大・理Ⅰ 「 一人では妥協してしまうことでも、みんなで一緒にやるなら頑張りぬける。これが「受験は団体戦」の意味だと思う」 「 集団(組織)の力」 北高パワーの源泉 だということを、先輩の先生方から叩きこまれてきた八幡
▲男女総合優勝を祝う「総体報告集会」
松江 北高 県 総体 白地にスクールカラーのエンジ で「疾風迅雷」(しっぷうじんらい) エンジに白字 の「疾風迅雷」 北高 「文武両道」 県 総体 総体 「総体応援激励週間」 総体 松江市内 総体 文化部 総体 コロナ禍で数年間は全校で応援に出かけることが困難な時期もありました。これは仕方がありません。コロナも落ち着いた二年前に私が頭にきたのは、総体 「応援に行きたい生徒は行け、学校に残って自習したい者は学校で過ごす」 北高 「組織の力」 北高 北高 「組織の力」 「文武両道」 総体男女総合優勝 高校入試 松江市 北高 甲子園 総体 学校自体が休みになった そうです。やりたい者だけがやればいいということなんでしょう。これでは学校が一丸になることも期待できません。14位→12位→5位と今年は成績が良かったと喜んでおられますが、近隣の松江東高 松江南高
10年前に定年退職して、よんどころない事情から、常勤講師として復帰して一人でやった仕事が、この総体 「応援激励週間」 壮行式 報告集会 「全校生徒応援」 松江市役所 「解散点呼無事終了」 総体 総体 組織 「集団の力」 ♥♥♥
楽すれば 楽が邪魔して 楽ならず 楽せぬ楽が はるか楽々
◎週末はグルメ情報!!今週はおはぎ JR岡山駅 「おみやげ街道」 おはぎ 「ぬれおはぎ」 神戸 「朝日新聞」 「記憶に残る和菓子」 「おはぎ(ぼた餅)」 「ぼた餅」 たい焼き 桜餅 大福
広島県 「河岡食品」 おはぎ 「ぬれおはぎ」 「今あるおはぎよりおいしいおはぎを作ってみよう」 「ぬれおはぎ」 「瀬戸乃屋」 河岡食品 一般的な餡子に比べると甘めではありますが、非常にさらさらと流れるような水分量を湛えているので、いつまでも口の中に残らず思いのほかすっきり。豆の食感も適度な粒立ちを保っているのですが、蜜が染みているのでざらつきなどもありません。これは確かに、ごくりと喉を鳴らして飲めてしまいそうなあんこ。上からかけるという新しいタイプです。
▲いかにも美味しそうでしょ?
また、岡山県産の糯米はあんこの水分量を加味しているのか若干固めに炊き上げられているのでしょうね、あんこの下に隠れている部分でもべちゃべちゃにならず、もちもちというよりはふっくらとした食感と旨味が引き立つ素朴さです。噛みしめるたびに甘味がじわじわと滲むタイプの糯米もありますが、今回はあっさりとした糯米が確かに合いますね!通常のおはぎに比べ、小豆の粒粒感、さらりとした甘み、しっとり感すべてが違います。つつむ、ではなく、かけるという新しいタイプのおはぎです。実に美味しい!お土産候補に入れてみてはいかがでしょう。
おはぎ 松江市 おはぎ 「根っこや」 おはぎ みしまや ♥♥♥
BS-TBS 「ラーメンを食べる。」 「あの店のラーメンはなぜうまいのか?」 「食べる人に感動を与えたい」 BS-TBS 「郷愁の街角ラーメン」 八幡 コチラ のYouTubeで見ることができます。♥♥♥ VIDEO
今年のお正月の1月5日(日)には、この番組の新春3時間拡大スペシャルが放送されました。2025年注目のラーメン店を、芸能人やTRYラーメン大賞審査員、料理評論家、ラーメンライター、ラーメンユーチューバーに聞きました。番組が密着したのは「麺家たいせい」「塩そば時空」「ウチデノコヅチ」「味噌っ子ふっく」「お茶の水 大勝軒」 増田貴久(NEWS)、岡田紗佳、松村沙友理、ユンホ(ATEEZ)、菅田愛貴(超ときめき?宣伝部)
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
朗報です!!これまで不定期で放送されてきた番組が、ついに2025年4月5日(土)からレギュラー放送化されました。毎週土曜日BS-TBSで午後9時54分から10時24分までです(次週の土曜日午後5時30分から再放送)。ラーメン好きには堪らない番組です。4月12日(土)の放送では、ゲストとして元・乃木坂の生駒里奈(いこまりな) 生駒里奈 コチラ に書きました)。♥♥♥
広岡達朗さん(ひろおかたつろう、93歳) 『93歳まで錆(さ)びない生き方』(幻冬舎) 「せっかくこの世に生まれたのだから、愚痴や文句で人生を濁さず、積極的に生きたらいい」 中村天風 藤平光一 世の中全体が「今さえよければいい」「この場さえよければいい」「自分さえよければいい」という感じで、視野が極度に狭くなっています。そこはとても心配です。目先の利益に囚われたら、未来は危うくなりますから。これは天地自然の法則でしょう。プロ野球だけでなく、政治も経済界も、あらゆる世界でスケールが小さくなっているのを感じます。どうにかしないといけないと氣がかりです。 一年前に奥様が91歳でお亡くなりになり、都内で一人暮らしをしておられます。毎日、台所に立って料理をし、かむ力が弱くなってからは食物繊維やビタミンが豊富なリンゴをジュースにして飲みます。関節を動かす体操を欠かさず、加齢に合わせて自ら、飲酒も大好きな水風呂も辞めました。2度の脳梗塞も、風邪をひいた時も、体の状態を教えてくれたものと受け止めるといいます。「食べたくない時は五臓六腑(ろっぷ)が弱っているわけだから食べない。食べたくなるまで放っておく」
第2章の題は「野球が教えてくれた、大切なこと」。大成した指導者の原点は呉 「軍艦は沈むと全員が死ぬ運命共同体。ひとりが手を抜いたり、勝手なことをしたりすれば全体に影響する」 広岡 「根気よく教えれば人は必ず育つ」 「監督は勝つのが仕事。選手の指導はコーチに任せればいい」 「選手を育てて勝つこと」「コーチを育てる」 広岡 「指揮官先頭」 絶えず 氣を入れておられたことです。 氣を入れるためには、監督が目を光らせておくことです。本当は監督は選手と一緒に走らなければダメなのです。広岡 「地獄の伊東キャンプ」 長嶋茂雄監督 「おまえらの動きは全部わかっているぞ」 氣を出しておられました。 当時は選手たちから「管理野球」 「やるべきことをやる」 広岡 16人 も輩出しているのです。田淵幸一、東尾 修、森 繁和、石毛宏典、渡部久信、工藤公康、辻 発彦、秋山幸二、伊東 勤、田辺徳雄、大久保博元、若松 勉、大矢明彦、尾花高夫、田尾安志、マニエル 川上哲治 野村克也 星野仙一
著書にはもう二人、人生の師が登場します。巨人に入団後、知り合った思想家の中村天風 藤平光一 「『氣』はエネルギーが八方に広がる様子を表している。氣を出して積極的に生きるのが大切」 「93歳になっても分からないことが多い。だから人生は面白いのだと思う」 「何歳まで生きたいと考えることはない。世の中に必要なければ天国に召されるだろうし、必要であれば生かされるのだろう」 ♥♥♥
今は島根県 「受験は他人との戦いではなく自分との戦いです。自分に厳しくなってください。そうすればその苦しみが本番には自信となって現れてくると思うのです。 」
①問題集は1冊か2冊に絞り、それを何度も繰り返す。
②分からない所はそのままにしないで必ず先生あるいは友人に聞く。
③理・社を疎かにしない。やればやっただけ得点が上がるからです。
④授業を大切にする。私が受けた某女子大で授業でやったのと同じ問題が出題されたのです。ごくまれにそういうこともあるので。
実にいいことを言っています。ぜひ参考にしましょう。いつも授業で当てられて答えられないと、涙していた生徒でした。時の経つのは早いものです。以下は私のコメントです。
①最近もある県外の高校で、問題集や単語集はいろいろなものをやった方がいいですか、それとも1冊を繰り返した方がいいですか、という質問を受けました。私は「繰り返す!」 松江北高 7回 繰り返しました。受検した模擬試験も何度も繰り返して読み込みたいですね。当時は「模試は6回見直す」 コチラ です)
②私が松江北高 「ごめん、休み時間にまた来て」 北高
③特に地方の公立高校で難関大学を受ける人のネックとなるのは理科・社会の遅れです。教科書が秋にしか終わらないのですから、とうてい間に合いません。1・2年生で英・数・国を終わらせて、3年生では理・社に時間を取るように指導していました。
④現役時代は「1時間の授業を大切にしよう!」 ❤❤❤
米子帰りの電車の中で、なぜか無性に昔のアイドル・河合奈保子(かわいなおこ) 「UNバランス」 『HALF SHADOW』 奈保子 「エスカレーション」 売野雅勇・筒美京平 「UNバランス」 売野 売野 「デビュー~ Fly Me To Love」 「エスカレーション」 「UNバランス」 「UNバランス」
私は若い頃は、「 キャンディーズ」 スーちゃん 河合奈保子 「西条秀樹の妹募集オーディション決勝大会」 「大きな森の小さなお家」 「ピアノ、ギターには自信があります。珠算2級で暗算3級、マンドリンもこなせます」 「ハイッ、ハイッ」 「ヤング・ボーイ」 「日本レコード大賞新人賞」 「スマイルフォーミー」「エスカレーション」 島根県・出雲市・大社町 竹内まりや 「けんかをやめて」
奈保子 「UNバランス」 「アンバランスという英語は無く、imbalanceである」 unbalance (アンバランス)”という英単語があり、辞書にも載っています(“imbalance ”という単語も存在しますが)。「UNバランス」 unbalance ” に由来することは明らかでしょう。unbalance よりもimbalance の方が普通と思われます(『ジーニアス英和辞典』)。
イントロのコーラスですが、この部分、当初はシングルリリースされたものとは異なっていまして、「UNバランス ア・UNバランス…」 『Naoko Premium』ボックス 「UNBALANCE」 「UNバランス」 「UN UN ア・UNバランス…」
冒頭の「ルルルルル…」 奈保子 奈保子 「エスカレーション」 「UNバランス」 「エスカレーション」 奈保子
サビでの歌詞「愛しさは淋しさの別の名前ね」 「エスカレーション」 「恋しさはどこかしら苦しみめいて」 売野雅勇 「コントロール」 「エスカレーション」 河合奈保子 「UNバランス」 筒美 ♥♥♥
VIDEO
2012年1月、写真フィルム業界のあの巨人・コダック社
40年ほど前に起きた日本の富士フイルム (小文字の「フィルム」 「フイルム」 とイーストマン・コダック社 「フィルム戦争」 コダック 富士フイルム 富士フイルム 富士フイルム コダック コダック社 「利己」 「利他」 コダック社
コダック ジョージ・イーストマン イーストマン ジョージ ジョージ ヘンリー・ストロング 「イーストマン乾板」 「あの乾板は、一冬越したらまるで駄目になってしまった。あんな不完全なものを押しつけては困るじやないか。おかけでこのごろは、お客様から小言や苦情ばかり持ち込まれてえらい迷惑だ」 イーストマン 「これはいかん。こんな不完全なものを売っては、信用にかかかる。人間は信用が第一だ」 「不完全な製品のために多大なご迷惑をかけ、なんともお詫びのしようもありません。残品があったら原価で引き取りますから、全部ご返送ください。思うところがあって、一旦工場は閉鎖いたしますが、いずれ完全なる製品を作ってお目見えするつもりであります。その節には、是非倍旧のご援助をお願いいたします」 イーストマン ニューカッスル写真研究所 イーストマンコダック コダック イーストマン 「正直」 コダック コダック ジョージ 「KODAK」 KODAK イーストマン・コダック
ジョージ 「カメラを鉛筆並みの便利な道具に生まれ変わらせたい」 コダック コダック 「あなたはシャッターを押すだけ、あとは当社にお任せください」 「レーザーブレード戦略」 コダック コダック コダック コダック コダック
コダック コダック カシオ計算機 「QV-10」 コダック コダック 「フォトCD」 コダック コダック コダック 「フォトCD」 富士フイルム
写真フィルムは、かつて世界でわずか4社しか製造できなかった商品です。アメリカのコダック アグファ 富士フイルム コニカ
ドイツのアグファ コニカ ミノルタ 富士フイルム コダック コダック
実はコダック コダック
①好業績企業の傾向
デジタル写真ではそれほど利益が上がらないと考えていたからです。ここに好業績企業の陥る罠があります。 企業では、「現在フィルム事業で儲かっているのに、なぜ、利益の上がらないデジタル化の事業に手を伸ばす必要があるのか? 」 「70セントを稼ぎ出すフィルム事業を5セントしか稼ぎ出せないデジタル化事業に慌てて転換するのはベストではない!」
②イノベーターのジレンマ
優良企業は、既存の顧客や投資家のニーズを重視するが故に、評価がまだ未知の、リスクの大きい、効率の悪い新技術への投資に対しては消極的になりがちです。たとえ、将来的に大化けする可能性を有した技術であっても、顧客や投資家が望まない投資行動は排除する論理が優先されるのです。新技術は、当初、小規模市場から受け入れられるので、大企業や短期リターンを重視する投資家は、小規模市場が成長するまで待つことを嫌がり、そうした市場に参入したがりません。新技術が成長して既存技術を脅かす破壊的技術に変わった時、これをうまく取り込めなかった大規模な優良企業は市場から駆逐されていきます。 このような現象を「イノベーターのジレンマ」 コダック の対応も、このような現象の典型的な例でした。
③閉鎖的な企業環境・企業文化、自己満足の文化
銀塩写真の技術開発への積極的な投資、製造への厳密なアプローチ、そして、地域社会と良好な関係を維持して行きたいというコダック
それに対して、富士フイルム
①時代潮流の洞察と対応
富士フイルム
②危機意識
経営陣が日頃から時代潮流の洞察を的確に行っていたので、デジタル化に対しても深刻な危機意識を共有していました。デジタル化は経営方法を大きく変え、これまでの銀塩写真のような収益は上がらないことも覚悟していました。 こうした心の準備を事前に持っていたことによって、危機に際して迅速に構造改革の断行ができたと考えられます。
③社風・企業文化
富士フイルム “ コダックに追いつき追い越すこと ” 富士フイルム 富士フイルム
④企業ビジョン
経営トップが企業ビジョンを明確にし、機会を捉えて内外に明示しました。「21世紀を通じてリーディングカンパニーとして生き続ける」 富士フイルム 「Vision75」 「自分の会社がどのような方向に進もうとしているか」
以上のことから、両社のデジタル化への対応には、大きな差が生まれました。コダック 富士フイルム コダック コダック 「コダックに追いつき追い越せ」 富士フイルム コダック 富士フイルム 富士フイルム 富士フイルム コダック
このような先人たちのジレンマを知っておくだけでも、物事を客観的に考えるきっかけを与えてくれるのではないでしょうか。以上、一度大成功を収めた企業が、重要な戦略変換のタイミングで二の足を踏んで変わることができずに倒産してしまったパターンとして、コダック ♥♥♥
今日6月24日(火)は私にしては珍しくたまたま休みだったのでお昼時にテレビを見ていました。フジテレビ系の「ぽかぽか」 KiLa 「マジックにらめっこ」 ルービック・キューブ キューブ KiLa 6秒 で揃えると言って 回転し始めました。あ~、これはゲストが適当に混ぜた面と同じ面に揃えるマジックだなと直感しました。さてここでハプニングが起こります。揃うはずのキューブ 「本当にしくじったな、本当にしくじったぞ」 と、 結局面が揃わずギブアップです。ここで突然コマーシャルに切り替わりました。生放送の怖さです。番組の最後に、もう一度リベンジする機会をもらって見事にリカバーして、最後には片手で6面を揃えておられましたが顔面は蒼白でした。今年の1月にもこの番組で失敗されたKiLa KiLa
「全力教室」 KiLa KiLa KiLa 「チャレンジして失敗を恐れるよりも、何もしないことを恐れろ」(本田宗一郎)
そういえば、思い出すことがあります。あの大御所Mr.マリック さん 「アッコにおまかせ」 マリック 和田アキ子 「マリックさん、失敗したなら失敗したと言っていいんですよ! 」 Tomas Medina(トーマス・メディーナ) 「Cardiologist Deck」 マリック マリック
私にも似たような苦い経験があります。2018年6月16日(土)東京・市ヶ谷・TKPセンター 「成功の秘訣は二つしかない。それはコツ コツ だ」 「サイコロの透視」 「 1ですか?」―「違います」―「2ですか?」―「違います」・・・―「6ですか?」―「違います」 第一段階 です。私はコレに見事に失敗してしまいました。ごまかすのに一苦労です。講演終了後に先生からは、「 失敗とは思いませんでした。わざとやっておられるものと思っていました」 第二段階 の実験に挑みましたが、これにも失敗します。パニック状態で、最高難度のサイコロ3個(白・黒・赤) 第三段階 に進みましたが、動揺は隠せず、2個は当たったんですが、1個をハズしてしまいました。いつもはパーフェクトに成功するんですが、この時はある原因(?)のためにハズしてしまいました。猛反省です。後日、東京羽田国際線ターミナル5階にご勤務のテンヨー 清水 太田
松江 ラーンズ 「 リベンジ期待しています!」 土浦 「うん、これなら大丈夫!」 と、自信を持って講演会を始めました。初めての先生方を相手に(サクラではない!)、第一段階成功、第二段階も成功、第三段階はなんと「3―3―3」とぞろ目が出たんですが、これも見事に「透視」に成功しました!リベンジ大成功です!大きな拍手をいただきました。私のこの時の大きな目標はコレだったので、ホットしました。一体何をしに行っているんだ、と叱られそうですが〔笑〕、「 コツコツ」 「 やりっ放しにしない!」 「指導哲学」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はぶどうパン 松江市山代町 HOK山代店 「手造りパン工房」 松江南高校 大庭町 「HOK」 山代 「大きなレーズンのパン」(511円) ♥♥♥
▲美味しそうでしょ!?
▲エナジェルインフリー
「エナージェルインフリー」 ぺんてる ゲルインク・ボールペン 「インフリー(infree)」 エナージェル (1)インスピレーションが湧く、なめらかな書き心地 (2)汚れを気にせず、ストレスなく書き進められる速乾性 (3)想いをしっかり伝えられるクリアで鮮明な文字、筆跡
筆跡の速乾性汚れを気にせず、ストレスなく書き進められる速乾性も魅力です。
濃く鮮やかな筆跡想いをしっかり伝えられるクリアで鮮明な文字、筆跡も気に入っています。
“スッと書けて、サッと乾く”エナージェルインキ・高発色の着色剤配合
・筆記時の粘度が従来のゲルインキより低い
エナージェルインキ エナージェルインキ リフィル(替芯) 「ピンク」 松江市 八幡 ♥♥♥
私は40歳で若くして亡くなったZARD 坂井泉水(さかいいずみ) 東京都・町田市 「ZARD―坂井泉水 心に響くことば展」 コチラ をご覧ください)を堪能してきました。彼女の書く詞の世界には、人を惹きつける不思議な魅力があるんです。清純派で歌が上手いのも大好きな点です。
「SARD UNDERGROUND」(サード アンダーグラウンド) 神野友亜 杉岡泉美 坂本ひろ美 坂井泉水 ZARD ZARD 長戸大幸プロデューサー 「作品を後世に伝えて」 坂本ひろ美(さかもと・ひろみ) 島根県松江市 島根県立 松江商業高等学校 コチラ )。デビュー直後のインタビューで、「性格が違う3人が混ざることで私たちだけの色が出せるようになれたら」 「その化学反応によって生まれた色は?」 「私たちならではだと思うし、すべてがちょうどいい」 坂井 ▲松江商業高校卒業の坂本ひろ美さん
デビューを目指してレッスンを受けていた頃から、ZARD ZARD 「デビュー当時は何が自分たちに合うのか、何もわからない状況だった」 神野 杉岡泉美 坂本ひろ美 「坂井泉水さんの歌への想いと世界観を大切にしている」 「聞けば聞くほど、歌えば歌うほど、ここもすごい、あそこもすごい、と発見することが多いです。とくに最近、よく思うのは、声が唯一無二ということです。今回レコーディングして、改めて、どれだけ頑張っても自分には出せないな、と思いました。だから私は似せるのではなく、私が出せる自分のよい声を見つけて、『この人の声、めっちゃいいよね』って思ってもらえるように頑張りたいと思っています」 (神野)
ZARD 「下手だからやめろ!」「こんなの意味がない!」 「死ねっ!」 「こういう人もいるから頑張れるな」
松江市 坂本 、 「私は何か起きたときにも動じなくなったというか、受け入れる心が大きくなったような気がします。その分、周りを見られる余裕ができたというか、視野が広がって、感受性のアンテナが増えたように思います。キーボードに関しては、弾けば弾くほどできない部分が見えてくるので、悔しくて、欲が出てきています。自宅では自分で弾いたものを録音して聞いて、また弾いて、を繰り返しています。上手な方の演奏を聞くと、まだまだだなって思うことばかりなので、もっと突き詰めて行きたいと考えています」
ところがびっくりしました。昨年9月に初の全国ツアーを終えたSARD UNDERGROUND 杉岡 坂本 杉岡 「今までの5年間や、これからの5年の話をメンバーとしたり、今後の自分を想像する機会が増える中で、SARD UNDERGROUNDの杉岡泉美ではなくひとりの人間として普通の生活を送ってみたいと思うようになり、決心しました」 坂本 「5周年を迎え、10周年を想像したときに、ひとりの人としてどう生きていきたいか悩み、今回の決断をしました」 SARD UNDERGROUND 神野友亜 神野 「三人で過ごした日々はかけがえのない時間です。三人で掲げていた目標も、追い続けます。私自身も、もっと強い人間になれるように頑張ります」
<神野友亜 コメント> SARD UNDERGROUNDメンバーの、杉岡さん、坂本さんが脱退することになりました。ライブツアーを今まで通り全力で楽しむため、そして、皆さまにも変わらない気持ちで楽しんでほしいという想いから、急なご報告になってしまいました。驚かせてしまって、申し訳ありません。5周年というタイミングで、三人で話し合うことが増え、それぞれの将来を遠く見つめていく中で、杉岡さん、坂本さんの二人から、新たな道へ進んでみたいという言葉を受けました。私は歌手になることが幼い頃からの夢だったので、一人になってもやめるという選択肢は一度も浮かびませんでした。これからも全力で続けていきたいし、ZARDさんの楽曲も届け続けたいです。この先もずっと三人で頑張っていきたかった、三人で夢を叶えていきたかった。という気持ちはもちろんあります。でも、二人が決めた道なので、応援します。悲しい。寂しい。悔しい。という感情は、少しずつ、これからの活動の燃料に変えていきます。 三人で過ごした日々はかけがえのない時間です。三人で掲げていた目標も、追い続けます。私自身も、もっと強い人間になれるように頑張ります。これから二人の歩んでいく人生が、豊かな心と共に、愛に満ちた幸せな日々であることを心から願っています。本当にありがとうございました。私は、変わらずSARD UNDERGROUNDのボーカルとして、今の環境を大切に、多くの方を笑顔にできるアーティストを目指して、歌い続けたいです。応援してくださっているファンの皆さま、これからもよろしくお願いいたします。 <杉岡泉美 コメント> いつもSARD UNDERGROUNDを応援してくださっている皆様へ 急なご報告ではありますが、私、杉岡泉美はSARD UNDERGROUNDを脱退することを決めました。今までの5年間や、これからの5年の話をメンバーとしたり、今後の自分を想像する機会が増える中で、SARD UNDERGROUNDの杉岡泉美ではなくひとりの人間として普通の生活を送ってみたいと思うようになり、決心しました。 このような形になってしまい、応援してくださっている方々には申し訳ない気持ちでいっぱいです。友亜ちゃん、ろみさんと一緒にこれまで色々な経験ができ、イベントやライブなどで沢山の方々とお会いできたこと、私にとって大切な思い出です。応援してくださった皆様、関係者の皆様、そして何より、友亜ちゃん、ろみさん、本当に今までありがとうございました。これからも、友亜ちゃんが続けていくSARD UNDERGROUNDの応援を宜しくお願いいたします。 <坂本ひろ美 コメント> いつも応援してくださってるみなさま、関係者のみなさまへ この度私、坂本ひろ美は2024年9月30日をもってSARD UNDERGROUNDを脱退することとなりました。5周年を迎え、10周年を想像したときに、ひとりの人としてどう生きていきたいか悩み、今回の決断をしました。驚かせてしまい、悲しい思いをさせてしまい、本当にごめんなさい。何から伝えていいのかわからないくらいいろんな感情で溢れています…。この世界に飛び込んで、ZARDさんに出逢い、メンバーと出逢い、人生、想像もしてなかった経験をたくさんさせていただきました。そんな5年間を過ごせたのも、ファンの皆様のあたたかい応援、メンバーの存在、スタッフさんの支え、関わってくださったみなさまのおかげです。私にとって本当に夢のような、幸せな5年間でした。本当に、本当にありがとうございました。SARD UNDERGROUNDずっとずっと大好きです。そして、メンバー2人の大ファンです。 それぞれの道を温かく見守っていただけると嬉しいです。そしてSARD UNDERGROUNDのこれからの活躍を心から祈っています。みなさまに出逢えて本当によかったです。関わってくださった方の愛を忘れず、これからの人生を生きて行きます。これからも自分のペースで、ピアノを弾くことは続けていきたいので、またどこかでお会いできたら嬉しいです。みなさまにとって幸せな日々が過ごせますように…。 5年間はあっという間でしたが、とても濃い時間でした。初めは環境にも慣れず、目の前のことに必死でした。活動していくうちに多くの方と出会い「こんな私でも応援し続けてくれる人がいるんだ」とすごく力になりました。リリースイベントで直接お話しをする時間は、すごくパワーをもらいます。交流サイト(SNS)のメッセージもすごくうれしいです。そして、ライブはやっぱり楽しいです!あの大きな音が響き渡っている空間がたまらないです。昨年はやっと声も出すことができて、ファンの方との一体感がより感じられて、うれしかったです。メンバーや、スタッフさん、ファンの方と過ごしてきた5年間はとても貴重で、すごく幸せな時間で成長させてもらいました。 公式の発表はざっとこのようなものですが、グループバンドからの脱退にはいろいろとドロドロしたものが隠されているのがこの世界の通例です。社内で何かのゴタゴタがあったのではないかと推察している八幡 ♥♥♥
大学進学を目指す浪人生を指導していた、鳥取 県立倉吉東高校 専攻科 「倉吉鴨水館」(くらよしおうすいかん) 倉吉東高、鳥取東高、米子東高 「経営を圧迫する」 鳥取東高 倉吉東高 米子東高 「大学進学に挑戦したい子の学びの場をなくしてはならない」 倉吉東高 「倉吉鴨水館」 「 倉吉鴨水館」 県立倉吉東高校専攻科 「 倉吉鴨水館」 東京大学 京都大 「勝田ケ丘志学館」
▲米子東高校の同窓会館内にある「勝田ケ丘志学館」
鳥取県立米子東高等学校 「専攻科」 「官から民へ」 NPO法人「勝田ケ丘志学館」(かんだがおかしがくかん) 米子東高校 山根孝正(やまねたかまさ)館長 米子東高OB 山根館長 「日本海新聞」 「高校と同じリズムで通え、地域の仲間と支え合いながら目標に向かって進める環境が整う。質の高い授業も提供できる」 山根館長
▲勝田ケ丘志学館・山根孝正館長
1.県外予備校に比較して授業料、生活費等が低額で、家計の経済的負担が減少する。 2.高校時代と同じリズムで生活、学習できるため、規則正しい生活を送り安心して学習に打ち込むことができる。 3.現役時代と同様に複数の模擬試験を受験することができる。 4.高校在学中に指導を受けた先生にも気軽に相談できやすい。(米子東校出身者) 5.鳥取県西部地区出身者同士が切磋琢磨することで、連帯感や地域への感謝の気持ちが育まれる。 6.現役時に、部活動や探究的な学習、ボランティア活動その他様々な活動に取り組むとともに、より高い目標に向けてのチャレンジが可能となりうる。 7.現役生が、受験に向けて真摯に取り組む補習科生の姿勢から多くを学ぶことができる。 8.自宅浪人生の模擬試験受験が補習科において可能となる。 9.単位制を活用しての授業の受講が可能であることから、在校生、補習科生ともに刺激し合うことができる。 10.高校教員が補習科で行われる高いレベルの講義を参観することができ、これにより教員の力量の向上が図られる。 11.鳥取県西部地区出身者が、浪人生活という人生の中で苦しい一時期を、仲間とともに支え合いながら苦楽を共にし、また切磋琢磨しながら、地域や同窓生、家族のもとで学ぶことにより、進学後ふるさとを離れても感謝の念を持ち続けてくれることが期待できる。 かつて、代々木ゼミナール 藤井健志(ふじいたけし)先生 鳥取大学 「現代社会では、経済的格差や社会的孤立の広がりの中で、様々な形で社会的に排除された人々が生み出されている。そこで、地域社会において実際に生じている社会的排除の事例をひとつ取り上げるとともに、その問題の克服に向けて求められる社会的包摂のあり方について論じなさい。(800字以内)」 『代ゼミ新小論文ノート2020』(代々木ゼミナール、2019年7月) 「勝田ケ丘志学館」
(中略) このような問題の克服のヒントになるのがこの春から鳥取県に開学した「校内予備校」だ。自分の財を原資にしてでもという情熱を持った元教員を中心に協力者や寄付金を募り、県立米子東高校敷地内の同窓会館を利用して、地域の高卒生ならば誰でも学べる、画期的な学びの場を創り出したという事例だ。隣県島根県の教員OBの方々も協力することになったらしい。一つの高校の同窓会やPTAが主体になりながらもその枠組みに縛られず、都道府県の境さえも越えて連帯するかたちは行政に押し付けられるのとは違う新しい公共の姿である。官・民といった区別を越えて地域の人間が共に主体となって考え、行動するところにこそ、特定の人間を排除することのない重層的で懐の深い社会的包摂が実現するのだと私は考える。 地元紙でも大きく取り上げていただきました(写真下)。
▲「日本海新聞」2022年11月10日付
▲「山陰中央新報」2023年3月15日付
今年の「勝田ケ丘志学館」 米子東 米子西 米子北 境 米子松蔭 ♥♥♥
最近、私が勝田ケ丘志学館 「Festīnā lentē.」 「ゆっくり急げ」 「フェスティナ・レンテ」 「ゆっくり急げ」 「急がば回れ」 アウグストゥス のスエートーニウス アウグストゥス 「Festīnā lentē.」 スエートニウス アウグストゥス 「大胆な指揮官より慎重な指揮官がまし」 「立派にできたことは十分早くできたこと」
最近、この言葉が意外な形で注目を浴びました。アメリカに2度目の関税交渉に出かけた赤沢経済再生担当大臣 「ある自動車メーカーのトップに話を聞くと、1時間に100万ドルずつ損をしていっている状況ですと。今、輸出すればしただけ損が出ますと。ゆっくり急ぐ ということをやらなきゃいけないと思っています」 石破茂首相 トランプ 「ゆっくり急ぐ」 「これは『名言』と言えば『名言』なのだが、『ゆっくり急ぐ』ということなのであって早ければ良いというものではない」
私の学生時代の恩師の故・安藤貞雄(あんどうさだお)教授 開拓社 安藤先生 『【新装版】基礎と完成 新英文法』
京都大学 田中秀央博士 ケーベル先生 田中先生 ケーベル先生 「フェスティナ・レンテ」 外山滋比古先生 『人生を愉しむ知的時間術~“いそがば回れの生き方論』(PHP文庫) 田中博士 研究社出版部 「フェスティナ・レンテ」 田中先生 「ゆっくり」とは、スピードを落とすこと。「急ぐ」とは、スピードをあげること。速くすることと、遅くすることは正反対の動きですから、一見矛盾しているように聞こえます。でも、実は、両者をうまく組み合わせるところに意味があるのです。ほどよい速さで着実に進むことで、また、途切れなく、毎日続けることでもあります。ものごとは、気持ちがあせると、身体の動きが鈍くなります。意識しすぎると、かえって、バランスがくずれてしまうのですね。長い目で見て、よりよい結果をもたらすためには、いっぺんにたくさんやろうとせずに、少しずつ、コンスタントに、進むこと。何かに到達するには、道の途中で疲れてしまわないように、自分をケアすることが必須条件になります。とは言うものの、「ほどよい速さ」とは何でしょうか?それは、何も考えなくても、いつも同じようにできるスピードのことです。つまり、いつも同じようにできる、続けられるような調子で、ということ。「いつも同じようにできる」ためには、鍛錬が要ります。
現代の私たちは、「急がなくちゃ」
世界中のことわざを集めた本を見ると、昔から、急ぎ、慌ててはいけないことに先人たちは気が付いていたことがよく分かります(下記参照)。時代と社会を超えて、その概念は世界で見事に一致しているのは驚くべきことですね。
急がばまわれ(日本)
ゆっくり行くことを怖れるな(中国)
ゆっくり行くものが遠くまで行く(イタリア)
急ぐなら、もっとゆっくりせよ(イギリス)
急いで行こうと思ったら古い道を行け(タイ)
ゆっくり行くものは確実に行く(フランス)
おそくても、ぜんぜんしないよりはよい(ドイツ)
急げば急ぐほど、まずくゆく(フランス) 外山先生 「田舎の学問より京の昼寝」 「田舎で勉強してもたかが知れているが、都はただそこにいるだけで見聞を広める材料がたくさんあるので知識が身につくということ」 「ゆっくり急げ」(フェスティナ・レンテ) 「一本調子ではなく緩急のリズムをつけることが、生活には大事である」 「よく学び、よく遊べ」(←All work and no play makes Jack a dull boy.)
あの文豪・森 鷗外 「フェスティナ・レンテ」 ♥♥♥
本多静六(ほんだせいろく)先生 東京山林学校 東京帝国大学農学部教授
若い頃、故・渡部昇一先生(上智大学名誉教授) 本多静六『私の財産告白』 本多先生 「これまでもたくさん本を書いてきたが、それらとはまったく異なった本を書く」 本多先生 「今ここに長い過去を省みて、世の中には余りにも多くの虚偽と欺瞞とご体裁が満ち満ちているのに驚かされる。私とてもまた、その世界に生きてきた一偽善生活者の一人で、今さらながら慙愧の感が深い。しかし、人間は八十五の甲羅を経たとなると、そうそう嘘偽りの世の中に同調ばかりもしておられない。偽善乃至偽悪の目をかなぐり捨てて真実を語り、本当の話をしなければならない。これが世のため人のためにもなり、それが我々老人相応の役目であると考える」 本多先生 「特に財産や金儲けの話になると、今までの社会通念においては、いかにも金儲けの話は心事陋劣のように思われ易いので、本人の口から正直なことは言えないものであるけれども、金の世の中に生きて金に一生苦労し続けるものが多い世の中に、金について真実を語るのが少ないのも、皆にそう思われるからである。しかし、やはり財産や金についての本当のところは、世渡りの真実を語るには必要欠くべがらざるものであるから、もっとも大切な点をぼんやりさせておいて所謂処世の要訣を説こうなどというのは、およそ矛盾である」 『私の財産告白』 本多先生 渡部先生
私がとても参考になったのは、収入の「4分の1」
貯金 = 通常収入×(4分の1)+ 臨時収入×(10分の10) 収入の4分の1は有無を言わさず貯蓄し、残り4分の3で生活するのは、もちろんたやすいことではありませんし、最初は大変です。しかし本多先生 「手かせと足かせ」 「はじめから4分の3のお金で暮らすのだと思えば、苦しくも何ともない」
お金を蓄えようとすると、ともすればケチと言われます。しかし、お金が貯まり実力がつけば、ケチと言われた人でも気前のいい人に変じます。逆に気前がいいと言われ、一生ピーピーで過ごす人もいます。本多先生 本多先生 「貧乏などは一時のものである。蓄財を心がければあれこれ言われるが、そんなことには耳を貸すな」 「 目をつむり腰をかがめて一目散に走り抜ければ、目先の煙に巻かれてまごつくようなことにはならず、そこを突破して弾みがつく生活になる」「金を馬鹿にする者は金に馬鹿にされる。財産を無視する者は財産権を認める社会に無視される」 本多先生 本多先生 日比谷公園、明治神宮、大沼公園、羊山公園、大濠公園 本多奨学金 本多先生 本多奨学金 本多先生 本多先生 本多先生 『私の財産告白』 本多先生 「人生即努力。努力即幸福」
定年退職時には、夫婦二人で老後を暮らせるだけの財産以外の、蓄えた富の多くを国立公園運動など公共のために寄付したのです。山林の大部分もその収益を育英基金 埼玉県 正金銀行 南満州鉄道 本多先生 「一国民として国家が潰れることなど予見しようもない。ジタバタしても仕方がない」
もう一つ、本多先生 「一日一ページ分(三十二字詰十四行)以上の文章、それも著述原稿として印刷価値のあるものを毎日必ず書き続ける」 「一日三ページ」 本多先生 「雪達磨の芯」(ゆきだるまのしん) ♥♥♥
とにかく、金というものは雪達磨のようなもので、初めはホンの小さな玉でも、その中心になる玉ができると、あとは面白いように大きくなってくる。少なくとも、四分の一天引き貯金で始めた私の場合はそうであった。これはおそらくだれがやっても同じことであろう。 (『私の財産告白』〈新装版〉)
さだまさし 「精霊流し」、「無縁坂」、 「雨やどり」、「案山子」、「関白宣言」、「風に立つライオン」 「HAPPY BIRTHDAY」
「HAPPY BIRTHDAY」 「道化師のソネット」(1980年) 『なぜか初恋・南風』 森光子
Happy Birthday 作詩・作曲 さだまさし
誰にだってひとつやふたつ 心に開かずの部屋がある 一生懸命生きているのに 傷を恥じる事などないさ
雨が降る日に気になるものは 雲の大きさばかりだけれど 空の広さに比べれば 別に大した事じゃない だから
HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY 昨日までの君は死にました おめでとう おめでとう 明日からの君の方が 僕は好きです おめでとう
幸せなんて言葉もあるが ひとそれぞれに坪が違う 人はひとだしあんたはあんた一生懸命生きているのに 別に張り合う事などないさ 雨が降る日派天気が悪い 雲には雲の行き先がある 空は確かに広いけれど 心の広さと比べてみるかい だからHAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY 昨日までの君は死にました おめでとう おめでとう 明日からの君の方が 僕は好きです おめでとう
VIDEO
明るい曲調のハッピーソングのように聞こえますが、歌詩の中にはドキッとするフレーズが出てきます。誕生日なのに「昨日までの君は死にました おめでとう おめでとう」 「やっぱりさだまさしは暗い!」
誰でも人生は思うようにはいきません。人を傷つけることもあれば、傷つけられることもあります。このままの自分でいいのかと真剣に悩むこともあるでしょう。しかし、それは昨日までの自分であって、昨日までの自分は実はもう過去の存在であってもういません。今新しく生まれたと思えばいいのです。明日からは違うあなたの人生が始まるのだ、という人生の応援歌なのです。そうか、これまでの自分から新しい自分に生まれ変わればいいのか。生まれ変わるなら、もう今までのことをあれこれと悩む必要はない。過去から解き放たれればいいのか、と。だからこその「死にました」 「HAPPY BIRTHDAY おめでとう」
松本秀男(まつもとひでお) さだ さだ さだ 音大附属高校 法学部 質屋 「いじめ」 さだ さだ 松本
ちなみに、NON STYLE 石田 さだまさし ♥♥♥
学生時代に、故・安藤貞雄(あんどうさだお)先生 「Yes!」「No!」「?」 「あ~そうか、本というのはこんな風に読むものなのだな」 松江 八幡家
渡部先生 赤線 を引きます。次に、もっと感心した箇所には線を引いた上に丸印 をつけます。さらに感心したらこの丸印を二重丸 にします。圧倒的に感服した場合は三重丸 。また、読んでいて疑問を感じたところには、疑問符 を書いておくのもいいかも知れません。あるいは、自分が関心を抱いている問題について特に重要だと思うことが出てきたら、本の表紙の裹などの余白に、そのページ数とテーマをメモ しておくのも役に立ちます。例えば、森 鷗外 「鷗外○○ページ」 「確か、あの本に書いてあったな」 「自分の知的財産とはなり得なかったのだ。まあ、仕方あるまい」 三段階渡部式読書法 自分の本を買って、重要だと思われる部分に線を引き、メモを記入し、それを自分の蔵書としておけば、何かの機会に「あの本ではどうだったか」と疑問が湧いた時、書棚に行ってページを繰るだけで、自分が考えていたことが生き生きとよみがえってきます。自分自身による、自分自身のための、かけがえのない思考の蓄積になるのである。そのような本を揃えていけば、それは自分にとっての最良の「書庫」となり、その場所が自分にとって最高に居心地の良い「書斎」になります。自分自身の思考の蓄積が、目に見えるかたちですぐ手に届く場所にあることは、便利なことこのうえないし、成果も一望できて気分もよい。自分の関心を中心に据えて書庫を充実させていけば、六畳一間、八畳一間でも十分に威力を発揮するのです。
▲先生の名言のエッセンスが満載の一冊!!
渡部昇一先生 『渡部昇一一日一言』(致知出版、2016年) 「読書が人を強くする」 ♥♥♥
絶えず本を読むことです。人生について書かれたものや、成功談というのは、やはりその人の長い人生での経験がつまっているものですから、それらに接している人はやはり他の人とは違ってくる。それは、立身出世主義だとかあるいはお説教じみているとか、道徳臭いとか何とか、悪口をいう人はいっぱいいる。だけど、心掛けて、そういったものを読み続けた人というのは、やはり何かの時には強いと思います。
今日は、私が毎日使っているホッチキス stapler(ステイプラー) 伊藤喜商店(現イトーキ) E.ホッチキス社 「HOTCHKISS No.1 」 ベンジャミン・B・ホッチキス E.H.ホッチキス社 ジョージ(George Hotchikiss) イーライ・ハベル(Eli Hubbell Hotchkiss) ベンジャミン・ホッチキス
昔ながらの、金具の裏側が山なりになるあれ、あのタイプを使い続けている人も多いんじゃないでしょうか。私の勤務していた松江北高 ホッチキス でも、事務をする人ならもう十分お分かりだと思いますが、冊子を作ったりした時、冊子を止める針の部分だけページが盛り上がります。部数の少ないときには気が付きませんが、50部とか作ると、置く場所にも困るくらい、留め具の部分が盛り上がってきます。ひどい時には積み重ねた書類の雪崩が起きます〔笑〕。 当時私は、「フラットクリンチ」 フラットクリンチ」 「フラットクリンチ」 「フラットクリンチ」 1.マガジンに装填された針が、バネの力によって前方に押し出される。 2.先頭の針がドライバーによって紙に打ち込まれる。 3.紙を通過した針は、クリンチャガイドに沿って最後まで打ち込まれる。 4.最後まで打ち込まれた針は、クリンチャの溝に沿って曲げられ押し上げられる。 ホッチキス 「クリンチャガイド」 「フラットクリンチ」 「フラットクリンチ」 「(株)MAX(マックス)」 「重ねた書類がかさばるので、ホッチキスの裏をかなづちで潰している」 「フラットクリンチ」 まあこれでも金具の厚み分は少しは盛り上がるんですよ。でも、従来品よりはだいぶマシです。 「フラットクリンチ」 「フラットクリンチ」 「フラットクリンチ」
▲「バイモ11」(マックス)
「文房具の八ちゃん」 「バイモ11」(マックス) ホッチキス 大きさです。 色もオシャレで選択肢が広がります。私はもっぱらブルーを愛用しています(写真上)。この「バイモ11」 「バイモ→倍も」「11→ホッチキスの針のサイズ」 ホッチキス 力がいるので手が疲れたりしていましたが、 これは片手で簡単に、しかも綺麗に綴じられます。綴じた 瞬間のパチンという音と感触が実に気持ちいい! 失敗知らずなのもうれしいです。軽綴じ仕様です。 簡単に40枚綴じることができました。 これなら大量の資料のホッチキス留めなども ストレスを感じることなくできそうな気がします。本当に軽い力でたくさん綴じることができます。厚みのあるものだけでなく、厚みのない2枚綴じでもキレイにしっかりと綴じてくれます。
▲窓から残った針の数が見える、これ便利!
ねえ!これ、気がつきましたか?針 の残り本数が横の窓から見えるようになっているんです。芯の残量メーター、「針残量確認窓」 これなら作業する前にチェックして、残りが少なかったら 足してから作業すれば途中でなくなっちゃうこともなくて 便利ですよね。 それに、裏を見ると、 針のサイズが確認できるように実寸の溝までついています。 こういう細かい心遣いって結構嬉しいものですよね。 使う人のことをよく考えて作っているという感じがします。みんなに好評だった「バイモ11スタイル」 バイモ 「バイモ11フラット」 どちらのバイモも「てこの力」で格段にかろやかな「綴じ感」を実現しています。 「バイモ11」 「バイモ11」 本体の大きさ、留める時の力はこれまでのものとほとんど変わりません。その上で40枚まで一気に留められる。これは意外と便利です。私も日常的には2~5枚程度を留めることがほとんどなんですが、たまに30枚とかの冊子を作ることがあります。そういう時にいちいち中型ステープラーを探さなくてもよい。これはずいぶん助かります。さらに芯を補填するために、本体を開けた際にロックがかかるようになっているので、安心して100本の針を装填することができます。 (株)マックス 「Vaimo11」 「Vaimo11 POLYGO」(バイモイレブンポリゴ) 「東急ハンズ」 「Vaimo11」 「No.11」 私は商売柄、たくさんの書類を綴じることが多いんです。この商品が出るまでは、分厚い書類を綴じる場合は、「卓上ホッチキス」 「No.3」 「Vaimo11」 「No.11」 「No.10」 「No.10」 「No.3」
「Vaimo11 Polygo」 50本 にまで減らすことによって、さらに小型化を図り、軽量化を実現しました(写真右)。小さい手にも収まり、使いやすくなっています。同シリーズの専用針は直径が細く、紙の抵抗が少なくなるため軽い力で留めたり外したりできるほか、仕上がりの見栄えもよいのです。綴じ裏は針が平らになり折り返しに膨らみの出ない 、例の「フラットクリンチ機構」 「針残量確認窓」 「針押さえ付きリムーバー」 「バイモ11」 何と言っても、手のひらサイズなのに40枚も綴じられるのが最大の魅力ですね。手や針に余計な負担がかからないよう、細部の仕掛けにこだわっており、想像以上の綴じの軽さを実現しています。「ガシャーン!」という衝撃を、「サクリ」という感触に転化させた点が評価されます。綴じの軽さと安定感はナンバーワンでしょう。いまだに昔のホッチキス 。ホッチキス ❤❤ ❤ ①軽綴じ機能で薄いも厚いもブレずにきれいに綴じられる ②サイズ感がコンパクトで握りやすい ③針押さえリムーバーで安全に使える ④残量メーターが分かりやすくて便利 ⑤大きく開いてらくちん針入れができる ⑥フラットクリンチで重ねてスッキリ
『鉄道ジャーナル』 『鉄道ピクトリアル』『鉄道ファン』 『鉄道ジャーナル』(成美堂出版) 「産経新聞」 『鉄道ジャーナル』 『鉄道ジャーナル』 休刊に関して、発行元の鉄道ジャーナル社 「長年にわたり支えてくださったみなさま、ご寄稿いただいた執筆者のみなさま、制作にご協力いただいた関係の方々に御礼申し上げるとともに、今後もご購読を予定されていた読者のみなさまには心よりお詫び申し上げます。」 『鉄道ジャーナル』 宮原正和編集長 「雑誌の休刊というと、売れ行き不振を理由に挙げることが多いですが、鉄道ジャーナルに関してはそういったことではなく、端的に説明することは難しいと感じています」「近年の鉄道ジャーナルは、ほかの媒体ではなかなか扱わないようなテーマや、ほかでは読めないような記事を載せていきたいと考えてきたのですが、伝統的な鉄道記事を愛する読者が想像以上に多かったということかもしれません」
近年の雑誌業界を取り巻く環境は、電子媒体の普及と併せ、読者層の変化、出版コストの増加など、逆風となる数々の厳しい要因を抱えています。その一方で、鉄道ファンの衰退を指摘する声もあります。2010年の「日本経済新聞」 野村総合研究所 「青春18きっぷ」 “乗り鉄” JR北海道 キハ285系 「寝台特急サンライズ出雲・瀬戸」 ユーチューバー
鉄道業界は近年、人気路線の減少や運行の効率化が進み、鉄道ファンの数も減少しています。特に新幹線の普及や高速道路の整備により、以前ほど鉄道に対する関心が高くなくなったことも影響しているのかもしれません。『鉄道ジャーナル』
『鉄道ジャーナル』
私が大好きでよくお邪魔する「京都鉄道博物館」 本館3Fギャラリー 写真展「『鉄道ジャーナル』一番すきな表紙を選ぼう」 『鉄道ジャーナル』 全704号分 をタペストリーで壁一面に展示しています。♥♥♥
「ミスタープロ野球」 巨人軍終身名誉監督 長嶋茂雄(ながしま・しげお) 「監督が心臓を動かそうとしている振動なんだと思います。私、こんなの見たことありません」 長嶋
▲東京ドームの長嶋茂雄レリーフ
現役時代に巨人で長嶋 広岡達朗(93歳) 「とにかくいいやつで、どこかに傷がつくような人間ではなかった」 長嶋 「素晴らしい才能だった」 長嶋 「今日は動けない」 広岡 「普通の人は動けない理由をあれこれ言ってくるものだけれど、あいつは余計なことは言わなかった」 長嶋 。 「何でも正直でね。本当に純粋な男だったね」 「長嶋の人間性を一言で言えば、正直で野球の能力にたけた『野球バカ』。一緒にプレーしたのは4年間でしたが、私にとっても勉強させてもらった。来た球は直角で捕るし、球際にめっぽう強かった。私の守備範囲の球まで捕るので「かっさらう」という人もいたけど、動ける選手が捕ればいい」
私の大好きなシンガー・ソングライターのさだまさし(73歳) 長嶋監督 長嶋 「太陽没す 長嶋さんは太陽でした。野球愛の根源でした。いつも優しく明るく照らしてくれました。誰へも分けへだて無く。野球を愛し野球に愛された人です。永遠に輝き続けます」 「何より自分のプレーは絶対に手を抜かないこと、結果はともかく一所懸命やることを教わりました。子供の頃からずっと勇気をいただきました」 「長嶋さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。合掌 さだまさし」
長嶋 桑田真澄2軍監督(57歳) 「プロ野球選手として大事なのは結果を残すこと、ファンサービス、メディアサービス。そういったことを体現し、身をもって教えていただいた」 「10・8」 長嶋監督 「『監督、試合自体がしびれるんですけど、どれぐらいで用意しておけばいいですか?』と聞いても、『しびれるところで』と」 槇原 斎藤 長嶋 「やれないとプロとして一流とは言えないんだよという話は、長嶋さんから学んで若い選手に伝えているところ」
巨人・長嶋茂雄終身名誉監督 松井秀喜 松井 「長嶋監督と生前に約束したこともあります。今はお話しすることはできませんが、その約束を果たしたいなと思います」 松井 「将来的な現場復帰を志す声なのでは」 松井
長嶋 迷言 も残しておられます。「失敗は成功のマザー」「勝負は家に帰って風呂に入るまでわかりませんよ」 I live in Tokyo. I live in Edo . 「肉離れ」 「ミートグッバイ」 松井秀喜 「松井君にはもっとオーロラ を出して欲しい」 「初めての還暦を迎えまして…」 「僕は文化勲章より世界遺産を狙っていたんだけどね」 長嶋 「セコム」 「セコムしてますか」 長嶋 「ミスター、セコムしてなかった」 「ええ、泥棒さんがお見えになりまして」 〔笑〕。
人間的な魅力はさておくとして、監督としては天才肌の人だけになかなかついていくのが難しかったと想像します。「パッと捕って、ビュっと投げる」 「来た球を打つ。あるがまま、なすがままの境地ですよ」 落合博満 「ピッチャーの配球を読んで打つなんて二流半のやることですよ」 「配球を読む」 野村克也監督 長嶋 「来た球を打つ」 長嶋 ガルベス投手 長嶋 「けじめをつけるんだ」
高校(甲府商業高)を卒業したばかりの18歳が開幕から13連勝と勝ち続けたのは、1965年の第1回ドラフトで巨人から1位指名された、堀内恒夫 「ボウヤ、いいぞ、ナイスピッチング!」 長嶋 堀内 「悪太郎」 長嶋 「新聞記者たちが、堀内は生意気だと長嶋さんに言ったらしい。その時、『まだまだ子供じゃないですか。大人の振る舞いはボウヤにはわかるわけないですよ』って、かばってくれたんだ」 「堀内」 川上哲治監督 堀内 川上 「仲人、やめる」 長嶋 川上監督 長嶋監督 「堀内をトレードに出せ」 堀内 長嶋 『堀内を出すわけがない』 堀内 康史(やすふみ) 康史 長嶋
徳光和夫 「プロ野球レジェン堂」 堀内 長嶋 堀内 「おい堀内、頑張れよ」 堀内 長嶋 「何してんだ、お前?」 「サイン出したじゃないですか?」 「いや、頑張れと言っただけだ」 堀内 「サインをよく見ろ!」 堀内
長嶋 柴田 勲 「おい、柴田、人間の理想の死に方って知ってるか?」 「考えたことないです、長嶋さんにはあるんですか?」 「うん、ある。晩年になった時に、縁側でコタツに入って、ひなたぼっこをこをしながら、みかんを食べる。食べ終わったらスヤスヤと眠るがごとく、そのまま逝く。それだよ」 三奈 長嶋 チヨ 長嶋 柴田 「予言者・長嶋」 柴田 長嶋 長嶋
13年ぶりに読売ジャイアンツの監督に復帰した1993年に、日本テレビ系巨人戦中継テーマソングの「果てしない夢を」 長嶋 ZARD 坂井泉水 WANDS 上杉 昇 ZYYG REV ビーイング 長嶋 ♥♥♥
VIDEO
今大きな話題になっているハーバード大学 「アイビーリーグ」 ジョン・ハーバード
アメリカのトランプ ハーバード大学 トランプ大統領 コロンビア大学 「ユダヤ系学生への嫌がらせに対応せず、高等教育機関の認定基準を満たしていない」 ハーバード大学 コロンビア大学 ハーバード大学 トランプ トランプ トランプ大統領 「ハーバード大学が政治的やイデオロギー的で、テロリストを支援する“病気”のような行為を推し進めるのであれば非課税資格を失い、政治団体として課税されるべきかもしれない 」 トランプ ハーバード大学 「政権が教育内容や教職員、学生への違法な統制を押しつけようとしている」 ハーバード大学 アラン・ガーバー学長 「全米の留学生にとっても深刻な警告だ」
ハーバード大学 トランプ オバマ元大統領 「ハーバード大学はほかの高等教育機関にとっての手本を示した」 「ハーバード大学は学問の自由を抑制しようとする不法で強引な試みを拒否した」 トランプ 「知的探求や徹底した討論、そして相互尊重の環境からすべての学生が利益を得られるよう具体的な措置をとった。ほかの機関もこれに続くことを期待しよう」 ハーバード大学 スタンフォード大学 「ハーバード大学が異議を唱えたのはアメリカの自由の伝統に基づいた行動で、この伝統は私たちの大学に必要不可欠で守る価値があるものだ」 ハーバード大学 プリンストン大学 ハーバード大学 「プリンストン大学はハーバード大学と共にある。力強い文書の全文を読むよう皆さんにすすめる」
一方、政権側は、パレスチナ自治区ガザ情勢を受けた学生の抗議活動を巡り、反ユダヤ主義への対応が不十分だとして、「反ユダヤ主義対策」の名目で大学の学内統制の強化を進めようとしています。大学側はこれを「表現の自由の侵害だ」として断固反対しており、双方の主張は平行線をたどっています。政権は4月以降、同大に対する補助金の凍結を段階的に進め、凍結額は22億ドル(約3,200億円)近くに達しました。
政権は、アイビーリーグ ハーバード大学 「譲歩の余地はない」
私たちの 『ライトハウス英和辞典』(研究社) D.ボリンジャー博士(D.Bolinger) ハーバード大学 松江北高 大谷はんな ハーバード大学大学院修士課程 松江北高生 アメリカ研修 ハーバード大学 ハーバード大学
エリック・シーガル(Eric Segal) 『ある愛の詩(ラブストーリー)』 ハーバード大学 「愛とは決して後悔しないこと」 エリック・シーガル シーガル ♥♥♥
皆さんは、プリンターのインクカートリッジを、純正品 互換インク=非純正品 純正品 エプソン、キヤノン 「純正品」 「非純正品」(=互換インク) キヤノン製 インクジェットプリンター レーザープリンター 純正品 非純正=互換インク 「大丈夫か?」「トラブルとか起きないかな?」 純正品
それもそのはず、巷では、「非純正品を使うとプリンターが故障する」「プリンターがインクを正しく認識してくれない」「互換インクはすぐにインクがなくなる」 「トラブル続出」 非純正品 互換インク
ここで、純正品・非純正品
【純正品のメリット】
●公式の商品だという安心感がある。
【純正品のデメリット】
●値段が高い。(それこそ数回分で安いプリンターなら1台買えてしまう)そう、純正品
【非純正品(互換インク)のメリット】 ●値段が安い。
【非純正品(互換インク)のデメリット】 ●品質が悪い可能性がある(場合によっては印字できないことも?)
まず起こりうるプリンターの不具合を考えてみると、次のようなものが挙げられるでしょう。
1.インクが出ない(途中で出なくなる)。
2.プリンターが認識してくれない(途中からインクを認識しなくなる)。
3.綺麗に印刷できない(かすれ等がある)。
4.プリンターが故障する(動かなくなる)。
といったケースが考えられます。本当にこんなことが頻繁に起きるであれば、非純正品(互換インク) 「不良品率」 互換インクカートリッジ 「正常稼働率99.9%」 非純正(互換)インク 「正しく商品を選べば、非純正品(互換インク)を買って使用しても問題なし、大丈夫」
1.懸念されるようなリスクはほとんど発生しないから。
2.万が一発生したとしてもたいした問題ではないから
安く買った非純正品 純正品 互換インク 「ジェネリック品」
キヤノンプリンター 黒インク 互換インク 「 ヤマダ電機」 「 エディオン」 「 イナイ」 純正品 マゼンタ 純正品 「インクを認識できません」 「インクを認識できません」 ♥♥♥
▲互換インク、マゼンタの爪が折れてしまった!
イギリスでの銀行スキャンダルを報じたレポーターが、次のように言っていたのを面白いと思って、すぐにメモしておいたのはもうずいぶん前のことでした。オヤッ?と思ったのですが、当時は、そして現在も、辞書への収録を見たことはありません。
This was comfortably
どう考えてもcrisis(危機) がcomfortably(快適に) Comfortably comfortably Comfortably the worst と共起することが多いことが分かりました。ある状況や物事がその分野で最も悪い、確実に最悪、間違いなく最悪といったニュアンスで、強い確信や自信を持っていることを示します。このように、英語の副詞 副詞 コチラ )。
comfortably the worst というフレーズは、通常、何かが非常に悪い状態であることを表現する際に使われます。他の選択肢や競争相手よりも圧倒的に最悪であることを強調する表現です。直訳すると「快適に最悪な」という意味になりますが、ここでのcomfortably 「余裕で」「際立って」 ●非常に悪い状態: 特定の状況や物事が非常にひどい状態であることを強調する言葉です。例えば、ある商品が「comfortably the worst 」だと言われると、その商品は非常に悪い品質であることを指します。「この小説は私が過去に読んだ中でcomfortably the worst の部類に入る」と言えば、中でも最悪な部類だと言っているのです。対象が最悪であることに対して、何の疑いもなく、他のどの例よりも悪いと断言しているのです。●比較的に他よりもひどい: 「comfortably」 「最悪な状態でありながら他よりも悪さが際立っている」 ●完全に他を凌駕して最悪である: 他の選択肢や競争相手よりも、顕著に最悪であることを指します。例えば、競技の中で「comfortably the worst 」と言われる選手は、他の選手と比べて著しく成績が悪いことを意味します。このフレーズは、文脈によっては軽い冗談や皮肉やユーモアの要素が含まれることもありますが、基本的にはその物事が他に比べて明らかに最悪であることを表現します。このフレーズは、比較的形容詞 名詞 ♥♥♥
今までたくさんの学校で生徒たちを教えてきましたが、英語の勉強をする際に、何か暗号の記憶か、電話番号でも暗記するかのような態度の人がずいぶんいました。とても無駄な事だと思います。これでは決して英語が得意になることはできないでしょう。例をとってみましょう。次の熟語を別個に一つ一つバラバラに覚えていきますか?それとも…?
■be afraid of ~(~が恐い) ■be fond of ~(~を好む) ■be proud of ~(~を誇りに思う) ■be ashamed of ~ (~を恥じている) ■be sure of ~(~を確信している) ■be ignorant of ~ (~を知らない) ■be certain of ~(~を確信している) ■be convinced of ~(~を確信している) ■be sick of ~(~にうんざりしている) ■be tired of ~(~がいやになっている) ■be doubtful of ~(~を疑っている) ■be weary of ~(~に飽き飽きしている) ■be suspicious of ~(~を怪しんでいる) 何か気が付くことはありませんか?そうです。上の全てが前置詞 of 「心情」を表す表現 「心情」 of 「なぜ心情を表す時にはofを取るのだろう?」 「効果的な勉強の仕方」 八幡
学校は勉強しに来る所ではない。「勉強の仕方」を学ぶ所だ ―さだまさし 生徒が一番苦労している「単語の暗記」も、「アタマ・オナカ・シッポ」 「丸暗記」 勝田ケ丘志学館 『必携英単語 LEAP』(数研出版、2018年) 松江北高 「語源プリント」(1日1項目) 松江北高 『英単語はアタマ・オナカ・シッポで攻略だ!』(自費出版、2011年) 「欲しい!」 と希望が殺到しました。すでに在庫は全部なくなっているんですが、今でも希望される先生方がおられるので、「センター教材データCD」 PDFファイル
▲プリントを求めて大行列が!!
▲自費出版した八幡の単語本(絶版)
▲こんな風に代表的な「オナカ」を押さえる
そのために今私が一番オススメしているのが、最新刊のすずきひろし『語源×語感×イメージでごっそり覚える英単語事典』(ベレ出版、2025年)、清水建二『英単語の語源図鑑』(かんき出版、2016年)、竹岡広信『必携英単語 LEAP 改訂版』(数研出版、2024年) ♥♥♥
▲これ、とても面白い!!
英語の力をつけるために、生徒たちにはとにかくこまめに辞書を引かせます。最近の英作文の授業で、Asian Asian 「アジアの;アジア人の」 『アクシスジーニアス英和辞典』『ワードパワー』 イギリス アメリカ アメリカ 日本・中国・韓国・ベトナム イギリス インド・パキスタン・バングラディッシュ・スリランカ スティーブ・モリヤマ『イギリス英語は落とし穴だらけ』(研究社、2016年) 『ライトハウス英和辞典』(第7版) 「《参考》 Asianはしばしば《米》では東アジア(日本・中国・韓国など),《英》では南アジア(インド・パキスタン・バングラディッシュなど)を指して用いられることがある」 『ロングマン英和辞典』 「アメリカではふつう日本,中国,韓国などの人を,イギリスではふつうインド,バングラデシュ,パキスタンなどの人を指す」 ♥♥♥
私がまだ教員になりたての未熟な若い頃の話です。何年前?ALTとのティームティーチングで、“So much for today’s lesson.” 「その表現を使うと、先生は授業がいやでようやく終わってやれやれだ、という否定的なニュアンスを伴うので、That’s all for today. と言うように」 「あー、そうなんだ」 So much for that subject.「その件についてはもう全部話したからもうこれ以上何も言うことはない」 「So much for today! (もううんざりなので[止むを得ない事情で])今日はこれまで」
So much for~ 「~はもうダメだ」「~には期待できない」「~は終わったも同然」
So much for
So much for
ちょっとしたがっかり感や、見込みが外れたときに使うので、相手によっては少しネガティブな印象を与えることもあります。皮肉っぽく使うこともありますが、カジュアルな会話でよく使われるフレーズです。
以来、このような辞書には載っていない用法や語法の細部に興味を持ち、いろいろと調査研究を続けてきました。その成果は『ライトハウス英和辞典』(研究社) ♥♥♥
so much for Oは不満や失望を表すので、授業の終わりにSo much for today.と言うと「授業は思ったほど成果が上がらなかった」という意となる。授業の終了の意の「おしまい」はThat’s it for today.かThat’s all I have for today.と言えばよい。――『ジーニアス英和辞典』第6版 …についてはこれだけ(で十分)、…はこれでおしまい《話などを切り上げたり却下するときに用いる》:So much for Bill. He doesn’t care about us after all. ビルの話はこれくらいにしよう。結局彼は私たちのことを何とも思っていないんだから。――『ライトハウス英和辞典』第7版
大好きなシンガーソングライター・小田和正(おだかずまさ) <明治安田Presents 「KAZUMASA ODA TOUR2025 みんなで自己ベスト!!」> 静岡エコパアリーナ 「自己ベスト」 ですね。ライブでは親子2、3世代でのファンも目立ち、関係者は「キャリアの中で今が一番チケットが取れない」
当日は、会場に集まった8,000人の観客の前に、若々しい白いYシャツ姿(背中にはALL TOGETHER(みんなで一緒に) 小田 小田 小田 「こうしてみんなに会えることを非常に嬉しく思います。どうもありがとう」 「僕の今日のテーマは最後まで転ばないでたどり着くこと」 とお茶目に笑い、会場を沸かせました。小田 「頑張って!」 「『頑張って』って言われるということは、どこか頑張ってないってこと…?頑張りま~す」 代表曲「ラブ・ストーリーは突然に」 オフコース
78歳1ヶ月 でツアーを完走する覚悟です。「最後までツアーを完走できるように頑張ります」 小田 「ちょっと前までは年齢の割には若いねって言われたこともあったけど、今は年相応になりました」 「大丈夫です。もっと身体をいじめてください」 「新しい曲を持ってみんなに会いに行く」 小田 『自己ベスト-3』 「その先にあるもの」 「すべて去りがたき日々」 小田 「ラブ・ストーリーは突然に」「たしかなこと」「言葉にできない」 オフコース 「Yes-No」 横浜アリーナ 小田 ♥♥♥
湯河原 西村京太郎先生 千歳川 湯河原 「万葉公園」 湯河原 国木田独歩 湯河原 「万葉公園」
「文学の小径」 「万葉公園」
公園内には、渓流に沿って「川の道」
川の道にはベンチが設置されていて、散策の途中でベンチに腰掛けて川の流れる音や鳥のさえずりに耳を傾けると、心がやすらぎます。川の道から短い階段を登ると、木々に囲まれた小屋のような場所も。隠れ家のようで、自然の中でまったり過ごすにはうってつけです。木々と渓流、滝を見渡せるのでフォトスポットとしてもおすすめですよ。
公園の奥にある小川では、毎年春に地域住民によって近くの小屋で飼育されたゲンジボタルを、地元の小学生が放流するという行事があります。毎年5月下旬から6月中旬まではホタルを観察できる「蛍の宴」が開かれています。
公園内に鎮座している「熊野神社」
熊野神社
公園内にはもうひとつ神社があります。5つ連なった赤い鳥居の先にある「狸福(りふく)神社」 「狸福神社」
昔々、怪我をしたオスダヌキが傷を癒すために湯河原の湯に浸かっていると、怪我をしたメスダヌキに出会いました。湯で仲を深めた2匹は夫婦に。湯河原温泉への感謝を込め、人に化けて湯の素晴らしさを説き旅人の願いを叶えるうちに、福をもたらす神の遣いとなりました。鳥居の近くに詳しい言い伝えが掲示されているので、ぜひ目を通してみてくださいね。♥♥♥
木村治美(きむらはるみ) 『黄昏のロンドンから』(文藝春秋) 「第8回大宅壮一ノンフィクション賞」 木村治美 木村駿 木村先生 千葉工業大学助教授 東京教育大学・英文科 外山滋比古(とやましげひこ)先生 「ロンドン通信」 「私の何か書きたいという気持ちと、先生の何か書けるんじゃないかという気持ちが同機でした」(木村) ロンドン通信 『英語文学世界』 こんな美しい文章を書かれる木村先生 外山先生 外山先生 外山先生 コチラ をご覧ください)。中でも『思考の整理学』(ちくま文庫) 「東大・京大で最も読まれた本」、「読まれ続ける「知」のバイブル」 米子東高校
私が最近読んだ先生の『新版 本物のおとな論』(中央公論社、2022年)
高学歴化社会である。同世代の50パーセント以上が大学へ入る。95パーセントが高等学校へ行く。“高等”という文字が空しくなっている。 かつて、といってもそんな昔のことではない。戦後しばらくのころまで、高校へ進 学するものは限られていた。大学へ入るものは数えるほどであった。 高学歴化して、ことばづかいを知らない人が急増した。おかしなことばが流行して も、それをとがめる人もないまま、どんどん広まる。 電車にのると、アナウンスがうるさい。 “かけ込み乗車はおやめください” “ケイタイ電話の電源はお切りください” “網棚の荷もつにもご注意ください” “ ください”ということばが、ていねいな言い方だと思っているのである。とんでも ない誤解である。 “ ください”は命令形である。……せよ、といった命令形よりはていねいだが、目上の人には使えないことばである。電車の乗客には、使えないことばである。それを知 らない人が。ください々ことばを乱用させたのである。 悪気があったのではない。知らないのである。 もともとは、主人や主婦が、お手伝いにものごとを命じるときに使ったのが、くだ さいである。“しなさい”よりはていねいだが、見おろしたことばづかいである 。 学校はことばを教えるけれども、ことばづかいは教えない。文字の読み書きばかり 勉強するが、口のきき方などテストもできないし、点もつけられないから、教える教 師はほとんどいない。だいいち教師も、ロクに口のきき方を知らないのである。授業のことばは沈黙のことばである。話すことばは声のことばである。 学校に長くいればいるほど、ことばづかいがおかしくなる。方言でも、ことばづかいを心得ている人のことばは美しいが、親が都市へ出てきたという都会二世は、まるきりことばづかいのしつけを受けないということもありうる。 “ください”を平気で使っているのも、そういう人たちである。(pp.81-83)
こんなことは私は今までちっとも知りませんでした。お恥ずかしい。「~ください」 ♥♥♥
巨人―中日戦 権藤 博(ごんどうひろし、86歳) 「わけのわからない解説」 大野雄大投手 井上監督 「自分なら代えない。巨人打線が全然合っていないのだから。見ていてご覧なさい。流れが変わりますよ」 。「なんで代えるんだ、という顔をしていますよ、大野は」 大野投手 権藤 『 権藤、権藤、雨、権藤…』 権藤 35勝 を挙げ最多勝、新人王、沢村賞、ベストナイン 権藤 「時代も違うんですよ。我々が投げてる時は、監督はみんな戦争帰りの人ばっかりなんですよ。弾をかいくぐって、帰ってきた人ばかりですから、投げて、次の日に『ちょっと、肘が痛い』と言ったら、『何? 肘が痛い? たるんどる。命までは取られはせん』のひと言ですからね」 権藤 「そりゃ、弾をかいくぐって、帰ってきた人たちからしたら、肘が痛いとか、肩が痛いっていうのはたるんどるのひと言ですよね。だけど、そういうことは通用しないんですよ、今はね」 徳光和夫 「プロ野球レジェン堂」 権藤 「ヒーローインタビュー」 「みんながチャンスを作ってくれたので返そうと思った」「打者が点をとってくれたので、抑えようと思った」 「ファンのみなさんの声援のおかげで打てました」 「応援よろしくお願いします」 企業秘密まで話してくれとは言わないが、もっと技術に触れて欲しい」 権藤 「 チラッとでいいから技術を語ることで、やっぱりプロはすごいやと勝負の迫力を伝えて欲しい 」権藤 権藤 「見ててご覧なさい。こうなりますから…」 落合博満(おちあいひろみつ) 野村克也(のむらかつや) 野村 「プロのすごみ」 ♥♥♥
京都 堀場製作所 「おもしろおかしく」 「どんな意味だ?」「社員はどう理解しているのか?」 キャンディーズ サザンオールスターズ 堀場製作所 「おもしろおかしく」
堀場製作所 堀場製作所 HORIBA 「おもしろおかしく」 堀場雅夫(ほりばまさお) おもしろおかしく仕事をしたら人の半分も疲れません。効率は倍になります。サラリーマンは生活時間の大半を仕事をして過ごすのですから、いやなことをして過ごすのは人生がもったいない。 人間の行動力はものすごく幅が広くて、同じ人間でもやる気を起こしている時と、そうでない時とでは全く違うのです。例えば、上司から「君、これをしなさい」と言われた通りの仕事をしている場合と、「自分でその仕事がやりたかった」という場合では、実測データで3倍とか4倍、能率が違うといいます。面白く仕事をしている場合、与えられた仕事を単にやっている場合に比べて、疲労度が2分の1から5分の1ぐらいだというデータもあります。したがって、「おもしろおかしく」
会社で働く場合、私たちは人生の多くの時間をその会社で過ごすこととなります。そうした会社での日常に生きがい、働きがいをもって「おもしろおかしく」 堀場 堀場 堀場 「堀場無線研究所」 「株式会社堀場製作所」 「おもしろおかしく」
そしてもう一つは、医学博士号 博士号 堀場 医学博士号 医学博士号 「おもしろおかしく」
そして1978年、堀場製作所 「おもしろおかしく」 堀場雅夫 HORIBA 「Joy and Fun」
「御社の社是は何か?」 堀場雅夫 「社是というものがいるのか?」 「おもしろおかしく」 堀場 『イヤならやめろ!』(日本経済新聞社、1995年) 堀場 「いくら何でもそれはひどすぎる!」 とか 「そんなことを言うとお客がモノを買わない!」 「こんないいいものはないのに」 「こんなにいいことが分からないのだったら役員なんて辞めてしまえ」 「おもしろおかしく」 「おもしろおかしく」 「記念品はいらないからあれを正式の社是にしてくれ」 「おっさんの言う通りにしなければしょうがないな」
この社是のベースになる思いは、創業者が「人間の可能性」に感銘したからです。物理を専攻していた創業者は起業後、企業としての格を上げるために社員に博士号を取ろう、という号令をかけました。その際に自らも博士号を取ろうと、専門であった物理ではなく医学博士 「 この人間が毎日、会社で10時間近く過ごすのなら、仕事が面白くなければその人の人生そのものが豊かにならない。堀場で働くなら、おもしろおかしく仕事に励み、そういった仕事から生まれた製品を使う人に届けたい」
また堀場 「81点のヒット商品」
創業者で、最高顧問の堀場雅夫 ♥♥♥
「ダイナマイトを発明したノーベル。強力な武器があれば誰も使うのが怖くてけんかをしなくなると考えたと思うが、結局は「戦争の道具」になってしまった。核兵器も同じ。ロシアのプーチン大統領はウクライナ情勢をめぐり、使う準備をしたという発言をしましたね。手に入れたら、使いたくなるのが人間の本能。嫌な感じがしています」
案山子
作詩・作曲 さだまさし
元気でいるか 街には慣れたか 友達出来たか 寂しかないか お金はあるか 今度いつ帰る 城跡から見下せば蒼く細い河 橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突 この町を綿菓子に染め抜いた雪が 消えればお前がここを出てから 初めての春 手紙が無理なら 電話でもいい “金頼む”の一言でもいい お前の笑顔を待ちわびる おふくろに聴かせてやってくれ 元気でいるか 街には慣れたか 友達出来たか 寂しかないか お金はあるか 今度いつ帰る
山の麓 煙吐いて列車が走る
凩が雑木林を転げ落ちて来る 銀色の毛布つけた田圃にぽつり 置き去られて雪をかぶった 案山子がひとり
お前も都会の雪景色の中で 丁度 あの案山子の様に 寂しい思いしてはいないか 体をこわしてはいないか
元気でいるか 街には慣れたか 友達出来たか 寂しかないか お金はあるか 今度いつ帰る VIDEO
私の大好きなさだまさし 「案山子」(かかし) 案山子 さだ 佐田繁理(さだ しげり) 繁理(しげり) 「案山子」 島根県 津和野町 島根県立津和野高等学校 さだ 「曲の原風景は津和野」 津和野 津和野 津和野城趾 さだ 「ふるさと」 霊亀山 津和野城跡 津和野市街 島根県鹿足郡津和野後田 津和野城(別名・天空の城) 霊亀山 津和野
さだ 「金頼む」 さだ 「案山子」 案山子 「離れて暮らす家族への愛情」 がこの歌のテーマだと私は感じました。
兄視点の歌ではありますが、それは都会に出た子どもを思う親の気持ちを歌っているようにも読み取れます。松の木が故郷の街並みを見渡して、遠く離れた娘や息子、あるいは兄弟などを想う大きな存在としてのイメージをさだ 「案山子」 さだ 繁理 大分 北九州 さだ 案山子 「かわいそうだな…」 案山子 「百姓は決して案山子を雪の中に置き去りになどしないものですよ」 案山子 さだ
2016年10月「関ジャム 完全燃SHOW」 さだ 「案山子」 津和野城跡 松の木が歌っているイメージで曲を書いた ことを番組内で話していました。「 案山子」 テリー伊藤『歌謡Gメン あのヒット曲の舞台はここだ!』
津和野は実に日本的な風景なんですよ。(中略)『日本のふるさと』の情景の典型とは何かと考えたときに、僕は城跡から眼下の街を見下ろしたときの風景だと思った。実は三本松城に大きな松の木があって、その松の木が子どもに語りかけているんです。 津和野城 三本松城 。さだ さんらしいですね。発表から、あと数年で50年になりますが(メロディーはさだ 津和野 高松市 「さだまさし展」 案山子 ♥♥♥
▲「さだまさし展」の会場でお出迎えする案山子
「喜多方ラーメン」 博多 豚骨ラーメン 札幌 味噌ラーメン 「日本三大ラーメン」 「平打ち麺」 喜多方ラーメン 「喜多方ラーメン坂内」 “毎日食べても飽きない味” カップ麺 「明星 喜多方ラーメン坂内 コク醤油ワンタン麺」 「喜多方わんたんラーメン」 「もちもちとした平打ちの生めん」 「肉そば」 「東北の蔵の里」 「喜多方」 「喜多方ラーメン坂内」 喜多方ラーメン 「坂内」カップ麺 喜多方ラーメン ♥♥♥
▲八幡は「九条ネギ」をトッピングして
▲このワンタンが最高に美味しい!!
モータは19世紀初めに誕生して以来、私たちの身の回りのありとあらゆる電気製品に使われ、生活には無くてはならない存在となってきています。そして、今やモータが世界で発電される電力量の約55%を消費していると言われるほど、たくさんのモータがさまざまな場面で使われています。それゆえ、モータの研究は、私たちの豊かな生活の維持と、地球環境の永続的保全の双方にとって、非常に重要なテーマとなってきているのです。このモータのみならず、発電機やアクチュエータ等の周辺分野も含めた技術の研究開発をより活性化させるとともに、夢を抱いて日々の研究開発に邁進する研究者・開発者を応援したいという思いをもって、世界一のモータ企業・ニデック 永守重信代表取締役グローバルグループ代表 公益財団法人永守財団 「永守賞」
今日(5月27日)の新聞紙上の広告で「第11回永守賞」 「第11回永守賞表彰式」 「永守賞大賞(500万円)」
昨年の「第10回永守賞」 ピーター・サージェント氏 サージェント氏 サージェント氏 「素材を再利用でき廃棄物や無駄のないモーター技術を開発したい」 「永守賞」 永守氏 「新進気鋭のモーター研究者の登竜門として賞を発展させたい」 「人工知能(AI)や半導体に続いてモーター研究への社会の関心が高まっている」
永守 京セラ会長 稲盛和夫 稲盛 「京都賞」 「人のため、世のために役立つことをなすことが、人間として最高の行為である」 「京都賞」 稲盛和夫
稲盛 「人のため、世のため」 稲盛財団 「京都賞」 「京都賞」 「京都賞」 「人類の未来は、科学の発展と人類の精神的深化のバランスがとれて、初めて安定したものになる」 稲盛 ♥♥♥
VIDEO
あの鎌田 實(かまたみのる)先生 「日刊スポーツ」 「鎌田式死ぬときに後悔しない生き方」 長野県諏訪地域で医療活動に従事する 鎌田先生 『がんばらない』 さだまさし 柴田紘一郎先生 「風に立つライオン」 鎌田先生 「八ヶ岳の野ウサギ」
「変さ値が大事」 「偏差値」 「変さ値 」 「変さ値」 「変さ値」 「変さ」 「変さ」 鎌田先生 「偏差値」 「変さ値」 もう一つは、「仕事とは何ですか?」 鎌田先生 プロレス プロレス プロレス プロレス プロレス 「仕事はプロレスに通じる」 鎌田先生 ♥♥♥
私の講演会ではスライドに注目してもらうために、いつもレーザーポインター 「赤」色 レーザーポインター 「緑」色
🔴 赤色レーザーポインター
波長 :650nm前後
特長 :価格が安く、電池持ちが良い
おすすめ用途 :プレゼン、室内使用
👉 一般的な使用には十分。コストパフォーマンスを重視するなら赤色がおすすめです。
🟢 緑色レーザーポインター
波長 :520〜532nm
特長 :非常に明るく、昼間でも見えやすい
おすすめ用途 :屋外での指示(建築、登山)、星空観察
👉 光が強く、特に夜間や広い空間での使用に最適です。視認性を重視する方におすすめ。
🔵 青色レーザーポインター
波長 :450nm前後
特長 :クールな印象で存在感がある
おすすめ用途 :DIY、ガジェット好きへのギフト、演出用途
👉 見た目もユニークで、レーザー愛好家の間で人気です。目立ちたい時には◎。
✅ 使用上の注意は?
レーザー光を人や動物の目に向けないこと
屋外で使用する際は、航空機や車両に向けないこと
ペット用として使用する際は、適度な時間で遊ばせて疲れすぎないよう注意すること
今私が使っている緑色 の緑 (株)ALATAMA 「MIDORI-CHAN Slim」 レーザーポインター ワイヤレスリモート機能
6月11日(水)予定の米子東高校3年生 ♥♥♥
私が名古屋 「矢場とん 」 みそかつ 名古屋大学 松江北高 JR博多駅 アミュプラザ9階 「矢場とん」 博多 「 矢場とん」 名古屋 「みそかつ」
「とんかつにみそだれをかければ良い」 「みそかつ」 「とんかつ」 「みそ」 「みそかつ」 「厳選された食材」 「とんかつの揚げ方」 「みそだれ」 「矢場とん」
その矢場とん 鈴木孝幸(すずきたかゆき) 名古屋名物「みそかつ」 名古屋 みそかつ 鈴木 名古屋 みそかつ
『藝大よ、地球を救え。』 東京藝術大学客員教授 さだまさし 東京藝術大学教授 箭内道彦 「アートの力で世の中を変えていこう!」 東京藝 さだ さだ 「矢場とん」 「社歌を作ってください」 「歌詞は自分で書くので、それに曲をあててほしい」 「矢場とん」 みそかつ “社員たちが一つになれる社歌” さだまさし 社歌「矢場とん一家の心はひとつ」 矢場とん 「あ~、食べに行きたいなあ」 ♥♥♥ VIDEO
大ファンの故・外山滋比古(とやましげひこ)先生 『「忘れる」力』(潮文庫,2022年)
欧文のパラグラフにははっきりした構造と組織がある。典型的なのはA・B・C の三部に分かれる。Aは一般的、抽象的な書き方がしてあり、Bはその具体例など が述べられる。Cはまた抽象的表現に戻って締めくくる。この三者が同心円のよう に重なるのがよいとされる。 この構造に不案内だったりするとひどい目にあう。以前、大学入試で英文和訳の 問題が必ず出た。その答案を採点していておもしろいことに気付く。さきのAの部 分の原文の下を鉛筆の線が往き来していて苦心のあとを留めている。それが突破で きずに失敗するのであるが、Bへ行けばわかりやすく、そこから返ってみればAも わかる。A止まりだから失敗するのである。(p.97) 毎年生徒たちに言って聞かせていることは、英語の文章は【抽象】 【具体】 【具体】 【抽象】 「あ、これはダメだ。分からない!」
尊敬する故・渡部昇一(わたなべしょういち)先生 『人生の手引き書~壁を乗り越える思考法~』(扶桑社、2019年) 「衝動的判断は×」
大学で英語の教師をやっていて、非常に面白いと思ったことがある。英文を訳させると、できない生徒は、決まってパラパラと見て知っている単語があれば、そこからパッと訳し始める。文脈などあまり考えず、知っている単語があると片っ端から訳していくのである。一方、できる生徒は、読むにしたがって次々と勝手な解釈が出てくるのを抑え、まずひととおり文脈を追う。わかる部分から始めたいという衝動を抑え、知っている単語があっても文脈からじっくりと捉えなおしているようである。 英語の訳文ばかりではない、ディスカッションでも、こう主張したいという衝動にかられることはよくあるが、できる人ほど、そこで少し抑え、冷静にデータなどの裏づけを検討してから発言するようである。人が発言しているときに、ちょっと自分の意見と相違があると思うとすぐに割り込みたくなるのはわかる。しかし、ここでぐっと抑えて、この人の意見にも一理あるかもしれないと考えるのが、大切である。アホらしい思いつきで笑わせるのはテレビのショー番組だけと思ってよい。漫才には漫才の効用がある。しかしショーや漫才は特別の世界である。大を笑わせたり、あっと言わせれば成功という世界だ。普通の人生を歩む大にとっては異質である。そこを間違えてはいけない。即断即決を否定するつもりはない。まるで天からの声が聞こえたかのように、直感が働くこともある。だが、文脈を追わずにわかるところから訳す、あるいは、前後の脈絡や人の意見など気にもせず自分の主張を繰り広げるなど、自分に対する甘やかしのような衝動は、あとから後悔することが多い。それは、直感とは程遠い、ただの短絡思考でしかないのだ。学生のうちは許されても、社会人ともなれば、甘やかされた衝動はますます抑えねばならなくなる。衝動的な人ばかりだと、組織がめちゃくちゃになってしまうからだ。たとえば、入社いくばくもない社員で、「この会社は能力を高く評価してくれない」と言って辞めてしまう人がいるが、これも、自分を甘やかしているにすぎない。もちろん、その人が辞めたことで会社の売り上げが極端に下がり、倒産の危機にさらされるようなことになれば、その人は正しかったと言えるのかもしれない。しかし、その人一人辞めたところで彼らの日常が変わらないとなれば、この衝動的な判断は、まったく役に立たなかったということだろう。道を誤らないためには、こういう幼稚で短絡的な衝動に飲まれないよう、心がけることだ。(p.166-168)
尊敬する故・渡部昇一先生(上智大学名誉教授) 補助の井戸 補助の井戸 森鴎外 島根県津和野町
渡部先生 専門分野の井戸は、誰よりも深~く掘り進めることが大切です。「智謀湧くがごとし」 東郷平八郎司令長官 秋山真之中将 東郷元帥 「智謀如湧」 「智謀湧くがごとし」 リソースフル(resourceful) リソースフル 渡部先生 リソースフル 「それだけでよしとしてはいけないよ」 リソースフル 「また同じことを言っている」 斎藤勇先生 福原麟太郎先生 安藤貞雄先生(広島大学名誉教授) ラッセル
私の尊敬する夏目漱石 漢学 吉川幸次郎博士 漱石 漱石 漱石 ラフカディオ・ハーン(小泉八雲) 東京大学 漱石 イギリス文学 『文学評論』 漱石 漱石
私は、大好きだった故・西村京太郎先生 松本清張 『かげろふ絵図』 『彩色江戸切絵図』 『昭和史発掘』 松本 清張 ♥♥♥
あの日産自動車 カルロス・ゴーン社長 日産 ゴーン 日産
2018年の年末年始は、(1)役員報酬の過小記載、(2)私的な目的で日産の投資資金を支出、(3)会社の経費の不正使用 特別背任 カルロス・ゴーン ゴーン 「申し訳ない」 「負の遺産」「憤り」 日産 ゴーン 東京拘置所 カップ麺 白米 エビやかまぼこ、黒豆 おせち
東京拘置所 カルロス・ゴーン容疑者 米誌『タイム』 英誌『エコノミスト』 ジェフリー・アーチャー アーチャー の ファンでしたから、興味を持ってニュースを見ていました。
ジョフリー・アーチャー
Not a Penny More, Not a Penny Less 『百万ドルをとり返せ!』 A Prison Diary (『獄中記』)Cat O’nine Tales (『プリズン・ストーリーズ』)アーチャー
一人または複数の主人公の生涯を描きだす長編小説(サーガ)、サスペンスやミステリー形式の作品、および短編集と3種類の形態で作品を発表してきています。これらの作品の中でジェフリー・アーチャー 『チェルシー・テラスへの道』 『ケインとアベル』 『ロスノフスキ家の娘』
私は教員に成り立ての頃、彼のデビュー作『百万ドルを取り返せ!』(新潮文庫) 永井 淳 アーサー・ヘイリー 永井 “page-turner” (この表現、米国週刊誌で覚えました) ともいうべき作品たちでした。
Not a Penny More, Not a Penny Less (1976) – 『百万ドルをとり返せ!』(1977年)Shall We Tell the President? (1977) – 『大統領に知らせますか?』(1978年)Kane and Abel (1979) – 『ケインとアベル』(1981年)A Quiver Full of Arrows (1980) – 『十二本の毒矢』(1987年)The Prodigal Dangher (1982) – 『ロスノフスキ家の娘』(1983年)First Among Equals (1984) – 『めざせダウニング街10番地』(1985年) どんどんと、あまりに膨大なページとなっていったもので、途中で挫折して以降は読んでいませんが、もう少し時間ができたら、最新作に手を出してみようかなと思っています。♥♥♥
奈良 奈良公園 鹿 奈良
奈良時代、春日大社 武甕槌命(たけみかづちのみこと) 春日大社 鹿 春日大社(かすがたいしゃ) 「神の使い」 「奈良のシカ」 鹿 奈良公園 鹿 奈良公園 鹿
奈良公園 鹿 鹿せんべい 鹿 鹿 鹿 鹿せんべい 鹿せんべい 鹿せんべい 鹿 鹿せんべい 鹿せんべい 鹿 鹿 鹿 鹿 鹿 奈良公園 鹿 鹿 鹿 鹿 奈良公園 鹿
さて奈良公園 鹿 「鹿せんべい」 鹿せんべい お辞儀 をしているようだということで知られていますね。このお辞儀行動を丁寧な日本文化と結びつけて、海外からの観光客にはなかなかの人気です。これが実に可愛らしいんです。それが人気の一つでもあるのですが、その様子を見たいがために、集まってきた鹿 鹿せんべい 一枚の鹿せんべい 鹿 鹿せんべい 鹿 おじぎ 「鹿せんべいをもらえる回数は多かった」 鹿せんべい 「ほとんどのシカがおじぎをした」 「おじぎをしなかった」 つまり、「おじぎすることが、せんべいをもらうのに有利 な行動だ」 鹿 鹿 「催促」の行動なんですが、それを受け取る人間側は「あいさつ」「感謝」などとズレた受け止め方をしているのかもしれませんね。♥♥♥
VIDEO
コンサートの間、5分でいいから、あなたの大切な人の笑顔を思い出して欲しい。そして、その笑顔を守るために自分に何ができるかを考えませんか。――「夏 長崎~ さだまさし」で、さださんが伝え続けてきた言葉
シンガー・ソングライターのさだまさしさん(73歳) 長崎市 稲 佐山公園野外ステージ 「夏 長崎から2025」(午後5時~) 「2025年。広島・長崎は被爆80年を迎えます。僕は再び長崎で歌う決心をしました」 と。
広島・長崎 広島原爆 長崎 「体力的にもこれが最後」 「生命の樹~Tree of Life~」 さだ さだ 長崎市 市営松山ラグビー・サッカー場 「夏 長崎から さだまさし」 「広島原爆の日に、長崎から広島に向かって歌う。それだけで伝わる人には伝わる」 さだ 「平和コンサート」 「夏 長崎から」 「このコンサートが終わるまでの間に、ほんの僅かな時間でよいから、あなたの一番大切な人の笑顔を思い浮かべて欲しい。そうしてその笑顔を護るために自分に何ができるだろうか、ということを考えて欲しい。実はそれが平和へのあなた自身の第一歩なのです。」 長崎 「平和を願う場所」 「500円でも1,000円でも料金が発生すると、子供たちは家で留守番になるでしょうが、無料なら家族連れで夕涼みがてら出掛けようという気になる。家族そろって音楽を聴く。これこそがまさに平和の姿だと思います」 村下孝蔵、来生たかお 松山千春 谷村新司、都はるみ、小田和正、泉谷しげる、加山雄三 さだ 「フェスの元祖」 長崎
「売名行為」「ただとは何か別の意図があるのではないか?」「長崎県知事になるための事前運動だろう」「いや長崎市長を狙っているらしいぞ」 「長江」 製作 の借金返済で苦しんでいた当時のさだ さだ 「長崎の夏の風物詩」 稲佐山公園野外ステージ パナソニック さだ 「夏 長崎から」 「お母さん、なしてこげんばいっぱい人がおると?」 「今日はね、平和を考える日やけんよ」 「こんなにたくさんの人が集まって、良い音楽を聞くことが平和なんだよ」 さだ 「まっさん、伝わっとるばい」 さだ 「頑張ってきて本当に良かった」
ただ、初めから8月6日を想定していたわけではありませんでした。さだ 長崎 長崎 長崎 長崎 さだ
1987年春、コンサートの合間に故郷・長崎 さだ 繁理(しげり) 雅人(まさと) 西岡武夫(1936~2011) 「8月9日、平和を考える野外コンサートを故郷・長崎でやりたい―」 さだ 西岡 西岡 さだ 西岡 「広島原爆の日に、長崎から広島に向かって歌えばいい。さだ君、それで君の思いは伝わるよ。それに右の人も左の人もみんな広島に行っているから、何も気にせず、ただ歌えばいい」 「夏 長崎から」 さだ 西岡
この「夏の風物詩」 さだ 「切迫感が薄まった」 「2006 夏 長崎から さだまさしファイナル」 さだ 僕のメッセージが伝わっているのか、いないのか?それを確かめるために現場を一度離れてみようと思う。「夏 長崎から」を20回で辞める決心をした」 「僕もお客さんも一呼吸置き、原点を見つめ直す時期だと思う。そのために一度、現場を離れることにした」「少なくとも達成感はない。以前は、主催者であると僕がいなくなっても続くコンサートになってくれれば、と思っていたが、その願いもかなわなかった。無力感のほか、悔しさもある」 さだ
●最も借金していた頃に始めた思いはあれから20年を経て変化していないか?風化していないか? ●心の熱は下がっていないか?これが本当に必要なのか? ●お客さんはどうなのか?これが本当に必要なのか? ●20年間訴えてきた平和への思いは伝わっているのか?あるいは無駄だったのか? ●子どもでも成人すれば(20年)親の手を離れてもいいのではないか? ●自分が永遠に続けられるものでもないだろう? これらを自分でもう一度客観的に見つめ直すために、一度現場を離れてみようという決意でした。長崎県 さだ 稲佐山 さだ 長崎 長崎 さだ 「これまで一つのことを訴えてきた。『コンサートが終わるまでの間に、あなたの大切な人の笑顔を思い浮かべて欲しい。そしてその笑顔を守るために、自分に何ができるのかを考えて欲しい』と。でも、2004年自衛隊がイラクに派遣された。大した議論もデモも暴動もなく、自衛隊はイラクに出て行った。強烈な無力感、喪失感にさいなまれた。だから、最後に言い足した。『大切な人の笑顔を守るためになにができるか分かったら、自ら行動してほしい』と。もう少し早く言えば良かったと思っている」
長崎 長崎 広島 旧 広島市民球場 「長崎っ子の意地で始めたコンサートだけど、一度も「長崎原爆の日」に歌っていない。8月9日に歌って初めて僕の「行(ぎょう)」は終わると思っている」 長崎 広島 長崎 「20年の思いを収めるためにも広島でやりたかった。長崎の原爆の日に広島で歌って長崎と広島をつなげたい」 「ちょっとだけでいいから、あなたの大切な人の笑顔を思い出してください」 「その大切な人の笑顔を守るために何ができるか、何をすべきかを一人一人が考えてほしい。それが平和への一歩」 「反戦のためにすべきこと。思うだけでなく行動を起こそう」 「僕は長崎をあきらめない。僕は平和をあきらめない」 さだ が歌ったのが、「遙かなるクリスマス」 。21年間の平和祈念コンサートを締めくくるには、まさにふさわしい反戦の思いのこもった熱唱でした。
「今年は戦後80年。この節目に、もう一度立ち止まって広島の空に向けて歌おうと思った。戦争反対や核兵器、原発など(政治的なことは)一切触れない」 「夏 長崎から」 「僕としては今後、誰かが受け継いでほしいなと思っています」 ♥♥♥
朝、JR 米子駅 0番線(境線)のホーム 「双頭レール」
「双頭レール」 新橋・横浜 ロック(J.Locke) 「ダーリントン・アイアン社製」
鉄道創業時の日本では、レールを輸入に頼っていたために、寿命の長い「双頭レール」 「双頭レール」 平底レール 平底レール
役目を終えた「双頭レール」 米子駅 ♥♥♥
プロレスの試合においては、試合前に勝ち負けはあらかじめ決まっています。マッチメイカー 「大阪スポーツ」 新日本プロレス ミスター高橋 『流血の魔術 最強の演技~すべてのプロレスはショーである』(講談社、2001年) 「ブック」 「ブック」 「アングル」 アングル(angle) 「魚を釣る」「魚釣りをする」 「釣る」 ブルーザー・ブロディ マッチメーカー 「自分が、自分が」 仙台駅 マッチメーカー 新日本プロレス プエルトリコ マッチメーカー アングル
タイガー・ジェット・シンのコブラクローで猪木さんが喉から出血したことがある。蔵前国技館での試合だった。シンの手を自分の喉元からふりほどくようなふりをして、自分で持っていたカミソリで喉を切った。後でビデオの録画を見たら、まさにシンの指が喉に刺さっているように見えた。リング内で見ているより迫力があった。ああやって、何ていうことのない技を最大限に迫力あるものに見せかけて、タイガー・ジェット・シンという選手の商品価値を高めていったのだ。自分の身を切り裂いてまで、徹底的に相手の凄みを引き出していく猪木さんの執念と上手さは、見ていて身震いするほどのものだった。(pp.156-157)
プロレスファンなら誰でも知っている「新宿伊勢丹事件」 猪木 倍賞美津子 タイガー・ジェットー・シン 猪木 猪木
さて、日本のプロレス史上で最も成功した「アングル」 「かませ犬発言事件」 「藤波、俺はお前のかませ犬じゃない!!」 藤波辰實vs長州力 「アングル」 新日本プロレス 米国 メキシコ UWA世界ヘビー級チャンピオン 長州 長州 「長州をどうするのか?」 長州 藤波 長州 藤波 アントニオ猪木 アングル 長州 長州 アングル 「このチャンスを生かさなければ、いつ俺はスターになるんだ」 長州 藤波
つい最近も、みえみえの「 アングル」 新日本プロレス IWGP世界ヘビー級王座戦 後藤洋央紀(45歳) ザック・セイバーJr.(37歳) IWGP世界王座 IWGPヘビー級王座 ザック 「昇天・改」 後藤 GTR ヨーロピアン・クラッチ ラリアート GTR 「GTR改」
後藤 「今日の勝利を、亡き父に捧げます。知ってる方もたくさんいるでしょうが、俺はバカです。長男でありながら稼業を継がず、プロレスラーを目指した。でもそんなバカな俺でも貫き通せば王者になれるんです。親父!取ったぞ!」 「一生に一度のことだぞ。子どもたちよ、この光景よく見とけよ。これがパパが目指した光景だ。この光景が見れたのは、家族のおかげ。そして仲間のおかげ。そして、何よりも俺の後押ししてくれた今日のお客様がた。そして最後に22年間、ここまでやってきた自分自身の体にありがとうございましたと伝えたいです」 後藤 「後藤革命はまだ始まったばかりだ。最後の最後まで後藤革命について来い!」 「IWGPのGは後藤のG!!」 後藤 新日本プロレス 。会場は興奮のるつぼ大熱狂です。 「9回目のIWGP挑戦。これが最後になるかもしれない、という覚悟はできてます。過去8回負け続けてきましたが、9年前とまったく同じ2月11日で大阪府立体育会館。何か運命的なものを感じる。格好つけることもないし、オレの格好悪いところはみなさん散々見てきてるだろうし、今は無理して格好つける必要もない。自分だけでなく応援してくれるファンの方々と一緒に夢を見たいですね。オレらの世代、結構追いやられてるイメージがあると思うんですけど、ここはオレが先頭に立って、若い世代のヤツらに見せつけなければいけない。そういう風に思ってます。新しい技っていうのはないです。ただ出してない技、彼の知らない技っていうのはまだあると思うので」 こうして苦労人が夢を叶えるという図式が完成したのでした。その後、棚橋弘至、永田裕志、デビッド・フィンレー、カラム・ニューマン、ザックセイバーJr. アングル ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はミルクジャム
JR元町駅 神戸南京町 「patisserie AKITO(パティスリーアキト)」 松江駅南口 「Ciistand」 「ミルクジャム」 田中哲人(たなかあきと) 「ミルクジャム」 「patisserie AKITO」 「ミルクジャム」
昭和40年頃、京都の中小企業経営者たちが集まった講演会に招かれた故・松下幸之助(まつしたこうのすけ) 「ダム経営のすすめ」 「ダム経営」 松下
堰き止めたダムの水によって干ばつがしのげるように、会社経営にも資金や設備あるいは在庫といったさまざまな面に「ダム」があれば余裕のある経営ができる、というのが松下幸之助 「ダム経営理論」 松下 「 松下さんのおっしゃるとおり、余裕があればそれにこしたことはないが、我々はその余裕がないから困っているのだ。どうしたら余裕が出来るんか、それを教えて欲しい」 松下 「 そうですなぁ。簡単には答えられませんが、やはりまず大切なのは、ダム経営をやろうと思うことでしょうな」 「な~んだ」
京セラ名誉会長 稲盛和夫(いなもりかずお) 京セラ 稲盛 「 そうか、まず思うこと、信じることが何にもまして肝要なのだ。その思いが経営に反映されるのだ。松下さんも今までそうしてきたからこそ、今日の松下電器があるのだ…」 「そのとき、私はほんとうにガツンと感じたのです。何か簡単な方法を教えてくれというような生半可な考えでは、経営はできない。実現できるかできないかではなく、まず『そうでありたい、自分は経営をこうしよう』という強い願望を持つことが大切なのだ、そのことを松下さんが言っておられるんだ。と、そう感じたとき、非常に感動したんです」 稲盛 松下 稲盛 京セラ 私は、何ごとによらず、それをなし遂げるために最も大切なことは、まずそのことを強く願うというか、心に期することだと思うのです。なんとしてもこれをなし遂げたい、なし遂げなければならないという強い思い、願いがあれば、事はもう半ばなったといってもいい。そういうものがあれば、そのための手段、方法は必ず考え出されてくると思います。 ―松下幸之助『経営のコツここなりと気づいた価値は百万両』(PHP) 松下 「なあ、きみ、人間の心は広がればなんぼでも広がっていく。縮まればなんぼでも縮まって、しまいには自殺までしてしまうんや。それはどの間を大きく動くわけやね。だからどんどん知恵が出ておるときには、非常にいい知恵が出る。しかし知恵が閉ざされてくると、どんな知恵も出ない。それで失敗してしまう」 松下 「何としても二階に上がりたい、どうしても二階へ上がろう、この熱意がハシゴを思いつかせ、階段を作り上げる」 「熱意」
*************************************************
生徒 :「八幡先生、僕、「共通テスト」で100点を取るにはどうしたらよいでしょうか? 」 八幡 :「そうですなあ。簡単には答えられませんが、やはり、まず100点を取ろうと思うことでしょうな 」 最近ある公立高校で、難関大学合格に向けた指導のヒントを教えていただきたい、という講演を先生方にしたんですが、これに対しても「そうですなあ。簡単には答えられませんが、やはり難関大学に合格させたいと思うことでしょうな」 ♥♥♥
昨年3月、ジェットストリーム(三菱鉛筆) 「ジェットストリームシングル(ライトタッチインク搭載)」 八幡 ジェットストリーム 「低粘度油性ボールペン」 「クセになる、なめらかな書き味。」 ジェットストリーム 「 ライトタッチインク」 ジェットストリーム 「文房具の八ちゃん」
▲ジェットストリームシングルの特長
「シングルボールペン」 事務的な印象を受ける今までと違い、プレーンなデザインと爽やかな印象を受ける、流行のパステルカラーを合わせて、女性にも受けやすいおしゃれなデザインになった グリップ部分もボディ同色にすることで、野暮ったさをなくしており、疲れにくさにも考慮 グリップ部が少し太く設計 クリップ部分も改良され、よりしっかりホールドしてくれるだけでなく、根元の取り付け位置が変わったため、胸ポケットなどに差した時に出っ張る部分が少なくなり、よりスマートに見える ようにもなっています。細かな点にまで気配りがなされています。仕事にもプライベートにも馴染みやすい、丸みのあるボディデザインで、カラーラインナップも周りの風景や雑貨に溶け込む優しくナチュラルな色合いが揃っています。クリップにまで同色のシームレスな洗練されたデザインは◎です。
今までの無骨さはまるっきりなく、非常に可愛らしく、シンプルなフォルムになっています。それでいて本体自体も軽く、実用性におしゃれさ・使いやすさを加えた、非常にコスパに優れた一本 本体自体も従来版よりも短くなっていて、携帯性にも優れて 書き出してみて、思うのは「本当に軽い」 元々通常のジェットストリームでも感じるものでしたが、今回の新モデルは「ライトタッチ」 感じがあります。水性ボールペンのようなスラスラ感ともまた違い、なんというか、本当に「軽い」です。書き味のいい上質な紙に、上質な鉛筆で書いているような感覚でしょうか。それでいてジェットストリーム 「よりかろやかな」 「紙すべり」 ジェットストリーム 「ライトタッチ」 「クセになる、なめらかな書き味。」 『JETSTREAM Lite touch ink』 ジェットストリーム 筆記時に振動や異音を抑えたノック棒、ポケットに挿した時に収まりのよいクリップ形状など、使い心地にもこだわりました。このインクでしかできない表現があるので、それを知ってもらう企画を色々と考えています。気軽に試して、既存のジェットストリームと書き比べてみてください。(商品開発部)
ここまで書くと、いいことばかりなのかと思いますが、個人的に気になる部分もあります。それは、「従来比で色が薄い気がする」「軽すぎる故、力を入れて書けない」 従来のものと黒色で比べると、今回のほうが少し黒さは薄いように感じ 特にマルチだと顕著なのですが、ボディも含めて軽い分、剛性感が薄く、とても力を入れて書けません 。「日本語を美しく書く」ために強弱をつけて、止め・はね・払いを意識して書こうとすると力が入りますが、そうするとなんとなく折れそうになります。
今回のライトタッチインク ジェットストリーム ライトタッチインク 芯(リフィル) 「ブルーブラック」
▲リフィルも豊富に品揃い
ちなみにこのボールペンは「2024年Bun2大賞」 『文具屋さん大賞2025』(扶桑社ムック、2025年2月) 「機能賞」 高畑正幸 「第14回OKB48総選挙」 「ジェットストリーム スタンダード」(三菱鉛筆) 「ジェットストリーム シングル(Lite touch ink搭載) 「ジェットストリーム」 「ジェットストリーム」 ♥♥♥
尊敬する医師の柴田紘一郎(しばた・こういちろう)先生 宮崎大宮高校 長崎大学医学部 長崎大医学部 熱帯医学研究所員 ケニア ケニア さだまさし 「風に立つライオン」 柴田先生 さだ 「風に立つライオン基金」 さだ 「半世紀以上のお付き合いでした。大好きな、素晴らしい兄貴でした」
「医者が患者から奪ってはいけないもの。それは命ではない。心なんだ『希望』なんだと。命が心につながってきますから、その心を大切にするような医療を続けていきたいし、そういう今からの医療であってほしいなと」 かつて英語を教えていた松江北高二年生(当時)の安樂万智子(あんらくまちこ) 「第33回高校生英語弁論大会」(全国国際教育研究協議会主催) コチラ に詳しく)。そこで私はこの柴田先生 「運命的な出会い」 柴田紘一郎先生 安樂 「松江日赤」 長崎大学 柴田先生 柴田先生 宮崎 「先生のホームページも拝見させていただきましたが、英語科の教師としてすばらしい英語教育に、またあまたの一般事象への高いご見識を常に発信されている姿勢に感銘いたしました。」(柴田紘一郎)
▲2013年宮崎での講演会にて 柴田紘一郎先生
さだまさし 柴田先生 「僕もいつか風に立つライオンのようになりたい」 「まさしさんはこれは僕の歌だと言うけど、これは『風に立つライオン』という歌であって、自分はこの歌のヒントになったに過ぎない。だけど僕はあなたの描いたライオンに一歩でも近づくために、これからもがんばっていきます」 さだ ケニアにある長崎大学熱帯医学研究所から帰ってきたばかりの柴田紘一郎先生に出会ったのは僕が二十歳の頃です。40年以上も昔のことです。 彼の語るケニアを聞き、その言葉のひとつひとつに憧れ、いつか歌にしたいとプロの歌い手になってからずっと思っていました。そして、ようやく15年かけて自分なりのケニアが身体の中に育ち、「風に立つライオン」という歌ができあがりました。 歌い続けるうちに、その歌は驚くほど多くの人達の心に強く働きかけるようになっていきました。この歌を聴いて医療従事者を志したり、青年海外協力隊に参加する若者がたくさん現れました。日本を離れ、海外で頑張っている医師も少なくありません。また、ある女性 はケニアでマサイ族の勇士の夫人となりました。少しずつ、沢山の人々の人生を変えていきました。そんな歌を僕は他に知りません。 大沢たかおさんもこの歌を愛してくれる一人で、彼の熱い思いによって、ついに映画になりました。 自分で作った歌というより、神様にいただいた歌なのだと感じていますが、これほど多くの方に愛され、影響を与えた歌を書いたという責任も感じていますし、少しでも海外で頑張っている人達の応援をしたいという思いで、今回、28年振りに歌い直したシネマ・ヴァージョンを配信でリリースして、売上の一部をチャリティとして寄付することにしました。 再録にあたり、新たに渡辺俊幸くんにリアレンジしてもらいました。元々8分半もある長い曲なので、映画の主題歌としてエンドロールで使っていただくには長すぎると思い、短くするつもりでしたが、オーケストラを使ったより雄大なアレンジになり、逆に40秒も長くなってしまいました。にもかかわらず、三池監督はフルコーラス、エンディングの一番いいところで使ってくださり本当に感激しています。ただ、映画に感動して泣きたいのに、自分の歌を聴いて泣いているように思われるのは嫌なので、できれば映画は、誰もいないところで、一人きりで見たいなとつくづく思います。(さだまさし) 医師を目指した理由を聞かれると、「非常に月並みですよ。何も変わったことは思っていないんですよ。小学校一年生の頃、親同士が国鉄ということで仲がいい女の子がおったんですよ。その女の子のお父さんが五右衛門風呂に入とってですね、板から出ていた釘が足に刺さって、七日後に死んだんですよ。今でいう破傷風ですね。まあ、元気で身近な人がいきなり亡くなると、悲しいですよね。皆さんと一緒で、非常に月並みな理由なんですよ。子供心に、非常に悲しかったんですよ。」
医者の良い点というのは、我々はどこにいても、例えば無医村にいても都会にいても、相手となる患者さんというのは尊厳価値においては同一じゃないですか。どういう所にあっても全力で仕事ができるというところでしょうか。悪い点は、医者の中には“自分が治している”と勘違いしている人がいる、ということでしょうね。患者さん自身が治ろうと、治そうとしているのに、医者はそれを神様と共にちょっと手助けするだけなのに、“自分が治している”と思い上がった心を持ってしまう…。まあこれは僕だけの意見ですけどね。
「理想の医者」 「僕の独断と偏見ですけど、臨床医は芸者ですよ。患者さんは心身ともに悩んでいるのですから…。医者は常に向学心を持ち、芸の心をもって、患者さんに尽くすこと。これが理想ですね。」 柴田先生 「大学病院にしか入らない」 柴田先生 「ベッドが空くまで待つ」 柴田先生 「お前が家内を殺した!」 「力足らずで申し訳ありませんでした」
毎年、教え子の多くが医学の道を志します。彼らに柴田先生
突然の事故。救急車で運ばれ、病院到着。
ドクター、ナースの顔を見てホッとする私に
「最悪だよな」
「先生と当直すると最悪の患者ばかりですね」と一言ずつ。
そんな中、「もう大丈夫ですから頑張ってくださいね」
看護学生のその一言に、
思わず涙が一粒こぼれた。 (児島美恵子) 柴田先生 「医療に携わって何年か経つと、どうしてもこのドクターやナースのように思う日が出てくるんですよ。僕だってそうですよ。でも、それじゃあいかんと…。初心を忘れるなとは、このことなんですよ。あなた方は今、ここに出て来る看護学生と同じ立場なんです。その気持ちをずっと忘れないでほしい。僕が言いたいのは、ただそれだけなんですよ」 ―― 「
そして2015年、大沢たかお 「風に立つライオン」 柴田先生 「映画館に5人連れて行くように」 「松江東宝」 (現在閉館) に案内して、約束を果たしました。実に感動的な映画でした。人生にはこうした不思議な運命・偶然の出会いというものがあるのです。映画を見終わって館内が明るくなって帰ろうと立ち上がった時に、私の席の後からいつもお世話になっている高梨泰至先生 ♥♥♥
▲大ヒットした映画「風に立つライオン」
最近はあまり聞かなくなったことばですが、 「着たきり雀」 「着たきり雀」 「旅行中の荷物を減らすと、『着たきり雀 』になってしまう」「父親が『着たきり雀 』のため、新しい服をプレゼントした」 それ以来何とも思っていませんでしたが、今になってこのことばを突然思い出してしまい、そういえばなんで 「雀」 雀 雀 「舌きりすずめ」 「着たきり雀」 私の尊敬する故・渡部昇一先生 上智大学 大学時代は、学生服一着の「着たきり雀」 「明治以来、書生は弊衣破帽が美徳だ」 そんな学生時代に、アメリカ留学の話が持ち上がりました。昭和25年頃のアメリカ留学といえば、今では想像もできないぐらい難しく、かつ光栄なことでした。成績・品行・健康などの点では最も有利な候補者であった先生は、当然成績トップの自分が選ばれるものと思っておられました。ところが「渡部は社交性がない」 「着たきり雀」 「非社交的」 ♥♥♥
最近「バタフライ効果」 「小さな蝶の羽ばたきが、遠くの国で嵐を引き起こす」 「バタフライ効果」(Butterfly Effect) エドワード・ローレンツ ローレンツ 「ほんのわずかな数値の違いが、将来的には全く異なる天候パターンを生み出す」 「ブラジルで一匹の蝶が羽ばたくことが、アメリカで竜巻を引き起こす可能性がある」 バタフライ効果 カオス理論 の一部として知られ、単純な原因と結果の関係では説明できない複雑なシステムの特徴を表しています。簡単に言えば、「小さなキッカケが、やがて大きな思いもつかないことに発展する」
このバタフライ効果
(1) 歴史におけるバタフライ効果 ●1914年、オーストリア皇太子フランツ・フェルディナント
●ナポレオン
(2)健康習慣におけるバタフライ効果 ●【食事】 毎日の食事の選択(野菜を多く摂るかジャンク・フードを食べるか)が、長期的には健康状態や疾病リスクに大きな影響を与えることがあります。●【運動】 定期的な運動習慣が、心血管の健康やメンタルヘルスの向上に役立ちます。逆に運動不足は、肥満や関連する健康問題を引き起こす可能性があります。(3)人間関係におけるバタフライ効果 日常的な些細なコミュニケーションや親切な行動が、信頼関係を築くのに役立ちます。友人、家族、職場の同僚に対する感謝の一言が、お互いの雰囲気や関係に大きな影響を及ぼすことがあります。
(4)キャリア選択におけるバタフライ効果 ●【教育】 学生時代の専攻や履修する科目の選択が、その後のキャリアに大きな影響を与えることがあります。特定のスキルを学ぶことで、その後の職業選択や昇進の機会が広がることがあります。
●【初めの仕事】 最初の職場での経験や得たスキルが、その後の自らのキャリアに大きな影響を与えることがあります。
(5)財政管理におけるバタフライ効果 ●【貯金と投資】 ちょっとした失敗を何とも思わずに、いつまでもダラダラと同じ失敗を繰り返す人がいます。5分の遅刻を、これぐらい遅れたことにならない、とたかをくくっている生徒もいます。生徒たちには、小さなミスが、重大な事故や危機に結びつく可能性を推計した「ハインリッヒの法則 1つの重大な事故や事件が起きた場合、その前には29の小さなトラブルや軽微な事故が発生し、さらにその29の小さなトラブルの前には、およそ300の小さなミスや勘違い、 ヒヤリとすること、ハッとしたことが隠れている これは、1941年にアメリカの損害保険会社の調査部にいたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒ
「事故」 「勉強」 「答案の見直し 」をうるさいくらいに言っている私ですが、この時期には1点のミスで、1年を棒に振る生徒をたくさん見てきました(「まあいいか、その一言でもう一年」 「共通テスト」 ♥♥♥
映画字幕翻訳家としておよそ1,500本もの作品を手がけた戸田奈津子(とだなつこ) 旭日小綬章(きょくじつしょうじゅしょう) 「私はこの仕事が好きでね、長い間、好きなことをずっとやってきて、それなりに楽しんできましたから。それでもう十分と思ったんですよ。だからなんでそんな今さらご褒美いただくのは恐縮しちゃってる」
大学の英文科を卒業して10年経った頃、映画『アリスのレストラン』(1966年) 「 この通訳という仕事、元来、私は大の苦手。私たちの世代は英語を聴いたり話したりの勉強はいっさい受けていないから、読み書きはできても会話はできない。私も当初は恥をかきかき、通訳の仕事をしていました。なにしろ初めて英語をしゃべったのは三十歳を過ぎてから」 以降、 一年に数本、字幕翻訳をするようになります。大きな転機は、さらに十年後の43歳のとき、フランシス・コッポラ監督 『地獄の黙示録』(1979年) コッポラ監督 「日本滞在中の監督の案内兼通訳のような役を務めた私を、鶴の一声で指名してくれた」 これで次々と仕事が舞い込むようになり、 一週間 一本の仕事のペースで字幕翻訳を依頼されるようになったのです。「20年待ち続けて、やっとやりたい仕事ができるようになった」 戸田 「素晴らしい人たちと親密な時間をもてた」 トム・クルーズ 「ミッションインポッシブル」(字幕担当:戸田奈津子) トム・クルーズ 「日本の母」
「字幕翻訳は直訳ではない」 「エモーション(感情)に訴えるのが映画」 「コンピューターではなく、感情を理解できる人間の頭を通過させたのが、字幕翻訳の言葉だと思う」 戸田奈津子 映画字幕翻訳 清水俊二 「とにかく難しい仕事だよ」 清水先生 「まだあきらめてはいません」 『PHP』2月号、2014年 「追い続けていると、夢はいつか必ずかなう 」などという人がいます。でもこれは、非常に危険な考え方です。夢がかなうかかなわないかは、五分五分、追い続けても、かなわずじまいで終わってしまうことも、決して珍しくありません。「かなわないこともある」という現実を直視することも大事です。私がホームレスを覚悟しつつ、一方では、目の前の仕事にも精を出していたのはそうした意識があったからです。(中略) 夢や目標を成就させるには、何よりまずその対象が好きなことが大切です。好きでないと長く続けられない。私は映画が好きだから英語を勉強しました。そうでなかったら、英語は勉強しなかったでしょう。(中略) 現実を見据えつつ、好きなことに打ち込む。結果がついてきたら、ラッキー。そう思って前を向き続ける人生もまた、素敵ではないでしょうか。 「映画にドラマを感じることが少なくなった」 タップダンス 『読売新聞』 「 全盛期のようにあれもこれもやると負担になる。体と相談しながら、老後を楽しまなくちゃね」 2014年9月に、戸田 戸田奈津子・金子裕子『KEEP 「このように内臓的にはいたって健康なのですが、唯一、眼にだけは酷使のツケが回ってきました。もともと超ド近眼だったのですが、それも原因で、左目が最近iPS細胞の移植ですっかり有名になった「黄斑変性症」になりました。左目の中心部がドーナツ状に真っ暗で、字も読めないのですが、幸い、眼は2つある!片方の目だけでなんとか今日まで過ごすことができ、かなり怪しくなったけれど運転も続けています。」(pp.176-177) 「映画だけで終わった人生なんて、単細胞かもしれませんけれど、ほかに行きたい道がなかったのだから仕方ありません。」 戸田
彼女の体験に基づく参考になる本は 『字幕の中に人生』(白水社、1997年) 『字幕の花園』(集英社、2009年) いくつかあります。若い頃、戸田 戸田 戸田 「ガーフィールド」 研究社
その戸田 『枯れてこそ美しく』(集英社、2021年11月) 戸田 村瀬実恵子(むらせみえこ) メアリー・バーク夫人 村瀬 「しぐさやものの考え方も、日本人としてのアイデンティティーを失っておらず、感銘を受けました。おしゃれで、いつもすてきな靴を履いている」
戸田 村瀬 人の心を打つ、人が感動する仕事に携わってきたことは共通していて、私も村瀬先生も仕事一筋。一人で生きてきた女性として、とても共感したんです」 「お互い運がよかった」 「村瀬先生は日本の美術がそれほど評価されていない時期に活動された。私も字幕翻訳者になるまで20年かかったけれど、好きなことに生きて、一生続いた。長く続く好きなものに出会えたことはお互い幸せだった」 「80、90歳なんてとんでもないおばあさんと思うかもしれないけど、自然体で全然飾ってませんから、年齢も意識しない。こういう生き方もあるって、思っていただけたらうれしい」 戸田 村瀬 『枯れてこそ美しく』
若い人たちには、次のような言葉が印象に残りました。戸田 ♥♥♥
夢が叶うか、叶わないか?いわゆる確率的には五分五分だから、大きなリスクですよ。それをわかってて、やっぱり覚悟していたのですから我ながら思い込みが強かったと思います。つまり字幕翻訳者になれないこともあると最初からわかっていて、どんな結果も受け入れる心構えがありました。覚悟を決めて、絶対にブレなかったから、情熱が長続きしたんだと思います。私は若い子たちから人生で重要なことは何かと聞かれたときには「自分がやりたいことをきっちり見極めて、自分で選択しなさい」ということをいつも言います。人の意見を聞いてもいいけど、選択するのは自分自身。最後の決断は自分で下すべきだと。人の言うなりになったり、右へ倣えしては絶対にダメよときつく言っています。
我が国のトラベルミステリーの第一人者・西村京太郎(にしむらきょうたろう)先生 649作 にのぼります。私がかつて湯河原 東京スカイツリー 635冊 を書くのが夢だとおっしゃっておられましたから、目標を優に達成されたことになります。熱狂的西村 西村京太郎 『戦争とミステリー作家 なぜ私は「東条英機の後輩」になったのか』(徳間書店) 「東京新聞」 「東条英機の後輩」 西村先生 「 東京陸軍幼年学校」 東条英機 西村 西村 陸軍幼年学校 山村美紗 山前 譲
55年振りの「大阪・関西万博」 「大阪万国博覧会」 松下グループ 「松下館」 松下電器 法隆寺 夢殿
開館まもないある日、次のようなことが起こっています。夏の炎天下、入場者の整理のため、入館待ちをしている人々の行列を映し出す事務室のテレビ画面に、どういうわけか松下幸之助(まつしたこうすのけ) 「いつも来られるときは事前の連絡があるのに、いったいどうしたことだろう? 「どうされたのですか」 と、 通用口からの入館を勧めました。しかし、幸之助 「この暑い中、長い列に並んでいる方々を見て、申し訳ない、すまないと思った。いったいどれほどの時間で入れるのか、いま自分で計っているところだから、心配しなくていい。」 幸之助 ①「もっとスムーズに列が進むための誘導方法を考えるように。」②「所々に日陰を作るための大きな日傘を設置するように。」③「並んでくださる方々に紙の帽子を配るように。」 「経営の神様」 「さすが、松下さんは商売上手だ、この会場を商売に使うとは」 紙の帽子 「松下電器」 「National」 「松下館」
自らが足を運んで、一般の人と同じ目線で体験するのが松下 「百聞は一見 にしかず」 松下 「百聞は一験 にしかず」 「現場、現物、現人」 松下 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はケーキ
▲宍道湖沿いに佇む「清松庵たちばな」
▲店内のケーキショーケース
リビドー 宍道湖畔 「清松庵たちばな」 リビドー 「喫茶コーナー」 宍道湖 「アップル」 コチラ )と「ロッド」 「ロッド」 リビドー ♥♥♥
▲私のお気に入りの「ロッド」
(株) UCC コーヒーカップ 「ノリタケ」 「ノリタケ」 ノリタケ 高い技術に裏打ちされた品質と品格、 創業以来変わらないデザインへのこだわり、 時代に合わせたラインナップなど、 さまざまなこだわりの中にノリタケ
森村市左衛門(もりむらいちざえもん) TOTO 日本ガイシ ノリタケ 森村グループ 「至誠事に当り、もって素志を貫徹し、 永遠に国利民福を図ることを期す」 森村 創始者である森村市左衛門 この言葉を自らの会社、 社員への訓戒として掲げました。 そして誠実であることこそ、 最も大切であると説いたその精神は、 今も脈々として同社に受け継がれています。 人は正直に全心全力を尽くして、一生懸命に働いて、天に貸してさえおけば、天は正直で決して勘定違いはありません。人ばかりを当てにして、人から礼を言われようとか、褒められようとか、そんなケチな考えで仕事をしているようでは、決して大きなものにはなりません。
労働は神聖なもので、決して無駄になったり骨折り損になどならない。正直な労働は枯れもせず、腐りもせず、ちゃんと天が預かってくれる。どしどし働いて、できるだけ多く天に預けておく者ほど大きな収穫が得られる。私は初めからこういう考えで、ただ何がなしに天に貸すのだ、天に預けるのだと思い、今日まで働いてきたが、天はいかにも正直。三十年貸し続けたのが、今日現にどんどんかえってくるようになりました。 この言葉は、「損得」 「尊徳」
ノリタケ株式会社 「ノリタケ(則武)」 愛知県愛知郡鷹場村大字則武(現・名古屋市中村区則武) 地名 に因むものであり、人名由来の社名ではありません。本社があった名古屋市西区則武にはノリタケ 「ノリタケの森」 「産業文化観光」 名古屋 「美しく精緻な磁器を日本でつくりたい」 ノリタケ 森村市左衛門 福沢諭吉 「金を取り戻すには、輸出貿易によって外貨を獲得することが必要だ」 市左衛門 「森村組」 豊(とよ) 「モリムラブラザーズ」 ノリタケ 森村組 市左衛門 「この美しい磁器を日本で作りたい」 ノリタケ 「日本陶器合名会社」 愛知県鷹場村大字則武(現 名古屋市西区則武新町) 「ノリタケチャイナ」
食器の世界ブランドとして発展する一方で、ノリタケ 「粉砕」「混練」「成形」「焼成」「印刷」 「砥石」 日本陶器株式会社 株式会社ノリタケカンパニーリミテド ノリタケ株式会社 ノリタケ
地球温暖化やエネルギー問題など、地球環境に関わる問題が顕在化している現在、ノリタケ 森村市左衛門 「至誠事に当たり、もって素志を貫徹し、永遠に国利民福を図ることを期す」 「美しく白い精緻な磁器をつくりたい」 ♥♥♥
私は文房具 文房具の八ちゃん 東京・銀座 「伊東屋」 間部香代『銀座伊東屋の仕事 文房具専門店クロニクル』(グラフィック社、2,090円)
最近では、『文具屋さん大賞2025』(扶桑社ムック)
さて今日のテーマ。偶数月一日に発行される文房具情報フリーペーパーマガジン 『Bun2(ブンツウ)』 松江・田和山 「ぶんぶん堂」 末次本町 「原文パピロ21」
八幡 「あ、これ気になっていたヤツだ」 高畑正幸 「この商品はお客様のこんな声から生まれました!」「ここを工夫しています!」 「あ〜だから使いやすかったのか」 「お店では気にならなかったけど、ちょっと試してみようかな」 「文房具の八ちゃん」 ♥♥♥
今井書店 「やっぱり楽しみでしたよ。ちょっと休みの間はさびしかったですね」 「もうずっと待っていたのでオープンを。本だけじゃなくていろいろ楽しんで帰れるってところがいいんじゃないですか」 本屋自体が、今までのマーケティングや店づくりに関してあまり関わって来なかったデジタルを上手に使って、そして大きなリアルの本屋と融合させることによって、山陰の地元の皆様にしっかり本を楽しんでもらえたらと思います。(今井書店・達山常務取締役)
松江市田和山町 「今井書店松江本店」 「今井書店グループセンター店」 「今井書店松江本店」 「書店ゼロ」 「すごせる書店」 鳥取県智頭産の杉 IAMCoffee Pizzeri & Cafe コワーキングスペース 今井書店 「今井書店がおかしい」 をご覧ください)。今回は人が多すぎて、隅々まで詳しく見て歩くことはできませんでしたが、「あ、いいな」と思った点は、①朝の9時から開店してくれること(~夜10時)。②文房具(特に私に貴重な筆記用具類)の在庫が充実していそうなこと。③デスクスペースがあること 私が学生時代には殿町 「今井書店本店」 島根大学 「園山書店」 アガサ・クリスティ(Agatha Christie) ♥♥♥
学校法人「広島女学院」 広島女学院大学 学校法人「YIC学院」 文部科学省
広島女学院大学 広島女学会 人文学部 人間生活学部 広島女学院ゲーンス幼稚園
大学経営からの撤退の背景には、若い世代の「女子大離れ」 「少子化」 広島女学院大学 「少子化」 「共学志向の傾向」 「定員割れの問題もあるし、最近ひどいので仕方ないかなと思う。」 湯崎英彦知事 「学校事業が受け継がれるのは高旺盛などの多様な進路の確保に繋がるものになると思うし、そうなってほしい」
移管先のYIC学院 文科省
中国地方では、2025年度以降学生の募集を停止したのが、就実短大(岡山) 美作短大(岡山) 安田女子短大(広島) 比治山大学 (広島市東区) 現代文化学部
私が教師としてまだ若かった頃は、国公立大学 私立大学 広島修道大学 広島大学 修道大 広大 広島女学院大学 広島女学院大学 「スキップ発祥の地」 なんだそうです。 明治34年、広島県広島市東区の広島女学院大学 マコーレー先生 広島女学院中学高等学校
1993年のピーク時には国公私立合わせて595校、学生53万人が在籍した短大も、1990年代以降、女性の大学・共学志向の高まりを受けて、大学に移行する短大が急増しました。2024年度には297校に半減、学生数は8万人にまで現象しています。学生募集を停止した短大は2025年度23校、2026年度21校、2027年度1校と急増しています。私立短大の約7割の収支が赤字です。2024年度に文科省 「3年連続で学生数が収容定員の8割未満となるだけで、原則、国の奨学支援新制度(低所得者向け支援)の対象外」
つい先日、今度は京都ノートルダム女子大学 人文学部言語文化学科 文科省
最近、財務省 文科省 「目指すべき方向は同じ」 「定員割れしていたり、基礎的な学びを取り入れたりしている大学の教育の質が一概に低いとは言い切れず、一面的で粗い考えだ。学力の成長度や進路実績なども含めた評価が必要だ」 松江北高 二次試験 ♥♥♥
公立・県立の高校に通う高校生のゴールデンウィーク golden week 勝田ケ丘志学館 勝田ケ丘志学館 鳥取県立米子東高等学校 「体験的学習活動等休業日」 「11連休」 「連休中は普段できないような体験的な活動を行うなど、時間を有意義に使いましょう。」(米子東高HP) 「昨年の10連休は何をしてた?」――「テレビを見ていました」「ユーチューブを見てました」 〔笑〕
平成29年9月に学校教育法施行令が一部改正され、「家庭や地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日」 「体験的学習活動等休業日」
1 体験的学習活動等休業日の趣旨 2 導入のねらい 「体験的学習活動」 (1)生活・文化体験活動・・・(遊び、お手伝い、スポーツ、地域行事)
(2)自然体験活動・・・(登山、キャンプ、星空観察、動植物観察)
(3)社会体験活動・・・(ボランティア活動、職場体験活動など)
「体験的学習活動等休業日」 「家庭や地域での活動を通じて自ら学び、考える力を育みます」 「働き方改革」 「力を尽くして狭き門より入れ」 無茶 はいけませんが、無理 はしないと結果は出ないのです。楽をして結果が残るのなら、苦労はしません。 このゴールデンウィークに「ラーケーション」 「学び」(ラーン) 「休暇」(バケーション) 愛知県 熊本、茨城、山口、徳島 ♥♥♥
▲どこにも行けない八幡はジバンシーのコーヒーカップでブルーマウンテンとCiistandのモンブラン
安藤忠雄(あんどうただお) 安藤 「直島」(なおしま) 安藤 地中美術館・ベネッセハウス 安藤 京都 奈良 安藤忠雄 安藤 大阪大学 京都大学 「忠雄ちゃんはおかしくなってしまった」 本質を知る人と、知らない人。その差はあとあとになって明確になっていきます。たとえ本質を勉強していない人でも、器用な人は、表面的に事象をとらえて、上手に仕事をこなすことができるでしょう。でもそれでは一流にはなれません。本質を勉強した人と、していない人の差は、初めはあまり現れません。特に若い時は、単純な仕事が多いので、本質を知らなくても、仕事は何とかこなせるのです。表面的に仕事を右から左に流しているだけの時は、大きな差は出ないことでしょう。しかし、ある程度の年齢になって、いろいろなことを総合的に判断しなければならない立場になった時、本質を知っているのと知らないのとでは大きな差が現れます。世の中は複雑で、年齢を重ね地位が上がるにしたがって仕事の複雑さは増していくからです。複雑なことを正しく判断するには本質を知らなければならないのです。
安藤 「東京大学特別栄誉教授」 安藤 「東大特別栄誉教授」 東大 安藤 安藤 東京大学 日本武道館 安藤忠雄
自立した人間を育てるために、親が子供を甘やかしてはいけないということはよく言われます。しかし、現代において全てを与えられている恵まれた子供たちは、「夢」を持てないでいるのです。考えてみれば気の毒なことなのかもしれません。格差社会です。幼い頃からさまざまな塾へ通い、恵まれた環境にいなければ、高偏差値の大学へ入学することは難しいのが現実です。ある程度、どういう暮らしをしてきたのかで、その後の人生が決まってしまうのです。安藤忠雄
安藤 胆管 胆嚢 十二指腸 膵臓 膵臓 脾臓 「膵臓の全摘をして生きている人はいるけれど、元気になった人はいない」 「五つも臓器を取って元気なのは縁起がいい」 「人々の記憶に残り、あってよかったと思ってもらえるものを造りたい」 安藤 「人生100年、熟さない青いりんごのように青春を生きる」 「1勝9敗」
NHKのEテレで、2017年3月26日(日) 午前5時~(60分)に放送した「こころの時代~宗教・人生~「“しゃあない”を生きぬく」」 安藤忠雄(あんどうただお) 「しゃあない」 安藤 「しゃあない」 安藤 「しゃあない」 「立ちはだかる壁にこそ無限の可能性がある」 建築家の枠にとどまることなく、幅広い社会活動にも専心しておられます。2019年に大阪市 「こども本の森 中之島」 「こども本の森 プロジェクト」 香川県 安藤 「こども図書館船ほんの森号」
安藤 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はアップルパイ 寒くなると、りんごがますますおいしく感じる季節ですね。りんごを使ったスイーツといえば、やっぱり「アップルパイ」 アップルパイ 「アップルパイ」 「ポテトサラダ」 岡山駅サンステ2階 「成城石井」 「アップルパイ」 「成城石井」 「アップルパイ」 「成城石井自家製 青森県産りんごまるごと1個使ったアップルパイ」(863円)
「プライムニュース」 反町 理(そりまちおさむ) 長野美郷キャスター 竹俣紅アナウンサー 長野キャスター 「今夜の番組は、先ほど公表されたフジテレビに対する第三者委員会の報告書を取り上げます。第三者委員会は報告書で、フジテレビの企業統治に問題があったと指摘しています。また、報告書には、反町キャスターの事案についても、フジテレビの対応に問題があったと指摘する部分があります。反町キャスターからは、状況に鑑み、番組の出演を見合わせたいとの申し出がありました。BSフジとプライムニュースではこれを受け、今夜は私、長野と竹俣アナウンサーの2人でお伝えします」 先日発表になった、フジテレビ問題の「第三者委員会」 反町 理 「プライムニュース」 中居正広 「多数の社員から反町氏が報道局の後輩女性社員2人に対して行ったとされるハラスメント行為の対応が不適切。昇進を続けることで、セクハラやパワハラを相談しても無駄と思わせる結果となっている」 反町 反町 反町 「プライムニュース イブニング」 『週刊文春』 宮内正喜代表取締役 「記事は事実無根」 反町 「プライムニュース」 反町 「流れ弾というよりも自業自得で、社内で相当嫌われていたんでしょうね。ハラスメント認定され、もうテレビに出ることはできないでしょうね」
ハラスメント行為としては、まず「女性社員mに対する行為」を挙げ「女性社員mの申告によると、2006年頃に、反町 反町 反町 反町
また、「女性社員nに対する行為」にも触れ「女性社員nの申告によると、2007年から2008年頃に、反町氏は女性性社員を一対一での食事に誘っていたりしていたが、あるときから、休日に今何しているのか写メを送れという趣旨のメールをし、食事の誘いをするようになったため、女性社員 はこれを断り、そうしたところ、女性社員nに対しても原稿が遅いなどと不当な叱責を部内一斉メールで送信したり、電話での論旨不明な叱責をしたりしたとのことである」
「本件ハラスメント行為に関する評価」としては「反町氏は、女性社員m及びnと食事に行った事実、女性社員mに対してメモを送付しなかった事実、女性社員nに対してメールを送付した事実を認めているものの、行為の詳細については記憶にない等と供述し、メモを送付しなかった事実については全員に送付しているわけではなく理由があるなどと主張し、叱貴の事実も否認する。本件ハラスメント行為は2006年及び2007年と相当程度前の出来事であるところ、その厳密な認定は困難ではある。しかし、女性社員m及びnの申告によれば、反町氏の行為は、一対一で食事に誘うものも含まれたり、プライベートの写真の送付を求めたりするもので、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動により職場環境が悪化したものとして、セクハラに該当し得るものである」 「また、休日に行動を共にさせたことや、業務上必要なメモを共有せず、周囲の社員に見えるように叱費をしたことは、上司という職場における優位的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えた言動で、労働者の就業環境を悪化させる行為として、パワハラに該当し得るものである」
BSフジでは4月2日「プライムニュース」 反町キャスター 「言語道断」「経営一部トップが(これらを)問題と思っていないのが大問題。おとがめもなく取締役になっていくとはあり得ない」「信賞必罰が全く行われていない」 反町 ♥♥♥
「超魔術」「ハンドパワー」 Mr.マリック(76歳) 「顔面神経麻痺」 「ハンドパワー」 「子供の頃から入院なんて一度もしたことがなかった」 マリック 顔面麻痺
「口に入れたつもりのモツが、ポロッと器に落ちたんです。それを拾って食べようとしたら、またポロッと。そうしたら、向かいに座っていた友人が『ちょっとトイレに行って、鏡を見てきてほしい』と言いました。きっと、(表情がおかしいと)言いづらかったんでしょうね」
その時は、まだ自らの異変に気づいていませんでした。しかし、鏡を見て驚きます。 「顔の半分がズレているんですよ。眉毛の高さが左右で違っていた。そのうち、目がチカチカしてきて、右目を動かせない。『何だこりゃ』と思いながら席に戻り、家に帰りました」 顔面神経麻痺 「耳の奥あたりにある神経が萎縮(いしゅく)していて、麻痺の症状が出た」 「それなら自宅から通院します」 「絶対に病院に来なくなるから、入院してください」 「とにかく、注射がメチャメチャ痛いんです。針を刺されると、何か体の中にブワーッと入ってくるのが分かった後、暴れたいくらい痛くなる。動くと危ないので、4人の看護師さんに体を押さえられて注射されていました」 マリック 「治療が始まると、注射を打たれた人の『ギャー』という悲鳴が聞こえる。それがだんだん近づいてくるんですよ。『あと2人、あと1人』となって『キターッ!』と(笑)。もう拷問でした」 『スポーツ報知』
マリック 超 ゆうむはじめ『Mr.マリック超魔術の嘘』(データハウス,1990年) でした(写真右)。 しかも何冊も続編が続きます。人気マジシャンの暴露本ですから、売れないわけがありません。マリック 顔面麻痺 それまでもマジシャンとして活動していましたが、1988年に日本テレビ系「11PM」 「超魔術」 「木曜スペシャル」 「でも、急に有名になったからか、周囲からいろいろ言われるようになりました。『マリックは超能力者なのかマジシャンなのか』とかね。それで『超能力なんてものはないからインチキだ』と。私は自分の力を超能力なんて言ったことはなくて、最初から『超魔術』と呼んでいたんですが。それで、仕事のストレスがどんどんたまっていきました」 当時はマネジャーもつけておらず、イベントに出演すると「お寺を差しあげますから教祖様になってください」「地図を持ってきたので、埋蔵金がどこにあるか指さしてください。見つかったら半分あげるので」
「娘(ミュージシャン・LUNA)が学校をクビになったり、家出して警察に呼び出されたりしてね。人間、悩み事が1つなら解決できると思うんです。でも、2つ以上あるとおかしくなっちゃう。私の場合は仕事と家庭でした。それで、脳が“交通事故”を起こしたんでしょうね。どこか弱い部分に影響が出てくる。それが、私の場合は顔面の神経で、麻痺となって表れたんだと思います」
ステージ上で「ハンドパワーです」 マリック LUNA 「 スプーンを親父に曲げてもらってこい!」マリック 超魔術 マリック
麻痺があっても、それを隠し通して仕事を続けました。右側の麻痺が完治しそうになった時、今度は左側にも同じ症状が出て、結局、闘病期間は2年にもわたりました。その中で変わったことは、将来に対する考え方です。この時期の苦しい経験が「先の目標を立てるよりも、目の前のことを一つ一つ、丁寧にしていく」
「今日元気でも、明日何が起きるか分からないということを体験しちゃったものですから。遠い目標を立てたり、先のことを心配して過ごすよりも、目の前に来た仕事を一つ一つ、丁寧にベストを尽くしてやっていこうと切り替えました。それを繰り返してきたら、こうして35年を迎えられたということですね」
4月25・26日には、東京 大阪 「Mr.マリック超魔術団2025」 マリック 「観客全員でスプーン曲げに挑戦」 マリック リュー・チェン チャーミング・チョイ 「超魔術」 マリック 「TAKUYA&YOURI」 マギー司郎
「今まで、私の人生の転換期に会った人への感謝を込めて、やりたいと思います。ただ、私の超魔術だけだと疲れてしまうので、マギー(司郎)さんにも入ってもらって笑わせてもらう。緊張、緩和、緊張、緩和とジェットコースターのようなライブにしようかなと思っています。人間はリラックスした時にパワーが出る。緊張している時は集中力が発揮できないですからね。リラックスしている時に『曲がれ!』と念じれば、スプーンは曲げられると思います」
マリック 「超魔術」 「徹子の部屋」 マリック マギー司郎 「超魔術」 「笑魔術」 ♥♥♥
「共通テスト」 「リーディングの問題形式は予想通り第1問~第8問でした。予想通り分量が激減。難度は去年より易しくなっています。でも第6問は生徒たちには解けません。」 【第6問】 ベネッセ・駿台 「共通テスト」 【 第6問】 問1 (29.5%) 問2 (56.3%) 問3 (46.8%) 問4 (32%) 中でも問1 (全問の中で最悪)と問4 (全問の中で二番目に低い)が極端に出来が悪かったのにもちゃんと理由がありました。
今年の「共通テストリーディング」第6問
(1)複雑な時系列構造(あっちへ行ったり、こっちへ行ったり) 時系列が前後する形式で記述されているために、時の流れを整理する力が問われます。ダイヤ(♦)マークが場面が切り替わるヒントになっていました。回想シーンを含めてあっちへ行ったりこっちへ行ったりで、受験生には話の展開が分かりにくかったと思われます。「共通テスト」
(2)推測力・想像力が必要(書いてない) 本文に書いていない内容を読み取る力、行間を読む力 が求められています。ここら辺が「共通テスト」 「息子とこのまま一緒にいる」 ということを、前後の文脈から把握しなければなりませんでした。
(3)選択肢の正確な分析が必要(精読の重要性) 不要な情報や曖昧な選択肢を排除し、本文の内容に基づいた正しい判断力が求められています。正しい「言い換え」 「精読」
(4)物語形式ゆえの高い難易度(物語は苦手な人が多い) そもそも「物語形式」の文章は受験生が苦手です。その理由は、①書き出しが分かりにくい ②話の流れをつかみにくい(5W1Hの法則) ③時系列で混乱 ④セリフが誰のもの? ⑤「言い換え表現」が多用される
「超能力を持った少年が成長する様子を描いた物語」を読んで、それに対する感想メモを完成させる問題でした。少年の成長を時系列に並べる問題が出題されましたが、回想シーンとして過去の話が挿入されており、話の展開がつかみにくかったと思われます。主人公とメロディの関係もはっきりとは書いてなく本文中の手がかりから推測しなければならないことも概要把握を難しいものにしていました。私は当初から、第6問 「心温まるいい話」 センター試験 【第6問】 勝田ケ丘志学館
今回何と言っても「最も難しかった問題」は第6問 「個人的にはへたくそな文章を読んでフィードバックしてあげる形式それ自体が、テストとしていかがなものかと思う。テストとしては、読みごたえがあり、しっかりした文章を読ませて、ちゃんと読めているかを確認したほうが、良いのではないか」 ♥♥♥
竹岡広信先生 『LEAP』(数研出版) 改訂版 「見出し語」 派生語 見出し語 竹岡先生 「『改訂版必携英単語LEAP』に抱く熱き思い」 コチラ で読むことができます)を読むことでよく理解できるでしょう。この理想的な単語集の私の詳細な書評はコチラ をご覧ください。 今日はその中でも最も注目すべき「QRコードコンテンツ」 QRコード 「動画解説」 竹岡先生 ①「語源の捉え方」、②「発音・アクセントのルール」、③「英作文で使える「英単語の使い方」」 「英単語の暗記」 「花より単語」 「語源の活用」 語根、接頭辞、接尾辞 『英単語はアタマ・オナカ・シッポで攻略だ!』(自費出版、2011年) 安藤貞雄先生 「Festina lente!」(ゆっくりと急げ) ①「語源の捉え方」(6本) 竹岡先生 ③「英作文で使える「英単語の使い方」」
その他にも「音声・ドリル問題」 QRコード ♥♥♥
▲書店に並んだ『LEAP』改訂版
【追記】 竹岡広信 先生 数研出版 「令和7年度大学入学共通テスト分析」 竹岡広信先生 「共通テスト」 竹岡先生 コチラ から
尊敬する渡部昇一先生(上智大学名誉教授) 渡部先生 『歴史通は人間通』(育鵬社、2014年) 扶桑社文庫 「人生の大局観を養い、機微を知る。」 「スピーチにも役立つ心に響く名文集!」 「歴史と人生」
「まえがき」
「いろいろ書いたものの中から、大越昌宏氏が拾い出して編集して下さったのが本書である。読者として、またすぐれた編集者としての大越さんの目にとまった章節ばかりであるので、これを読まれる方にも何程かの愉悦と人生のヒントを与えてくれるのではないかと期待している次第である」 大越昌宏 PHP研究所~致知出版社~育鵬社
本書は非常に良く編まれた『渡部昇一名文集』 オーウェン・バーフィールド 「歴史というものは虹のようなものである。それは近くに寄って、くわしく見れば見えるというものではない。近くに寄れば、その正体は水玉にすぎない」 という言葉が紹介されています。著者は、この美しい言葉について、 「見る側の人間がいなければ、虹と同様で『歴史』は存在しない。いわゆる客観的なものは個々の『史実』だけであり、それはあくまでも虹における水滴のごときものなのである」
また著者は、「歴史を語る2つの態度」ということを次のように述べています。
「私は、自分の国の歴史を語ることは、結局、自分の先祖を語ることだと考えている。要するに、自分の親や祖父について語るようなものだと思う。また、その際、どうしても語る時点の自分の感情がからまってくる。そしてその場合、2つの態度があると思う。1つは、親を憎み、それを告発するような態度をとることである。日本史の暗黒面をあばきだし、きびしい批判をあびせ、しかも、それが激しければ激しいほど真実に近く、正義であるとする立場である。もう1つは、まず親に対する愛情から出発する態度である。親の弱点や短所を承知しながらも、それを許容し、むしろ親の長所やユニークな点に重点を置いて語る立場である」
この2つの態度を紹介した上で、著者は自身の立場(=二番目)を明らかにします。
「私は、まず自分の先祖を愛する立場、先祖に誇りを持つ立場から日本史を見てみたい。愛と誇りのないところに、どうして自分の主体性を洞察できるだろうか。非行少年の多くは、自分の親に対する愛と誇りを失うことによって、基本的な主体性を失い、非行グループという偽の主体性を得た若者たちであるといわれている。それと同じように、国民が自分の国の歴史に対する愛と誇りを失えば、日本人としての主体性(アイデンティティ)を失い、日本よりさらに野蛮な国に、自分の主体性を委ねたりすることになるのではないだろうか」
歴史を鏡に、己の人生の大局観を養うにもうってつけの章です。3「歴史人物に学ぶ生き方」では、「伝記を読もう」として、次のように述べます。
「伝記を読んで感奮すると、その偉人に一歩近づくことになる。さまざまな伝記を読んでいると、その中に必ず自分に合っていると思うものが出てくる。同じ感動の仕方でも、これは他のものとちょっと違うという伝記が現われるのだ。そしてこれが、だんだん自分の人生の理想、生きる目標となっていくのである」 「子供には偉人伝を読ませよう」 として、次のように述べています。
「道徳、あるいは徳目の起源については諸説があるでしょうが、先人や他人の行為を見て『美しい』と感じることができる時に、その行為につけた名前が徳目ではないでしょうか。『忠』とか『孝』とか『悌』とか『信』とか、徳目が名づけられる前には、その基となる何かしらの人を感心させた行為があったに違いありません。そのような、よい徳目が発揮された話は、読んだり聞いたりした人を感激させ、共感させ、心のどこかにその影響を残すのです」
明治維新以降にも、偉大な日本人はいました。松下幸之助 松下幸之助 コチラ をご覧ください)。彼は「経営の神様」 「 PHP運動」 「PHP」 「Peace and Happiness through Prosperity」 「スルー・プロスぺリティ」 松下
「ピース(平和)とハピネス(幸福)はみんな説いています。釈迦でもピース・アンド・ハピネスです。麻薬でもピース・アンド・ハピネスは得られる。しかし、それではダメであり、繁栄(プロスペリティ)によって得るピース・アンド・ハピネスでなければならないと松下幸之助は考えた。お父さんが働いて月給を家に持ってくる。それをもって家が治まりハピネスになる。こういうような感じでしょうか。これは世界に類を見ない。『繁栄のための努力によって』というのは、通俗といえば通俗だけれども、強力な哲学であると思います」
16「人生を充実させるための仕事術」では、「溶鉱炉のごとく」として、次のように述べています。
「溶鉱炉は一度火を消してしまうと、再び鉄が溶けるようになるまでに、たいへんな時間を必要とする。そこでどんな場合でも火を消さないようにするというのである。そしてひとたび火をつけたなら、火を落とすことなくどんどん温度を高めていかなければならない。知的作業もそれと同じで、頭のエンジンも中断されることなく回転していけば、温度が次第に上昇してきた溶鉱炉のごとく、頭はますます冴えてくるものだ。かくて、その仕事に取りかかった時には、予想もしなかった展開や思いがけないひらめきが次から次へと生まれてくるのである」
そして、17「読書で耕す人生」では、「読書の醍醐味」についてもこう語ります。
「人間は時間と空間に限定されて生きている。平均に生きても80年に足らず、せいぜい旅行してもそれほど多くを見るわけにいかない。また一生の間に会う人の数、特にすぐれた人に会う数は知れたものである。ところがひとたび狭い書斎にひきこもり、書物を取り出せば、たちまち時間の制約も空間の制約も取り払われてしまう。そしてどんな時代の、どの国の偉大な思想家の考えにも触れうるのである。読書というものの不思議さは正にここにあると思う。深夜の物音1つしない書斎でこの人たちの書いたものを開けば、その人たちは眼前に立ち現われて私に語りかけてくるかの如くである」
まさに「人生の大局観を養い、機微を知る」 「なるほど!」 と納得させられてしまう珠玉の言葉が並んでいます。自分に恍惚を感じさせてくれるものは何で、それはどこにあるのか?人生の後半において最も大切なのはそれを発見することであり、足元と行く先を照らしてくれる灯火となる一冊です。それぞれの文章の最後には出典が明記されていますから、気になった言葉はオリジナルの本に当たればよいでしょう。改めて自分でも驚いたのは、私は著者の本をほとんど読んでいたこと。本書に登場する本で、未読のものはなかったと思います。いかに、私の魂が著者から薫陶を受けていたかがよく分かりました。なお「あとがき」 渡部先生 早藤眞子 渡部家 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はオランダケーキ
▲長崎の「福砂屋本店」
私は1624年創業の長崎・「 福砂屋」のカステラ コチラ )。旅行で都会へ行く度に、自宅用にお土産用に買って帰ります。私がいつもそれと一緒に買い求めるのが、同じ福砂屋 「オランダケーキ」
▲「福砂屋」のカステラとオランダケーキ
中からオランダケーキを取り出すと、ココアの香りがあたりにほわ~んと漂います。すでにあらかじめ10切れにカットされているためナイフは不要です。カステラの生地にココア くるみ レーズン
まずは一口。ココアの香りがふんわりと香ってきます。カステラ同様のしっとり・ふわふわとした食感に、きめ細かく繊細な口どけです。濃厚ながら品の良い甘さが広がります。見た目からふわふわ食感が伝わってきますね。これにココア クルミ レーズン
ジューシーで甘酸っぱいレーズン 福砂屋 「オランダケーキ」 「オランダケーキ」 ココア 福砂屋
クルミ レーズン 岡山 天満屋 ♥♥♥
巨人 戸郷翔征投手(とごうしょうせい、25歳) 戸郷投手 阿部監督 「全て今かみ合ってない状況なので、ほんとに全て治さないといけない。こんなに思った通りいかないのも初めて」 阿部監督 菅野智之投手 戸郷投手 「順調にいける野球人生ってそうそうない。彼はまだ壁という壁にぶつかってないはずだから。壁にぶつかってまだまだ成長していかないといけないし、今がマックスだったらこの先ダメだと思う。」 戸郷 「監督に呼ばれてね、ファームっていうのも告げられましたし」とし、「もちろん3試合良くなかったんでね。(今回ダメなら)もちろんファームっていうのは分かってましたし、直すところっていうのは監督もね、明確だし。でも、今日のピッチングの出力的にはね、“凄い良かったよ”って言ってくれたんで。いいものもあるけどね、もうこんだけね、点取られても、示しもつかないしっていう話で。頑張ってね、また戻っていきたいなと思います」 「いい具合の変化球を見られたりだとか。いいものもありましたけど、初回良かったんでね、どんな感じになるだろうと思いましたけど。なかなかやっぱり3試合はね、良くなかったんで。なんかやっぱりうまくいい思考にならなかったりとか、そういうのが多かったんでね。また見つめ直して、強くなってね、帰ってきたいなと思いますけど」 「もう、体は凄い元気なんで、試合勘だけ。試合勘というか、その癖の部分だったりだとか、何が悪くなってるか分からないですけど、もちろん結果を残しつつね、やっぱりこんだけチームに迷惑かけたんで、金曜日の選手がね、こういうピッチングだと。なんとか他のピッチャー頑張ってくれてるんで、あまり大きく目立たないですけど。やっぱり柱となるピッチャーがね、こういうピッチングだとやっぱりいい影響は流れないと思うんで、またそこを見つめ直してやっていけたらなと思います」 「いや、もう考え方もありますし、もちろん技術の、それがダメだった時の対応だったり、そういうところっていうのが少なかったと思うんで。今まではできてたことができなくなったりだとかしてたんで。でも今日、凄い出力的には凄い良かったんで。腕の振りも良かったじゃないかなって自分でも思いますし。結果を出さないといけない世界なんで、見つめ直して、また帰ってきたいなと思います」 「いや、真っすぐ、凄い良かったんじゃないですかね。あとはもう変化球の精度だったり、ほんとに駆け引きだったりだとか、必要な部分っていうのもたくさんありますし。そういうところが良くなれば、もっといいものがね、出せるんじゃないかなと思います。抹消して10日間しっかり自分と向き合ってやっていけたらなと思います」 翌朝「正直あまり寝られませんでした。こんなに打ち込まれて2軍に落ちるのは初めての経験ですし、難しかった。でも一つのいい挫折を味わった。ここから復活するにも落ちていくにも自分しかない。自分を律して見つめ直して、前に戻ろうとは思わないけど、また新しい自分をつくっていけたらと思います」
巨人元監督の堀内恒夫さん(77歳) 「『自分で悪いところを知り自分で直せ!』 そして、早く戻ってこい!」 堀内 戸郷 「広島の選手にも見切られている」 堀内 「これだけ打たれてしまうと 打たれることに怖さを感じてしまうことがあるかもしれん。でも、戸郷の場合 それじゃあ困るよ」 戸郷 「本来であれば1軍で投げながらこの壁を乗り越えて欲しかった。悪い悪いと言っても戸郷がいなくちゃ巨人は勝てませんよ。体のキレもボールも悪い。どんなにいいピッチャーでも少しのズレで全ての歯車が狂ってしまうもんさ。最後に今 戸郷に伝えたいことがあるとするならば『自分で悪いところを知り自分で直せ!』 そして、早く戻ってこい! 頼みましたよ!」 。「実は原始的と思われるかもしれないが、走ることしかないんだよ。走って、今回の失敗は一度、忘れる。走りながら己の原点を思い出すことしかないと思うよ」
チーム状態が上がらない中、開幕投手の戸郷投手 菅野智之投手 井上温大(いのうえはると)投手 戸郷投手 「戸郷さんに今まで引っ張ってもらった。少しでもカバーできたら」 「いない間も、戸郷さんの分までチームを勝たせられるように投げていこうと思う」 戸郷 「ラグザス プレミア12」 「それだけしないと、あのレベルにはいけないんだ」 山崎伊投手 戸郷投手 ♥♥♥
「ブラザー・ジョン・ハーマン」(Bro.John Hamman、1927-2000) 「ハーマン・カウント」「ジェミニ・カウント」「フラシュトレーション・ムーブ」 「ミスティック・ナイン」 「マイクロ・マクロ」 ハーマン リチャード・カウフマン(Richard Kaufman) The Secrets of Brother John Hamman マジックランド 小野坂トン 『ブラザー・ジョン・ハーマン カード・マジック』(東京堂出版、2007年) トン 日本語版 トリック・カード 日本語版 トリック・カード ミニデック・ケース ▲Brother John Hammanのトリックカード
私は、ずっと昔に、デニス・ショーン( Dennis Shoen) ジョン・ハーマン Hank Lee ギャフ・カード 「蔵」 ハーマン トリック・カード
▲アッカーマンのビデオ 大盤振る舞いで使用するトリックカードも付いている!
メリー派(Society of Mary) ブラザー 「ハーマンカウント」 ポール・ルポール ルポール ハーマン 「ミリオン・トゥー・ワン・チャンス」「テーブルを通り抜けるキング」「ミスティックナイン」 高木重朗 金沢文庫 「ファイナルエースルーティン」 ルポール アレックス・エルムズレイ 「アトミックエーセス」 「マイクロマクロ」 ジョン・ケネディ トミー・ワンダー 、 ジョニー広瀬 フーディーニ・マジックショップ ハーマン アラン・アッカーマン(Allan Ackerman) トリック・カード 「蔵」 トリック・カード
少子化の影響で、全国の公立高校 島根県 日比谷高校 岡山朝日高校 桐蔭高校 「寝屋川ショック」 寝屋川 八尾 授業料無償化
岡山朝日 高畑勲 小川洋子
岡山朝日 「隔年現象」 「問題の自校作成」 岡山朝日 岡山朝日高校 岡山朝日 岡山朝日 岡山朝日 岡山朝日
また、和歌山県でもトップ校とされる桐蔭高校 「少子化の影響が大きい。地域ごとに進学の選択肢を確保する必要があり、定員を大きく設定するので倍率は小さくなる」
島根県内の公立高校でも、難度が高いとされる「理数科離れ」 松江北、出雲、大田、浜田、益田 理数科 総合入学者選抜(自己推薦型) 「 そこまで勉強しなくていいのではとの意識が広がっている」 松江北高 「そんなにガツガツ勉強なんかせずに、のんびり過ごしたい。そして楽をして大学に入りたい」 ♥♥♥
2月に英作文の添削をしていた女子生徒が、作文中にachie ve という単語をachei ve と書いてきました。綴り字がie ei ie ei ie/ ei belie ve, achie ve, recei ve, decei ve, percei ve, shrie k, nie ce, relie f, concei t, grie ve, prie st, recei pt, concei ve, thie f, belie f, yie ld … あー、もう一体どっちなんでしょうか?ここでそれを簡単に見極める方法(必殺技)をお教えしましょう。まずアルファベットを全部書いてみましょう。
a b c d e f g h i j kl n o p q r s t u v w x y z 次に、上の該当単語中のie ei 直前の文字 に注目して下さい。bel ieve はl ですから、i やe は左方向にあります。l から左の方に(←) i と e の順で並んでいますからie rec eive はc ですから、e とi の順で右側 に(→)並んでいますから、ei ach ieve の場合はh ですね。すぐ右側に(→)i 、そしてずっと離れて左側に(←)e ですから、近い方から拾っていきie 「ie/eiは直前の綴り字に注目ダ!」 seize /si:z/はありますが。この話をしてあげた女子生徒は、今までこんなことは聞いたことがありませんでした、と感謝されました。♥♥♥
NHK連続テレビ小説 小泉八雲 小泉セツ 「ばけばけ」 「ばけばけ」 「怪談」 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) 小泉セツ 松江藩 島根県松江市 熊本 松江市
▲松江北高でのロケ風景
前回、松江 「だんだん」(2008年~2009年) 「だんだん」 「ありがとう」 三倉茉奈・三倉佳奈 島根 京都 めぐみ のぞみ 松江市 松江北高 30人 ほどの松江北高生 北高 校舎へ登る坂道での自転車登校場面の撮影、生徒たちがグランドで戯れる場面の撮影、等々いろいろと思い出はありますが、一番思い出に残っているのは、北高4階の社会科教室(当時)で、担任の先生が通信簿を返却する場面・昼休みの昼食場面の撮影でした(写真上)。この教室の窓からは、真正面に国宝・松江城 北高生
▲カラコロ広場の壁にあしらわれた後ろ姿の小泉八雲
松江市末次本町 の 「カラコロ広場」 ヘルン(小泉八雲) 「あっ、寅さんだ!!」 「カラコロ広場」 小泉八雲 ウェルドン 島根県尋常中学校 パトリック・ラフカディオ・ハーン(Patrick Lafcadio Hearn) Hearn(ハーン) 「ヘルン」 「ヘルン」 「カラコロ」 小泉八雲 松江大橋 「小泉八雲旧居」 「小泉八雲記念館」 八雲 月照寺 普門院 ♥♥♥
神戸 「劇場型アクアリウム アトア」 新大阪駅 JR神戸線 「三ノ宮」駅 阪神電気鉄道 「三宮」 「神戸三宮」 「神戸の中心だと明確にするため」 阪急電鉄 「神戸三宮」 神戸市営地下鉄 「三宮」 神戸新交通ポートライナー 「三宮」 JR西日本 「三ノ宮」
▲三ノ宮駅前
神戸
大阪―神戸 神戸駅 『神戸』 神戸駅 「三宮神社」 「三ノ宮」 「三宮」 神戸 「ポートループ」 「さんみや」 「さんのみや」
その後、太平洋戦争中の神戸大空襲で、兵庫駅周辺に広がる旧市街地は甚大な被害を受けました。市庁舎が1957年、現在の旧居留地東側に完成。三宮 兵庫駅 神戸駅 三宮 阪神電鉄 東京駅 名古屋駅
JR西日本 「西ノ宮」 「西宮」 神戸市 三宮 「三宮」 三ノ宮
三ノ宮駅 JR、阪急電鉄、阪神電鉄、神戸市営地下鉄、ポートアイランド線 神戸 ♥♥♥
▲JR三ノ宮駅改札口
◎週末はグルメ情報!!今週は天丼 松江市殿町 「魚一 蓬莱吉日庵」 松江市天神町 『魚一』 「魚一 蓬莱吉日庵」 『魚一』 商店街の中にひっそりと佇み、歩道を中へと入っていきます。店に向かって右側に提携パーキングがあります。お昼過ぎにお邪魔しましたが、商店街そのものは閑散としているのに、お店の中は予約のお客さんでいっぱいで、満席でした。松江市 「上天丼」 「魚一と言えば天ぷら」 天丼 「天丼」 「天丼」
新しくなったお店では、大将が目の前で天ぷらを揚げておられる姿がガラス越しに生で見ることができます。運ばれてきた「天丼」(1,320円) エビ 「しじみの味噌汁」 松江 ♥♥♥
▲私の大好きな「ゆふいん驛」
世界的な建築家としてその名が知られる磯崎 新(いそざきあらた) 磯崎 丹下健三(たんげけんぞう) 「Arata Isozaki & Associates」 磯崎 北九州市立美術館(1972〜74、福岡)、水戸芸術館(1986〜90、茨城)、アリアンツタワー(2003〜14、ミラノ)、カタール国立コンベンションセンター(2004〜11、ドーハ)、上海シンフォニーホール(2008〜14、上海) ロサンゼルス現代美術館 バルセロナオリンピック屋内競技場 「第6回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」 「金獅子賞」 「プリツカー賞」 「東洋が西洋文明の影響を強く受けていた時代に海外に出て、みずからの建築術を確立した真に国際的な建築家だ」 丹下健三 槇文彦 安藤忠雄 妹島和世+西沢立衛 伊東豊雄 坂茂 JR 由布院駅 磯崎 『芸術新潮』10月号(2023年) 「いまこそ知りたい!建築家磯崎新入門」 磯崎
磯崎 磯崎 私はグランドゼロで育ちました。建築もビルもなく、街さえもなかった。だから、私の建築の最初の経験は建築の空白であり、私は人々がどのように家や都市を再建するかを考えるようになりました。 磯崎 丹下健三 「大文字の建築家」 「小文字の建築」 磯崎
最近、私が訪れた「別府国際コンベンションセンター ビーコンプラザ」 磯崎 「フィルハーモニーホール」 「大分県立別府コンベンションホール」 「グローバルタワー」 「展望台」 別府 ♥♥♥
▲別府国際コンベンションセンター「ビーコンプラザ」
▲グローバルタワー
キャッチフレーズ「BE KOBE」 阪神・淡路大震災 「市民が神戸市民であることを誇りに思う気持ち」 2017年4月「メリケンパーク」 「BE KOBE」 広々とした芝生が広がる展望広場と、西日本最大級の新しい「スターバックスコーヒー」
BE KOBE BE KOBEは、阪神・淡路大震災から20年目の2015年、「人のために力を尽くす」という市民の熱い想いを集めて生まれたメッセージです。「市民が神戸市民であることを誇りに思う気持ち」を表しています。 先進的で開放的、さらには豊かな創造性と国際性に富んだ、みなとまち。 “神戸らしさ”を育みながら大きな苦難を乗り越えてきた「これまでの150年」から、若者が挑戦し活き活きと活躍する「これからの150年」に向けて、神戸は出航します。 神戸開港150年記念 2017年4月 神戸市
「神戸メリケンパークオリエンタルホテル」 「BE KOBE」 「神戸ポートタワー」 「BE KOBE」 神戸 周辺には、神戸海洋博物館 モザイク大観覧車 神戸 神戸 ハーバーランド 神戸 「BE KOBE」 神戸港 行ってみると、神戸 神戸 「ポートタワー」 神戸 神戸 「ポートタワー」 「カワサキワールド・神戸海洋博物館」 「umie」 「モザイク」 ハーバーランド 現在ではこの種のモニュメントは、神戸 6つ もあるそうです。私は今日リニューアルされた「神戸ポートタワー」 「BE KOBE」 トートバッグ(2,200円) ♥♥♥
JR九州 観光列車 「D&S列車」(デザイン&ストーリー列車) 「D」 「デザイン(Design)」 「S」 「ストーリー(Story)」 「デザインと物語のある列車」 JR九州 観光列車 「物語」 物語 九州 JR九州 「D&S列車」 九州 JR九州 観光列車 「D&S列車」
▲私の一番好きな「ゆふいんの森一世」
そんな「D&S列車」 特急「ゆふいんの森」 博多駅〜由布院駅 JR九州 「D&S列車」 「ゆふいんの森」 「D&S列車」 由布院 ドーンデザイン研究所 水戸岡鋭治(みとおかえいじ)先生 「かんぱち・いちろく」 IFOO 「D&S列車」 観光特急 「D&S列車」
観光列車名
運転開始時期
ゆふいんの森 1989年3月11日 ★私の一番好きな観光列車
九州横断特急 2004年3月13日
海幸山幸 2009年10月10日
指宿のたまて箱 2011年3月13日)
あそーぼーい 2011年6月4日
A列車で行こう 2011年10月8日
或る列車 2015年8月8日
かわせみやませみ 2017年3月4日
36プラス3 2020年10月16日
ふたつ星 2022年9月23日
かんぱち・いちろく 2024年4月26日
水戸岡先生 唐池恒二(からいけこうじ)社長 ♥♥♥
水戸岡さんのデザインは、はじめて見たときとても感動する。しかし、はじめて見たとき感動するのは、どのデザインにも共通することだ。デザイナーが手がけたものであれば、彼らはプロだから、それは当然といえる。水戸岡さんのデザインが他と違うのは、何度見てもそのたびに新鮮な感動を覚えることだ、斬新だと思えたデザインでも、何度か見ていると次第に感動が小さくなっていき、やがては飽きてしまう。しかし、水戸岡さんのつくった通勤電車の車両は、毎日同じ駅の同じホームから眺めてもまったく飽きることがない。 水戸岡さんは、デザインの構想を練るときコンセプトを最も大切にする。そのコンセプトは、どこからくるのか。列車のネーミングだ。水戸岡さんは、列車名をコンセプトにして内外装のイメージを固める。ネーミングは、私の専権事項だ。水戸岡さんは、私が列車名を考えつくまでデザインに着手しない。列車名が固まると、水戸岡さんはあっという間にデザインの“あらすじ”をまとめる。その“あらすじ”が、列車一本一本がこれから身に付けていく物語の始まりとなる。 (『鉄客商売 JR九州大躍進の極意』(PHP出版、2016年))
蛍光マーカー (株) パイロット 蛍光マーカー 蛍光マーカー パイロット 「太さが変わらない線をまっすぐ引きやすく、手も紙面も汚れない新しい蛍光マーカー」 「KIRE-NA」(キレーナ) 蛍光マーカー 「キチントトトノウ(きちんと整う)」 蛍光マーカー 米子市 天満屋 「LOFT」 松江市 今井書店学園店 「文房具の八ちゃん」
▲米子LOFT売り場にて
パイロット 月に発売された「 KIRE-NA 」(キレーナ) “もしかしたら歴史を変えるかもしれない蛍光マーカー” 色と、女性が好む淡いペールトーンカラー5 色の全10 色展開です。同じ系統の色味を揃えているので、例えば教科書とノートで使い分けることもできます。 外見は、最近のパイロット 「完全に新しいインク」 「今までにない構造のペン先」 ラインを引く“太”、文字書きもできる“細”のツインチップ仕様ということで、まずは太い側のキャップを開けると、なにやら見慣れない雰囲気です。その原因は、チップを挟むように両脇から生えている半透明のパーツ。これが、線の太さを変えずまっすぐ引きやすくするための秘密兵器「キチントガイド」
▲使う際には、カラーパーツに親指を乗せるとガイドの水平が取れて、線が引きやすい
ペン先を紙に当てると、まずよくしなる特殊なナイロン素材でできたソフトなチップがフニャッとしなるように紙に触れ、その直後に新開発の「キチントガイド」
蛍光マーカー だから、書き始めは線が細く、書いているうちに刃先の全域が紙に当たるようになって線が太くなってしまうのです。最初からチップをまっすぐ紙に当てれば問題ないのですが、とはいえ常にベストな角度で書き始めるのは、なかなか難度が高い技術なのです。従来にも、チップの傾きを解消するために弾力のあるソフトチップを採用した製品は、いくつか発売されていました。この場合、紙にむぎゅっと押し当てることでチップ全域が紙に当たるため、傾きは発生しなくなります。しかし、引く際の筆圧を一定化させないと、結局のところ線は太くなったり細くなったりで安定しないのです。そこで、その筆圧を安定させるのがこの「キチントガイド」 その結果、どれだけ線を引いても常に同じ太さになる、というすぐれた仕組みなのです。 さらに、ソフトチップは曲面に強いという性質も持っています。例えば分厚い教科書を開いた時のふくらんだページの曲面にもピッタリとフィットします。紙面がカモメの羽のように曲がって広がりますが、柔らかく弾力のあるチップなら、その曲がりに沿って動くため、チップが紙面から外れずに安定して線が引き続けられるのです。今日私が購入した「KIRE-NA」(5色セット) 「やわらか定規」
▲ガイドのおかげでチップが定規に触れないので、フチのインク汚れを拭き取る手間もないのが嬉しい
従来の蛍光マーカー 「KIRE-NA」 チップの傾き ・筆圧 ・インク染み という3つのトラブル要素を気にしなくて良くなったことで、線を落ち着いてまっすぐ引けるだけの余裕が生まれるのです。
「KIRE-NA」 「速乾顔料インク」 。「速乾性を上げることには限界がありますし、浸透性を上げすぎると紙に対して裏抜けが大きくなってしまいます。そのバランスを調整しながらインクを開発することが一番難しかったです」 パイロット 「瞬筆」 「KIRE-NA」 「瞬筆」 蛍光マーカー
太チップがあまりにも革新的すぎてつい存在を忘れそうになりますが、細チップも速乾インクを共有しているため、擦れ汚れの心配なく書けるのはメリットです。実際、蛍光マーカー 「マーキング+コメント書き込み」
私は資料のチェックなどで蛍光マーカー 蛍光マーカー 「KIRE-NA」 「ソフトチップ」+「キチントガイド」 蛍光マーカー 「KIRE-NA」
発売後の売れ行きは想定以上で、主なユーザーは、学生と40~50代の方々で、狙った通りの層の方に届いているようです。機能面に対する評価はもちろんのこと、価格面でも「これだけの新機能を詰め込みながらこの価格(132円)はすごい!」 「サヨナラ蛍光ペンストレス」 『文房具屋さん大賞2025』(扶桑社ムック、2025年2月) 「キレーナ」 「大賞」 ♥♥♥
今年の勝田ケ丘志学館 「入学式」 「象使い」と「象」 Google チップ・ハース、ダン・ハース 『スイッチ「変われない」を変える方法』 ジョナサン・ハイト 「象と象遣い」 「象さん」 「象使い」
「感情」は象 ――「心」 「理性」は象使い ――「頭」 私たちの象、つまり感情や本能は怠け者で、気まぐれで、長期的報酬(やせること)よりも、短期的報酬(アイスクリーム)に目を奪われてしまう。変化が上手くいかないのは、たいてい象のせいだ。 私たちの中には「象使い」 「象」 「象」 「象使い」 「象」 「象使い」 「象」 「象使い」 「象」 「象使い」 「象」 「象使い」 「象」 象使い 「象」 「象」 「象使い」 「象」 「象使い」
理性の御者は、暴れん坊の馬を従えている(哲学者プラトン) いくら「受験に絶対必要だ」「英語は現代生活に重要だ」「毎日コツコツやれば必ずできるようになる」 「象使い」 「象」 「象」 「象使い」 「英語を学習するのは正しい」 「この計画なら効率的に学習できる」 「象」 「象」 「象」 「象」 「象さんに方向を指し示すこと」 象 「象」 「象使い」 「象」 「象」 「象」 「象」 「目的地の絵はがき」
先輩で東北大学 東北大学 小田和正 「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」(THE) 「THE日本大学ランキング2025」 東北大
1位 東北大 2位 東京工大(現東京科学大) 3位 東京大 4位 京都大 5位 九州大 6位 大阪大 7位 名古屋大 8位 北海道大 9位 筑波大 10位 国際教養大 世界大学ランキングで知られるTHE 「日本版大学ランキング」
文部科学省が世界水準の研究大学を作るために創設した、10兆円規模の大学ファンドの支援候補に、東北大学
こういったことから「どんなことをしても東北大学に進学したい」 「象」 ♥♥♥
「soon=すぐに」 「すぐに…」 soon soon “in a short time from now” [LDCE ] /at a time that is not long from now [NWALED] 「ただちに」 「まもなく」 「そのうちに」 「もう少し後で」 soon 「ただちに、今すぐに」 right away, at once, immediately
では、soon 「すぐに」 「話者の主観的な感覚で決まり、時間幅が曖昧である」 soon 「How soon…?」 「すぐにやります」 soon right now soon soon soon
The bus will come soon そのうち 来るさ)
The mailman should be coming soon そのうち 来るはずです。)
It’s my birthday soon もうすぐ 私の誕生日です。)
My son will come home from school soon そのうち 学校から家に帰ってきます。)
It will be the summer vacation soon もうすぐ 夏休みですね。どこに行こうかな?)
It will be dinnertime soon もう 夕食ですよ。やっている事を終わらせてキッチンに来て下さい。)
私たちの『ライトハウス英和辞典』(第7版) 【類義語】 ♥♥♥
soon あまり時間がたたないうちに事が起こったことを意味するが、どのくらいの長さの時間であるかは前後関係によって異なり、かなりの時間を意味することもある: They will soon arrive. 彼らはもうすぐ到着するでしょう。
◎週末はグルメ情報!!今週はキューピーサラダ キユーピーマヨネーズ 「キユーピー マヨネーズのはじまりのポテトサラダ」 HOK
キユーピー マヨネーズ キユーピー 食品工業株式会社 中島董一郎(なかしまとういちろう) 「キユーピー マヨネーズ」 中島 中島商店 キユーピー 中島 “オレンジママレード” “マヨネーズ” 中島 食品工業 「おいしく、栄養のあるマヨネーズを、生活必需品となるまで広く普及させて、日本人の体格と健康の向上に貢献したい」 「キユーピー マヨネーズ」 「キユーピー」 「キユーピー マヨネーズ」 「キユーピー マヨネーズ」 中島 中島 「志を同じくする人と業を楽しんで悦びをともにする、そこに仕事のやりがいがある」 キユーピーグループ 「楽業偕悦」(らくぎょうかいえつ) キユーピ ー マヨネーズ 「キユーピー マヨネーズのはじまりのポテ トサラダ」 デリア食品株式会社 キユーピー マヨネーズ キユーピー マヨネーズ キユーピー 中島董一郎(なかしま とういちろう) 「キユーピー マヨネーズのはじまりのポテトサラダ」 キユーピー マヨネーズ キユーピー マヨネーズ ・キユーピー マヨネーズのコクを生かした味わいと口どけを実現したポテトサラダです。 ・具材はじゃがいも・たまねぎ・ゆでたまごのみのシンプルな配合です。 ・パッケージ蓋のキユーピー マヨネーズのワンポイントシールが目印です。 「愛は食卓にある」 キユーピー株式会社 キユーピー 「キユーピー」 「キューピー(QP)」 「キユーピー」 デザイン上の問題 です。小文字の “ュ” ではなく大文字の “ユ” の方がデザイン的にふさわしいと判断し大文字の “ユ” を使用しているのです。商標登録を行った1922年以来のなごりで、デザイン上のバランスを考慮して大きな「ユ」のままとなりました。似たような例に、「キヤノン」 「シヤチハタ」 キユーピー株式会社 「食品工業」 「キューピー」 キューピー人形 ローズ・オニール キューピッド 「キューピー KEWPIE」 オニール 「ローマ神話に登場するキューピッドCUPIDは、人々のこころにいたずらをするけれど、わたしのキューピーには愛だけをはこんでほしい…」 日本キューピークラブ ローズ・オニール遺族財団 キユーピー株式会社 「キユーピー」 日本キューピークラブ キユーピーマヨネーズ キユーピー
ついでながら、キユーピー ♥♥♥
直木賞 泡坂妻夫(あわさかつまお) 『魔術館の一夜』(現代教養文庫,1987年) 松田道弘(まつだみちひろ) 「奇術書の革命であり奇跡である」 泡坂 『泡坂妻夫マジックの世界』(東京堂、2006年) 「ワープナイン」 ( 名付け親は、あのマックス名人 小野坂トン マジックランド 「厚川昌男(あつかわまさお)の魔術館の♡9」 「泡坂妻夫」 (A WASKA TSUMAO)さんというのは、本名の「厚川昌男」 ( ATSUKAWA MASAO)の「 アナグラム」(anagram) 「 アナグラム」 コチラ をご覧ください)。♠♣♥♦ VIDEO
巧妙なトリックを凝らしたミステリ-や、職人の誇りと人情の機微を描いた小説で直木賞 泡坂妻夫 直木賞 紋章上絵師 作家・創作奇術家 第2回石田天海賞 「厚川昌男賞」 泡坂 泡坂 『しあわせの書 迷探偵ヨギガンジーの心霊術』(新潮文庫) の大ファンで、この本で不思議な「ブックテスト」 コチラ です この本は仕掛けを知らない人にとっては、ただの小説なんですが、マニ アにとってはあこがれの一冊なんです。価値を知らない人が「ブックオフ」 ♠♣♥♦
▲とんでもない仕掛け本です 古本屋で見つける度に買っています もう何冊たまったことか!!
▲一個440円で私は手に入れました
「教育省」の解体、保健福祉省の一万人解雇、政府系メディアの縮小(私は「VOA」 トランプ大統領 カードケース 「とらんぷのマジックをご覧頂きましよう。」 トランプ
トランプ米大統領 「ペニー」 1セント硬貨 ベッセント財務長官 トランプ大統領 「あまりにも長い間、米国は文字通り2セント以上のコストがかかるペニーを鋳造してきた。これはあまりにも無駄だ!新しいペニーの製造中止を財務長官に指示した」 「偉大な国の予算から、たとえ1ペニーずつでも無駄を取り除こう」 トランプ米大統領 「紙ストローは機能しない。これまで何度も使ってきたが、破れたり破裂したりする」 「プラスチックのストローに戻る」 「プラスチックが海で泳ぎながら食べているサメに大きな影響を与えることはないと思う」 「反プラスチック製ストローの理不尽なキャンペーン」 バイデン
1セント硬貨 ヘンリー・アーロン 「ペニーを廃止しよう。ついでにニッケル(5セント硬貨)も。この通貨の残骸がなければ人生はもっとシンプルになる」 1セント硬貨 トランプ大統領 「米国は長きにわたり2セント余りのコストがかかる1セント硬貨を製造してきた。無駄遣いだ」 イーロン・マスク 「政府効率化省」
ではひるがえって、日本のお金の場合はどうでしょうか?「国民の貨幣に対する信任を維持するためや、貨幣の偽造を助長するおそれがあると考えられる」 「いらないのではと思っちゃう、かさばるので。作らなくてもいいのではと思う。」「なくても困らない。1円とかそういう単位がなくなっていったら完全にいらないのでは。」
現在の硬貨の流通枚数は、約851億枚です。そのうち364億枚ほどが1円玉だそうです。1円玉の製造枚数が最も多かったのは1990年。1年間で27億枚以上が製造されていました。1990年前後に1円玉の製造枚数が劇的に増加した理由を専門家に聞くと、1円硬貨の製造枚数は消費税率の変動や経済状況など様々な要因によって変化してきましたが、特に1989年に消費税3%が導入された際には、端数処理の必要性から1円硬貨の需要が増加し発行数も増加したとのことです。ただ一方、ここ数年最も多かった頃の5,000分の1程度、50万枚程度で推移しています。今後アメリカのように、日本でも1円硬貨の廃止論は出てくるのでしょうか?確かにキャッシュレス化が進む中で、1円硬貨の存在意義はますます薄れてきています。将来的には1円硬貨の廃止や新たな活用方法の模索がさらに進む可能性があるでしょう。今後、世界的にもますます進むというキャッシュレス化。「1円玉、チリも積もれば山となる」
ちなみにアメリカでのコインの呼び方は、penny(1セント)、nickel (5セント)、dime(10セント)、 quarter(25セント) ♥♥♥
「MINIATURE LIFE展」 (入場料金1,200円) がパート2として作品を一新、バージョンアップして米子市美術館 勝田ケ丘志学館 米子市美術館 田中達也(たなかたつや) 田中達也 「さすが!」 「見立ての世界」
▲ハングリーハンター
▲季節の衣替え
▲マミーサイドアップ
田中達也 「MINIATURE LIFE展」
▲しばらくここで待ってクリップ
▲おスシティー
米子市美術館 「しばらくここで待ってクリップ」 「おスシティー」 「ベッドに砂丘」 鳥取砂丘
▲ベッドに砂丘
「どうして、アイデアが尽きないのですか?」 田中 田中 田中 「見立て」 田中達也 田中 ♥♥♥
▲XXXXXLサイズの波
4月1日「エイプリルフール」 岩崎研究会
毎年4月1日が来ると、いつも思うことがあります。「四月バカの日」(エイプリルフール) April Fools’ Day [A型] としておきましょう。ところが、当時私が、英米の新聞や百科事典を見ていると、[B型] April Fool’s Day 「(株)海外新聞普及」 八幡成人 「語法ノート:April Fool’s Day」 Lexicon, No.17(1988)(岩崎研究会) 三木悦三教授(熊本女子大学)
◎April Fools’ Day 『和英大辞典』(研究社) 『新英和中辞典』(研究社)『ルミナス和英辞典』(研究社) 『ライトハウス和英辞典』(研究社) 『アドバンスドフェイバリット和英辞典』(東京書籍) 『エースクラウン英和辞典』(三省堂) ◎April [All] Fools’ Day 『オーレックス和英辞典』(旺文社) 『新和英中辞典』(研究社) ◎April Fools’ [Fool’s] Day 『グランドセンチュリー和英辞典』(三省堂) 『英和大辞典』(研究社) 『リーダーズ英和辞典』(研究社) 『E-ゲート英和辞典』(ベネッセ) ◎April Fool’s [Fools’] Day 『ジーニアス和英辞典』(大修館) 『フェイバリット英和辞典』(東京書籍) 『スーパーアンカー英和辞典』(学研) 『ウィズダム英和辞典』(三省堂) 『ライトハウス英和辞典』(研究社) 『コンパスローズ英和辞典』(研究社) 当時、私たち『ライトハウス英和辞典』 ロバート・イルソン博士(ロンドン大学) メリアム・ウェブスター社 ミッシュ編集長 [A 型] と[B型] の比率は3:1だということでした(ただし用例が少々古いので現代英語を反映しているかどうかは疑問だ、と断っていらっしゃいましたが)。1987年に、八幡がアメリカの4月1日付けの新聞13紙を調べたところでは、逆に2:3で[B型] の方が多かったんです。私たちの編集顧問・故ボリンジャー博士(ハーバード大学名誉教授) [B型] だということでした。で、博士は、地元新聞(Palo Alto)の編集者たちに聞いてくださったんですが、やはり同様の結果が得られました。句読法の研究で知られるCharles F. Meyer教授(マサチューセッツ大学) [B型] を好む者13名、[A型]を好む者が8名、ということでした。やはり[B型] の方が一般的のようです。少なくとも、[B型] が無視できなくなっていることは、次の記述からも分かりますね。
The occasion celebrated on the first day of April is officially called April Fools’ Day in the United States. Each word of the titled is capitalized and the fool is plural possessive. The singular fool’s is listed as a variant spelling. However, this is not standardized and the main listing seems to vary from dictionary and dictionary (i.e., whether the plural or the singular is listed as the main spelling). Actual usage seems to support this non-preference, with both spellings being used about the same frequency . (Grammarist より、下線は八幡)
私は今、間違いなくApril Fool’s Day April Fools’ Day Longman Dictionary of American English ではApril Fool’s Day Oxford Advanced Learner’s Dictionary (9th ed. 2015)では、見出しがApril Fool’s Day [B型] の方が[A型] よりも優勢となっています。グーグルに出現する頻度を比較してもやはり[B型] の方が[A型] よりも圧倒的優勢となっています。私はこのような実態を受けて、『ライトハウス英和辞典』(第6版) 『コンパスローズ英和辞典』 [B型] を主見出しとして扱いました。
現在優勢なはずのApril Fool’s Day コチラ に“What’s the correct spelling of April Fool’s Day?” ♥♥♥
プロ野球が開幕しました。私の大好きな巨人軍 甲斐、キャベッジ、石川、田中瑛、マルティネス トレイ・キャベッジ外野手(27歳=米国 推定年俸2億) 巨人 若林
試合後、お立ち台に上がったキャベッジ 「本当に興奮した気持ちで開幕を迎えました。神様に感謝したいと思います。そして、なによりチームが勝ったので、それが一番うれしいです」 「父親に渡したい。今までも節目のヒットの度に記念球は父親に渡してきましたので今回も同じように父に渡したいというふうに思います」 阿部監督 「キーマンはキャベッジになる。そこが一番だと思うよ」 。「そうですね。そう言っていただけることは非常に嬉しいですし、今日みたいな活躍をこれからもしていきたい。ただ、誰がキーマンとかそういうことよりは、みんながカバーし合って、1人1人が自分の役割をしっかりと果たして、で、その先にリーグ優勝と日本一があるというふうに思ってますので、これからもそういう意識で助け合いつつシーズンを送っていきたいと思います」 「特にやってるルーティンはないんですけれども、今朝に関してはメジャーの開幕戦がテレビでやってたんでそれをゆっくり見ながら朝食をとって、朝のコーヒーを飲んだって感じです」
第2戦でも右中間へ2戦連続で3ランホームランを放ち、試合を決定づけました。球団の新外国人の開幕2戦連発は球団初の快挙です。第3戦でもツーベースヒットを放っています。
不振だったオープン戦とはまるで別人のようです。出場14試合で、打率2割1分4厘(42打数9安打)、0本塁打、3打点と全く振るいませんでした。日本の投手とタイミングが合わず、直球には差し込まれ、変化球には体勢をを崩されていました。特に三振が44打席で14個(約32%)と非常に多かったのです。オープン戦では何でもかんでも力任せに振りにいっている印象でしたが、開幕してからはコンパクトに振り始め、お陰で軸がぶれずにバットが素直に出ていました。オープン戦と比べると、スイングにキレが出てきたみたいです。幸先の良いスタートを切りましたね。今後が楽しみです。
“変身”のきっかけの1つは、打順にもありそうです。キャベッジ 岡本和真内野手 岡本 キャベッジ エリエ・ヘルナンデス外野手 キャベッジ
2015年のMLBドラフト4巡目(全体110位)でミネソタ・ツインズ エンゼルス 「トリプルスリー」 吉村禎章編成本部長兼国際部長
この27歳は手を抜きません。全体練習前に早出して打ち込んできました。開幕日もチームで一番早くバットを振り始めました。そうした努力が結果に結びついています。足も速く、試合となればヘッドスライディングも厭わずユニホームは真っ黒です。コーチたちもみな口を揃えて「真面目だ」
丸佳浩外野手 若林楽人外野手 阿部慎之助監督 ヘルナンデス 吉川尚輝内野手 岡本 村田真一 「キャベッジ、オレはかならず打つと思ってるよ」 ♥♥♥
▲松江大橋南詰の桜
▲千手院のしだれ桜
◎週末はグルメ情報!!今週はラーメン (株) ベネッセ 中村友樹 「麺酒 一照庵」(めんさけ いっしょうあん) 「丸善」 岡山 「麺酒 一照庵」 「麺酒 一照庵」 「一隅を照らす」 『自分が今いる場所で精一杯努力して、光り輝くこと』 岡山 岡山 「麺酒 一照庵」 中に入ると、10人座ることができるテーブル席やカウンター席を完備しています。メニューは、国産親鳥をふんだんに使用し北海道産の昆布や鰹、椎茸を使った和風出汁があっさりしたシンプルな中華そばや、ラーメンとともに味わいたいよだれ鶏などの一品メニューに加え、酒屋さんを通して全国から仕入れる日本酒も用意されていますので、居酒屋としての利用もありです。カウンター席に案内されると、お水を運んで来られた係の女性が「ご来店ありがとうございます。お仕事お疲れ様でした!」 中村 「鶏中華そばクラム」(1,180円) 「ポテトサラダ」(500円) 「岡山ラーメン博グランプリ」 「ミシュランガイド大阪・京都+岡山版」
▲こんなポテトサラダ食べたことない!!美味しい!
▲スープが何とも味わい深い!
まず最初に出てきた人気の「ポテトサラダ」 ポテサラ いぶりがっこ 大根を燻製にして漬け込んだ発酵食品です。 スモーキーな香りが特徴で、パリパリとした食感が楽しめます) の入ったポテサラ 「クラム」
▲鶏中華そば塩
▲唐揚げセット でっかい唐揚げ一個にちょこっとポテサラ
あまりの美味しさに感銘を受け、このラーメン店「麺酒 一照庵(いっしょうあん)」 倉敷 「天満屋倉敷店」 JR 倉敷駅 倉敷 「麺酒 一照庵 倉敷天満屋店」 「クラム」 「鶏中華そば塩」(1,080円) 「唐揚げセット」(210円) いぶりがっこ 「ポテトサラダ」 ♥♥♥
▲「一照庵倉敷店」の店長さん
「神戸須磨シーワールド」 「須磨海浜水族園」 鴨川シーワールド 鴨川 シャチ 「鴨川シーワールド」 「名古屋港水族館」 「神戸須磨シーワールド」 シャチ 「読売旅行」 岡山 新幹線「ひかり」号500系 西明石 「須磨海浜公園駅」 「当日券の販売は12時より」 「混雑時には入場制限が行われることがあり、特に週末や祝日は事前予約が安心です。」 ちょうど2時間半待って何とか中に入ってシャチのショーを見ることはできましたが、おかげで島根に帰ってから足がパンパンです。ただでさえ股関節の手術をしてまだ万全ではないのに、もう勘弁してよ~。教訓!「娯楽施設を訪問する時には、必ず事前に予約してから出かけるべし!!」 ♥♥♥
私は週に3日、松江 米子 「ウェザーニュース」 『朝日新聞』 『読売新聞』 「ウェザーニュース」 「ウェザーニュース」 古志原 温熱療法(テルミ) 日本気象協会 「ウェザーニュース」 「ウェザーニュース」 ウェザーニューズ 「ガイアの夜明け」
「降水捕捉率」 「ウェザーニュース」 降水捕捉率 88% となりました。気象庁 「ウェザーニュース」
「ウェザーニュース」 気象庁 1つ目は予報を組み立てる手順や方法が、各気象会社・機関によって異なるということです。コンピューター・シミュレーションでこの先の予想を計算させるのは、どこの機関も同じなのですが、その計算方法や計算結果に、各機関の専門家によって独自に情報を加えています。また、「ウェザーニュース」 気象庁
2つ目は、天気予報を発表する場所の単位が1km四方と、とても細かい範囲で予報をしているということ(気象庁 東京駅 新宿駅
3つ目は、予報時間のきめ細やかさです。「ウェザーニュース」 気象庁
4つ目は、予報を1日のうち決まった時間に数回発表するのではなく、随時最新の天気予報を発表・更新していること(気象庁 「ウェザーニュース」
適中率 「ウェザーニュース」 適中率 「ウェザーニュース」
まず1つ目は、日本最大の気象観測網 を持っている点です。「ウェザーニュース」 アメダス 約13,000か所 の気象観測網を備えています(他社の10倍)。また、全国の「ウェザーニュース」 世界各国の気象予測モデルを独自に最適化 している点です。「ウェザーニュース」 気象予報士 1km四方という超高解像度な天気予報 の発表です。ウェザーニューズ
「ウェザーニュースYouTubeチャンネル」 ♥♥♥
JR京都駅 原広司(はら・ひろし) 東京大学 東大生産技術研究所 「空き地の空気は自由だ。空き地の空気はカオスだ」 梅田スカイビル JR京都駅ビル 札幌ドーム 隈研吾(くまけんご)
日本のかつての首都であった京都 「京都駅ビル」 京都 原 広司 「BCS賞」、「ブルネル賞」、「京(みやこ)環境配慮建築物優良賞」 原
JR京都駅 JR西日本 京都市 原広司 、安藤忠雄 、池原義郎 、黒川紀章 、ジェームス・スターリング 、ベルナール・チュミ 、ペーター・ブスマン 原広司 安藤 スターリング 原広司 黒川 安藤 原広司
京都駅 原 「歴史への門」
建築は、地上16階、地下3階、延床面積236,000平方メートルの規模で、高さは京都市最高の60m。駅ビルの幅は450mにも及び、百貨店(JR京都伊勢丹 ホテルグランヴィア京都 京都劇場 ホテルグランヴィア京都 JR京都伊勢丹
一方、コンコース東側より吹抜け大空間を見ると、テラス、室町小路広場、大階段とガラス屋根の架かった屋外空間にはホテル側と百貨店側の東西を空中で結ぶスカイウェイが見える。大階段は百貨店の各階へとアクセスし、キャノピーは円弧を組み合せしたトラス構造となっています。
大階段を登り切った屋上には「大空広場と葉っぴいてらす」 「大空広場と葉っぴいてらす」 京都 「京都駅ビル」 京都 京都 京都
西村京太郎先生 『京都駅殺人事件』(2000年) 西村先生 京都駅観 ♥♥♥ <京都駅長殿>
京都の新しい駅は、醜怪である。歴史の町京都には、まったくふさわしくない。
古都の景観を損ない、内外の笑い物だ。
私は、この醜いビルを破壊することを決意した。
まず、自分たちの手で破壊し、真に京都にふさわしい駅に造り変えことを約束せ
よ。
それが出来なければ、私が爆破する。これは、脅しではない。私は、時限爆弾を
用意している。
七月九日の午後二時に、電話する。
それまでに考えておけ。 真に京都駅を愛する者> (pp.35-36)
「新京都駅については、賛成、反対と、意見はありますし、投書も来ます。京都
の町にマッチしていないとか、この京都駅が壁になって、京都の町が見えないと
いった苦情もあります。京都タワーのときと同じです。しかし、気に入らないか
らといって、爆破するという脅迫は初めてです。」……「設計が斬新だという人も
いますし、身障者に優しい駅だと、賞めてくださる人もいるんです。構内にホテ
ルもあって、便利だという声もあるんです」 (p.44)
「だから、自分たちで、破壊しろといってるんだ。一時、駅を閉鎖して毀してい
けば、誰も傷つかないじゃないか。あんたたちは、そうやって古い駅舎を毀し、
軍艦みたいな今の駅舎を造ったんだ。同じことをやれと、いっているんだよ」
「駅を改修したのは必要があったからで、今の駅舎を、君のように嫌いだという
人もいれば、素晴らしいと賞めてくれる人もいる。従って、本当の評価は、何年
も何十年もたってから下されるものだ。それまで待ってほしいね」 (p.49)
その点、新しい京都駅の駅舎は、車椅子がいつでも自由に使えるし、各ホームを
つなぐ跨線橋の上の各ホーム真上に、エレベーターの入り口がある。荷物兼用で
はないので、車椅子の人間が、勝手にそのエレベーターに乗って、ホームへ降り
られるのだ。車椅子の人も足腰の弱い老人も、エレベータでホームへ降りられる
し、別のホームへ移っていける。 (p.53)
窓際に腰を下ろして、駅舎を見ながら、コーヒーを飲む。「堂々としているとい
えばいえるし、犯人のいうように、醜悪だといえば、いえる建物だな」 (p.67)
屋根のない空中庭園へ行く階段とエスカレーターである。
二人も、昇りのエスカレーターに乗ってみた。ゆっくりと昇って行くにつれて、
駅全体が視界の中に入ってくる。
各階には、踊り場的な広場ができていて、そこで乗りかえて、エスカレーター
はさらに昇って行く。
四階には、コンクリートむきだしの広い庭園ができていた。まだ作業が続いて
いて、ユニフォーム姿の五、六人の作業員が、植木をコンクリートの鉢に植えて
いた。
コンコースの混雑から逃れて、この空中庭園で、ぼんやり休息をとっている何
人かの乗客の姿があった。……
「ひょっとすると、この空中庭園で、犯人と追っかけになるかもしれませんね」
と、亀井が周囲を見渡した。
ここから、さらに、昇りの階段があり、「空中径路」という文字が見えた。
Sky Wayという英語もあった。が、時間制限があって、入り口は閉ざされていた。
そこを、警察手帳を見せて、二人は昇ってみた。
たぶんここが、京都駅でいちばん高い場所なのだろう。ジュラルミンのパイプ
が頭上で交錯し、その下を細い通路が延びていた。
「まるで檻の中だな」と十津川は感想をいった。 (p.76)
「そうだ、だいたい、今の京都駅は醜悪だ。これは京都の駅なんかじゃない。
そんな駅に京都という標示板を飾るな、あれを撤去しろ。そうしたら、もう一度、
交渉に応じる。それができなければ、こちらとしては交渉を止め、駅を爆破する」
「ネオンを消すだけでは、駄目か?」
「そんな姑息なことで、我慢できると思っているのか。全部、撤去しろ。それ
から、ステーションという文字もだ。あの建物は駅なんかじゃない」 (p.105)
<醜悪な京都駅を、建て直しましょう。
古都にふさわしい駅をという、人々の願いは、軍艦のような新しい京都駅によっ
て、みじんに、砕かれてしまいました。
四十五メートルの高さ制限も破られ、今やあの不粋な建物によって、京都は南北
に分断されてしまったのです。
私は、古都、京都を深く愛する一人であります。毎日、あの醜悪な建物を見てい
るのに耐えられなくなっています。私と、同じ思いの人々は、たくさんおられる
と思っています。
今からでも、遅くはありません。一刻も早く、あの建物を取り毀し、真に古都に
ふさわしい駅舎を建てましょう。
皆さん、声をあげてください。 真に京都駅を愛する者> (p.192)
▲コンサート会場の島根県民会館
▲県民会館の楽屋入り口には朝からコンサートトラックが
島根県民会館 「 さだまさしアコースティックコンサート2025」 4,688回目 のコンサートです(グレープを入れれば5,000回以上)。もちろん日本新記録です。松江商工会議所130周年記念 松江南高 江角健一 さだ さだ 松江 2021年2月6日 、コロナ禍の真っ最中でした(⇒私の詳しいコンサート実況中継はコチラ です)。「音楽の灯を消してはならない」 さだまさし 松江 さだ 「人間の集中力が持つのは1時間40分。今日は1時間45分を目標に頑張る」 「エーーーッ!!!」
▲開演前の大ホール 超満員!
【本日のセットリスト】 1:案山子 2:Birthday 3:交響楽(シンフォニー) 4:無縁坂 5:道化師のソネット 6:関白宣言 (曲の途中からずっこけ トークをからめ)⇒関白失脚 7:北の国から~遙かなる大地より~ 8:いのちの理由 9:主人公 ※予定になかった曲です 10:修二会 アンコール 11:風に立つライオン この日のさだ 『生命の樹』(Tree of Life)〔グレープの曲が3曲入る予定とか〕 さだ グレープ さだ 初 記録、「北の国から」 いしだあゆみ 倉本 高度な ギャグが目白押しで、その都度爆笑連発のコンサートでした。普段しゃべりを生業にしている私にはとても参考になります。終わったのは19時10分でした。いつものようにステージの最後に、「今日も素晴らしい演奏をしてくれたステージのメンバーに拍手をお願いします!」 「そして今日も皆さんの見えないところでこのステージを支えてくれているスタッフの仲間にも大きな拍手をお願いします!」 さだ
「コンサートパンフレット Vol.79」、「51ベロアポーチ」「51クリアフィアル」、「さだまさしアクリルキーホルダー」 ♥♥♥
西武ライオンズ 伊東 勤(いとうつとむ) 『黄金時代の作り方 あの頃の西武はなぜ強かったのか』(ワニブックスPLUS新書、2025年2月) 西武 広岡達朗監督
唐突ではありますが、あらかじめ言っておきますと、これから西武ライオンズ黄全期を築いた広岡達朗監督の管理野球についていろいろと綴る中で、何か広岡さんに対して否定的な印象を持たれるかもしれません。 でも、私は本当に広岡さんには感謝しております 。若いうちに体づくりの基本を叩き込んでくれたこと、レベルの高い野球を目指すために必要な練習を教えてくれたこと、これらは、私がその後の長い間、野球選手として、また野球指導者、そして解説者として生きていく上で、大いに役に立ちました。 そして、強いチームで野球ができたことで得られたものは私の財産になっています。そのことだけははっきり書いておきます。 かつて、徳光和夫(とくみつかずお) 「プロ野球レジェン堂」 東尾修(ひがしおおさむ) 広岡監督 「広岡監督辞任」 伊東
広岡さんの雰囲気をひんやりとした空気と言いましたが、最大限に良く言うと「冷静 沈着」、ちょっと良く言って「クール」、普通に言えば「冷徹」で、悪く言うとかなりの「陰湿」でした。 一番嫌だったのが、コーチと会話をしているときに織り交ぜるモノマネです。選手の欠点を指摘しているのでしょうが、直接「こうなっているぞ。もっとこうしろ」と言ってくれるのならまだいいのですが、あくまでもそのモノマネは、コーチとの会話の中でやるわけです。そして、それが実に特徴を捉えていて、しかもそれが誇張されていてうまいんです。観察眼の素晴らしさは認めますが、すぐにわかるだけに、やられるとこたえました。 それは私には陰湿に感じたのですが、フォローするとしたら、誰に対しても同じように接していた点はいいところでした。新人だろうが、ベテランだろうが元メジャーリーガーだろうが、平等に陰湿な対応をしていました。 1985年の日本シリーズ終了後、確か選手全員で治療を兼ねた1泊の伊香保温泉旅 行に出かけたバスの車中に「広岡監督は今年いっぱいでユニホームを脱ぐことになりました」と連絡が入ったんです。みんながワーッて大歓声を上げて、さらに万歳三唱したんです。今でもはっきり覚えています。 まあそれくらい、何か鬱屈した思いで野球をやっていたんですね。勝利、優勝の喜びはありましたが、日々の面白くないという思いは、またそれとは別にあったということなんです。私も「プロ野球っって面白くないな」っていう気持ちだったので、一緒になって歓声を上げていました。 余談になりますが、2007年終了後に西武を退団して、NHKでお世話になること となり、ワールドシリーズの取材に行かせてもらいました。当時のフィリーズの監督が、ヤクルト、近鉄で活躍したチャーリー・マニエルさんでした。それで少し話す機会をもらえたので、「私も広岡さんから指導を受けたんです」と伝えると、「それは大変だっただろう」と言っていました。 さらに、マニエルさんは日本で広岡監督から何を学ばれましたかって質問すると「我慢することだ」と言っていました。かなりしごかれたんだと思います。 先日、かつてのチームメイト・工藤公康が「当時の広岡野球を思い出すと、やってい るときは苦しかったけれど、自分が監督になったとき、やっぱりすごく参考になりました 」と言っていました。 この年齢になって、自分たちが指導者の立場を経験して、やっと理解できたというのはあります。ただし、また広岡さんの下でやりたいかと問われれば、やりたくないという人がほとんどでしょう。私もそうです(笑)。 工藤公康(くどうきみやす) 投内連携だけで2時間といった猛練習漬けの毎日でしたが、そういう練習量がプロ野球チームでは当たり前だと思って育ちました。監督やコーチから「やれ!」 「はい!」 広岡監督 「どんなに練習しても壊れない強い体」 広岡 広岡 16人 も輩出しているのです。田淵幸一、東尾 修、森 繁和、石毛宏典、渡部久信、工藤公康、辻 発彦、秋山幸二、伊東 勤、田辺徳雄、大久保博元、若松 勉、大矢明彦、尾花高夫、田尾安志、マニエル 川上哲治 野村克也 星野仙一 プロ野球ファンの中には、広岡 「冷酷な絶対権力者」 工藤 広岡 野村 「データ野球」 広岡 「野球必勝法70か条・野球必敗法70か条」 「どうしたら試合に勝てるのか?」 「必勝法・必敗法」 川上哲治 牧野茂
西武の教え子の石毛宏典(いしげひろのり)
「広岡さん自身が根気よくいろいろと基礎中の基礎を指導してくれたおかげで、8度のベストナイン、10度のゴールデングラブ賞を受賞して40歳まで現役を続けられました。 あの頃基礎を学んでいなかったら、広岡さんの言うように30過ぎで引退していたかもし れません。間違いなく広岡さんのおかげです。結局、広岡さんが弱いヤクルトを、弱い西武を勝たせたじゃないですか。だから僕のなかで名将、知将と呼べるのは広岡達朗しかいないんです。野村さんはヤクルトは勝たせたけど、阪神、楽天では勝てなかった。森さんも西武で勝ったけど、ベイスターズでは勝てなかったですから。 プロ野球チームという技術屋集団において、技術屋をまとめるリーダー(監督)には『技術はこうすれば高くなるんだよ』という指導理論が備わっていることがまず必須。さらに、どんな相手でも納得させるだけの絶対的な理論を持つことが、リーダーの資質とし て最も重要な部分だと思うんですよ。それまで『プロの二軍選手は未熟だから練習しなきゃいけない』『プロの一軍選手は完 成された選手だからマネジメント的なものだけでいい』と言われてきましたけど、広岡さんは一軍だってヘタなやつがいっぱいいると高らかに言っていました。そりゃそうですよ、誰も四割も打ったことないプロ野球界。まだまだ未熟者ばかりです。どうすればスキルアップできるか。広岡さんはヤクルトでも西武でも、選手個人をしっかりスキルアップさせ、二割五分の人間を二割七分、二割七分の人間を三割近く打てるようにしてチーム力を上げていったんですから」 今でこそ、1アウト二塁だったら右方向に打ってツーアウトランナー三塁にする「有効凡打」 「自己犠牲」 「有効凡打」 「自己犠牲」 広岡 「今の野球界を見ても、アマチュアからプロまでの野球観の向上っていうのかな、日本の 野球観をレベルアップさせたのは、僕は広岡達朗と思ってますけどね 」 石毛 広岡野球
私は若い頃に、広岡達朗 『勝者の方程式』 「勝者の方程式」
「鬼だ」「悪魔だ」 と嫌われようと煙たがれようとも、自分の信念を通して生徒達を徹底して鍛える、後になってあの時教えてもらったことがよかったと思ってもらえるように全力投球していたことを思い出します。退職してからその時の生徒達が、こんなことを言ってくれただけでもう十分です。「手が震える思いで受けた英語の授業、怖かったです。ですが、そのおかげで英語は得意科目となりました。」 「先生の怒濤の教壇の姿が今でも目に浮かびます。今でも感謝しています。」 「長い間お疲れ様でした。高校時代のことはずっと忘れません。」 「高校時代には、先生から厳しいご指導を多々いただきましたが、今思えばすべてがありがたいお言葉であり、その一言一言に感謝しております。」 「先生に鍛えられた高校時代がついこの間のように思われますが、もう20年以上経ったのですね。」 「毎日情熱をもって、熱心にご指導いただいたことが、どれだけ有り難いことだったか、分かる歳になりました。本当にありがとうございました。」 「先生に高校時代教えていただいた英語が、こんなに必要になるとは夢にも思わず、ただただ感謝しております。もう少しで3歳になる息子がいますが、将来八幡先生のような厳しくそして温かみのある先生に出会って欲しいなと切に願っています。」 「八幡先生の一本筋の通った教えは、今の自分の仕事にも活かされています。」 ♥♥♥
英語の基本単語であるfavorite 「お気に入りの」 favorite オーラルコミュニケーション favorite 「お気に入りの」 my favorite~ と言ったら、「その種の物 の中でそれが私の一番好きな 物だ」 favorite city だ」と言えば、「私は他のどの都市よりも金沢が好きだ」という意味であって、単に「私は金沢が大好きだ」という意味なのではありません。もう一つ重要なことは、一方で考慮している種類や集団を特定し、ここでは「都市」(city)としての種類・集団を特定しているので、金沢より好きな「町」(town)や「村」(village)があっても全然構わないのです。「その種の物の中で それが私の一番の好きな物だ 」 竹岡広信先生 『LEAP』 、 「favorite「一番好きな」(*×most favoriteは不可。「好きな本を買う」はbuy a book you like [×your favorite book]と表現する)」
もし、favorite a favorite )、Okonomiyaki is a great favorite in our family.(お好み焼きはうちの家族の大のお気に入りだ)のように、事実上、単に「すごく好きなもの」という意味になります。
『ライトハウス英和辞典』(第7版) 「(いちばん)お気に入りの」 「誤用注意報」 ○my favorite color ×my most favorite color ★favroiteはそれ自体が最上級としての意味を持つのでmost favoriteとは言わない。 という注記を与えている意味がお分かりいただけるかと思います。♥♥♥
〔注〕ただし、「my favorite singerは複数おり、その中でも一番好きな歌手」という意味でmy most favorite singerと言うことはあります。
世間から見て「裏方」と思われている業務でも、実に奥深いものがあります。日々見直すべき点を見つけては改善を図り、その業務を一層高度なレベルに高めて世界的な名声を得ている企業があります。よく知られたところでは、新幹線の「奇跡の7分」 コチラ に私の解説が)。毎回新幹線を利用する度に、頭が下がる思いです。
もう一つの例が、関西国際空港 (新関西空港株式会社) 関西国際空港 8度目の「世界一位」 の評価を受けたのです。イギリスの航空サービス調査会社・スカイトラックス社 「手荷物サービス」 関空
新関西空港株式会社
・経由地での荷物の積み忘れや積み間違い ・手荷物タグの発行ミス(カウンターで行き先と違うタグが発行されてしまう) ・手荷物タグの紛失(タグが手に持つから外れ搭載する航空会社や行き先が不明になる) ・出発地で荷物を違う便に載せる積み間違い ・ベルトコンベヤーからの落下 また、飛行機を降りた後に荷物を受け取るまでの時間の短さ、旅行者が取りやすいように持ち手をそろえてターンテーブルに置くなどのきめ細かいサービスも評価されています。テレビの報道番組でも紹介がありましたが、担当者の奮闘ぶりには、同じ日本人としてとても誇らしく感じます。飛行機が到着すると速やかに荷物を降ろし、「荷さばき場」に集められ、乗客が待つ受け渡し場の裏側で、社員が手作業でターンテーブルに載せるのですが、扱いが丁寧です。乱暴に投げたりすることはありません。それどころか、スーツケースの持ち手も乗客がピックアップしやすい向きに瞬時に揃えてベルトコンベヤーに載せているのです。長尺荷物やベビーカーは手渡しする、雨天時には雨で濡れてしまった荷物はタオルで拭き取りをする。こんな些細なことが、仕事をグレードアップさせているのです。「あっという間に荷物が出てきた」「ほかの空港では考えられない」「信じられない」「日本のおもてなしの文化が分かった」 関西国際空港 「お客様の手荷物を大切に取り扱う」 関西国際空港 「直接お客様と顔を合わせる仕事ではないですが、どのように扱えば喜んでもらえるか、いつも心がけています。」
仕事に「主」も「従」も、そして「雑」もありません。そもそも「雑用」という言葉は間違っていると私は思っています。仕事のプロセスにおいて「雑」なる仕事など存在はしません。関空 「裏方の彼らこそ、花形である」 ♥♥♥
英語を指導する際に、特に重要なことは「英語では同じ言葉の繰り返しを避ける」 「ほら、さっき出てきた言葉が、今度はこんな表現で言い換えられているよ」 「 同じ言葉の繰り返しを避ける」
1. 言語のリズムと流暢さ 英語は、リズムと流暢さを重視する傾向があり、同じ単語やフレーズを繰り返すと文章が単調で冗長に感じられることがあります。「繰り返し」 elegant variation(洗練された変化)
2. 語彙の多様性 英語には豊富な語彙があるため、同じ意味を表現する異なる単語やフレーズを使うことで、表現に幅を持たせることができます。言葉を繰り返すことなく、さまざまな表現方法を使うことで、文章がより精緻で興味深くなります。
3. 冗長性の回避 「繰り返し」 4. 言語的な効率性 言葉の「繰り返し」 「繰り返し」
5. 語法的・文法的な慣習 英語の文法には、「同じ言葉の繰り返しを避ける」 接続詞 代名詞 代名詞 he, she, it, they など)や不定冠詞 定冠詞 同義語
昔々、おじいさん おばあさん おじいさん おばあさん おばあさん おばあさん おじいさん おじいさん
Once upon a time, there lived an old man an old woman the old man The old woman went to the river to wash clothes, and then she She her husband he agreed.
日本語では「おじいさん」、「おばあさん」がそれぞれ4回ずつ繰り返されています。一方、英語ではan old man and an old woman、 the old man、the old woman、 she、 her husband、 heなど同じ対象(この場合では「おじいさん」と「おばあさん」)を繰り返して取り上げるにしても、冠詞 代名詞 代名詞
このように、「繰り返し」 同じ言葉の繰り返しを避ける ♥♥♥
松下電器産業(現パナソニック) 松下幸之助 松下幸之助 八幡 パナソニック製品 『TIME』 松下 『タイム』 文化勲章 「経営の神様」 「無から最大の電器工場を作った男」「製造、販売の天才」「ちょっと悲しい目つきの男」
また1964年の米国『Life』 松下 「5つの顔を持つ男」 松下 松下
(1)最高の産業人であること。 (1)は、アメリカ人は機構組織の中で出世した人よりも下積みからたたき上げの実力で出世した人物を讃えるので、松下 松下 松下電器 「最高の産業人」
(2)は、大金持ちであるということです。松下電器の大株主であり、当時長者番付のトップは松下
(3)は、日本人にはない、とても面白い見方だと思われます。アメリカ人は、松下 「わたしの会社は“人をつくる会社”。本業が人づくり、家電製品は副業」 「経営の神様」
(4)は、PHP研究所 『PHP』 『PHP』
(5)松下
松下幸之助
①ビジネスで成功し、億万長者となった。 ②思想家、哲学者としての顔も持ち、著作はベストセラーを連発した。 ③雑誌、出版社のオーナーでもある。 ④経営者だけでなく、一般の人からも広く尊敬されている。 ⑤学歴もなく、貧乏だったところからスタートして、大成功した。 ここまで広範囲に活躍した人はいないでしょう。欧米では、哲学者、思想家でかつビジネスでも成功を収めた知的文化人として尊敬されているのです。当時は不況と経済の弱体化に悩むヨーロッパでも日本に注目するようになり、松下幸之助
私の尊敬する故・渡部昇一先生 『キング』 松下 松下 松下 渡部先生 松下 渡部昇一 『松下幸之助全研究 日本不倒翁の発想』(学習研究所、1983年) 渡部昇一『松下幸之助成功の秘密75』(致知出版、2012年) 松下 ♥♥♥
▲『ノジュール』最新号
昨年末に『ノジュール』12月号(JTB出版) 「東京駅丸の内駅舎と辰野金吾」 辰野金吾(たつのきんご)
エジソン 辰野金吾 ジョサイア・コンドル 辰野 日本銀行本店 “辰野式” 重要文化財 辰野 辰野金吾 東京駅 24件 あります。全部制覇したいと密かに狙っていますが、今日は私の出かけた4件を取り上げます。 さて、そんな辰野金吾 “辰野式” 東京駅 辰野金吾 「旧松本邸」 「南天苑」 辰野 辰野金吾 東京駅 辰野 フランツ・バルツァー 辰野 バルツァー 「レンガ造りでありながら、瓦屋根に唐破風をあしらった和洋折衷のデザイン」 辰野 日本銀行本店 帝国議会議事堂 東京大学工学部 帝国大学工科大学
▲335mの正面長 堂々たる存在感
▲美しいドーム天井
辰野 「辰野式建築」 「辰野堅固」 辰野 東京駅 東京駅 辰野 「武雄温泉楼門」 辰野 東京駅
二つ目。大正・昭和初期までの北海道・小樽市 「北のウォール街」 辰野 「日本銀行旧小樽支店」 金融資料館
▲日本銀行旧小樽支店金融資料館
三つ目。「大分銀行赤レンガ館」(旧本店) 大分市 国登録有形文化財 大分市 東京駅 辰野金吾、片岡安 東京駅 「辰野片岡建築事務所」(辰野金吾・片岡安) 辰野金吾 日本銀行本店 東京駅 片岡安 大阪商工会議所 「辰野式ルネッサンス」
▲大分銀行赤レンガ館
4件目。奈良公園内に、明治42(1909)年に誕生した「奈良ホテル」 チャップリン ヘレン・ケラー、オードリー・ヘップバーン 東京駅 日本銀行本店 辰野金吾 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!今週はケーキ 「パティスリーアキト」(patisserie AKITO) JR 神戸・元町駅 松江駅 「Ciistand」
▲パティスリーアキト
小さなお店ですが、店内には「イートインスペース」
「Ciistand」 「パティスリーアキト」 「ミルクジャム」 ミルクジャム
ミルクジャム 「イートインスペース」 ミルクジャムは古くから世界各地で親しまれてきた伝統的なコンフィチュール(ジャム)で、多くは「Dulce de Leche(ドゥルセ・デ・レチェ)」 「Confiture de lat(コンフィチュール・ド・レ)」 「パティスリーアキト」(patisserie AKITO) 兵庫県淡路島産 ミルクジャム
「Ciistand」 「パティスリーアキト」 「ラクテシトロン」 「エレガンス」 「フレジェ・ビスタージュ」(冬季限定) 「ミルクジャム」 南京町 ♥♥♥
文芸評論家で海外ミステリ研究の第一人者である直井 明(なおいあきら)
▲こんな精緻な研究書は見たことがない!
直井 年生まれ。東京都出身。東京外国語大学インド語科卒業後、商社の海外駐在員としてニューヨークなど世界各地で勤務され、アメリカ人推理小説家・エド・マクベイン87分署 エド・マクベイン 『87分署グラフィティ―エド・マクベインの世界』(六興出版) 「第42回 日本推理作家協会賞(評論部門)」 マクべイン マクべイン マクベイン 直井 マクベイン マクべイン マクべイン 学生時代に、故・大谷静夫先生 三島房夫先生 エド・マクベイン(Ed McBain) マクべイン 山田政美・田中芳文(編)『エド・マクベイン英語表現辞典』(2005年、英語の言語と文化研究会) 私は彼の作品によく出てくる警察のten codes 10-20, 10-34 直井 マクべイン コチラ です)。お世話になりました。エド・マクべイン 直井 マクべイン “The 87th Precint with Akira Naoi “ マクべイン 直井 エド・マクベイン 直井 早川書房 直井 『エド・マクベイン読本』 「海外ミステリ風土記」 「ヴィンテージ作家の軌跡」 直井 『海外ミステリ見聞録』 『本棚のスフィンクス 掟破りのミステリ・エッセイ』 『スパイ小説の背景』
心よりご冥福をお祈りいたします。♠♠♠
「コピー機」 井上義昌 コピー機 今ではコピー代も安くなって、何でもかんでもコピーを取れる便利な時代になりましたね。ところが、仕事にしろ勉強にしろ、要領よくやるものの、本当に身になる勉強や仕事をしていない人も多いようです。本来非常に便利な知的生産のための道具が、人々を一層怠惰にしてしまうこともあるのです。機械を駆使するあまり、機械の奴隷になってしまい、自分の知的生産の向上に役立てているとはおよそ言いがたい側面があるのです。コピーも、盛んに使われている割には勉強のためにはあまり役立っていません。昔なら、他人からノートなどを借りて、それを自分の手で写すしか方法がありませんでした。そこには大きな学びがあったのです。コピー機もあるにはありましたが、非常に高かったので、自分の手で写し取るほうが安上がりでした。それがコピー機 「目的」 「手段」 コピー機 ワープロ
私たちが使う辞書もそうですね。紙の辞書⇒ 電子辞書⇒タブレット⇒スマホ 「英語の力は辞書を引いた回数に比例する」 ユーチューブ ♥♥♥
今年のお正月に、故・草川隆(くさかわたかし、1935-2022) 『寝台特急「冨士」の殺人者』(廣済堂、1992年) 「下段柱」(げだんばしら)
この日、彼女はいくつかの仕事をすますと、神田駅前にオフィスを持つ、庄司探偵事務所を訪れた。といっても、べつに探偵社に用があるわけでなく、そこの調査員の大森拓郎に毎号頼んでいる“下段柱” の原稿を取りに行くためだった。“下段柱” というのは、コミック誌の下段のページの余白のミニ知識のことだった。二行八十字に詰め込んだ文章で、その号によって、さまざまな分野の雑学が盛り込まれる。いわば読者サービスの欄だったが、毎号これを楽しみに読み、話のタネ本にしている読者も少なくない。(pp.45-46)
折から、“下段柱” の執筆者の一人が病気にかかり、新しい書き手を探していたので、彼女は“世界の刑罰” “世界の名探偵”といったテーマのミニ知識を書いてくれないかと、彼に頼んだ。これがきっかけで、大森はこの欄の定期的な執筆者の一人になった。そして、一年半ほど付き合っているうちに、彼女も大森の影響でミステリーのファンになった。(p.46) 彼が再び、本来の目標に立ち返ったのは、侑子と知り合い、“下段柱” を依頼されたためだった。作家志望だっただけに、文章を書くことは好きだ。それに、何よりも侑子に心を奪われた彼は、小さな仕事でも、それを引き受けることで、彼女とのつながりを維持しようとしたのだった。(p.48) 「“下段柱” の仕事は、調べる事が好きなぼくの楽しみの一つだったんだが……できれは……」(p.49) 漫画の版面の外に記す重要な情報を「柱(ハシラ)」 「ハシラ」 「断ち切り」 「断ち落とし」 「ハシラ」 「ハシラ」 断ち切り 「ハシラ」 「下段柱」
作者の草川 隆 『時の呼ぶ声』 『アポロは月に行かなかった』『幽霊は夜唄う』 『個室寝台殺人事件』 トラベル・ミステリー ♥♥♥
あの「経営指導の神様」 船井幸雄(ふないゆきお) 渡部昇一先生(上智大学名誉教授)
上智大学に渡部昇一先生という人がいます。この人はすばらしく頭のいい人で、物事をまとめる名人のように思います。それも複雑に入り組んだことがらを、単純化してまとめるのがうまい人です。 ――船井幸雄『これから10年 本物の発見』(サンマーク出版、1993年)
竹内 均(たけうちひとし)先生(東京大学名誉教授) 渡部昇一先生 渡部先生 「渡部昇一訳『どう生きるか、自分の人生』三笠書房…」 渡部昇一先生 「要約」 竹内先生 「要約」 「東京新聞」 渡部先生 渡部先生 「要約」 「要約」 「知的生活ブーム」 渡部昇一先生 『知的生活の方法』(講談社現代新書、1976年) 「クーラーをつけることが知的生活の一つの方法である」 「クーラーがないと知的生活ができない」 、「紅茶を飲まないと知的生活ができない」 「大きな書庫がないと知的生活ができない」 竹内先生 渡部先生 竹内 均先生 竹内先生 東大教授 東大名誉教授 ニュートン編集長 船井幸雄 渡部昇一先生 ♥♥♥
▲多摩市のベネッセ東京本社
朝フジテレビ系の「めざましテレビ」 東京・多摩市 「ベネッセスタードーム」 株式会社ベネッセコーポレーション 多摩市 ベネッセ東京本社 「共通テスト」 福武總一郎さん(現・ベネッセホールディングス名誉顧問) 「社員に、日常の制約を超えて宇宙適視野の体験をすることによって、新しい視点を獲得するきっかけにしてほしい」 ベネッセコーポレーション東京本部オフィス 「Benesse=よく生きる」 「よく生きる」 福武 「ベネッセアートサイト直島」 「ベネッセスタードーム」 「よく生きる」 直島
【ストーリー】 「宇宙」と聞いて、どんな世界を想像しますか?古来から人類は、美しい星空を見上げ、好奇心を抱き、その好奇心によって、「宇宙」の姿を解明してきました。この番組では、私たちが住む「宇宙」の「時間」「空間」(時空)を巡る旅に出ます。私たちが見上げる夜空に輝く天の川銀河、そして最新の宇宙望遠鏡によって映し出された様々な天体の数々。観測技術の進歩により、私たちの知る「宇宙」はどんどん広がっています。そしてそれと同時に、今なお解き明かされていない宇宙の姿もあるのです。宇宙がどのように誕生し、私たちの地球が生まれたのか。46 億年前に誕生した太陽と、そこから生まれた奇跡。最新科学で解き明かす宇宙の姿。この旅を終えた時、きっと「私たちはこの広い宇宙の一部である」ということを感じられるはずです。
大きなリニューアルポイントとしては、中央に超高輝度のLEDを採用した光学式プラネタリウム投映機「Cosmo Leap Σ(コスモリープ シグマ)」 「Media Globe Σ(シグマ) SE 4KTOL」
▲寝ころびスペース
座席数は61席で、リニューアル後は、靴を脱いで寝転びながらプラネタリウム鑑賞できる各回1組限定の「寝ころびスペース」 (最大利用人数6名まで) が新たに設置されました。観覧料金は大人(高校生以上)600円、子ども(中学生以下)とシルバー(65歳以上)は300円。「寝ころびスペース」は鑑賞料金に加えて2,000円(※最大利用人数6名まで利用可)が必要です。
▲私が訪問した時の館内
もう一つ忘れてはいけないことは、ここはビルの最上階(21階)にあるので、その眺めが絶景ということです。東京都心を360度見渡すことができ、遠くに富士山 ♥♥♥
教員不足 教員採用試験 島根県 教員採用一次試験 文部科学省
こうした状況を受けて文部科学省 ・2025年は教員採用試験実施の「標準日」を5月11日へとさらに前倒しすること ・試験を複数回にわたって実施すること ・大学3年生のうちに試験の一部を受けられるようにすること
などを全国の自治体に要請しています(今年の全国の採用試験の日程一覧はコチラ をご覧ください)。
しかしどう見ても、これらの施策が抜本的な解決につながるとは私にはとうてい思えません。抜本的な教員の処遇改善や働き方改革を早急に進めない限り、人気回復を期待することは難しいでしょう。それどころか、こうした施策が逆に「教職はこんなに不人気ですよ」 「ネガティブ・キャンペーン」 公立学校教員採用試験 文部科学省
ここでエジプトのお話です。三人の人夫が重たい石を運んでいました。かなりの重労働です。そこに一人の旅人が通りかかり、一人目の人夫に尋ねました。「何をやってるの?」 「ごらんの通り石を運んでいるんだ」 (牢働) 「何をやってるの?」「あそこをごらん。何か建物がつくりかけてあるだろ。あのための石さ」 (労働) 「何をやっているの?」 「自分はいまエジプトの文明を築く仕事をしている最中です」 (朗働) 「牢働」「労働」「朗働」
教員採用試験 「ネガティブ・キャンペーン」
教員志望者を増やす対策の一つとして、文部科学省 教員採用試験 「お試し受験」 コチラ の記事をご覧ください)。採用試験の早期化は、「早期化すること」が目的ではなかったはず。教育改革においては、いつの間にか「手段」が目的化することはよくあります。すでに走り出したとはいえ、採用試験のあり方や方法について、一度立ち止まって、功罪を検証し、より意味のある政策を打ち出すべきだと思います。
教職の道に進む学生・社会人は年々減少しています。2021年度の公立学校教員採用試験 教員採用試験 「教師のなり手不足」 「組織で人材の質を維持するのに必要とされる倍率は3倍とされ、『危険水域』を割った」
教師は決して子どもたちに人気のない職業ではないのに、どうして教員採用試験
1つは、大量退職、大量採用の波
2つめは、民間企業に人材が流れてしまう
3つめが、教職へのイメージの悪化 「ブラック労働」 「学校=ブラックな職場」
教員の不人気による教員不足からくる深刻な事態が顕著になってきています。「教職不人気で加速する『教員の学力低下』の深刻度」 『Newsweek日本版』 「倍率が高かった20年前であれば採用されなかったような人が、教壇に立っている」 「教員の学力の低下」 教職調整額
「そもそもお金云々ではなく、教員があたかも『何でも屋』のように扱われている現状を変えなければならない。現場の教員が思っているのは、『カネはいいから、時間(ゆとり)をくれ』に尽きる。教員は、教えることの専門職。この原点に立ち返り、役割革新を進めることが真の処遇改善というものだ。」 それともう一つ大切なこと。「働き甲斐」 ♥♥♥
この度22年も連続で「日本一の庭園」 足立美術館 足立全康(あだちぜんこう) 『庭園日本一 足立美術館をつくった男』(日本経済新聞社、2007年) 足立 「足立時間」
私が、目上の人と会うときに心がけたものの一つに、時間を厳守することがある。誰と会う場合でも、こちらから訪ねるときは必ず十分前には到着した。いくら金がなくても、その気になれば必ず守れるのが時間だ。こちらの都合だけで、決して相手の時間を無駄に費やさせてはならない。 地元の人たちの間では、「足立時間」と言ったら、約束の時間の十分前にはちゃんと着くことを意味するそうだ 。十分早く着いてさえいれば、相手の人の事情と都合によっては、それだけ長く面談できる可能性もある。礼儀を欠く恐れもない。 時間にルーズな人間を、私はあまり信用しない。誠実さが感じられないと思うからである。私の経験からいって、デートの時に遅れて来るような女性は見込み薄である。だから社員はもとより、身内の者にも時間だけは厳守するように、口を酸っぱくして言っている。時間通りに来た社員には賞与をやるが、遅れた人間にはやらないというくらいに徹底した。タイム・イズ・マネーを身をもって知らせた。 また、私は人と会う際、必ず備忘録なるものを携帯した。聞きたいこと、知りたいこと、相談したいことを予め項目別に書き記しておくのである。それとともに、そこでどんなことを話し、そのために何をなすべきかを素早くメモに書き留めた。というのも、決められた時間内に話を要領よく切り上げることが礼儀であり、ひいては第一印象を良くすることになると考えたからである。分刻みのスケジュールで動いているような人に対しては、ケジメをつけることが付き合いの第一歩だと思う。 (pp.234-235) 約束の時間を守る、というのはとても大切なことです。誰かと会う時は私は遅くとも10分前には着くようにしています。私は現役で勤めていた頃は、「提出物は期限内にきちんと出しなさい。」 にいつもうるさく言っていました。期限を過ぎてから出すなどもってのほか、と厳しく指導し、遅れた提出物は一切受け付けませんでした。残念ながらここら辺をルーズにする教員がいっぱいいます。陸上の幅飛びであれ、砲丸投げであれ、ちょっとでも足が出たら即失格でしょ。信用はまずこんな小さなところから積み重ねるものです。こういう小さなことを疎かにする人は、大きなことはできません。小さな約束を守る人は成功します。ある会社の代表取締役さんの言葉です。
会社の信用も個人の信用も同じです。口約束をふくめてすべての約束は守ることから信用は生まれる。ですから、うちで中途採用の面接をするときには、だれが何時何分に到着したか、すべて記録させていますよ。約束の時間の10分前に来ていなければだめです。時間ピッタリでもだめです。ちょっとしたアクシデントでもあったら、それで遅れてしまいますからね。10分前に来ない人はそれだけでマイナス50点です。 島根県立大田高等学校 ベネッセ 松江市 「 ホテル一畑」 大田駅 特急 「おき」 松江 松江 宍道 松江駅 「止めて~!」 何が起こるか分からない 、やはり何事も時間に余裕を持って行動しないといけない
「飛行機を使えば余裕で間に合うのになんで前日に移動するんですか?」 出雲空港(JAL) 米子空港(ANA) 羽田空港 新幹線 JR 松江駅 特急「やくも」 東京駅
ラーンズ 「英語は絶対に裏切らない! 生徒の英語運用力を磨く研究会」 名古屋駅 「TKPガーデンシティ名古屋新幹線口バンケットホール」 松江駅 特急「やくも」 名古屋駅 名古屋城 特急「やくも」 新見駅 岡山駅 「のぞみ」号 新神戸駅 名古屋 伯備線(出雲市~岡山) やくも号 名古屋 世の中、 何が起こるか分かりません。 「時間に余裕を持って」 ♥♥♥
松江北高を辞して、平日も2日ほど昼間に家に居ることが増え、午前10時半からテレビ朝日 「大下容子のワイドスクランブル」 大下容子(おおしたようこ) 大下容子 『THE 21』1月号(PHP研究所) を参考にしました。
不特定多数に向けて情報を正確に伝えると同時に、エンターテインメントとして視聴者を楽しませることが求められるワイドショーの司会者として、どんな話し方を心がけているのでしょうか?「まずは基本的なことですが、『ゆっくりと、大きな声で、丁寧に話すこと』と『正しい日本語を話すこと』がアナウンサーとして最も大切だと考えています。例えば、「コンビニ」ではなく「コンビニエンスストア」と言うなど、なるべく丁寧に正しく話すことを心がけています。どんなに情報を詰め込んでも、聞き手の方たちに伝わらなければ意味がありません。舞台俳優の方が、「どんなにいいセリフを言っても、観客に届かなければ意味がない」とおっしゃるのを聞いたことがありますが、アナウンサーも全く同じです。私たちの仕事は、人に伝えることですから、ひとりよがりの独白にならないよう、『聞く人に伝わっているか』を常に意識しながら話すようにしています」
正しく伝えることに加えて、ワイドショーでは面白さや楽しさも視聴者に届けなくてはいけません。「そこが一番難しいところだと感じています」 大下 「ただ次から次へと情報を伝えるだけでは、きっと視聴者もつまらなく感じるでしょう。お昼の情報番組ですから、ユーモアや笑いをお届けすることも大切ですが、私白身がそれを発信するのは本当に難しい。あらかじめ用意したジョークを言ってみたこともありますが、狙って言うと絶対にウケないとわかりました〔笑〕。『ワイド・スクランブル』と同時間帯に放送されている他局の番組では、タレントさんや芸人さんが司会を務めているので、面白く話すという話術の面では、私のようなアナウンサーは足元にも及びません。ですから私は、その役目は他の人にお任せすることにしています。デーブ・スペクターさんのようにユーモアのあるコメンテーターがレギュラー出演しているので、私はその方たちに質問して、話を引き出す役割をする。そして、出演者のコメントを私白身も楽しむようにしています。私たち出演者が楽しんでいれば、それを見ている視聴者の方たちも楽しんでくださるだろうと思いますから」 と。
テレビ朝日 大下 「今もですが、若い頃は本当に話すことに自信がなかったので。そんな中で先輩に褒められるととても嬉しかったんです。ですから私も、後輩たちの良いところをできるだけ伝えるようにしています。注意することがあっても、まずは一つでも良かった点を挙げてから、ここはもっとゆっくり話したほうがいいかもね」といった伝え方をします」 「聞きたいことがあれば、まずは自分と年齢の近い先輩に相談すると思うんです。私も若い頃はそうしていましたから。それに若手が最年長の私からいきなり注意されたら怖いだろうと思うので〔笑〕、私からはあえてあれこれ言わず、アドバイスを求められたら答えるというスタンスを取っています」
メインキャスターという立場なら、「自分が主役」 大下 「私は中学・高校とバレー部でセッターを務めたのですが、メインキャスターはまさにセッターみたいな仕事なんです。コメンテーターの皆さんがアタッカーで、セッターの私はアタッカーが気持ち良く打てるようなトスを上げる役目。数人いるアタッカーの誰に打たせるかもセッターに任されますが、私も番組で『今日はこの人が調子いいな』と思えば、そのコメンテーターに多めに質問したりするので、そんなところも似ています。セッターは縁の下の力持ちみたいなポジションですが、アナウンサーの仕事と共通する点はとても多いですね」 なるほど、バレーボールのセッターとアナウンサーは共通点があるのですね。
彼女のポリシーは、 「アナウンサーは自分でコメントするよりも、的確に質問することが一番大事な仕事なので、『誰に何を聞くか』というポイントだけはしっかり捉えたいと思っています」 大下 「『ワイド・スクランブル』は生放送なので、その日の放送で扱うテーマが最終確定するのは当日朝。その日の内容を確認してから、アナウンス部にある一般紙とスポーツ紙合わせて10紙に目を通して、テーマに関連するニュースをチェックするのが日課です。情報番組を20年以上やっていても知らないことだらけなので、新聞を読みながら『何がわからないのかもわからない』という状態から、『自分がわからないこと』を明確にしていきます。そうすれば、『番組の中でこれをコメンテーターやゲストに聞いて みたい』というポイントもはっきりします。こうしてしっかり準備することで、『これだけ準備をしてもわからないということは、堂々と“わからない”と言っていいのだ』と自分を安心させることもできます」 「ただし、相手のことを理解するには、自分に余裕がなくてはいけません。打ち合わせの時も自分のことで頭が一杯の状態だったら、他人に注意を向けることはできませんよね。ですから私は毎朝6時前に出社して、早めに自分の準備を済ませます。そうすれば、打ち合わせでは周囲の様子を観察するだけの余裕を持って、人の話をきちんと聞けるからです」 「キャリアを重ねれば重ねるほど、準備の大切さを実感するようになりました。できる限りの準備をしておけば、たとえ生放送中に想定外のことが起こっても、『これだけ準備したのだからなんとかなる』と腹をくくれます。今思えば、昔は横着していましたね。若い頃は、新聞もサッと目を通すだけでした。それでも、番組は滞りなく進行できるんです。うんうんと相槌を打って、『○○さん、いかがですか』と台本通りに話を振るだけでなんとかなるし、極端な話、私が何もしゃべらなくても番組はそれなりに進んでいくものなんです。でも最近は、メインキャスターを任されたからには、自分なりの視点を持って番組に臨みたいと思うようになりました。自分の意見をオンエアで口に出すか出さないかは別として、自分の考えを持って主体的に取り組んだほうが自分にとって得るものが大きいと気づいたからです。ニュース原稿を読むときも、自分の中でなんとなくでも考えるように心がけると、だんだんニュースが面白く感じられるんですね。自分が面白ければ、視聴者にもそれが伝わるはず。それに気づいてからは、台本通りに話して終わり、というやり方はしなくなりました」 うまく話すためのアドバイスをお願いすると、こんな答えが返ってきました。 「話すことよりも、まずは相手の話を聞くことを心がけるとよいのではないでしょうか。自分が一方的に話すより、相手の話を受けて言葉を返すほうが印象に残るし、相手も気持ちよく話せるはずです。話すときも常に相手がどんな気持ちでそこにいるのかを考えて、その話に耳を傾ける。そんな聞く姿勢がある人は、とても素敵だと思います」 まさにコミュニケーション原点のコツですね。人間の言語活動は50%が聞くこと、30%が話すこと、15%が読むこと、5%が書くことだと、デール・カーネギー 「耳は二つあるが、口は一つしかない。だから口の二倍は耳を使わねばならない」 ♥♥♥
1991年1月、故・ジョージ・H・W・ブッシュ大統領 宮澤喜一首相 ブッシュ大統領 宮澤首相 バーバラ・ブッシュ夫人 ブッシュ大統領 バートン・リー博士 「ディナーが終わるまでテーブルの下で寝かせてくれ」 「晩さん会の参加者には『インフルエンザである』と言ってほしい」 ブッシュ大統領 「 ちょっと皆さんの注意を引こうと思って」 「気を失ったことは全然覚えていない。自分は神秘主義者ではないが、最後に記憶にあるのは、静かな天国にいるような心地であったことである」 「よく覚えていない」 スコウクロフト大統領補佐官 バーバラ大統領夫人 「私はここにいます。私が席を立つと、世界に悪いサインを送ることになるのでここにいます」 「皇太子さまと午後に、テニスを一緒にやったのが良くなかったのかもしれません。ここにいるアマコスト大使(駐日米大使)も一緒でした。ブッシュ家の家訓ではテニスに負けるわけにはいかないのです」 「日本人にはとうていできないことだ」
公の場で倒れて弱い姿を国民にさらしたブッシュ大統領 クリントン トランプ候補 トランプ
欧米ではスピーチの際、発するジョークのセンスは発言者の洗練度、人間的奥行きの深さを測るバロメーターとも言われますが、日本にはそういった文化はありません。このジョークを理解できるかどうかは、日本人にとっては実に難しい問題を含んでいます。一例を挙げてみましょう。
1992年、当時のジョージ・H・W・ブッシュ米大統領 宮澤喜一首相 宮澤首相 『テーブルの上に立っていろ』 宮澤首相 ブッシュ大統領 長井鞠子(ながいまりこ) ブッシュ元大統領 「宮澤氏には、あのときのお返しがしたいのでテキサスの我が家に来てほしい、もちろん今度は“Dinner is on me.”で、とお願いしてあります」 ブッシュ大統領 宮澤首相 “ Dinner is on me.” 「今度はわたしのオゴリで」 「今度はわたしの上にゲロを吐いてもいいよ」 長井 「今度はわたしのオゴリで」 『伝える極意』(集英社新書) ♥♥♥
▲実に面白い体験記でした
最近、マスメディアでwoke “woke” wake (動詞:目覚める・起きる)」の過去分詞形です。アフリカ系アメリカ人のコミュニティでは「awake (形容詞:目が覚めている・起きている)」の代わりに“woke” 「主に人種差別を始めとした社会問題について敏感でいる」 “woke” “woke” 「人種差別や社会問題に対して関心を持つこと、敏感でいること」 “stay woke” 「人種差別について関心を持ち続ける、社会正義に目覚めている」
The race riots that happen in Europe and the United States feel like somebody else’s business, but we all have to stay woke
「見えない差別や偏見のコードにも神経を研ぎ澄ましていること」を意味します。日本語の「意識が高い」「意識が高い人たち」といった表現の意味するところに近く、より挑発的なニュアンスが感じられます。
少しこの表現の歴史に歴史を振り返ってみたいと思います。⇒詳しくはコチラ をご覧ください
「ウォーク」(woke) レッドベリー 「スコッツボロ・ボーイズ」
古くは1940年代に遡り、1970年代にはアメリカの戯曲のセリフで使われるなど、徐々に市民権を得ていきました。“stay woke” エリカ・バドゥ(Erykah Badu) 「マスター・ティーチャー」(Master Teacher) 「ブラック・ライヴズ・マター」(Black Lives Matter) マイケル・ブラウン(Michael Brown) ブラウン woke “stay woke” Black Lives Matter運動 “woke” “woke” OED に追加されたのは2017年のことで、“being ‘aware’ or ‘well-informed’ in a political or cultural sense”と定義されました。ソーシャルメディアを中心にwoke Wokeness
一方、Wokeismという新語が台頭してきました。保守的な人たちが進歩派を攻撃する時に使う言葉です。黒人が苦しんできた人種差別の歴史を、子どもたちに性格に伝えるべきだとする考えを、保守の一部はWokeism(やりすぎなWoke意識)だとして批判します。さらに、黒人が奴隷として苦難の道を歩いたことを題材にする書籍は、白人の子どもにとって愉快ではないので、図書館から除外するべきという主張さえするのです。アメリカの南部を中心に、政治・教育の場で、進歩派と保守派の対立はWoke/ Wokeismをもとにして、ますます激しくなりそうです。――旦 英夫『米語ウォッチ』(PHPエディターズグループ、2024年7月) 「意識の高いやつら」といった感じでwoke 否定的な意味合い で用いられることも多く目に付くようになりました。ポジティブな意味でwoke “woke” 、 「先進的だと気取って過激なことを言ったりやったりする危ない人」 ♥♥♥
毎年「読解」の授業で、2004年度の北海道大学
Ten or 15 years ago Ten or 15 years ago ここで、私が教えている勝田ケ丘志学館 京都大学 「なんで英単語(Ten)と数字(15)がごちゃまぜになっているのですか?」
確かに英語で数をどのように表現するかについては、高校時代、授業であまり習った記憶がないのでしょう。しかし英語には明確なルールが存在しています。英語では基本的に数字が使用される場面や数字の大きさによって、算用数字表記 英単語表記 The Chicago Manual of Style 1桁の数字は英単語で、2桁以上は算用数字で書く のが一般的です。大きな数字の場合には、英単語で書くよりも視覚的に認識しやすいため、10以上は算用数字で表記するというのがルールなのです。しかし注意すべき例外としては、例えば「8人の男性と20人の女性」のような同じ文中に1桁と2桁の数字が混ざっている場合には、eight males and 20 femalesではなく、8 males and 20 femalesというように数字で揃えて書くことが推奨されます。また、「参加者のうち15人は13歳~19歳(teenagers)でした」のような文脈で、文頭に 数字が来てしまう場合には、15 of the participants were teenagers.ではなく、Fifteen of the participants were teenagers.と文頭の15を英単語で表記することになっています。このようなことを頭に入れておくと、上記の英文で“Ten or 15 years ago” ♥♥♥
【算用数字表記をする場合】 ・10より大きな数字 ・単位の前に来る数字 ・統計学や数学的な場面で使用される数字 ・パーセントや比率を表す数字 ・時間・日付・年齢・点数・金額を表す数字【英単語表記をする場合】 ・10以下の数字 ・文章・タイトルなどの始めに来る数字 ・おおよその量を表す数字
カシオ計算機 電子辞書 カシオ 電子辞書 「EX―word(エクスワード)」 シャープ キヤノン 電子辞書 カシオ 「GIGAスクール構想」 電子辞書
▲私の愛用する電子辞書
近年の電子辞書 電子辞書 文部科学省 「GIGAスクール構想」 電子辞書
カシオ 増田裕一社長 「教育現場でハードの需要が減少しており、すでに展開している教育アプリなどのソフト事業に切り替えていく」 「EX-word」
カシオ 電子辞書 電子辞書 カシオ
もうずいぶん前のことになりますが、岡山県立笠岡高等学校 カシオ計算機岡山支社 電子辞書 かたくなに電子辞書の教室への持ち込みを禁じてきました。松江に帰ってから、 「授業に生かす電子辞書セミナー」 米子・ビッグシップ 神戸市外国語大学 野村和宏教授 非常に勉強になりました。英語教育論だけでなく、実際の機器を試しながら、電子辞書 野村先生 小西友七先生 野村先生 のお話を聞き、特に現在の電子辞書
▲神戸市外国語大学野村和宏教授と
そんなこんなで、カシオ計算機 、学校に来ていただいたり、電子辞書 松江北高等学校 電子辞書 カシオ 電子辞書 ♥♥♥
カー用品チェーン大手「イエローハット」 鍵山秀三郎(かぎやま・ひでさぶろう) ローヤル 「掃除」 「①気付く人になれる ②謙虚な人になれる ③感動の心がはぐくまれる ④感謝の心が芽生える ⑤心が磨かれる」 「日本を美しくする会」
鍵山秀三郎さん(イエローハット創業者) 「掃除」 「掃除くらいしかできることがないのだろう」「どうせすぐにやめるさ」 鍵山 「では、他に会社をよくする方法があるのか?」 「掃除」 「やはり、今までやってきたことは間違ってはいなかった」 鍵山 鍵山 「他人のゴミ袋を勝手に開けるのはプライバシーの侵害だ!」 「この人たちは街を美しくしようと掃除をしてくださっているんですよ。何が悪いんですか!」 鍵山 鍵山 鍵山 鍵山 。「御社の社員は、言葉遣いや態度が他社の人とはずいぶん違いますね」「車の停め方ひとつをとってみても、きちんとされていますね」 「掃除のやり方を教えて欲しい」 鍵山 ここからもまさに「10年偉大なり。20年畏るべし。30年歴史なる。」 鍵山 「大きな努力で小さな成果」 「エーッ、その逆じゃないんですか?」 と言われることがよくあります。「小さな努力で、大きな成果」 「大きな努力で、小さな成果」 『ライトハウス英和辞典』(研究社)
鍵山 「小さな努力」 「大きな成果」 「小さな努力」 「大きな成果」 「大きな努力」 「小さな成果」 「大きな努力」 「小さな成果」
鍵山 『致知』(致知出版) 鍵山 「もっと、もっと、もっと・・・」 『請求書の人生』 「もっともっと」 『領収書の人生』 『領収書の人生』 「ありがとう、ありがとう」 『領収書の生き方』 『請求書の生き方』 『領収書の生き方』 鍵山 イエローハット 『領収書の人生』 『請求書の人生』
鍵山 「三冠王」 「三感王」 「 あ~そうだなあ」 「感動」 「関心」 「関心」 「感動」 関心 感動 「感謝」 関心 関心 感動 と 感謝 「感(関)」 鍵山 「三感王」
関心 ⇒ 感動 ⇒ 感謝 ができるようになれば、立派な「三感王」 「三感王」 ♥♥♥
「感(関)心」: 幾つになっても新しいものに興味を持ち続ける。 「感動」: 幾つになっても感動する心を持つ。 「感謝」: 幾つになっても感謝の心を忘れない。
松江 「 入浴剤」 「バスクリン」
(株)バスクリン 津村順天堂(現・ツムラ) 「浴剤中将湯」 「浴剤中将湯」 「バスクリン」 「 バスクリン」 「浴剤中将湯」 「クリンバス」 「CLEAN」 「 CLIN」 「ツムラサイエンス」 「 日本の名湯」 「きき湯」
温まるのは「温泉ミネラル成分」(乾燥硫酸ナトリウム・炭酸ナトリウム) バスクリン 「天然エホバオイル」
私の自宅のお風呂には、ジャグジー 「美泡湯」 ミストサウナ ヒーリングライト 冷暖房設備 「入浴剤」 「きき湯」 「アーユルタイム」 バスクリン社 「ウェルネス」
(株)バスクリン 「日本の名湯」 「日本の名湯 夢ごこち」 「日本の名湯 夢ごこち」 「大分長湯」「木曽福島」「奥会津金山」 「大分長湯」、「木曽福島」、「奥会津金山」
▲新発売は三種類
「微細発泡にごり湯」 「きき湯」
「日本の名湯 夢ごこち 大分長湯」新登場! 「ウェルネス」 「日本の名湯 夢ごこち 木曽福島」新登場! 「日本の名湯 夢ごこち 奥会津金山」新登場!
▲私の一番のお気に入り
どんな風にシュワシュワと泡立つのか、その様子が映像で公開されています。♥♥♥
VIDEO
松下幸之助(まつしたこうのすけ) パナソニック 「水道哲学」 「水道哲学」 松下 「水道哲学」 松下電器産業 松下 松下 松下 松下 「水道哲学」 水というものは、人間にとってなくてはならない貴重なものです。それを通りすがりの人が思う存分に飲んでいます。しかしそれを誰一人として泥棒だと責め立てたりはしません。それは水が豊富にあり価格も安いからです。 「これだ!―いい物をたくさん!!これを実現することにより、物質的な豊かさを生み出し、人々の幸福を実現していくお手伝いをすることこそ、自らの使命だ!」 松下 「水道哲学」 松下幸之助 「ダム経営理論」
どうして松下 成功哲学 成功哲学 成功哲学 松下 「いわば水道の水のように、いい物を安くたくさんつくるということは、いつの時代でも大切なことやで」(松下)
よくよく考えてみると、「いい物」というコンセプトと、「安く」というコンセプトと、「たくさん」というコンセプトは相矛盾する考え方です。「いい物」をつくろうとすれば手間もかかりコストも高くなる。それを「たくさん」つくるというのは、不可能に近い至難の業です。その不可能を可能にすべく、科学者、技術者、産業人が必死の努力を重ねたからこそ、今日の発展・繁栄をみることができたのです。「いい物を安くたくさん」 松下 「水道哲学」
なおこれには後日談があります。高度成長が行き詰まった後のことですが、この「水道哲学」 「最近は水道の水のように、あふれんばかりにモノを作るようになったから公害が出る、といわれて具合が悪くなった」 「水道哲学」 「水道哲学」 ♥♥♥
直島(なおしま) 直島 宮浦港 草間彌生(くさまやよい) 「赤いかぼちゃ」(1994年) 「Open Air “94 “Out of Bounds” —海景の中の現代美術展—」 「ベネッセハウス」 「どこにでもある瀬戸内の風景を、ここにしかない風景に変える」 「太陽の「赤い光」を宇宙の果てまで探してきて、それは直島の海の中で赤カボチャに変身してしまった」 草間 草間 草間 「南瓜」 直島 「Open Air ’94 “Out of Bounds” ―海景の中の現代美術展―」 「南瓜」 直島 「南瓜」 「南瓜」 「南瓜」 「南瓜」
● 水に浮いているような唐突感を出したい
● できるだけ突端の部分に作品を置いてみたい
という狙いで、海の青や木々の緑に囲まれた風景の中で、より人々の目を引くよう黄色に彩色されているのも特徴です。この場所に設置されているということに、「在るものを活かし、無いものを創る」「無名の場所を特別な場所へ作り替えていく」
「南瓜:かぼちゃ」 直島 「南瓜」 直島 「ベネッセアートサイト直島」 「南瓜」 草間 「無限の可能性」 「自然との調和」 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はポテトサラダ 松江市の片原町、老舗洋食レストラン「西洋軒」 居酒屋「だんだん」 「友達のポテサラ」 岡山 「成城石井」
▲メニューにも大きく紹介
▲うず高く盛られて出てくる「友達のポテサラ」
でもやはり今のところナンバーワンは、この「だんだん」 「友達のポテサラ」 「ポテトサラダ」 ポテトサラダ ポテトサラダ 「ポテトサラダ」 ポテトサラダ 「だんだん」 米子 「お持ち帰り」(テイクアウト、600円) ♥♥♥
JR 米子駅 米子東高校 「勘弁してよ…」 「がいなロード」( 米子駅 ▲米子駅「がいなロード」
さて、乗ったタクシーの運転手さんに、米子 東高 米子駅 米子駅 「がいなロード」
さて、年が明けました。JR米子駅 「シャミネ米子」 「シャミネ米子」 米子駅 輸入食品専門店「ジュピター」 JR 松江駅 牛タン専門店「炭焼き牛タン東山」 松江店 「残念ながら、ちょっとこのお店のラインナップにはガッカリです。もっと素敵な飲食店がいっぱい入るといいなと期待していたものですから。」 鳥取駅 松江駅 のシ ャミネ
次はここに何のお店が入るのでしょうね? 駅の利用者に要望を聞いてみると「ご飯を食べられるところがもうちょっとあったらいいですね。ちょっと電車の間隔が空いていたりするのでそういう時にあるといい。」 「昔本屋さんが米子駅にあったんですよ。乗るときに買って乗れるし。あとは、ささっと食べられるうどん屋とか。」 「カフェがあったほうがいいね。おしゃべり友達だからやっぱりカフェ行かんと。」 「コワーキングスペースみたいなのがあるといいですね。そしたら時間潰しじゃないですけど、そういうときに仕事を一つできたりとかするので良いかなと思います。」 「シャミネ米子」 JR西日本山陰開発 松江駅 「だいぜん」 「レクラン」
話は変わって、JR松江駅 「待合室」 「待合室」 米子駅 「待合室」 新型「特急やくも」 ♥♥♥
「ゴディバ」(GODIVA) ベルギー・ブリュッセル ゴディバ ブリュッセル ドラップス一家 ゴディバ ベルギー・ブリュッセル ドラップス 「ショコラトリー・ドラップス」 ピエール・シニア・ドラップス ドラップス夫人 ジョセフ ピエール・ジュニア フランソワ イヴォンヌ ▲やはりゴディバは入れ物もおしゃれでチョコも美味しい
「ショコラトリー・ドラップス」 「ゴディバ」 ブリュッセル 「ゴディバ」 「ゴディバ」 レディ・ゴディバ レディ・ゴディバ ジョセフ・ドラップス ガブリエル 「ゴディバ」 「ゴディバ」 「私たちは記憶に残る幸せな時を届けます」 ゴディバ ブリュッセル 「ゴディバ」 ゴディバ
中世から続く、伝統ある「ベルギー王室御用達」 「ベルギー王室御用達ブランド」 「ゴディバ」 「ベルギー王室御用達」 アソシエーション・オブ・ザ・ベルジアン・ワラント・ホルダーズ ゴディバ 「ベルギー王室御用達」
日本では、高級チョコレートの先駆けとして、1972年に日本に出店しました。現在、国内では百貨店やショッピングモールを中心に300店舗以上を展開するほか、コンセプトストアの「ATELIER de GODIVA(アトリエ ドゥ ゴディバ)」 「GODIVA café(ゴディバ カフェ)」 「GODIVA Bakery ゴディパン」
例えば、ベルギーチョコレートといえば「外側のパリッとした食べ応え」と「内側の甘美で柔らかな食感」のプラリネが有名ですが、ゴディバ ゴディバ
ベルギーの小さな自宅工房で生まれたゴディバ ゴディバ ゴディバ 「We Create Memorable Occasions of Happiness.(私たちは記憶に残る幸せな時を届けます)」
「ゴディバ」(GODIVA) レディ・ゴダイバ 「ゴディバ」
▲高松のゴディバ
▲松江のゴディバ
領主レオフリック伯爵 レディ・ゴディバ レオフリック伯爵 レオフリック伯爵 レディ・ゴディバ レディ・ゴディバ 「もしおまえが一糸まとわぬ姿で馬に乗り、コベントリーの町中を廻れたなら、その時は税を引き下げて建設計画を取り止めよう。」 一糸まとわぬ姿で馬にまたがって町を廻りました 。感激した領民たちは、そんな彼女の姿を見ないように、その日家の窓を固く閉ざして敬意を表しました。そして伯爵は約束を守り、ついに税は引き下げられたのでした。
ゴディバ ジョセフ・ドラップス ガブリエル レディ・ゴディバ 「ゴディバ」 ゴディバ 味わう人すべてを幸せで満たす芳醇な味わいは、人を思いやる深い愛を伝えます 。ゴディバ 「バレンタインデー」 松江駅 ♥♥♥
アンドリュー・カーネギー(Andrew Carnegie 1835-1919) 「 USスチール社」 「鉄鋼王」 カーネギー カーネギー・メロン大学 カーネギー・ホール カーネギー財団 彼は医者の手も借りず、助産婦の世話にもならずに生まれました。それほどまでに貧乏世帯だったのです。初めて働きに出たときの賃金は1時間2セント。それが後に4億ドルもの資産を築き上げるのです。彼の若かりし頃を見てみましょう。
彼は少年時代、腹に子を宿しているウサギを一頭つかまえました。たちまち子ウサギが何匹も生れましたが、それを育てるための餌がありません。これは困ったなと思った途端に名案が浮かんで、彼は近所の遊び仲間に宣言しました。「クローバーの葉だのタンポポの葉だの摘んできてくれないか。この子ウサギを育てるんだ。その代り、摘んできてくれたお礼に、君たちの名をこの子ウサギの名につけてやるよ」 アンドルー J・エドガー・トムソン氏 カーネギー J・エドガー・トムソン製鉄所 トムソン氏 カーネギー カーネギー カーネギー カーネギー カーネギー カーネギー カーネギー ミダス王 アンドルー・カーネギー リンカーン アンドルー・カーネギー
彼こそが真の富豪だと思います。「自分が築いた富の使い道を考えずして死んでしまうのは、真の富豪ではない」 三通り あるというのが、カーネギー 「児孫の為に美田を買わず」 アンドリュー・カーネギー カーネギーホール 「一年先を考えるのなら、金を貯めよ。十年先を考えるのなら、木を植えよ。百年先を考えるのなら、人を育てよ」
彼は生涯に合計たった4年間しか学校へ行きませんでしたが、旅行記・伝記・随筆・経済など著作は8冊もあります。公共図書館へ寄付した金は計6,000万ドル、教育制度改善のための寄付も計7,800万ドルに及びます。彼はスコットランドの民衆詩人ロバート・バーンズ ウィリアム・ シェイクスピア 『マクベス』 『ハムレット』 『リヤ王』 『ロミオとジュリエット』 『ベニスの商人』 カーネギー カーネギー 「金を残して死ぬのは恥辱だからね」 ♥♥♥
「英語=日本語」 「morning=朝」「night=夜」「evening=夕方」 「salad=サラダ」
▲付箋は出たときに読んで気づいた誤訳箇所
私が大好きなシンガーソングライター・岡村孝子(おかむらたかこ) 『昨日よりも今日よりも~』(飛鳥新社、1992年、1,500円) がアルバム『mistral』 バーバラ・アン・キッパー 「 思わずニッコリ微笑みたくなる幸せのリスト」 「バーバラさんは、辞典の編集などにも携わっていて誤植が大嫌いという人。当然、誤訳も…(好きな人はいないが)。心配で胃が…。」 「salad days」 「サラダの日々」 学生時代にサラダばっかり食べていたのでしょうか?それとも、おしゃれカフェのサラダに、そんなメニュー名でもついていたのでしょうか?丁寧に辞書を引く手間を惜しんだために起こった誤りです。私の生徒だったらこってりと絞られるところですが、ご愛敬としましょう。 salad days 「サラダの日々」 green のイメージですよね。実は英語のgreen にも、「未熟な、経験が浅い」 という使い方があります。そして、このsalad days green なのですが、転じて未熟な物を表すようになったのです。つまり、salad days 「若くて経験が浅い未熟な頃」 (例)I was in my salad days
ただし、このイディオムにはもう一つの意味合いがあります。若さには「未熟な、経験が浅い、世間知らずな」というネガティブなイメージがあると同時に、「青春時代、全盛期」 one’s heyday(全盛期) という意味でも使われるようになりました。
ちなみに、このsalad days ウィリアム・ シェイクスピア(William Shakespeare)
“My salad days, when I was green in judgment”
シェイクスピア 『アントニーとクレオパトラ』 「判断力が未熟だった若い日々」 「green」 は「未熟」を意味、さらにサラダの新鮮な野菜が、「若さ」を連想させる比喩になっているということです。直接訳すと、「判断力が青かった、サラダの日々」 salad days=若く未熟な日々
「サラダ」 カマラ・ハリス候補 「ワードサラダ」(word salad) カマラ・ハリス
元々は「言葉のサラダ(word salad)」 「文法的には正しいが、単語の使い方がでたらめなために意味不明の文章」 「言語明晰意味不明」 ハリス副大統領 「時間に関する期限を設けることを含め、我々が自らに課す指標を適用すべきだと考えています」 ♥♥♥
毎年、小学6年生と中学3年を対象に「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト) 「意味があるのか分からない問題を解かせられながら、平均正答率で並べ比べられる」 文部科学省 「全国学力テスト」 文科省 「全国学力テスト」
秋田県 「全国学力テスト」 秋田県 秋田県 国際教養大学の初代学長 中嶋嶺雄(なかじまみねお)先生 コチラ )が明らかにしておられました。
結論だけを先に述べると、養育期の子供をもつ親は、次の四項目 を実践することだと言います。①必ず家族揃って朝食・夕食をとる ②塾に頼らず家庭で勉強させる ③テレビばかり見させない ④地域の行事に必ず親子で参加する
こんな簡単なことで、いい家庭環境が築けるのか?学習成績が向上するのか?そんな疑問を抱く人もいるでしょうが、ここに挙げた項目は、秋田県 中島先生 「家庭のあり方」 「好結果を生んだ要因の一つとして、家庭がしっかりしていることが挙げられた。朝食、夕食を両親や家族とともに規則正しくとる。それは学童・生徒の精神や情緒の安定につながっている」 「秋田の子どもたちは塾に通う率がきわめて低い。しかしその分、家庭で予習・復習する。テレビを見る時間も少ない。さらに、子どもたちが地域社会で役割を演じていて、田舎に行けば行くほど鎮守の祭りにも多く加わっている」
何のことはありません。日本社会で昭和30年代頃まで行われていて、だんだんと廃れていった家庭生活こそが、子供たちの教育にとって一番良いということなのです。今の時代、子供をどんなふうに教育したらいいかと、迷っている親御さんも少なくないことでしょう。あまりにも価値観が多様化して、「何でもあり」の世の中になってしまったからです。しかし、この問題をあまり難しく考える必要はなさそうです。試しに、前記の四項目を一ヵ月でもきっちりと守ってみてはどうでしょう。バラバラになった家族の絆がよみがえるに違いありません。家族の絆がよみがえることが、すべての始まりのようだ、というのが中島先生
「元来、子供の性質は、わが父母は善き人と思い、わが家を楽しきところと思う心あるゆえ、この子供心を利用すべし」(福沢諭吉) ♥♥♥
フジテレビ 中居正広 『週刊文春』 「被害者のX子さんはフジ編成幹部A氏に誘われた」 「X子さんは中居氏に誘われた」 橋本徹
「センター試験」 「共通テスト」 「リーディング」 「昨年並み」 「これは絶対に解けません。問題量が多すぎるし、受験生は最後まで行きませんし、引っかかる問題が多数盛り込まれています」 「私の予想通り、去年よりも問題量が激減しており、時間不足という大きな問題はクリアされ、昨年よりも簡単になった。しかし第6問は絶対に解けない。難しすぎる」 島根大学会場 「生徒は簡単だった、と言っていた」
◆各予備校の平均点予想の推移 【リーディング】
【リスニング】 共通テスト英語の平均点 「大学入試センターから発表される中間平均点速報の第一弾 よりも1、2点低いのが最終平均点となる。共通テスト終了直後に最も速く公表される、北九州予備校の山口・九州地区の平均点 に+1点したものが、最終平均点になる。」 毎年私は追検証していますが、 大学入試センター 「経験」 ♥♥♥ 【リーディング】 中間① 59.65点(中間② 57.87点) →北九州予備校 55.2点→ 最終平均点 57.69点 【リスニング】 中間① 62.91点(中間② 61.44点)→北九州予備校 59.5点→ 最終平均点 61.31点 ◎経験は最良の教師である。ただし授業料は高い。 (トーマス・カーライル) ◎賢者は歴史に学ぶ (ビスマルク)
明日が支払い期限の市民税を払おうとして、ATMでごうぎんのキャッシュカード 「暗証番号」 「え~と??」 『暗証番号が間違っています』 「あ、思い出した。あれだ!」 「お取り扱いできません」 「おかしいな~正しい番号なのに…」 ごうぎん古志原支店
「暗証番号」 の4桁数字を、全部忘れてしまうという方は少ないでしょうが、間違える場合ってたいていは、使った数字は覚えているが、並びの記憶が曖昧で本当は1234なのに、4321とか、1243とか、そんな感じで間違えてしまう方が多いのではないでしょうか?私もそんな感じで入力をミスったんです。たった4桁とはいえ、その数字の組合せの種類は膨大ですからね。
3回目の「暗証番号」 「暗証番号」 「暗証番号」 「セキュリティロック」 「セキュリティロック」 キャッシュカード キャッシュカード 「セキュリティロック」 「このカードは使用できません」「銀行にお問い合わせください」 キャッシュカード キャッシュカード 「暗証番号」
ちなみに、「暗証番号」 「暗証番号」
翌日、ごうぎんの本店に出かけて、現金を引き出し、キャッシュカード ♥♥♥
「黒い呪術師」 アブドーラ・ザ・ブッチャー フォーク 五寸釘 地獄突 き エルボードロップ ジャイアント馬場 空手の「決めポーズ」 朝日2 「ワールドプロレスリング 俺の激闘」 ブッチャー 蝶野正洋 ブッチャー ブッチャー 「ぼうや、どうしたの?」 「この新聞が売れないと家に帰れない」 ブッチャー 「 人と違うこと」 ブッチャー 「人と違うことをやる」 「自分もプロレスで稼げるのではないか」 「 人とは違う」 フォーク 五寸釘 ギミック
私は生徒たちにも、「人とは違うことをやれ!」 島根県・出雲市 「日本一の都市」 岩國哲人(いわくにてつんど)出雲市長 ① 人より早く ② 人より多く ③ 人と違ったやり方で 松江北高 岩國 教科 校務分掌 松下幸之助 江口克彦(えぐちかつひこ) 「プラスアルファの仕事」 「自分の仕事」
「プラスアルファの仕事」をすれば、「与えられた仕事」が「自分の仕事」になります。 「与えられた仕事」は、必ずつまらなくなるものですが、「自分の仕事」となれば、これ ほど楽しいことはありません。 与えられた仕事に、自分の工夫を加える。 プラスアルファで、自分なりの仕事の仕方を考え、上司に言われた以上の成果を出して いく。これは、将来あなたが「社内の階段」を上がっていくときに、そして何より「人生 の階段」を上がっていくときに気づくと思いますが、極めて重要なことです。 なぜなら、あなたがその上司から教えられた通りのやり方、指示された通りのやり方で、 指示された通りの成果を出し続けていくとされば、いつまでたってもその上司を追い抜く ことはできません。いつまでたっても、その上司のレベル以下です。
板坂元(いたさかげん) E. ヘミングウェイ 『日はまた昇る』 「それを実験しましょう」 ヘミングウェイ ヘミングウェイ 「変わった人になる努力」 ♥♥♥
竹内 均先生(たけうちひとし、東京大学名誉教授) 「時間の断片」 15分 。だから、15分で400字詰原稿用紙に三枚くらいの原稿を書かれるのでした。つまり、「400字詰原稿用紙三枚・15分」 仕事の単位 だったのでした。 15分という時間(ユニット)は「端数」みたいなもので、一日の中で結構ころがっているものです。これが一時間、二時間という単位で、毎日時間を空けようとすると大変なことになりますが、15分であればそれほどの努力は要りません。非常に取り扱いやすい時間なのです。どんな忙しい人でも「15分」という時間なら取れるものです。何かの都合で15分の時間が空いた時、「これは神様の配慮で15分が使えるのだ」
竹内先生 『物理の傾向と対策』(旺文社) 秘書 「あいつは何も勉強しないで、アルバイトばかりしている」 「竹内君は人が家に帰ってゴロ寝をしている時に受験参考書を書いた。それを書いていても、彼のやった研究は優れているではないか。だから、受験参考書を書いていることは問題にならない」
「やりたいことがあるんだけど、それに取り組むまとまった時間がなかなかとれなくて……」 「まとまった時間」 「まとまった時間」 「時間をまとめる」 「やりたいけど時間がなくて……」 「やりたくなくて……」 「時間がない」
イギリスの作家・アーノルド・ベネット 『自分の時間』(渡部昇一訳、三笠書房) トランク ベネット 「トランクの真ん中から荷物を詰める」 トランクの四隅
100冊の本を書くとしましょう。まず1ページ目から書き始めて、2ページ、3ページ…と書き進め、300ページまで書いて一冊目は終わり。次に二冊目の1ページから……。こういう「書き方」を竹内先生 「本を書くときは1ページ目から順々にやらなければならない」 「一つの流れ」
故・竹内 均(たけうち ひとし) 先生から教えてもらった貴重なことの一つが、この「15分活用法」 「スキマ時間」 竹内先生 東京大学 『ニュートン』 代々木ゼミナール 札幌校、仙台校、大阪校 メガネの三城 皆に平等に与えられているはずの24時間を上手に使うしかなかった のでしょう。竹内先生 私は「スキマ時間」 「 先生、忙しいのに、よくこれだけ毎日のようにブログの更新ができますね」 「先へ、先へ、前へ、前へ」 松江北高 「チリも積もれば山となる」 ですね。 チョットしたことでも、長年続けていれば大きな成果が得られるものです。
竹内先生 『勉強術・仕事術 私の方法』(知的生き方文庫) 「頭をよくする特効薬」「忙しい人の時間の有効な使い方」「頭を鍛える本の読み方」「頭の疲れをとる3つの方法」 竹内先生
よく「時間が無い…」「忙しくてできない…」「時間が足りない…」「まとまった時間が取れない」 竹内先生 「 ミスター講道館」 嘉納治五郎(かのうじごろう)先生 「 時間は工夫して作るもの」 ♥♥♥
よく時間がない、時間が足りぬとかこつける人があるが、時間というものは、たとえば泉の水のように、いくらでも出て来るものである。たとえばここに一升枡があるとして、その中に粟を一升入れたら、もう何も入らないかといえば、決してそうでなく、その粟の間に豆粒を入れれば、まだ大分入るわけだ。もうそれで入らないかといえば、その間に粟粒を入れたらまだ相当入る。それに水を入れたらまだまだ入るだろう。そのように時間の活用には、上には上があるもので、それをもっとも有効に利用したものに、もっとも立派な仕事ができるものだ。
昨年大きな盛り上がりを見せた米国の大統領選挙は予想に反してトランプ候補 「大接戦」「予測不能」「トランプ若干リード」「ハリスが逆転か?」 「おい、違うだろ!!」 “You’re fired. Get out of here.” “low IQ candidate” トランプ候補 ハリス候補 「Word Salad」(言葉のサラダ) トランプ大統領 「スピード感」 「有言実行力」 「言ったこと全てを実現するのは民主主義政党がやることではない」 トランプ氏 トランプ氏 「勝利のための3つのルール」
①攻撃あるのみ ②非を認めるな ③劣勢でも勝利を主張して負けを認めるな
ということです(1月18日付「日本経済新聞」朝刊)。これまでのトランプ氏 プーチン大統領 トランプ氏 プーチン氏
******************
ただ昨年のキャンペーンで一つだけ私が感心したことは、トランプ
トランプ大統領候補 マクドナルド 「アルバイト」 カマラ・ ハリス候補 「マクドナルドでアルバイトをしていた」 ハリス候補 ハリス候補 トランプ候補 「フェイク」 「アルバイト」 「庶民派」 「私は今、カマラよりも15分長く働いた。彼女はここで働いたことがない」 ハリス候補 “マックバイト発言” VIDEO トランプ候補 トランプ候補 「TRUMP」 Make America Great Again! トランプ候補 「ゴミの島」 バイデン大統領 トランプ候補 「ゴミ」 「私のごみ収集車はどうだ?このトラックはハリス氏とバイデン氏に敬意を込めたものだ」 トランプ候補 「非常に有能な人たち」 「最も人気があった時期のケーリー・グラントに似ていた」 バイデン大統領 ♥♥♥
「亀の井バス」 大分県別府市 「亀の井旅館」 「亀の井自動車」 別府市 由布市 福岡 「地獄めぐり」 最も長い歴史を持つ定期観光バス で、加えて日本で初めて女性バスガイドを採用した事業者 でもあるのが特徴です。
これらの設立へと舵を切ったのが、「九州観光の祖」「別府観光の父」 油屋熊八(あぶらやくまはち) JR 別府駅 熊八 「旅人をねんごろにせよ」 油屋熊八 「地獄めぐり遊覧バス」 少女車掌 バスガイド バスガイド 「気候の温暖なること実に熱海以上なり 風光は瀬戸内海を前に控え 後に由布鶴見の火山あり」(油屋熊八 1916年)
▲バスツアーの出発地JR別府駅前の油屋熊八像
「亀の井定期観光バス」 地獄 「七五調」 JR別府駅
▲いかにも地獄めぐり風の観光バス
カラーは青である事から「青鬼」 「鬼のパンツ」 角(つの) も付いています。それにしても、ここまで凝ると、まさに「地獄=鬼 」という印象が色濃く出ていますね。
そして、この車の登録ナンバーは、「大分230あ19-28 」と言うことで、亀の井バス 1928年 )を表していて、「イクスパ (温泉)」の語呂合わせにもなっています〔笑〕。手が込んでいる!
さて、JR 別府駅東口 「地獄めぐり」 カーテン ヘッドレスト
▲コロナ解禁で満席の観光バス
創業時より運行されている人気の定期観光バスですので、それほどこの「地獄めぐり」 「海地獄」 ♥♥♥
島根県立松江南高等学校( 31期) 齋藤さや子(旧姓・堀江) 「かわつレディースクリニック」 「内覧会」 7人 が医者として活躍しています。今から8年前には、その一人、山本真人 松江市立病院 「やまもと整形外科クリニック」 齋藤 「先生の命はぼくたちが守ります」 山本先生 「日赤」
▲山本真人くんと
「かわつレディースクリニック」 「ウェルネス川津北店」 コチラ です。齋藤 「まつえ城下町レディースクリニック」 山本 齋藤院長
▲「かわつレディースクリニック」正面から
帰り際に齋藤院長 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はうどん 松江駅 「シャミネ松江」 「松江うどん屋だいぜん」 「牛たん東山」 米子駅シャミネ 「牛たん東山」 「だいぜん」 九州 讃岐 「牛ごぼううどん」 「肉うどん」 7時 からやっているのが嬉しいですね。駅に早く着いた旅行客には、体が温まるのできっと喜ばれるお店になるかもしれません。夜の10時までぶっ通し営業しているのも便利です。私も米子 シャミネ 今日はお薦めの「肉丸太牛蒡天うどん」(869円) 牛蒡天 牛肉 温玉 ♥♥♥
(株)PHP研究所 JR九州相談役 唐池恒二(からいけこうじ) 『ななつ星への道 Stairway to Seven Stars』(税込1,760円) 唐池 「ななつ星 in 九州」 「コンデナスト・トラベラー」 「ななつ星」 唐池恒二
2009年、JR九州 唐池 九州新幹線 「ななつ星」 豪華列車「ヘラン」 「九州レールクルーズ創造委員会」 「ななつ星」 唐池 「ななつ星」 唐池 「ななつ星」
① 思い切り心ときめく車両 ② 「ほおぉうっ」と唸る物語 ③ 誰も体験したことがない「おもてなし」 ④ わがままで傲慢な、販売戦略とブランディング ⑤ 「変幻自在」の広報宣伝 中でも②の「『ほおぉうっ』と唸る物語」 「ななつ星」 水戸岡鋭治(みとおかえいじ) 酒井田柿右衛門(さかいだかきえもん) 大川組子 「ななつ星」 「ななつ星」
「ななつ星」 水戸岡先生 「ブルネル賞」 水戸岡先生 唐池 「ななつ星」 水戸岡先生 「ななつ星」 「ななつ星」 JR九州 「皆さん、九州に世界一立派な豪華寝台列車を走らせませんか」 「こんなときに何を話しているのか」 九州新幹線 。「九州新幹線全線開業はJR九州発足以来の悲願。ようやく夢がかないます。しかし、それは夢がなくなるということでもあります。新幹線の次の夢を一緒に見ませんか」
▲私は唐池さんのファンです
この構想は唐池 「九州で寝台列車を走らせたらヒットする」 「D&S(デザイン&ストーリー)列車」 「今だ!」
「経営者の役割の一つは、従業員に夢を与えること」 唐池 「世界一の豪華寝台列車を走らせたい」 「そんなものは夢物語だ!」 とか、 「採算が取れません。社長の道楽には付き合えません」 古宮洋二 JR九州 「事業として厳しいのでは」 唐池 「必ず成功させます」 古宮洋二部長(現・JR九州社長) 古宮部長 「韓国の寝台列車『ヘラン』に乗ろう」
ただ、現在も続く大人気ぶりを見れば、「ななつ星」 「コンデナスト・トラベラー」
この本で特に印象深かったのが、唐池 「神社参道論」 「神社の参道は長いほどありがたみが増し、参拝時の感動が大きくなる」 世阿弥 「序・破・急」 「ななつ星」 「最上級のお客さまが最も長い距離を歩くけれど、主役は最後に優雅に登場するものだ」 JR九州 「よろず相談承ります」 唐池 唐池 「良きリーダーになるための十箇条」 ♥♥♥
第一条 逃げない 第二条 逆境をバネにする 第三条 夢をみる 第四条 本質に気づく 第五条 まず行動する 第六条 勉強する 第七条 伝える 第八条 思いやる 第九条 決断する 第十条 真摯さ
癌(ガン) cancer cancer 「癌」 「大 きなカニ、かに座」 Krebs カニ 「癌とカニ」
これはラテン語 癌 カニ ヒポクラテス 「医学の祖」、「医学の父」 「ヒポクラテスの誓」 『ヒポクラテス全集』
彼はこの本で、乳がんの研究結果を書いているのですが、その中で乳がんのがん細胞のジワジワとした広がり方が、たくさんの足を持つカニ ヒポクラテス 「カニのような(カルキノス)」 カニ カニ 「カニ」 ヒポクラテス 「癌とカニ」
これが、ラテン語で広くヨーロッパに伝わったため、英語でもドイツ語でもがん カニ がん カニ(cancer) がん(cancer) カニ crab の方が一般的です。
私が「理想の単語集」と評価する竹岡広信先生 『LEAP』(数研出版) cancer の項目に「「ガンを取り巻く血管が、カニの足に似ている」ことに由来」 コチラ です)。みなさん、書店で手に取ってみてください。♥♥♥
二年前の冬のことです。松江北高補習科 松江駅 「ドトール」 松江駅 米子 ベンチコート 家のカギ 家のカギ ミサワホーム 「最悪、家の玄関のカギを壊して入るしかありません」 米子 タクシー会社 松江駅の喫茶店、松江駅、松江北高事務室・研究室 (株)ロックサービス松江 八幡家 ミサワホーム 「玄関のカギを壊して新しいものに付け替えたら数十万円かかるところでした。これからは気をつけてください」 「一体どうなるんだろうか?」
さて二年経った今日のことです。自転車に乗って買い物に向かっていると、ベンチコート 「カギ騒動」
ポカ パケット・マジック ポール・ゴードン(Paul Gordon) 「THE EVOLUTION」 「イモムシ⇒蝶々」 勝田ケ丘志学館 パケット・ケース ポール・ゴードン 「これは困ったぞ!!」 。あっ、 もしかしたら電車の中で、他の書類を引っ張り出す際にポロッとこぼれ落ちたのかもしれないぞと思い、ダメ元で「JR西日本落とし物センター」 JR 出雲市駅 出雲警察署(会計課) パケット・トリック 出雲警察署 これにはまだ続きがあるんです。 年末にこのカードケースを買い物袋にいれて、古志原 テルミ 「またかよ!!」 「かつや」「松江市立図書館」「スーパーまるごう」 「NO!」 ポカ 今日も、通勤途中に手袋 ポカ バーバリーのマフラー ギミック・コイン 、今大騒ぎになっている東京のフジテレビ SDカード ♥♥♥
選⼿として29年、解説者として3年、そして監督として7年の野球人生。ソフトバンク 工藤公康(くどうきみやす) 最優秀選手(MVP) 最優秀防御率 最高勝率 広島球場 工藤投手 「優勝請負人」 工藤 孫正義 孫 「10連覇できる強いチームを作ってほしい」 読売巨人軍 工藤 「ならば自分が責任をとる以外の方法はない」 工藤
現役時代は「前後裁断」 道元禅師 沢庵禅師 「過去も未来も裁ち切り、今に集中すること」 「前後際断」 工藤
工藤 広岡達朗監督 広岡監督 工藤 広岡監督 「成長の跡がない、お前も修行してこい」 「ミールマネー(1日の食事代)」 「これからどうするの?」 「またトライアウトを受けて大リーグを目指す」 「野球への情熱」 「もっと自分の可能性を信じるんだ」
工藤 広岡達朗監督 「やれ!」 「はい!」 広岡監督 「どんなに練習しても壊れない強い体」 広岡 広岡 広岡 「冷酷な絶対権力者」 工藤 広岡 野村 「データ野球」 広岡 「野球必勝法70か条・野球必敗法70か条」 「どうしたら試合に勝てるのか?」 「必勝法・必敗法」 川上哲治 牧野茂
工藤 甲斐拓也捕手 甲斐捕手 工藤監督 「扇の要に育てよう」
「努力と根性」 「ここまでやらなければいけないのか?」 「自分に負けたくない」 「努力と根性」 「一生懸命ではまだ足りない」「必死にやれ」 「私も監督をやっている7年間、練習は厳しかったです。なぜそこまで練習するのか。選手の未来を創るためです 」
監督は、選手やコーチとフロントの間に立って、チームが機能するよう、常に準備する人間です。上層部の要望を聞きながら、リーダーとして現場を束ねる立場は大変ですが、それで結果を出す喜びは何物にも代えがたい。それがプロ野球チームの監督という中間管理職を経験した工藤 徳光和夫 「プロ野球レジェン堂」 ♥♥♥
このブログのトップに挙げた言葉「力を尽くして狭き門より入(い)れ 」 新約聖書ルカ伝 アンドレ・ジイド 『狭き門』 「災難は楽をして生きようとする輩を好む 」(文覚) 新約聖書の マタイ伝 「狭き門を通って入りなさい。滅びに至る道は広くて大きく、それを通って入っていく人は、多いからです。一方、命に至る道は狭く、その道は狭められており、それを見出す人は少ないのです」 詩人のロバート・フロスト 「森に二すじの道があった。そこで私は、みんながあまり足を踏み入れない道を選んだ。その決定が、私の人生の全てを変えたのである。」
ある新入社員に人事部の人間が尋ねました。「どこに配属されたいか」――「できるだけむずかしい部署にしてください」――「ほう、どうしてか」――「あとが楽ですから」 阪急グループ 小林一三(こばやしいちぞう)
生徒たちによく下の話をしました。 私は、若い頃に、渡部昇一先生 「力を尽くして狭き門より入れ」 鉄砲打ちの名人に、ある人が「地面にいる鳥と、高い枝に止まっている鳥、どちらのほうが撃つのが難しいですか?」と尋ねました。すると、名人は、こう答えたと言います。「地面にいる鳥も、高い枝に止まっている鳥も、どちらとも撃つには同じくらいの集中力と技術がいる」 素人考えで見ると、地面にいる鳥の方が楽に撃てそうですが、実際に要する集中力と技術は同じだと言うのです。つまり、一見難しそうな目標であっても、そこへ到達するのに必要な努力は、一見容易そうな目標とさして変わらないということです。逆に言うならば、一見たやすそうに見える目標も、難しそうな目標を達するくらいの努力が必要だということです。要するに、目標が高かろうが、低かろうが、必要な努力は同じだということなのです。ならば、高い目標を掲げたほうが得策ですね。
教員人生最後の卒業式で、教室に帰って生徒・保護者のみなさんに贈った私からの最後のはなむけの言葉は、「老婆は一日にしてならず (笑) 。親に感謝の気持ちを忘れないこと。被災地の復興の手助け・日本の発展に寄与できる、困っている人の手助けができる有為な人となるために、大学では死にもの狂いで学ぶこと。「力を尽くして狭き門より入れ 」 楽な道と苦しい道と二つの道があったら、自ら進んで苦しい道を選択すると、後で楽しいことが待っているぞ。」
「サービスが先、利益は後」 ヤマト運輸 小倉昌男(おぐらまさお) 「ありがとう」 「松本ミカン事件」 ヤマト運輸 小倉昌男社長 ヤマト運輸
クロネコヤマト 「お客様への感謝」「ドライバーさんへの感謝」 今でこそヤマト運輸 日本通運 佐川急使 ヤマト運輸 ヤマト運輸 大和運輸 ヤマト運輸 大和便 「クロネコヤマトの宅急便」 ヤマト運輸
戦後、貨物の長距離輸送が鉄道からトラックにシフトしていった時、ヤマト運輸 ヤマト運輸 ヤマト運輸 小倉昌男 小倉 小倉
一つは、「日本経済新聞」 吉野家 吉野家 「そうだ、これだ!」 小倉 吉野家 ヤマト 小倉 吉野家
もう一つ、小倉 UPS(ユナイテッド・パーセル・サービス) UPS UPS 「日本でも、これから個人宅配ビジネスの成長が期待できるのではないか」 ヤマト運輸 ヤマト運輸 日本通運 佐川急便 「宅配便」 「これからは、箸でひとつずつ豆を移すんだね。それが宅急便だよ」 11個 でした。それが初年度には170万5195個もの荷物を配送、現在の総個数が48億個を超えるまでに拡大しています。(2022年3月発表)その中でクロネコヤマト ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週はラーメン 松江市・西津田町 「谷屋ん」 八幡 「花さか」 今井書店学園通り店 「花さか」 「醤油ラーメン」 「あのー、頼んでないんですけど」―「大将からのサービスです」 「先生も大変だのー。頑張ってーや」 島根大学 「昭和軒」 「天真爛漫」 松江 「花さか」 「谷屋ん」 「花さか」 ユニクロ マクドナルド 「開運稲荷入口」 路地裏に佇む「隠れ家」のようなラーメン屋で、 テーブル17席、カウンター4席の小さなお店です。
開店当時は、ラーメンの前に野菜サラダ 鶏がらと豚骨・野菜をじっくり煮込んだコクのあるだしと、のどごしのいい中太玉子麺を使っているのが特長で、一度食べたらクセになる味わいです。 私はいつも醤油ラーメン 「花さか」 「花さか」 チャーシュー麺 「花さか」 醤油ラーメン 「谷屋ん 塩ラーメン 「をっちゃんラーメン」 「ラーメン長さん」 中華そば 「中村製麺所」 松江市
「来来亭(らいらいてい) 松江店」 が、何とその「谷屋ん」 「ラーメン戦争」 、ご主人と話すと、あちらは鶏ガラ系でうちとはまったく異なるラーメンなので心配はしていない、味には自信がある、とプライドをのぞかせておられました。ただ夜営業になると、大きな看板と建物で、うちのお店がみんな隠れてしまうのがちょっと困った点、とおっしゃっておられました。私の住んでいる近くの学園通りも、数多くのラーメン屋さんがしのぎを削っておられますが、大規模チェーン店と老舗の味を受け継ぐ名店、共存共栄となるのか、それともどちらかが倒れてしまうのか、注目すべき「ラーメン戦争」 どうなることかと心配しましたが、そこはやはり味で勝負です。おいしさは比べものになりませんから。店長さんに聞いてみました。「来々亭の影響はどうですか?」―「あっちがいい人はあっちに行きますし、こっちがいい人はこっちに来てくれますから」 あれから10年。どちらのお店も繁盛しておられます。 今年最初にお邪魔した「谷屋ん」 秋鹿 大東 。「来来亭」 「ないことはない」 ネギ増し 「醬油ラーメン」(880円+150円) 「悟空」「香味徳」「唐崎商店」 ♥♥♥
生きていく上で、自分が絶えず大切にしている方針。それを「ポリシー」 「ポリシー」 「まあいいか…」 石破総理 「ポリシー」
私は今から22年前 の2002年7月22日に、島根県立 津和野高等学校 3年1組 「あむーる」 に 「ポリシーを持って生きていますか?」 ポリシー
確固たるポリシーを持った人が好きだ。私の応援する芸能人から紹介する。
◆小田和正 。『いつかどこかで』という映画を作った彼は評論家から強烈なバッシングを受けた。それこそボロくそに叩かれた。にもかかわらず、また映画を作った。『緑の街』だ。今度は映画館での上映ではなく、全国264ヵ所にも及ぶ公民館や小ホールでの自主上映だった。「自分を本当に応援してくれる人だけ見てくれればいい」小田 さんの反骨精神を見る思いで、拍手を送りながら県民会館へ出かけたものだ。この映画、彼の自伝でもある。 ◆絶対にテレビに出ない。コンサートもやらない。ZARD というグループだ。坂井泉水 さんの書く詩が好きでファンクラブに入って応援している。『The Single Collection~軌跡』というベストアルバムが出た時、中に豪華客船で初めてのライブにご招待の応募ハガキが入っていた。ついにライブをやらないZARD のベールが脱がされることになったのだ。でもよくぞここまで我が道を行ったものだと思う。 ◆28歳で30億円(!)の借金を抱え込んださだまさし 。それも祖父の思い出のある中国の映画を撮るために(『長江』)。年に一度原爆の落ちた日に長崎の稲佐山で無料平和コンサートを続けている(「夏長崎から」)。大赤字を出しながら故郷の皆さんにご恩返しだという。長崎にできた巨大世界地図の壁に赤いレーザー光線で紛争地帯を点滅させるという 「ピーススフィア」の運動も彼の発案によるものだ。一人千円しか寄付をしてはいけない(!)という変わった募金活動によるモニュメントの完成だ。 ◆アンコールをやらないCHAGE&ASKA 。「出たり入ったりする時間があれば1曲でも多くみなさんに聞いてもらいたい」この言葉には感動したものだ。 ◆靴をはかずに靴下でNHKホールのステージに出てきたジョージ・ウインストン 。「自分のピアノの音だけを聞いてもらいたい」ペダルのそばにはボロ布が置いてあり、彼の足はそこに置かれていた。「あこがれ・愛」の演奏が始まった時にはあまりの美しさに言葉も出なかった。服装はジーパンにTシャツというおよそらしからぬものだった。これも彼のポリシーだ。 ◆大学生の頃からヤマハの援助で音大に通いCDを出していた西村由紀江 さん。全く売れない時代にも負けずに頑張り通した。「101回目のプロポーズ」の音楽を担当することになった、とハガキをもらった時には飛び上がった。渋谷のベルコモンズで開かれた内輪だけのパーティに招かれた時に、サインを頼まれた生徒の話をすると出たばかりの楽譜集に「私も頑張ったらいいことがあった。生徒さんにも頑張るように言って」とサインしてくれた彼女。「湖にピアノを浮かべて聞いてもらうのが夢」と語った彼女も今ではインストの女王と呼ばれるようにまで成長した。何度もくじけそうになった時に負けなかったことが今日の彼女を作った。 ◆元ちとせ 。あの独特のコブシで100年に一度の「神の声」と言われる。歌手になろうというきっかけが「週刊朝日」7月26日号のインタビューで明らかになった。先日広島へ行って彼女のデビュー前のCD2枚を探し当ててきた。自分の声を絶対に曲げない姿勢はこの頃からのものだ。今日もViewsicでオリコン一位のアルバム『ハイヌミカゼ』の曲の解説をするインタビューを1時間見てますますその音楽に対する姿勢に打たれた。スペースシャワーで23日にもインタビューが予定されている。8月9日には何とあのNHKが彼女の特別番組を夜11時から流すことが決定した。益々の活躍が期待できる今旬の歌い手だ。 ▼皆さんはポリシーを持って生活していますか?ただ何も考えずに流行に流されて いませんか?10代の貴重な時期を大きな夢を持って胸をはって堂々と生きています か?後で振り返って後悔の残る生き方だけはして欲しくないものです。 私は今でもこれと同じことを若い人たちに訴え続けています。私がシンガーソングライターの小田和正 小田和正 ♥♥♥
何事もそうですが、最後まであきらめずに粘ることが大切です。受験も全く同様です。あきらめずに最後の最後まで頑張っていると不思議なことにいいことがあるんです。3年担任や進路部長を務めていた時には、生徒たちにはいつもこのことを強調していました。生徒たちも、先輩たちが最後まで頑張っている姿を見ているだけに、そして逆転合格を果たした生徒をたくさん知っているだけに、推薦で不合格になったとしても、前期で落ちようが、後期の最後まで最善を尽くし、逆転合格を果たした生徒が数多くいました。私が松江北高
私が一番印象に残っている生徒は、看護系志望で、推薦で鳥取大学 医学部保健学科看護 鳥取大 前期 島根県立看護短大 新見公立短大・看護 石見高看 岡山県立大学 浪人 石見高看 「信じられない!」
2017年7月29日(土)付けの『山陰中央新報』 「若者よ」シリーズ 松江北高 はせがわいずみ 「海外に出て独立心を培え」
はせがわ 松江北高校 「ハリウッド・ニュース・ワイア」 「24―Twenty Four」 『 メイキング・オブ・24―Twenty Four―』(竹書房、2007年 ) 松江北高 「夢は叶う!」 松江北高『図書館報』第100号 。 「夢は叶う、あきらめないで!」 はせがわ ♥♥♥
▲松江北高卒業生のはせがわいずみさん
高校、大学などの入学試験を控える受験生にエールを送る「天神様の合格応援きっぷ」 JR松江駅 JR西日本 菅原道真 菅原天満宮 天満宮 島根県立松江南高等学校 狩野道彦先生
▲松江駅の案内掲示
他の駅は安来駅 宍道駅 出雲市駅 「天神様の合格応援きっぷ」 宍道駅、来待駅 菅原天満宮 松江駅、宍道駅、出雲市駅 乃木駅 安来駅 「天神様の合格応援きっぷ」 「宍道(しんじ)→来待(きまち)」 「宍道」 「来待」
勝田ケ丘志学館 「共通テスト」 ♥♥♥
◎「共通テスト」を検証する 「共通テスト」 【 リーディング】 【 リスニング】 【 リーディング】 「 試作問題」 「 モニター調査」 第1問~第8問 『重要問題演習 2025共通テスト 英語リーディング』(ベネッセ) 『直前演習 2025 共通テスト 英語(リーディング)』(ベネッセ) 「ギャンブラーの誤謬」 コチラ をお読み下さい)が重要だということが分かりました。【リーディング】 書かずに論理的な文章を書かせる【第4問】(文章の論理の構成や展開に配慮して文章を修正する)、話さずにプレゼンを組み立てる【第6問】(自分の立場に立って、自分の意見の理由や根拠を明確に示すために複数の資料を活用して文章のアウトラインを組み立てる)が「試作問題」で公開されており、来年の「新課程共通テスト」の目玉問題となります。今行われている各社の模擬試験問題もこれらを含めた【第1問】~【第8問】の8問構成となっています。 (2024年11月12日付け) ▼予想通り「試作問題形式」を含む第1問~第8問構成となりました(解答マーク数49→44に減)。第4問と第8問 に配置されました。演習や模試で練習した通りでした。やはり大学入試センターからの発信・試作問題はきちんと読んでおかないといけません。 問題用紙が配られたら、まずザーッと第1問から第8問(?)までに目を通しましょう。大きな変更点がないかどうかを確認します。今年は新課程入試で大きく内容が変わることが予想されています。もし変更があったとしたら、それを頭に入れた上で解き始めます。ああ、ここが新しくなっているんだなと頭に入れて問題を解くのと、やみくもに最初から解き始めて途中でビックリするのとでは、心理面でも大きな影響があります。ここで覚えておいて欲しいことは、新傾向問題が登場した1年目は、問題の難易度は決して高くありませんから、落ち着いて解けば必ず解けるはずということです。 (2025年1月16日付け) ▼配置順の変更はありましたが、新傾向問題の第4問と第8問は試作問題通りの出題で、難易度は難しくありませんでした。新傾向問題が出題される一年目は難易度は《易》であることは過去の出題からも明らかでした。 私がじっくりと読み込むことをオススメしている大学入試センターから公表されている「共通テストリーディング」に関する「問題評価・分析委員会報告書」でも、この分量の多さについての言及・苦情がありました。現場からのこれだけ強い要望と、このようなやり取りを頭に入れると、新課程の「共通テスト」リーディングでは、伸び続けた語数の増加はいったん歯止めがかかるのではないか 、と私は踏んでいます。 (2025年1月15日付け) リーディング問題文の長さに関しては、今年は歯止めがかかるのではと予想しています。(2025年1月16日付け) ▼私の予想通り、昨年度より約700語程度短くなりました。やはり「問題評価・分析委員会報告書」 は読んでおかないといけないと強く感じました。今まで主張してきた通りです。 私が「NOT問題」と呼ぶものです。「notなものを選ぶ」「errorを指摘する」「remove(取り除く)ものを選ぶ」これらは全て「NOT問題」です。いずれも今年の「共通テスト」で出題されて受験生を悩ませた問題です。正しいものを一つ選ぶ従来の設問に比べ、正しいものを一つずつ3つ外していかねばなりませんから、余計に時間がかかります。《難問》と言えましょう。これに深入りして最後に時間不足が起こらないように注意が必要です。間違いなく来年も出題されます。 (2024年11月12日付け) ▼ remove~ の形で1問出題されました(第7問問1)。物語を改善するために盛り込んだ方がよいものを二つ選べという問題も、本文に書かれていないものを選ぶので「NOT問題」の変形と呼べるものです(第6問問4)。 私が「推測問題」と呼んでいるものがあります。今年の「共通テスト」では「most likely~」で設問が導かれていました。implyやinfer(暗示する)で導かれる問題もこれに相当します。本文に明確に書かれていないことを、書かれた内容から推測する問題です。解答が直接書かれていないことを推測して読み取るわけですから、当然難しくなります。 (2024年11月12日付け) ▼ most likely ~ 「事実」と「意見」の問題・・・この種の問題が消えるという議論がありますが、私は引き続き出題されると思っています。「意見」は形容詞・助動詞で表される特徴があることは一応頭に入れておきましょう。 (2025年1月16日付け) ▼「意見」(opinion )を選ぶ問題が一問出題されました(第2問問3)。「事実」と「意見」をきちんと区別できる力は今日のネット社会では重要です。 正答率を見ると、出来事の並べ替えを苦手にしている生徒が多いようですが(⇒解き方についてはコチラ を参照)、ここは選択肢まで「先読み」して簡単にメモしておくのが効率的です。どんな出来事が登場するのかを頭に入れてから本文を読み、それが出てきたところで番号を振っていくのです。注意することが2つあります。第7問は5つの選択肢から4つ選ぶようになっていますから、ここで5つ全部答えてしまい以降のマークの順番が狂わないように注意しましょう。もう一つは、出てきた順番 が必ずしも起こった順番 とは限らないことに注意しましょう。着眼点は、①時を表す表現、②時制(過去完了、助動詞)の二つです。 (2025年1月16日付け) ▼予想通り二問出題されましたが(第3問問2、第6問問1)、二問とも5つの選択肢から4つを選ぶ形式となりました。ダミーに注意です。 「問題作成部会」の見解を読むと、「温かみのある物語文」が予告されているように感じます。私はセンター試験時代の過去問から選りすぐりの心温まる英文を読ませて送り出しています。もし他種類の英文を出したら詐欺ですよ[笑]。 (2025年1月16日付け) ▼この部分だけ(第6問)予想がハズレました。詐欺です〔笑〕。回想シーンを含む難しい小説問題で、感動や面白みはありませんでした。最後のオチ(Melodyは誰?)が分からなければ何の話なのかが全然分からない、受験生にとっては唯一酷な問題でした。この問題は正答率が目茶苦茶低くなります。 【リスニング】 今 年は特にリスニングが難しくなると思っておいた方がよいでしょう。(2025年1月16日付け) ▼形式は昨年通りでしたが、昨年よりも少し難しくなりました。注目すべき点が三つありました。 ①昨年までは第1問~第3問までの配点が59点 でしたが、今年は58点 となりました(第1問25点→28点 第2問16点→12点)。やはりリスニングが苦手な受験生に点を取らせたい配慮です。
②第5問は試作問題C の形式を踏襲していました。やはり大学入試センターからの発信には注意しておかなければいけません。
③第6問Bのディスカッションは昨年は4人だったのが3人に 減り、受験生の負担が大きく軽減しました。
不 正行為 ・・・ネット全盛時代に新手の電子機器を使った不正行為が増えています。「共通テスト」ではどんな不正行為があるのですか?という質問を受けました。馳浩文科大臣の時から内容が公表されるようになりました。昨年の「大学入学共通テスト」でも、4人の不正行為を確認しています。大学入試センターによると、不正行為のあった4人のうち、2人はカンニングペーパーの使用でした。山口県内の会場で地理歴史・公民の試験時間に受験生1人が複数枚のメモを机上に置いているのが確認。広島県内の会場では受験生1人が数学2での時間に、数式が書いてある紙を机上に置いていたといいます。残る2人のうち、1人は東京都内の会場で、外国語の試験時間が終了して「解答やめ」の指示があったのに従いませんでした。過去に一番多い不正行為がこれです。試験監督の指示にきちんと従うことが大切です。もう1人は岐阜県内で理科2の試験時に不正行為とされる定規の使用が確認されたといいます。 (2025年1月16日付け) ▼今年も不正行為がありました。大学入試センターによると、不正行為のあった4人のうち1人はカンニングでした。北海道の会場で、数学②の試験時間中、監督者が、机に数学の公式が書き込まれているのを確認したといいます。別の1人は、高知県の会場で、英語リスニングの試験時間に、「解答はじめ」の指示の前にICプレーヤーを再生し、解答をしていたといいます。他の2人は、いずれも「解答やめ」の指示があったのに従いませんでした。1人は福井県の会場であった地理歴史・公民の試験で、もう1人は大阪府の会場であった情報の試験での行為でした。 前日に「握手をお願いします。」 個別試験 私大試験 ♥♥♥
「平和祈念像」 「日本被団協」 「平和祈念像」 長崎市民の平和への願いを象徴する像の高さ9.7メートル、台座の高さ3.9メートル、重さ30トン、青銅製の巨大な「平和祈念像」 北村西望(きたむらせいぼう、1884~1987年) “原爆の脅威” “平和” “原爆投下直後の長崎市の静けさ” “原爆犠牲者の冥福を祈る” 原爆が投下されてから80年。あの惨禍を二度と繰り返してはいけないと、雄大な姿のその像はこれからも被爆地・長崎で平和を祈り続けます。でもなぜこれほどまでに巨大な裸体の男性像になったのでしょうか?平和のイメージといえば母子像や鳩の姿です。この像はそれとあまりにもかけ離れた姿だったために多くの批判にさらされてきました。「あれが表象するものは、断じて平和ではない。むしろ戦争そのものでありファシズムである」 堀田善衛 「あまりに醜くてカメラマンもとても撮る気にならない」 黒澤明 見つかったのは、像の制作が構想され始めたころの写真などをまとめた「スクラップブック」 「雑記帳」 スクラップブック 雑記帳 平和祈念像 北村西望 「平和祈念像」 「平和祈念像」 北村
実は、「平和祈念像」 スクラップブック スクラップブック 雑記帳 「人間的なものから非人間的なものへそしてさらに超人間的なものへ 」
その中に残されていた「昭和25年11月25日」という記述の脇にある「平和祈念像」 北村
さらに、雑記帳 北村 「人間的なものから非人間的なものへ そしてさらに超人間的なものへ」 “超人間的” “エクストラヒューマン” 北村 「人類が希望し尚且人力を以て未だ成らず」 「人間を超えた存在」
さらに、北村 「極右、極左、保守、中庸派なるものが生ずる原因に就て深く考慮すべきだ」 北村 平和祈念像 ♥♥♥
◎週末はグルメ情報!!今週は豚丼屋 「元祖豚丼屋TONTON」 島根県松江市春日町 「元祖豚丼屋TONTON 松江店」 北海道帯広 豚丼 松江 帯広 豚丼
「元祖豚丼屋TONTON」 帯広
松江店 豚丼 「てっぺん盛り」 「豚ロース丼」(830円) 「並盛り」 豚丼 1割引 をしてくれました。ラッキー!!♥♥♥
JR九州 唐池恒二(からいけこうじ) 『逃げない。』(PHP出版、2020年) 博多・釜山 JR九州船舶事業部 唐池 大嶋良三 大嶋 宇野 高松 宇高連絡船 大嶋 「難局に直面したときには、逃げずに正面から立ち向かう。」 「逃げない!」 私の大好きな さだまさし 長江 さだ 「歌で返す」 「過払い金はなかったのかなあ。10-10-10に電話してみようか」 「その責任の重さに眠れない日もありましたが、一方で、あまり大したことだとは思っていなかったんですよね。カネのことですから。要するに、駄目だったらつぶれるだけですし。自分が不名誉なことになって、抹殺されたとしても、その程度のことだろうと。みんなの前で公開処刑されるわけでもないし、そういう意味じゃ、破れかぶれのところがありましたね。僕個人が借りたカネですから、他の選択はなかったです。破産して借金から逃れる気持ちもなかった。今思えば、そこまで頑なに返済にこだわったのは、父の夢の後片付けだったからあもしれませんね。父が生きているうちに全額返済できてよかったです。」 多額の負債を背負い、自分のことも大変困難だった時代にも、1992年の長崎・雲仙普賢岳の噴火災害のチャリティライブ 「夏長崎から~平和祈念コンサート」
そのうちなんとか なるだろうって信じて 毎日頑張った。 何とかなるモンだよ 。 何とかなると思って、 放っておくんじゃなくて、 何とかなると思って がんばっていれば、 事態はいくらか変わってくるものだ。 (「さだまさし一所懸命日めくりカレンダ-」より) その昔2016年11月8日(火)、午後8時からテレビ朝日系列「人生で大事なことは…”○○から学んだ!”」 さだまさし 『長江』 『BIG tomorrow』 2017年2月号(青春出版社) 「借金があったから頑張れた!僕のお金と幸せ人生道、今も驀進中」 「関白宣言」「親父の一番長い日」「北の国から」 さだ 「今振り返るなにくそ!人生の軌跡」
大借金の原因となったドキュメンタリー映画『長江』 さだ 「貸した方もプロだから、さだなら返せるとふんだのでしょう。そう思ったら、自分も一生懸命返すしかないと思った」 「過払い金とかなかったのかなぁ…。ちゃんとした銀行だから、それはないか?!」
1981年、28歳のさだ 『長江』(主演・監督・音楽=さだまさし) 「大河の最初の一滴を見たい」 雅人 「今、長江を撮影する企画は6カ国が競合している。おたくの会社を調べたが、大変小さい会社だとわかった。しかし、お金が仕事をするのではなく、人が仕事をするのだから、最も優れた企画を出した貴社に撮影の権利を与える」
監督と主演はさだ 市川 崑監督 雅人 さだ 「名前が載っているだけで何もしていない」 『長江』 繁治 雅人 雅人 『長江』 まさし さだ 雅人 長江 さだ さだ さだ
なぜ中国で映画を撮ったかというと、ある意味で佐田家 さだ ウラジオストック 「松鶴楼」 さだ 佐田繁治 「滔滔と流れ続ける長江はまた、故郷長崎まで一直線に伸びたシルクロードと感じていた」 さだ 雅人 さだ 雅人 「親父は最後まで、とうとう一度も侘びも礼も言わなかった」
金利を入れて35億円近い借金は、僕の会社ではなく、僕個人の借金ですから返さざるを得ない。でも、会社を維持し、社員に給料を払い、なおかつ税金も払いながらの返済ですので、かなり厳しかった。10日ごとに8千万円、5千万円、1億5千万円という手形を落とさなければならなかったわけですから…。負債額がわかったとき、破産宣言するよう勧めてくれた人もいました。「そうすればチャラになって楽になるから」と言って。このときは一晩考えましたね。その結果、貸した側の身になって考えてみよう、と。お金に関してはプロの銀行が融資してくれたのは「さだまさしなら返せる」と考えたからに違いない。だったら返せるんじゃないか。ここは”プロの勘”に懸けてみようと思ったんです。返済の過程で二度不渡りを出したことがありました。半年に二度不渡りを出すと銀行と取引停止になるんですけど、僕の場合は数年おいてでしたから会社はつぶれなかった。つぶれなかったことで「このままいけば返せるんじゃないか」と。そうすると勇気がわいてきて、それが「返そう!」というモチベーションになるんです。返済が終わったときは、ある種の脱力感に襲われたし、「ああ、これで返済に追われなくてすむ」と思いましたね。
借金を返済する過程で感じたり、学んだことはいっぱいあります。ひとつは”人の情け”です。銀行の担当者をはじめおおぜいの人達が僕を助けてくれた。そういう意味では、僕はついていたし、本当に人に恵まれているな、と思ったことが何度もありました。それと、何事も最後の最後までわからない。だから、諦めてはいけないということも学びました。だから、僕は決して投げないですよ。そして何よりも僕のファンであり、コンサートに来てくださる方たちのパワーです。僕が莫大な借金を返済できたのも、前人未到のソロコンサート4千回を達成できたもひとえにファンのみなさんのおかげです。これからは、みなさんに恩返しをしなければいけない。ということは、僕は歌手をやめたくてもやめられないんですよ(笑)。 ―『女性自身』1月21日号
さだ 「とりあえず、いくら足りないんだ」 「今月はこの金をあっちに回して」 さだ 「ごめんね」 「お前には金のことはわからないから、向こうに行っとけ」 さだ
1987年、そんな自分の借金返済で大変な中、広島に原爆の落とされた8月6日に、長崎から平和を祈る野外コンサート「夏・長崎から」 「そんなときに何でまた。そんなことをとお思いのことでしょう。…ほんと、何考えてんだか」 さだ さだ 「有料にすれば只の商売にしか写らない。俺は故郷に世話になってきた分、どうしても平和を考えるコンサートをやりたい。と、なれば有料は駄目だ。誰でも来られる、それこそ夕涼みがてら家族で俺たちのコンサートを聴きに来るという”家族の構図”がもう平和の象徴になる。料金を取れば子供や老人は留守番になるかもしれない。チャリティにすれば志は曖昧に見えるのが世の常、人々はそこで動く”金額”にだけ気を取られる。純粋に俺が長崎で好きなことをやる、その代わりに、メッセージを伝える。だから無料でなければ駄目なんだ。スポンサーを探し、あちらこちらに頼み込む。俺が自分で頭を下げて歩くから、頼むから無料でやらせてくれ」 コチラ です)。この決断に対して、事務所の社長であった弟・佐田繁理 さだ さだ さだ
今から10年前、デビュー30周年、コンサート3000回突破記念の時に、この借金のことを振り返って、次のように語っておられました。
金 のことについては後悔はしています。あれが有意義でなかったとは少しも思わないけど、同じ額使うのなら、もっと効果的な、もっと世の中の役に立つ金の使い方もあったな、と。でも、これは結果論。あれは100年後に評価されますから。ま、返済には一生かかるけどね(笑う)。でも、金に対する恐怖心が消えた事件だったよね、僕にとっては。“何とかなる”ではなく、“何とかしなきゃ”って。身体の病気は金では治らないけど、貧乏は金で直るからね、翌日。金さえあれば翌日直っちゃうんだから。簡単なことだと。ただ、稼ぐのは大変だけど…。もし、あの時僕が35億借金していなければ、今その額を持っているかというと、たぶんそれはないと思うし。もしあの時に借金していなければ、その後はバブルで引っかかっているな、とね。一生立ち直れないくらいの傷を負っていただろうってね。あの時、まだ30歳前だったから、頑張って立て直そうと思ってきたし。この年になってみればまぁ冒険野郎だったな、と思うね。年とったときのネタになるね。話のネタに。“お前ら、スケールちいせぇよ”っていえるもん(笑う)。“5千万や1億でガタガタいうんじゃねぇ” って。会社の借金じゃなく、個人の借金だよ。俺、だから逃げ隠れできないんだよね(笑う)。あの時には社員にも迷惑かけたけど、立ち直ってきた今になれば、いい思い出だよ。 ―『週刊女性』
返済には1にも2にも、音楽という本業での稼ぎを充てるしかなかったのです。そして、さだ 「神出鬼没コンサート」 さだ 精霊流し」「無縁坂」 「雨やどり」、「関白宣言」、「道化師のソネット」、「防人の詩」、「秋桜」 「風に立つライオン」 さだ 「さださんのコンサートに行って、話術を勉強して来い」 さだ 「コンサートに来たお客さんから、曲はレコードで聞くから、もっとトークを聞かせてくれって言われちゃいました」 さだまさし さだ 「会場を満員にするにはどうしたらよいか?」 雅人 さだ 『長江』 雅人 雅人 さだ
「ひたすらライブやって一心不乱になって返しました。借金から逃れる気持ちはなかった。たかだかお金のことだから返せるか返せないかでしょう。今思えば、そこまで頑なに返済にこだわったのは、父の夢の後片付けだったからかもしれませんね。父が生きているうちに全額返済できてよかったです。」(さだ談) 雅人 58歳になり「もう借金の心配をしなくてもいい」 「ああ、これで歌手をやめることができる」 「よし、60歳になったらやめよう!」 東日本大震災 階上中学校 「苦境にあっても天を恨まず」 コチラ です)、目を覚まされたと言います。「がっかりしている場合じゃない。とにかく現場に行こう」 さだまさし 「そうか、こういうときのために、さだまさしは有名になったんだな」 「今日のコンサートが、ラスト・コンサートになっても恥ずかしくないステージをやろう」 さだ
さだ 「借金を返せたのは、ひとえにファンの皆さんのおかげ。また助けてくれる仲間がいたから」 「 そうした皆さんに恩返しをするためにも、まだまだ引退することはできない」 借金返済後も、 「お客さんに育ててもらったのだから、お客さんに納得してもらえるまで走り続ける」 さだまさし
2025年1月13日には、能登半島地震で被災した石川県輪島市 珠洲市 を訪れ、昨年10月に長崎市で開いたチャリティーコンサートで集まった約2,400万円を、被災地や伝統工芸団体などに寄付しました。名曲「いのちの理由」 「日本中に応援している人がいる。明日に向かって頑張りましょう」「本当に二重三重苦の中で、それでも頑張ってやろうって思っている人がたくさんいらっしゃるというのは、本当に心打たれますし、日本中で応援している人はいっぱいいるから、ここで切らないで、またつないで、明日へ向かって頑張りましょうというエールを届けに来ました」
3月23日(日)には久々に(前回はコロナ禍真っ最中に人数制限をして対策下で強行)松江・島根県民会館 ♥♥♥
「共通テスト」 勝田ケ丘志学館
(1)問題用紙の確認 第1問 第8問(?) 新課程入試 新傾向問題 解答用紙
(2)「場面設定」 ①「誰が?」②「何をしている?」
(3)「設問の先読み」 本文 設問 「設問の先読み」 ワークシート
(4)「事実」 「意見」 「意見」 形容詞・助動詞
(5)イギリス英語
(6)時系列並べ替え問題 コチラ を参照)、ここは選択肢まで「先読み」 出てきた順番 が必ずしも起こった順番 とは限らないことに注意しましょう。着眼点は、①時を表す表現、②時制(過去完了、助動詞)
(7)第7問は温かみのある物語文 「 問題作成部会」 「温かみのある物語文」 センター試験 過去問
(8)概要の読み取り 「要旨」 「タイトル付け」 「一言メモ」 ①各段落の最初と最後(これが圧倒的!)、②「しかし」の後、③疑問文(問題提起) タイトル付け問題 第1段落 最終段落
(9)各問いの難易度 「センター試験」 問1~問5 「共通テスト」 大学入試センター 設問別正答率 「言い換え」 「スリ替え」 「原文典拠の法則」
(10)リーデイングが終了してリスニングが始まるまでの休憩時間 糖分 「耳慣らし」
(11)難易度 リスニング リーディング
(12)不正行為 「共通テスト」 不正行為 馳浩文科大臣 「 大学入学共通テスト」 大学入試センター
(13)デマ デマ 難易度 デマ
(14)二次対策の過去問 10年分の過去問 は用意してありますね?自己採点
(15)志望校の合格最低点 「合格最低点」 「 自己採点」
(16)試験当日の朝
以上です。
毎年「共通テスト リーディング」 「リーディング」試験
▲2024年2月10日の講演会資料より
講演を終えた後、私がじっくりと読み込むことをオススメしている 大学入試センター 「共通テストリーディング」 「問題評価・分析委員会報告書」 ◎過去最高の語数であり、問題文だけで4ページにわたる設問があったことに鑑みると、全体的に受験者が落ち着いて問題に取り組める大問構成とすることを検討してもよいと思われる 。 (高等学校教科担当教員の意見・評価) ◎ただし分量については再考を要する 。上述のように各設問の設計は適切であるものの、全体の分量が試験時間に比して過大であるように思われる 。思考力・判断力・表現力等を適切に測るべく出題に様々な工夫をする場合、受験者が十全に力を発揮することができるよう解答時間を保障することが不可欠である 。 (高等学校教科担当教員の意見・評価) ◎速読と精読のバランスの観点、特に思考力を測定する観点からすると、これ以上語数を増やすことは有効でないと考える 。情報量が増え、問題も複雑になり、短い時間の中で単に注意力や情報処理能力を測定するような試験に陥るのではなく、じっくりと考える時間を設定して思考力を十分に測るような試験問題に改善することが求められるのではないかと考える。 (教育研究団体の意見・評価) このような切実な現場の要望に対して、「問題部会」
▲高校教員からは、全体の分量が試験時間に比して過大であり、分量の適正化を検討するよう要望があった。読む量だけでなく、内容の複雑さも適正となるよう、今後の出題に向けて検討を続けて行きたい 。 (問題作成部会の見解) 現場からのこれだけ強い要望と、このようなやり取りを頭に入れると、新課程の「共通テスト」リーディング いったん歯止めがかかるのではないか 、と私は踏んでいます。みなさんはどう予想されますか?♥♥♥
【補記】 今年の「共通テスト」のリスニングは間違いなく難化します。ずーっと平均点が上昇を続け、もうこれ以上はないだろう、というところまで来ているからです。
不安や緊張と戦いながら勉強を続ける受験生にとっては「お守り」や「縁起もの」は心を支え、大きな励みになるに違いありません。受験シーズンに大人気の「キットカット」(ネスレ) バレンタイン、ホワイトデー
「キットカット」 「受験生」 「キットカット」 ネスレ日本コンフェクショナリー事業本部 「キットカット」 「受験生へのお守り」 「縁起担ぎ」 「キットカット」 「きっと勝っとお」 「きっと勝っているはずだ」「きっと勝っています」
1999年、ネスレ日本 「九州のスーパーに受験生向けPOPを作りたい」 「大切な登録商標を語呂合わせや言葉遊びするのは、ブランドとしてよくないと、まずは慎重に判断してしまったのです」 「キットカット」 「日本人にとっての本当の意味での『ブレーク』とは何か?」 「Have a break, have a KitKat.」 「あなたにとってのブレークとは、どんな瞬間ですか?」
日本はストレスの多い国とも言えます。まじめに取り組む人ほどストレスはかかります。なかでも「受験」は学生時代のいちばんのストレスではないか、との仮説が上がり、九州から上がってきた声とシンクロしました。そしてついに、当時マーケティング本部長だった高岡浩三氏(現・ネスレ日本代表取締役社長兼CEO) 「九州の消費者から上がったユニークな現象。これこそがリアルで新しい消費のされ方だ」 ネスレ日本 「キットカット」 「「キットカット」で応援されていることは、少しでも気持ちがやわらぐ瞬間になるのではないか。ストレスをリリースするため学生さんを応援するツールになれば、本当の意味でのブレークではないかと考えたのです」
旅館に泊まった人は五万円払っても、「ありがとう」 「ありがとう」 「お世話になりありがとうございました」 ネスレ 「受験にきっと勝つ」 「キットカット」 「御社の販促手段でしょ?」「どうして協力しなくちゃならないんですか?」「それも無償で」 「感謝されました」「礼状も届きました」 「キットカット」 「キットカット」
「受験当日、祈るような気持ちで息子のポケットに「キットカット」を入れました」、「勉強の合間に、願をかけて食べていました」 「キットカット」 「リラックスして合格しました、みんなで試合前に食べて勝ちました、などですね。皆さんの深いところに到達したのかな、と感動します。これは商品担当として、かけがえのないことです」
「キットカット」 「キットカット」 「キットカット」 ♥♥♥
「ミスしたら負け」 「センター試験」 「共通テスト」 「自己採点」 「成績開示」 「自己採点」 「進研・駿台共通テスト模試」 82% もあります。模試会社の公表によれば、85% とも言われています。ですから少々自己採点が間違っていても、「横断歩道、みんなで渡れば怖くない」 「二段階選抜」 松江北高補習科 「自己採点」 「きちんとしなさい!」 松江北高 基本のキ 「ABC」(当 たり前のことをバ カになってち ゃんとやる)
下の例をご覧ください。これは既卒生(=本番を経験している浪人生)の「第1回駿台・ベネッセ大学入学共通テスト」(2023年9月) 11% 、なんと89% の受験生が自己採点ミスをしており、全体の6割が実際よりも高めに採点していました。自分に甘い傾向が見られます。
◆模試における自己採点の誤差の実態 誤差 受験生(既卒生)中の割合 実際より高め に自己採点 採点が完璧 ±0点 11% 私のこれまでの経験・観察では、得点の高い人が必ずしも「自己採点」 「自己採点」 「自己採点ミス」 2回点検 することで防げる凡ミスばかりです。勝田ケ丘志学館 「その秘訣は?」
【自己採点を間違える原因】 (1) 【模試当日】 問題を解く際に、自分の解答をきちんと問題用紙に転写していない。問題番号をずらしてしまう。不鮮明でどれにマークしたのかが読めない。消しゴムできちんと消していない。その結果、自己採点当日に自分の答案が再現できなくなる。致命的な「ダブルマーク」や「科目コード」の記入ミスも見られます。細心の注意が求められます。
(2) 【自己採点当日】 問題用紙の自分の解答を「自己採点用紙」に転記する際に、うっかり写し間違える。もう1回再点検することで防げるミス。
(3)「正解」と「自分の解答」を照合する際に、うっかりして○×を間違える。これももう1回点検することで防げるミス。
(4)得点を「小計」、「合計」する際に暗算でやって間違える。必ず電卓を使って、2回計算することで正確に合計できる。自己採点当日、電卓を忘れ手計算でいい加減にやっている生徒も目につく(そもそも電卓を持って来いという指示を出していない学校すらも…)。
(5)解答用紙にマークする際に、決められたようにマークしていないので(形、濃さ、消し忘れ)、機械が読み取れない。鉛筆は本番と同じようにH、F、HBを使いたい。
これらのミスはもう一度見直す(「検算」) 「自己採点」 先生 に計算してもらったことがあります。それによれば9,504人 です。長文問題1問分6点違うと、28,621人 です。どうです?馬鹿にならないことが一目瞭然でしょう?たった1問でこれだけ順位が異なってくるのです。模試の判定でも、自己採点がデタラメ状態では、デタラメな志望校判定結果しか返って来ません。ましてやこれが本番となると…?この恐ろしさを生徒にきちんと伝えて、毎回追跡をかけて、限りなく自己採点ミスを0点に近づけていく努力を怠ってはなりません。現場では「忙しい」と称して、こうした努力を行っていない学校が数多くあります。私には本末転倒の「言い訳」としか思えません。生徒の「自己採点」
【自己採点の正式手順】 (1)まず自分の問題用紙に1問に1つ○がしてあるかどうかを確認する。 (2)問題用紙の自分の解答を、鉛筆 で自己採点用紙の解答欄に転記する。終わったら正しく転記できているかどうかをもう一度再確認する。 (3)「正答」と「自分の解答」を見比べて、一致していれば 配点を赤ペン で囲む。違っていれば配点に×印。終わったらもう一度点検する。 (4)赤○の配点を電卓に入れて足し算をし、「小計」を計算する。もう一度間違いないかどうか確認する。「小計」を電卓で足して「合計点」を算出する。もう一度確認する。以上終了。 私はまだ若い頃、島根県立松江南高等学校 「北高に追いつけ、追い越せ!」 島根県 「センター試験」 「自己採点用紙」 島根大学 ①初日、家に帰って自ら自己採点をしたりして、2日目に動揺する生徒を出さないため 、②学校での「自己採点」当日の問題用紙忘れを避けるため 、そしてここが一番重要なんですが、③担任がその夜のうちにクラス全生徒の自己採点をして、翌日学校で生徒の自己採点との照合をして正確を期すため 96.4点 で、私のクラスの生徒たちはかなり高得点を取っていたにもかかわらず、見かけの点の低さに愕然としたものです。英語の「センター試験」の全国平均点が100点割れを起こしたのはこの年だけです)。すでに「自己採点」 「自己採点」 「二次試験に向かって明日からスタートだ!」
教員が「忙しい」と称して、肝心の所で手抜きをしているのがとても気になっています。事情の分かっている私などは、「ここできちんとやっておけば、後で楽ができるのに……。結局、後で苦労することになるのになあ……」 野村克也 「負けに不思議の負けなし」 「自己採点」 松江北高現役 松江北高補習科 勝田ケ丘志学館 「自己採点」
本番試験の翌日、朝早くから各教室で自己採点が始まります。正確を期して複数回点検をさせて結果が出ます。まだここから大変な作業が待っています。私が若い頃は、ベネッセ、河合塾、駿台、代ゼミ、大阪北予備 ベネッセ・駿台・河合塾 母集団(参加者)
12月中旬に勝田ケ丘志学館 大学入試センター ショート動画 「もうすぐ共通テストがあるね?」 「ファックション!」 「そうかfunctionだった」 「地歴公民と理科を受けるね?受験案内についてたリーフレット読んだ?」 「読んでない……」 「今回から地歴公民と理科の解答用紙には裏面がある!」 大学入試センター 国語・数学 「情報」 地歴・公民 ♠♠♠
お正月に街をブラブラして気のついたことが一つあります。かつては、お正月になると車のフロントグリルにしめ縄 しめ縄 しめ縄 「神様を迎える準備ができていること」 しめ縄 「お焚き上げ」 「どんど焼き」
▲八幡家の玄関
昔はお正月には車や玄関先にしめ縄 しめ縄
◆しめ縄をつけなくなった理由① 車のデザインに合わない
昔の車はしめ縄 しめ縄
◆しめ縄をつけなくなった理由② 正月文化が希薄になった
時代の移り変わりによって、 しめ縄
◆しめ縄をつけなくなった理由③ 車に傷がつく可能性がある
しめ縄
◆しめ縄をつけなくなった理由④ 車が所有するものではなくなってきた
レンタカーやカーシェアの普及による車の利用方法の変化で、自分の物ではないからつけづらくなりました。所有者以外の車の利用方法が増えているのです。
◆しめ縄をつけなくなった理由⑤ お守りが身近になった
交通安全のために車につけるしめ縄
▲自転車にもゲン担ぎ
▲最上稲荷奥之院本堂
私は毎年自転車カゴにもしめ飾り 「ゲン担ぎ」 最上稲荷奥之院 最上稲荷 心臓の手術 股関節の手術 交通事故 自転車で転倒 ♥♥♥
▲いつも母が守ってくれています
巨人軍 川上哲治(かわかみてつはる)監督 V9 というとてつもない栄光の記録を残しました。あの頃は本当に強かった(「巨人・大鵬・卵焼き」 長嶋、王、高田、柴田、土井、黒江、末次、国松、森……。 金田、堀内、髙橋一三、城之内 森 祇晶(もりまさあき)
私はこれに対していつも即座に「ノー」と答える。たしかにV9当時のジャイアンツのメンバーはすごかった。打者は長島、王、土井、高田、柴田、黒江、末次……。ピッチャーには堀内をはじめ城之内、高橋一三と、他のチームがうらやむくらいのエース級がそろっていた。一時期には、金田投手もいた。いわば、“綺羅星の如く”スター選手が並んでいた。これだけの豪華メンバーが集まれば、監督なんか目をつぶっていても勝てると思うかもしれない。ところが野球というのは、そんな単純なものではない。スター選手というのは善かれ悪しかれ傲慢さを持っているし、自己中心的な性格の持ち主が多い。勝ち続ければ、慣れというのも生じてくる。そうした危険な芽を摘み取り、数多くの個性を束ねていく監督の仕事は簡単ではない。連覇すれば、「勝って当たり前」というプレッシャーもかかってくる。そうしたなかで勝ち続けるのは筆舌に尽くしがたい努力がいる。 (森祇晶『森祇晶の知のリーダ学』(ごま書房、1997年2月) あの毒舌・ボヤキの故・野村克也 川上
ONという真の中心選手がいて、その前後を固める選手たちにそれぞれの特徴があって、彼らが首脳陣から求められる役割をきちんと理解していたからこそ、リーグ優勝、ひいては日本シリーズで9連覇という前人未踏の記録を成し遂げることができたのである。そこにある適材適所の重要性を見抜き、つながりのある打線を組み、それぞれの打者に合った役割を徹底させた川上哲治監督の眼力と手腕を見逃してはいけない。 (野村克也『戦略の書 組織を動かす極意』(セブンアイ出版、2018年10月)) ◆巨人V9の軌跡 当時巨人は、1950年から11年間にわたって水原茂監督 川上監督 アル・キャンパニスコーチ 「ドジャースの戦法」 川上 川上 金田正一 水原茂監督 三原脩監督 大洋 川上 川上 国鉄 金田正一 金田
川上監督 「球際」 川上監督 「飯さえ食えれば死なんばい」
1961年(1位) 71勝53敗6分 勝率.569 1962年(4位) 67勝63敗4分 勝率.515 1963年(1位) 83勝55敗2分 勝率.601 1964年(3位) 71勝69敗0分 勝率.507 1965年(1位) 91勝47敗2分 勝率.659 1966年(1位) 89勝41敗4分 勝率.685 1967年(1位) 84勝46敗4分 勝率.646 1968年(1位) 77勝53敗4分 勝率.592 1969年(1位) 73勝51敗6分 勝率.589 1970年(1位) 79勝47敗4分 勝率.627 1971年(1位) 70勝52敗8分 勝率.574 1972年(1位) 74勝52敗4分 勝率.587 1973年(1位) 66勝60敗4分 勝率.524 1974年(2位) 71勝50敗9分 勝率.587 当時、川上 金田正一 広岡達朗 川上 川上 藤田元司 長嶋茂雄 川上 王 貞治 森 祇晶 高田 繁 土井正三 堀内恒夫 川上 人としていかに生きるべきか、あるいは人の和の大切さ、礼儀やマナーという人間学 を中心に話をしていたそうです。野球人である前に、一人の人間 としてどうあるべきかを説き続けたそうです。「人間とは何か?」「社会とは何か?」 といった人間学・社会学を選手たちに考えさせていたといいます。川上 永平寺 「人間として尊敬」 『遺言』 私の時代は、チームをひとつの「家庭」と考えていた。監督はいうならば父親だし、コーチは母親だ。(中略)父親が父たりえて、母親がまた母親たりえて、時には厳しくしつけ、愛情をもって目を配り、きちんと子供を育てていかなければ家庭だとてチームだとて、まっとうなものにはなりにくいものだ。声高に「個の尊重」「個の自己責任」という今ならば、なおさらにその個をはぐくみ、その個を形成する家庭というものが大切になってくるはずだ。 「トイレのスリッパは揃えて脱げ」 川上監督 「 後に使う人のことを考えろ」 川上監督 王選手 長嶋選手 「人間教育」 野球選手というものは、自分が大金を稼ごうと一所懸命やっていればそれでいいと考えている。それがファンのためにもなると思っている。自分のためにがんばる。それは当然のことだが、その一点に終始すれば、それは平凡な小我の世界だと言わざるをえない。常に自分で、まずおれが―自分の欲、自分の満足のみに終始、踏みとどまるということであれば、いくら良い成績をあげられてもその選手は、『技術』だけの人である。たんに仕事ができる小我の人と、その職業や社会に報恩感謝の気持ちをもってやっていく人では、日々の取り組み方も、選手としての充実も、ふくらみがまったく違うものである。自分の今ある立場、自分が生かされている環境や社会に報恩感謝の心を強めていってこそプロ野球の道、人の道である。 当時の巨人の名ショート黒江透修(くろえゆきのぶ) 川上 「 ご主人は頑張っています。何の心配もいりません」 「 体を休めるだけでなく、これまでお世話になった人に手紙を書く時間に充てなさい」 9年連続で日本一 になりました。いい話です。私はそんな巨人軍が大好きだったんです。今でも熱狂的な巨人ファンですが、ここ最近の指導体制には辟易しています。
川上監督 「思い切っていけ」 淡口憲治(あわぐちけんじ) 王 「足の上げ方が遅い」 平松 長嶋 「長嶋、打てんじゃ困るじゃないか!」 柳田 「柳田、バットをふらにゃァ~当たらんぞ」 黒江 「好球必打というが字の通りではダメだ。ど真ん中に来てもタイミングが合わない時は打つな。狙いを絞ってタイミングが合った時に初めて打て」 淡口 「何やっとんじゃ!あれでホームに帰れんとはプロとして恥ずかしいわ」 淡口 川上 「集中力」 川上
米粒に字を書く人のことを知っているか。その人は筆を直角に持つのだそうだ。そして体全体の自然な動きに任せて筆先を動かして、あの小さな文字を書く。手先ではない。体で書く修練を積んでいる。修練で自然に精神が集中できるようになっている。 かつて川上 淡口憲治 「この選手は親孝行だから大成しますよ」 淡口 「コンコルド打法」 川上 牧野 川上 河埜和正 定岡 近鉄 野球と親孝行? 「親孝行」 「いい成績をあげるにはどうすればいいか?何をしたらよいか?」 野村 川上 「親孝行」 川上 あの名監督・野村克也(のむらかつや) 「親孝行」 野村 「親孝行は、大成するための必要にして最低限の条件なのである」 「 自分は誰かに支えてもらって生きている」 「 大勢の人が自分を支えてくれている」 「 報恩感謝」 今の球界を見渡しても、川上 「人間教育」 「 点さえ取ればそれでよし」 「あー、これではな…」 とため息が出ます。❤❤❤
川上さんは、組織はリーダーの力量以上には伸びないっていう、これを地でいった人だと思うんですよ。チームを強くするのに、みんなどのチームも、いい選手を集めたり補強だのなんだのっていう、そういう方向に頼っていますけど。やっぱり川上さんはその辺が違う。自分自身が成長進歩しないことには、チームも成長していかないっていうような思いがあったんだと思うんですよ。(野村克也談)
「超魔術」 Mr.マリック LUNA(ルナ) 「徹子の部屋」 LUNA マリック マリック 「これはいちばん驚きましたね。マジックより驚いた!」 ダイエットインストラクター LUNA 「コロナ禍で歌の仕事もお休みになってしまったので、その間にダイエットインストラクターの免許を取ってみようかなと。なので、徹子さんのボディメークもできます」
マリック 千葉 マリック LUNA
ずいぶん前のことになりますが、テレビ朝日系「しくじり先生 俺みたいになるな!!」(2017年6月25日) Mr.マリック ヒップホップ・レゲエ歌手 Luna 「 きてます」「ハンドパワー」 マリック 、 自らの失敗から導き出した「家庭崩壊を引き起こす親にありがちな3つの特徴」 マリック 「修復不可能なくらいまで家庭崩壊しちゃった先生」 「仕事を優先し過ぎて、家庭を崩壊させないための授業」 長女のLuna マリック ストレスによる顔面麻痺 「ハンドパワーです」 マリック LUNA さんが、父親が有名人のために小学校でいじめられ(「 スプーンを親父に曲げてもらってこい!」マリック それが、こうして2人で番組出演することが奇跡のように思えるという親子ですが、どのように家庭が崩壊していったのか?そしてどのように立ち直っていったのかを、赤裸々に解説しました。マリック 「家庭崩壊を引き起こす親にありがちな3つの特徴」 LUNA 家庭内での3つのしくじりとして、( 1)家庭を顧みず仕事優先。仕事と家庭のON、OFFがない。(2)家でもMr.マリックの衣装で生活。(3)子育てを妻に丸投げし、大事な時に(子どもを)叱れない人間 「家族写真は1枚しかない」 そんな父親にLUNA 「小学校3年で父に話しかけるのをやめた」 「ほとんどの校則を破った」 「グレることで個性を出そうとした。どこにいってもマリックの娘だった」 。ヤマンバ・メイクで、渋谷センター街 そこから向き合ってくれた父親。立ち直るきっかけ、歌うことのきっかけをくれたことに「父からもらった、家族愛のパワー。本気で叱ってくれたパワーは、ハンドパワーよりもすごい。ありがとう」 マリック 「こんな言葉を聞けるとは思わなかった。本当に困ったことだった。中学を追い出されたら本当に困る」 アポロシアター 「よし、行け!」 アポロシアター LUNA 最後は「仕事を優先して家庭を顧みない人へ」 「家庭より大切な仕事はない」 有名になる以前のマリック カズ・カタヤマ 『図解マジックパーフォ-マンス入門』(東京堂、2006年) マリック MAGIC の2010年11月号には(今は廃刊)、 マリック AKB 「No rain, no rainbow!」
▲マリック特集のMAGIC とカズ・カタヤマ本
▲『MAGIC』2010年11月号のマリック特集
「Mr.マリック超魔術団2024」(東京公演) ・ Mr.マリック LUNA LUNA 「Mr.マリックと天才頭脳集団の見破りバトル」 Mr.マリック Mr.マリック BS朝日
時は過ぎて、先日11月25日(月)のカズレイザー 「X年後の関係者たち」 「超魔術師Mr.マリック」 「きてます」「ハンドパワー」 Mr.マリック LUNA ♥♥♥
受験用の単語集を見ると、「 問題」=problem=issue 『ターゲット』、『システム英単語』 「問題」 problem 『ライトハウス英和辞典』 【類義語】 「関係者全員に対して害を与える問題」 problem 「人によって害になったり利益となったりする問題〔争点〕」 issue
「problem」 「解決すべき困難な問題」 「深刻な問題」 「problem」 「solution」 「解決されるべき困難な問題」 「problem」 problem problem 「飲酒運転」「高い犯罪率」「肥満」 「社会的・組織的な」 「problem」
My car has a problem
There is a problem
The company is facing a financial problem
Aging society is a serious problem
Defects are a serious problem
一方、それに対して「issue」 「議論されるべき問題点」 竹岡広信先生 『LEAP』(数研出版) 「(多くの人々に影響を与える、社会[政治]的な)問題」 「issue」 「賛成する人がいたり反対する人がいたりする賛否両論に分かれる話題、論争点」 選挙権の年齢制限、選択的男女夫婦別姓、退職年齢の引き上げ、税制改革、「103万円の壁」 「issue」 「issue」 「外へ出る事・物」 「問題」 「issue」 「論点として外に出てきた」 「論点として外に出てくる」 「議論されるべき問題点」 issue 多義語 「出す」「発行する」「発行物」「問題点」 『ライトハウス英和辞典』(研究社) 「語義の展開」 多義語
▲『ライトハウス英和辞典』の「語義の展開」
では用例を見てみましょう。♥♥♥
CEO’s words and actions raised an issue
The President made a political issue
How are we going to handle the issue
Gun control is a big issue
例えば、受験熟語集の木村達哉『ユメジュク』(アルク) 「make an effort 努力する」 「effort=努力」 effort(努力) 否定的な使われ方をすることが多い のです。例えば、Thank you for your effort. 「失敗してしまったけれど、努力してくれてありがとう」 デイビッド・セイン(David Thayne)先生 work Thank you for your hard work.
配達時間を短縮できるよう努力しております。
△We are making efforts to shorten our delivery times.
◎We are working hard to shorten our delivery times.
会議に時間通り行けるように努力した。
△I made an effort to be on time for the meeting.
◎I tried hard to be on time for the meeting. (デビッド・セイン)
「報われない努力」 We are making efforts…… 「努力しておりますが、実現できておりません」 I made an effort…… 「ちょっとは努力した」 cf. デイビッド・セイン『英語ライティングルールブック 改訂新版』(学研、2024年) make an effort make an effort make an effort cf. デイビッド・セイン『ネイティブが教える英語の動詞の使い分け』(研究社、20212年) 「理想の単語集」 竹岡広信先生 『LEAP』(数研出版) 「「(ちょっと)頑張る」の意味なので、人命救助などの場合、make a great effort「大いに努力する」などと表現する」
▲この辞典が実に面白い!!
ここら辺が英語の実に難しい所で、どんな辞典や参考書を見ても、このような細かいニュアンスまでは分かりません。こんな時に私がとても重宝している一冊をご紹介します。Longman Essential Activator (Longman, 1997)
make an effort to do sth : to try hard to do something, especially something which you do not want to do but which you think you should do : I made an effort to sound interested in what he was saying./ I wish you’d make an effort to be freindly to her. この辞典が、他の辞典とひと味もふた味も違うという例を、もう一つだけ挙げておきましょう。受験英語ではarrive at= get to= reach という書き換えをよく見ます。受験レベルではこれで十分です。しかし、この辞典によれば、arrive at は、get to よりもより<formal> reach の定義を見てみると、“to arrive at a place, especially after a long or difficult journey” とあります(下線は八幡)。こうした説明があれば、「ああそうか 、reachは同じ「着く」でも「たどり着く」という感じなのだな」 ♥♥♥
It took them over three days to reach
◎週末はグルメ情報!!今週は中華 ▲松江市東津田町の「中村製麺所」
島根県松江市東津田町 「ラーメン・まぜそば 中村製麺所」 松江駅南口 「中村製麺所」 「ラーメン・中華 中村製麺所」
▲松江駅南口の「ラーメン中華中村製麺所」
「ラーメン・中華 中村製麺所」 松江市朝日町 JR松江駅南口 「ホテル α-1 第2松江」 「山陰炭焼ごっつぉ酒場 善次郎」 松江駅
米子 「中華そば」(750円) 「チャーハン」(600円) 「チャーハン」 「おお、美味しいぞ!!」 「塩名人」
すぐに「中華そば」 「中華そば」
私が入店した午後6時頃はまだ誰もお客さんはおられませんでしたが、私が食べている間にお一人さん、グループでどんどん入って来られました。みなさんが「スタミナ中華そば」 餃子 「町中華で飲ろうぜ!」
今日は試しに「石焼き麻婆豆腐」(700円) と 「餃子」(400円) 「麻婆豆腐」 激カラ ノーマル 普通 四川飯店 陳建一 松江・京店 創作中華 「爸爸厨房」 岡山 「梅蘭」 麻婆 餃子 餃子 「中華そば」 「チャーハン」
今日は人気の「スタミナ中華そば」(990円) にんにく、背油、自家製チャーシュー6枚、もやし、白ネギ 「中華そば」 ♥♥♥
「ハウステンボス」の夜景 夜景鑑定士 「全国イリュミネーションランキング総合エンターテインメント部門」 、「夜景日本一」 「イリュミネーションアワード」 「イリュミネーションアワード」 「第1回International Illumination Award(インターナショナルイリュミネーショナワード)」 「イリュミネーション部門優秀エンタテインメント賞 「ハウステンボス」
オランダの街並みを再現した美しいテーマパーク「ハウステンボス」 「ハウステンボス」 「ハウステンボス」 アムステルダム広場 「ファンタジック・スノーナイトショー~白銀の世界 点灯式~」
そして演奏もクライマックスになったところでアムステルダム広場
その見どころの1つがイルミネーション 「光の王国」 イルミネーション
日が落ちてあたりが暗くなったら、アムステルダム広場
18:00になると神聖な雰囲気の中、真っ白な衣装を身にまとったシンガーの透き通る歌声と共に一斉に白いイルミネーションであたりが包まれる「白銀の世界」誕生の瞬間は、息をのむ美しさ。あたりは歓声に包まれ、場内のあちらこちらから拍手が巻き起こるとても素晴らしい瞬間です。点灯式の後は、場内のそこかしこが美しいイルミネーションに彩られます。雰囲気も良く、夜からは家族連れをはじめカップルもたくさん訪れて、写真を撮る人たちで賑わい始めます。
「アンブレラストリート」 「ショコラ伯爵の館」
願いを込めてコインを投げ入れれば、必ず叶うと言われているマウリッツの泉のそばには、音楽に合わせて輝く「光の天空ツリー」
「ハウステンボス」 「白い観覧車」
昼間は荘厳で落ち着いた雰囲気だった場内の運河を巡る「カナルクルーザー」
こちらはオーケストラを乗せた「カナルクルーザー」 カナルクルーザー
夜景を「ハウステンボス」 「ドムトールン」
昼間は長崎の島々やきれいな海が見渡せますが、夜は場内一面に広がる光の演出を楽しめるので、ぜひ上ってみてくださいね。
タワーの麓に見えるひときわ目立つ青い光は「光の滝・ブルーウェーブ」 「ドムトールン」 「アートガーデン」 「ドムトールン」 「光の滝・ブルーウェーブ」
アートガーデン 「光のどうぶつえん」
メルヘンな世界とは一変、口から炎を吹くドラゴンもいますよ! 全長13メートル、高さ6.5メートルのロボットだと構えても、大人でも身じろぎしまう迫力です。
神話をイメージした華やかな世界観を堪能できる、日本初の3階建てメリーゴーラウンドがあります。世界最大級の高さ15mを誇り、イタリア製の馬車やゴンドラはまさに芸術品で、昼と夜でまったく異なる表情を見せてくれるのも魅力のひとつです。夜になるとライトアップされて一層ロマンティックになります。3階からは「 ハウステンボス」 「ハウステンボス」 ♥♥♥
竹内 均先生(たけうちひとし、東京大学名誉教授) 「できる男は「朝」で差をつける」 「早寝早起き」 竹内先生 カント ゲーテ カント カント カント ゲーテ
竹内先生 東京大学 「私はここの教師だ。通して欲しい」 「東大の先生がこんなに朝早く来るんですか? 「大学の教授はお昼頃、出勤する」
大学紛争で思い出される逸話がもう一つあります。ある日、先生の研究室のある建物が封鎖されたことがありました。しかし学生たちが登校(?)してきたのは朝の9時頃でした。もちろん先生は朝の7時半に研究室に入っておられたので、すでにセッセと仕事に打ち込んでおられます。先生の秘書が9時頃にやって来て、学生たちにつかまりました。そこで先生のことが大いに問題になったそうです。「タケキン(先生の愛称でした)を引っ張り出せ!」 「先生はしょうがない」 。「建物の封鎖をやるならもっと真面目にやりなさい。私が7時半から来ているのに、君達が9時では遅すぎるではないか!」
私も小さい頃から「早起き」 松江北高 北高
物音一つしないシーンと静まりかえった学校で、始業時までの約2時間を、予習や調べ物、教材作成に充てることができました。これを毎日続けるわけですから、年間にすれば相当の仕事量になりますね(「チリも積もれば山となる」 カール・ヒルティ 「仕事というものは本当に熱心にやると、面白くなるという性質を持っている」 Virtue is its own reward. 「徳はそれ自体が報いである」「徳行は自ら報いる〔報酬を求めない〕」「善行の報いはその中にあり」「徳行はそれ自体が尊い」「美徳はそれ自身の報酬である」 『ライトハウス英和辞典』(研究社) 「徳はそれ自体が報いである(徳はそれを行うことで得られる満足感で十分報いられる)」 ♥♥♥
「能力」の差は、小さい。
◎ みなさん、良いお年をお迎えのことと思います。昨年もブログをご愛読いただき、ありがとうございました。今年もお役に立つ情報を発信していきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。幸い手術した股関節の調子も良く、新しい年を穏やかに迎えることができました。健康に留意しながら、今年も精一杯活動を続けたいと願っています。♥♥♥ ◎2024年の八幡5大ニュースを振り返って ①生まれて初めて交通事故に遭う!
▲事故現場の横断歩道
命びろい 交通事故 青 股関節 「運」
②松江北高を離れる 長年(18年間)勤めた松江 北高 補習科 北高
③念願の「直島」訪問実現 瀬戸内海 「直島」 安藤忠雄 「ベネッセハウス」 ④『ライトハウス英和辞典』(第7版)出る 長年携わってきた『ライトハウス英和辞典』(研究社) 第7版 「辞書を引いた回数に比例する」
⑤巨人4年ぶりのセリーグ優勝!! 大好きな巨人軍 阿部慎之助監督 横浜ベイスターズ 「守り」 阪神 「守り」
お正月は少し贅沢をしようと、佐賀県 宮地ハム 「こだわりロースハム」 博多 「ふくや」 明太子
年末に買い溜めていた本をぼちぼちと読んで、お正月をのんびりと過ごしています。♥♥♥

















































































































































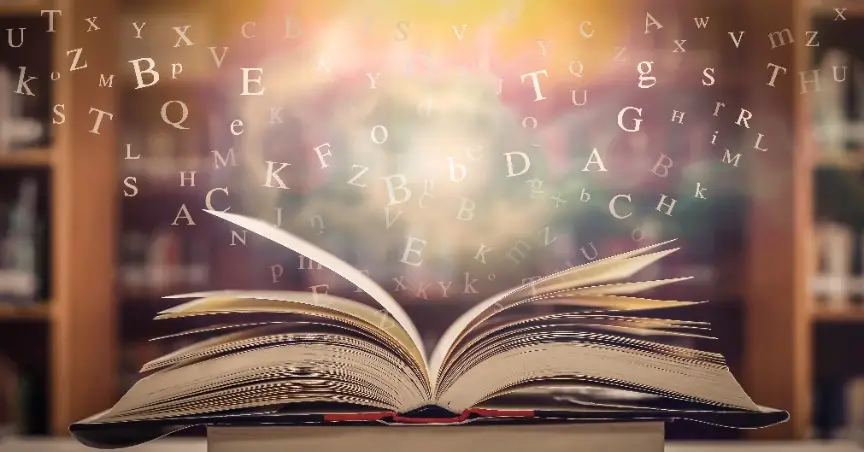


















































































































































































































































































































































 ▲
▲








































































































































 オーナーシェフの細木さんは、日本における「四川料理の父」とされる陳 建民氏の直弟子さんで、ここでは本格的な四川料理を味わうことができます。中でも「麻婆豆腐」は絶品です。熱々の鉄板で提供され湯気がモクモクと立ち上がっています。辛さが堪りません。見た目通り、どっさりの山椒と、ラー油のダブルパンチで非常に辛いです。後に痺れるような感覚が残ります。お水を
オーナーシェフの細木さんは、日本における「四川料理の父」とされる陳 建民氏の直弟子さんで、ここでは本格的な四川料理を味わうことができます。中でも「麻婆豆腐」は絶品です。熱々の鉄板で提供され湯気がモクモクと立ち上がっています。辛さが堪りません。見た目通り、どっさりの山椒と、ラー油のダブルパンチで非常に辛いです。後に痺れるような感覚が残ります。お水を たっぷり取りながら汗をかきかき食べます。ランチでいただくのですが、小鉢・小皿・サラダ・スープやらいろいろついていて、結構なボリュームでお得感があります。デザートに「杏仁豆腐」までついて、これでかつては850円でしたが、今は1,100円に値上がりしました。時代の流れです。
たっぷり取りながら汗をかきかき食べます。ランチでいただくのですが、小鉢・小皿・サラダ・スープやらいろいろついていて、結構なボリュームでお得感があります。デザートに「杏仁豆腐」までついて、これでかつては850円でしたが、今は1,100円に値上がりしました。時代の流れです。 松江の観光スポットの近くに立地しており、価格的にもとてもリーズナブルです。地元の生鮮食材をふんだんに使っているため、食材の特徴を生かした創作中華となっています。お昼はランチで価格、量、味で満足、夜は食事はもちろん、お酒とともに美味しい中華料理で満足といったところでしょうか。本当に美味しいです。♥♥♥
松江の観光スポットの近くに立地しており、価格的にもとてもリーズナブルです。地元の生鮮食材をふんだんに使っているため、食材の特徴を生かした創作中華となっています。お昼はランチで価格、量、味で満足、夜は食事はもちろん、お酒とともに美味しい中華料理で満足といったところでしょうか。本当に美味しいです。♥♥♥